一人の理解者が変えてくれた未来
現在、息子は通塾していません。しかし、一つだけ希望の光がありました。
英検受験の際、姉が通っていた塾で短期の英検対策講座を受講することになりました。個別対応で、姉の時もお世話になった塾だったため、息子の特性を理解した上で丁寧に対応していただけました。
そこでは、私がずっと願い続けていた配慮がありました。「あと◯回」「あと◯分」という具体的な声かけ。見通しが立つことで、息子の癇癪は激減し、最後まで講座を受けることができたのです。
英検受験の際、姉が通っていた塾で短期の英検対策講座を受講することになりました。個別対応で、姉の時もお世話になった塾だったため、息子の特性を理解した上で丁寧に対応していただけました。
そこでは、私がずっと願い続けていた配慮がありました。「あと◯回」「あと◯分」という具体的な声かけ。見通しが立つことで、息子の癇癪は激減し、最後まで講座を受けることができたのです。
この経験を通して、特性がある子も、声かけの仕方次第で学習意欲を増すことができ、成長していけるのだと改めて実感しました。家庭と塾とで連携しつつ通塾できれば、どれほどありがたいことでしょう。
すべての子どもに「学ぶチャンス」がある社会を願って
振り返れば、暗闇の中を手探りで歩くような日々でした。息子の存在を否定されるたび、何度も心をえぐられる思いでした。しかし、たった一つの、理解ある出会いが、私たちの未来を大きく変えてくれました。短期講座でお世話になった先生には、感謝しかありません。
今、同じように、お子さんの学びの場や居場所探しに悩んでいる方がいらっしゃるかもしれません。発達障害への理解は、まだまだ社会に浸透しているとは言えません。
それでも、どんなお子さんにも、学ぶチャンスは与えられるべきです。そして、声のかけ方や少しの配慮で、子どもたちは驚くほど大きく成長できる可能性があることを知ってほしいです。
社会全体が、目に見えない障害特性がある子どもたちを温かく見守り、その子の「好き」や「学びたい」という気持ちを応援してくれる。そんな未来になることを、心から願っています。
イラスト/マミヤ
※エピソード参考者のお名前はご希望により非公開とさせていただきます。
(監修:室伏先生より)
英語塾や個人塾、サッカークラブなど、学びや成長の場として本来は安心して通えるはずの場所で、理解を得られず、逆に拒絶されてしまった時のお気持ち、本当におつらかったですね。お子さんは、自分に合った声かけや少しの工夫があれば、「学びたい」という気持ちを持ち続けることができます。お姉さまが通われていた塾で、息子さんが最後まで講座をやりきれたことは、その大切さを教えてくれる象徴的なエピソードですね。
ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)のお子さんは、先の見通しが立たない状況に強い不安を感じやすいことがあります。「もう1回」「ちょっと待って」という曖昧な言葉は、ゴールが見えないために不安やパニックを引き起こしやすくなります。これに対して、具体的な回数・時間を伝える、視覚的な支援を活用する(時計やタイマー、カードなどの使用)、終わりを予告する(活動が終わる少し前に「あと1分で終わります」と知らせる)、などの工夫を行うことで、安心感が大きく高まり、活動への集中が続きやすくなります。
保護者だけでなく、社会全体が、声かけや配慮で子どもの力が引き出せることを理解し、誰もが安心して学べる場づくりを目指すことで、子どもたちの可能性が広がるはずです。同じように悩んでいるご家庭が少しでも希望を持てるよう、社会全体が子どもたちの「学びたい」という気持ちを応援できる未来になることを願っています。
今、同じように、お子さんの学びの場や居場所探しに悩んでいる方がいらっしゃるかもしれません。発達障害への理解は、まだまだ社会に浸透しているとは言えません。
それでも、どんなお子さんにも、学ぶチャンスは与えられるべきです。そして、声のかけ方や少しの配慮で、子どもたちは驚くほど大きく成長できる可能性があることを知ってほしいです。
社会全体が、目に見えない障害特性がある子どもたちを温かく見守り、その子の「好き」や「学びたい」という気持ちを応援してくれる。そんな未来になることを、心から願っています。
イラスト/マミヤ
※エピソード参考者のお名前はご希望により非公開とさせていただきます。
(監修:室伏先生より)
英語塾や個人塾、サッカークラブなど、学びや成長の場として本来は安心して通えるはずの場所で、理解を得られず、逆に拒絶されてしまった時のお気持ち、本当におつらかったですね。お子さんは、自分に合った声かけや少しの工夫があれば、「学びたい」という気持ちを持ち続けることができます。お姉さまが通われていた塾で、息子さんが最後まで講座をやりきれたことは、その大切さを教えてくれる象徴的なエピソードですね。
ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)のお子さんは、先の見通しが立たない状況に強い不安を感じやすいことがあります。「もう1回」「ちょっと待って」という曖昧な言葉は、ゴールが見えないために不安やパニックを引き起こしやすくなります。これに対して、具体的な回数・時間を伝える、視覚的な支援を活用する(時計やタイマー、カードなどの使用)、終わりを予告する(活動が終わる少し前に「あと1分で終わります」と知らせる)、などの工夫を行うことで、安心感が大きく高まり、活動への集中が続きやすくなります。
保護者だけでなく、社会全体が、声かけや配慮で子どもの力が引き出せることを理解し、誰もが安心して学べる場づくりを目指すことで、子どもたちの可能性が広がるはずです。同じように悩んでいるご家庭が少しでも希望を持てるよう、社会全体が子どもたちの「学びたい」という気持ちを応援できる未来になることを願っています。
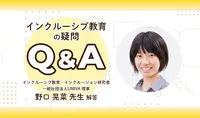
インクルーシブ教育とは?実践例や合理的配慮の求め方【専門家QA】

失敗したときに、イライラせずに次に進むにはどうすればいい?
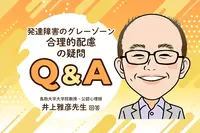
発達障害グレーゾーンでも学校で合理的配慮を受けられる?学校での実例は?【公認心理師・井上雅彦先生にきく】

習い事でトラブル続出!練習にも集中できない発達障害息子。周囲への配慮と親の精神的負担、どうする?

習い事が長続きしない発達グレー息子が「eスポーツ」にはまった!楽しいだけではないその魅力とは?
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-
 1
1
- 2
















