失読症について、文字が読めなくなる原因や詳しい症状や治療法を解説、失読症とディスレクシアとの違いも
ライター:発達障害のキホン
失読症とは、後天的な脳の損傷によって文字が読めなくなったり読みづらくなる障害です。脳の病気の中でも脳梗塞の後遺症として現れることが多いといわれています。本記事では失読症の原因、症状、治療法のほか、失読症と混同されやすいディスレクシア(読字障害)との違いなどを解説します。
失読症とは?どんな障害?
失読症は、脳梗塞や脳卒中、脳出血などにより脳の中の言語をつかさどる領域が損傷することで、文字や文章を正しく認識したり理解したりする能力が損なわれる障害です。脳の損傷により、言語・記憶・行為・学習・注意など認知機能に障害が起こる「高次脳機能障害」の一つです。
高次脳機能障害の中で代表的な障害として知られているものの一つに「失語症」があります。失語症では、「話す」「聞く」「読む」「書く」4つの言語機能の1つあるいは複数に影響が生じますが、中でも「読む」機能に障害が現れるものを失読症と呼びます。
高次脳機能障害の中で代表的な障害として知られているものの一つに「失語症」があります。失語症では、「話す」「聞く」「読む」「書く」4つの言語機能の1つあるいは複数に影響が生じますが、中でも「読む」機能に障害が現れるものを失読症と呼びます。

失語症とは?原因や症状、リハビリの方法や周りの人とのコミュニケーションまとめ
脳梗塞と失読症
失読症は、脳の病気の中でも脳梗塞の後遺症として現れることが多いといわれています。これは、脳内の「脳梗塞を起こしやすい部分」と「視覚に関する領域」が重なっているためです。
失読症は多くの場合、左脳の後頭葉から側頭葉が損傷した場合に引き起こされます。
言語能力は、左脳がつかさどっており、後頭葉から側頭葉は視覚情報を扱う領域です。そのため、左脳のこの領域が損傷してしまうと視覚情報を言語と結び付けられなくなり、その結果文字がうまく読めなくなるというメカニズムです。
脳梗塞はこの側頭葉から後頭葉で起きることが多いため、失読症の原因となることが多いのです。
失読症は多くの場合、左脳の後頭葉から側頭葉が損傷した場合に引き起こされます。
言語能力は、左脳がつかさどっており、後頭葉から側頭葉は視覚情報を扱う領域です。そのため、左脳のこの領域が損傷してしまうと視覚情報を言語と結び付けられなくなり、その結果文字がうまく読めなくなるというメカニズムです。
脳梗塞はこの側頭葉から後頭葉で起きることが多いため、失読症の原因となることが多いのです。
純粋失読―書けるのに読めない
三輪書店
Amazonで詳しく見る
失読症の症状とは?
失読症の人は、文字が読み取りづらく、語句や行を抜かしたり、逆さ読みをしたり、音読が苦手な傾向があります。また、平仮名と漢字の両方の読む機能が侵されたり、平仮名の読みの障害の方が漢字より強く現れるようなケースも報告されています。
このような読みの障害の多様性は、病変部位や病変の大きさの違いによって左右されると考えられています。
以下では具体的な症状をいくつかご紹介します。
■文字がにじむ・ぼやける
水に浸したように文字がにじんで見える、目が悪い状態のように文字が二重になる、あるいはぼやけて見えたりします。
■文字がゆがむ
文字がらせん状にゆがんだり、3Dのように浮かんで見えたりします。
■逆さ文字(鏡文字)になる
鏡に映したように文字が左右反転して見えることがあります。
■点描画に見える
文字が点で描いているような点描画に見えることがあります。
言語や記憶の障害は、肢体不自由のように明らかな身体障害がなく、外見からうかがい知るのが難しいことから「見えない障害」とも呼ばれます。失読症もこうした特性を持つため、病気を知らない周囲の人から誤解されてしまうこともあります。残念なことに日本での失読症への認知度は依然低いままであり、今後社会全体による「見えない障害」を持つ人への配慮がより広がっていくことが待たれています。
このような読みの障害の多様性は、病変部位や病変の大きさの違いによって左右されると考えられています。
以下では具体的な症状をいくつかご紹介します。
■文字がにじむ・ぼやける
水に浸したように文字がにじんで見える、目が悪い状態のように文字が二重になる、あるいはぼやけて見えたりします。
■文字がゆがむ
文字がらせん状にゆがんだり、3Dのように浮かんで見えたりします。
■逆さ文字(鏡文字)になる
鏡に映したように文字が左右反転して見えることがあります。
■点描画に見える
文字が点で描いているような点描画に見えることがあります。
言語や記憶の障害は、肢体不自由のように明らかな身体障害がなく、外見からうかがい知るのが難しいことから「見えない障害」とも呼ばれます。失読症もこうした特性を持つため、病気を知らない周囲の人から誤解されてしまうこともあります。残念なことに日本での失読症への認知度は依然低いままであり、今後社会全体による「見えない障害」を持つ人への配慮がより広がっていくことが待たれています。
純粋失読―書けるのに読めない
三輪書店
Amazonで詳しく見る

合理的配慮とは?考え方と具体例、合意形成プロセスについて【専門家監修】
ディスレクシア(読字障害)との違いは?
症状は似ているけど、原因は異なる
「失読症」は、学習障害の分類のうちの「読むことの困難さ(ディスレクシア)」の代替用語として用いられることがありますが、実はその根本原因は全く異なります。
障害の種類という側面から見ると、ディスレクシアは発達性の学習障害の一つであるのに対して、失読症は後天的な脳の損傷によって起きる高次脳機能障害の一つであるという説明ができます。
学習障害とは、全般的な知的発達に遅れがないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」能力のうちいずれかまたは複数のものの習得・使用に著しい困難を示す発達障害のことです。
つまり、ディスレクシアは先天的な脳の特徴が原因で起こる、生まれつきの発達障害のために文字を読むことに困難が生じているのです。
障害の種類という側面から見ると、ディスレクシアは発達性の学習障害の一つであるのに対して、失読症は後天的な脳の損傷によって起きる高次脳機能障害の一つであるという説明ができます。
学習障害とは、全般的な知的発達に遅れがないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」能力のうちいずれかまたは複数のものの習得・使用に著しい困難を示す発達障害のことです。
つまり、ディスレクシアは先天的な脳の特徴が原因で起こる、生まれつきの発達障害のために文字を読むことに困難が生じているのです。

LD・SLD(限局性学習症)とは?症状や特徴、診断方法について【専門家監修】
純粋失読―書けるのに読めない
三輪書店
Amazonで詳しく見る
ディスレクシアはこの点において、後天的な脳の損傷が原因で文字通り「読」む力を「失」ってしまう失読症とは全く異なっているのです。また、ディスレクシアは発症も、就学などによって文字を読む場面が出てくる学童期の子どもに多く見られます。
ディスレクシアの治療・対処法は失読症のリハビリや対処法と類似している部分もありますが、相違点もあります。詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧になってみてください。
ディスレクシアの治療・対処法は失読症のリハビリや対処法と類似している部分もありますが、相違点もあります。詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧になってみてください。
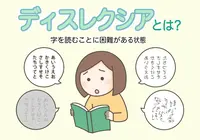
ディスレクシア(読字不全)とは?症状の特徴や生活での困りごとは?
















