LD・SLD(限局性学習症)とは?症状や特徴、診断方法について【専門家監修】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
LD・SLD(限局性学習症)は発達障害のひとつです。LD・SLD(限局性学習症)にはディスレクシア、ディスグラフィア、ディスカリキュリアなどさまざまなタイプがあり、また人によって症状の現れ方も違うので、診断が難しい障害でもあります。LD・SLD(限局性学習症)のある人の中でも文章を構成するのが得意な人もいれば、算数が得意な人もいます。このコラムでは、LD・SLD(限局性学習症)の3つの種類とそれぞれの症状、そして、具体的な特徴や受けられる支援について詳しく解説します。

監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
LD・SLD(限局性学習症)とは?主な症状と3つの種類
「学習障害(LD)」は、医学的な診断基準とされるDSMの最新版のDSM-5-TRでは、診断名が変更され、「限局性学習症(SLD(Specific Learning Disorders))」になっています。
限局性学習症(SLD)は、学習における技能に困難さがみられる発達障害の一つです。読むことやその内容を理解することの困難さ、書くことの困難さ、数の理解や計算をすることの困難さなど大きく3つの分類があります。これらの困難が、知的障害(知的発達症)によるものでないこと、経済的・環境的な要因によるものでないこと、神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと、学習における面のみでの困難であること、という場合に限り診断されます。
学校教育が始まる就学期になって診断されることがほとんどですが、就学前の段階で言語の遅れや数えることの困難、書くことに必要である微細運動の困難などがあることでその兆候に気づかれることもあります。
現在も「学習障害(LD)」と呼ばれることが多くありますが、この記事では「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。
また文部科学省の定義と医学的な診断基準には、違いがあります。文部科学省では、学習障害を以下のように定義しています。
限局性学習症(SLD)は、学習における技能に困難さがみられる発達障害の一つです。読むことやその内容を理解することの困難さ、書くことの困難さ、数の理解や計算をすることの困難さなど大きく3つの分類があります。これらの困難が、知的障害(知的発達症)によるものでないこと、経済的・環境的な要因によるものでないこと、神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと、学習における面のみでの困難であること、という場合に限り診断されます。
学校教育が始まる就学期になって診断されることがほとんどですが、就学前の段階で言語の遅れや数えることの困難、書くことに必要である微細運動の困難などがあることでその兆候に気づかれることもあります。
現在も「学習障害(LD)」と呼ばれることが多くありますが、この記事では「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。
また文部科学省の定義と医学的な診断基準には、違いがあります。文部科学省では、学習障害を以下のように定義しています。
基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。
学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。(出典:文部科学省 学習障害(LD)の定義)

発達障害とは?特徴・症状・分類や診断方法について【専門家監修】
種類別のLD・SLD(限局性学習症)の特徴
LD・SLD(限局性学習症)で大きく分類される「読字不全(ディスレクシア)」「書字表出不全(ディスグラフィア)」「算数不全(ディスカリキュリア)」の3つの特徴を紹介していきます。それぞれのLD・SLD(限局性学習症)の人に見られる主な特徴を紹介しますが、LD・SLD(限局性学習症)の特徴は人それぞれであり、同じ障害に分類されていても、その中の全ての特徴があてはまるわけではありません。また、他の発達障害がある人は、その特徴が合わさって出ることもあります。
読字不全・読みの困難(ディスレクシア)
読む能力に困難がある読字不全は、LD・SLD(限局性学習症)と診断された人の中で一番多く見られる症状であり、別名でディスレクシア(dyslexia)と呼びます。欧米では約10~20%の人がこの症状があると言われています。ディスレクシアは、ギリシャ語で「読むのが困難」という意味です。
読字不全があると、結果として文字を書くことにも困難を感じる場合が多いため、読み書き障害と呼ばれることもあります。
読字不全の人の中には「見た文字を音にするのが苦手」という症状があります。その原因は、情報を伝達し処理する脳の機能がスムーズに働いていないことだと考えられています。文字の見え方にも特徴があり、文字がぼやける、黒いかたまりになっている、逆さまに見える、図形に見えるなど違った見え方になってしまい、認知の仕方が異なります。
また音韻認識が弱く、ひらがなやカタカナのひとつずつは理解していても、漢字(単語)になると理解できなくなってしまうこともあります。漢字の音読みと訓読みの使い分けができなかったり、単語や文節の途中で区切った読み方をするなど、変わった読み方をしてしまいます。
【読字不全の特徴】
・形態の似た字である「わ」と「ね」、「シ」と「ツ」などを理解できない
・小さい文字「っ」「ゃ」「ょ」を認識できない
・文章を読んでいると、どこを読んでいるのかわからなくなる
・飛ばし読み、適当読みをするなど文章をスムーズに読めず、読み方に特徴がある
・音声にするなど耳から情報は理解しやすい場合が多い など
読字不全があると、結果として文字を書くことにも困難を感じる場合が多いため、読み書き障害と呼ばれることもあります。
読字不全の人の中には「見た文字を音にするのが苦手」という症状があります。その原因は、情報を伝達し処理する脳の機能がスムーズに働いていないことだと考えられています。文字の見え方にも特徴があり、文字がぼやける、黒いかたまりになっている、逆さまに見える、図形に見えるなど違った見え方になってしまい、認知の仕方が異なります。
また音韻認識が弱く、ひらがなやカタカナのひとつずつは理解していても、漢字(単語)になると理解できなくなってしまうこともあります。漢字の音読みと訓読みの使い分けができなかったり、単語や文節の途中で区切った読み方をするなど、変わった読み方をしてしまいます。
【読字不全の特徴】
・形態の似た字である「わ」と「ね」、「シ」と「ツ」などを理解できない
・小さい文字「っ」「ゃ」「ょ」を認識できない
・文章を読んでいると、どこを読んでいるのかわからなくなる
・飛ばし読み、適当読みをするなど文章をスムーズに読めず、読み方に特徴がある
・音声にするなど耳から情報は理解しやすい場合が多い など
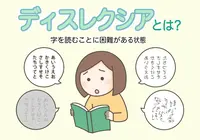
ディスレクシア(読字不全)とは?症状の特徴や生活での困りごとは?

失読症について、文字が読めなくなる原因や詳しい症状や治療法を解説、失読症とディスレクシアとの違いも
書字表出不全・書きの困難(ディスグラフィア)
「文字が書けない」「書いてある文字を写せない」などの書く能力に困難があるLD・SLD(限局性学習症)を書字表出不全・ディスグラフィア(dysgraphia)と呼びます。文字が読めるのにもかかわらず書けない場合も書字障害に分類されます。
書字表出不全の人は、自分では文字を正確に書いているつもりなのに鏡文字になってしまうなど、文字を書くという動作が苦手です。原因としては、脳内で身体に指示を出し手を動かすという伝達機能がうまくいっていないからだという説が有力です。そのため、文字が書けなかったり、文字を書く速度が遅くなってしまうのです。
【書字表出不全の特徴】
・鏡文字や雰囲気で「勝手文字」を書く
・誤字脱字や書き順の間違いが多い
・黒板やプリントの字が書き写せない、時間がかかる
・漢字が苦手で、覚えられない
・文字の形や大きさがバラバラになったり、マス目からはみ出したりする など
書字表出不全の人は、自分では文字を正確に書いているつもりなのに鏡文字になってしまうなど、文字を書くという動作が苦手です。原因としては、脳内で身体に指示を出し手を動かすという伝達機能がうまくいっていないからだという説が有力です。そのため、文字が書けなかったり、文字を書く速度が遅くなってしまうのです。
【書字表出不全の特徴】
・鏡文字や雰囲気で「勝手文字」を書く
・誤字脱字や書き順の間違いが多い
・黒板やプリントの字が書き写せない、時間がかかる
・漢字が苦手で、覚えられない
・文字の形や大きさがバラバラになったり、マス目からはみ出したりする など

「書くのが苦手」はディスグラフィア(書字表出不全)かも?症状、原因、困りごと、対処法まとめ【専門家監修】
算数不全・算数、推論の困難(ディスカリキュリア)
数字や数式の扱いや、考えて答えにたどり着く推論が苦手なLD・SLD(限局性学習症)を算数不全・ディスカリキュリア(dyscalculia)と呼びます。数字に関する能力にのみ障害がある人が多いため、算数の学習を始めてから発見される場合がほとんどです。
「1」「2」「3」などの基本的な数字や、「x」「+」などの計算式で使う記号を認識することに困難をもっています。算数不全の人は数字そのものの概念、規則性、推論が必要な図形の領域を認識するのが難しいです。また、視覚認知の機能が弱く、数字を揃えて書く、バランスを考える、文字間の距離感を取るなどが苦手です。そのため、筆算を書く際に桁がずれることも多くなります。
【算数不全の特徴】
・簡単な数字、記号を理解しにくい
・繰り上げ、繰り下げができない
・数の大きい、小さいがよく分からない
・文章問題が苦手、理解できない
・図形やグラフが苦手、理解できない など
「1」「2」「3」などの基本的な数字や、「x」「+」などの計算式で使う記号を認識することに困難をもっています。算数不全の人は数字そのものの概念、規則性、推論が必要な図形の領域を認識するのが難しいです。また、視覚認知の機能が弱く、数字を揃えて書く、バランスを考える、文字間の距離感を取るなどが苦手です。そのため、筆算を書く際に桁がずれることも多くなります。
【算数不全の特徴】
・簡単な数字、記号を理解しにくい
・繰り上げ、繰り下げができない
・数の大きい、小さいがよく分からない
・文章問題が苦手、理解できない
・図形やグラフが苦手、理解できない など

算数障害とは?チェックリストや症状、診断、対処法まとめ【専門家監修】
年齢別に見たLD・SLD(限局性学習症)の症状の現れ方
LD・SLD(限局性学習症)は、本格的な学習に入る小学生頃まで判断が難しい障害です。子どもの成長速度は人それぞれ。「なかなか歩かない」「全然しゃべらない」といった子どもの行動の一つ一つは気になりますが、ただ成長がゆっくりである可能性もあります。
LD・SLD(限局性学習症)の人の中にはADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの他の発達障害の併存症状がある人も多く、その場合は、乳幼児期に特徴があらわれる場合もありますが、併存がない場合は、この時期にはっきりと判断をするのは難しいと言えます。ある程度知能が育ち、行動に特徴が現れやすい学習を始める小学生頃にならないと、LD・SLD(限局性学習症)とは判断しにくいのです。
特に乳児期はLD・SLD(限局性学習症)の特徴は見分けにくいといえます。他の発達障害の特徴として、抱っこされるのを嫌がる、視線を合わせない、言葉を真似する行為が見られないなどの症状がみられるなど、他の発達障害の症状を目安にし、LD・SLD(限局性学習症)の確実な診断は学習を始める年齢以降にするしかありません。
以下では年齢別に見られるLD・SLD(限局性学習症)の特徴を紹介します。幼児期の目安もあくまで他の発達障害を併存している場合です。
LD・SLD(限局性学習症)の人の中にはADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの他の発達障害の併存症状がある人も多く、その場合は、乳幼児期に特徴があらわれる場合もありますが、併存がない場合は、この時期にはっきりと判断をするのは難しいと言えます。ある程度知能が育ち、行動に特徴が現れやすい学習を始める小学生頃にならないと、LD・SLD(限局性学習症)とは判断しにくいのです。
特に乳児期はLD・SLD(限局性学習症)の特徴は見分けにくいといえます。他の発達障害の特徴として、抱っこされるのを嫌がる、視線を合わせない、言葉を真似する行為が見られないなどの症状がみられるなど、他の発達障害の症状を目安にし、LD・SLD(限局性学習症)の確実な診断は学習を始める年齢以降にするしかありません。
以下では年齢別に見られるLD・SLD(限局性学習症)の特徴を紹介します。幼児期の目安もあくまで他の発達障害を併存している場合です。
幼児期
就学前なのでLD・SLD(限局性学習症)の特徴はまだ現れにくいですが、この頃から子どもは言葉を話し始めたり、学習を始めます。少しずつLD・SLD(限局性学習症)の子どもの多くが持つ特徴が見えてきます。
【幼児のLD・SLD(限局性学習症)の特徴】
・文字に関心が薄い
・単語の発音を正確に言えないことがある
・歌の歌詞がなかなか覚えられない
・文字を書くことを嫌がる、または関心がない など
【幼児のLD・SLD(限局性学習症)の特徴】
・文字に関心が薄い
・単語の発音を正確に言えないことがある
・歌の歌詞がなかなか覚えられない
・文字を書くことを嫌がる、または関心がない など
小学生(6歳〜12歳)
小学生になると本格的に学習が始まります。勉強において特定の科目が苦手な場合や読み書きに困難がある場合、LD・SLD(限局性学習症)の可能性があります。同年代の子どもと比べて学習の習得が著しく遅い場合、学校の先生や専門機関で相談してみることをおすすめします。ここからは就学期に入るため、「読字不全」、「書字表出不全」、「算数不全」ごとに特徴を分けて書いていきます。
【小学生のLD・SLD(限局性学習症)の特徴】
・授業を真面目に聞いていても勉強が苦手、ついていけない など
■読字不全
・ひらがな・漢字が読めない
・たどり読み・推測読みになってしまう
・行を飛ばして読んでしまう
・文章を読むのを嫌がる など
■書字表出不全
・うまく文字を書くことができない(線を抜かしたり、鏡文字を書いてしまう)
・板書ができない、時間がかかる
・行やマス目からのはみ出しが大きい
・文字を書くのを嫌がる など
■算数不全
・数が数えられない、とばして数えてしまう
・時計が読めない、時間が分からない
・計算ができない
・筆算をするときに数字がずれて間違えてしまう
・計算を嫌がる など
【小学生のLD・SLD(限局性学習症)の特徴】
・授業を真面目に聞いていても勉強が苦手、ついていけない など
■読字不全
・ひらがな・漢字が読めない
・たどり読み・推測読みになってしまう
・行を飛ばして読んでしまう
・文章を読むのを嫌がる など
■書字表出不全
・うまく文字を書くことができない(線を抜かしたり、鏡文字を書いてしまう)
・板書ができない、時間がかかる
・行やマス目からのはみ出しが大きい
・文字を書くのを嫌がる など
■算数不全
・数が数えられない、とばして数えてしまう
・時計が読めない、時間が分からない
・計算ができない
・筆算をするときに数字がずれて間違えてしまう
・計算を嫌がる など
中高生(12歳〜18歳)
中高生になるとはっきりと学習能力の偏りが見えてきます。何かの能力が極端に低い場合には、単なるなまけや得意・不得意だとは判断せず、LD・SLD(限局性学習症)である可能性も考えましょう。英語の学習が始まると、国語にはあまり不自由しなかった子どもも、英単語の読み書きなどに極端に困難さを感じる場合もあります。
【中高生のLD・SLD(限局性学習症)の特徴】
■読字不全
・小学生で習うような漢字であっても読めない場合がある
・英語の単語が読めない など
■書字不全
・卒業作文などの長い文章がかけない
・英単語が書けない など
■算数不全
・計算はできるが、文章題が解けない
・図形関連の問題が解けない など
これらの特徴も、発達障害の併存症として現れることもあります。
【中高生のLD・SLD(限局性学習症)の特徴】
■読字不全
・小学生で習うような漢字であっても読めない場合がある
・英語の単語が読めない など
■書字不全
・卒業作文などの長い文章がかけない
・英単語が書けない など
■算数不全
・計算はできるが、文章題が解けない
・図形関連の問題が解けない など
これらの特徴も、発達障害の併存症として現れることもあります。
最近では、大人になってからLD・SLD(限局性学習症)だと診断される人も少なくありません。もし大人になってからさまざまな学習困難に直面したら、学生時代や子どもの頃を振り返ってみて、LD・SLD(限局性学習症)と疑われる特徴があった場合には、一度、発達障害者支援センターなど、専門機関に相談しましょう。また、LD・SLD(限局性学習症)以外の発達障害との併存症がある可能性も考えられます。早めに診断を受けに行きましょう。
【成人のLD・SLD(限局性学習症)の特徴】
・上司の注意を聞いてもうまく理解できず同じ失敗をする
・電話で聞きながらメモを取れない
・話がうまくまとめられず企画案を作成できない
・集団で指示されるのが苦手で会議で辛い思いをする
・レポートが書けない
・お釣りの計算や金銭管理ができない など
【成人のLD・SLD(限局性学習症)の特徴】
・上司の注意を聞いてもうまく理解できず同じ失敗をする
・電話で聞きながらメモを取れない
・話がうまくまとめられず企画案を作成できない
・集団で指示されるのが苦手で会議で辛い思いをする
・レポートが書けない
・お釣りの計算や金銭管理ができない など















