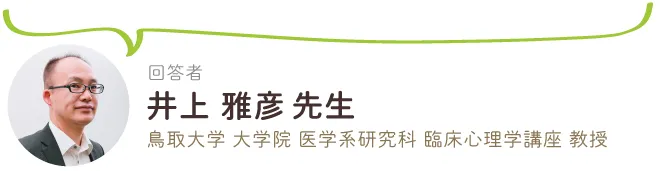授業中はサポートできないけれど、家でできることは親子でやってみる
娘は、みんなと同じ勉強方法・勉強量では、ついていけません。
小学校に通っているからと言って、 学校にすべてを任せるのではなく、 娘がみんなと同じようにやれるように…
家でも、努力でカバーできることは、 とにかくやってみる!! そういう気持ちをもって、取り組んできました。
そうするうちに、授業を少しずつ聞けるようになってきたようで、予習をすることも少しずつ減ってきました。
算数に関しては、ほとんど必要ないほどに。
言語が苦手な娘は、国語が苦手。文章を読み取って問題に答える、文章問題や、文章を自分で構成しなければならない、感想文や作文は、まだまだです。ですが、徐々に、授業でやったプリントを、先生の指示を聞きながら、自分で丸付けできるようにもなりました。
1年生も、残り僅か。
4月には、娘も2年生になります。2年生になれば、勉強もより難しくなります。
宿題やテストの結果などから、娘の学習状況を確認しつつ、担任の先生に授業の様子を細かく聞きながら、予習を調整していきたいと思っています。
小学校に通っているからと言って、 学校にすべてを任せるのではなく、 娘がみんなと同じようにやれるように…
家でも、努力でカバーできることは、 とにかくやってみる!! そういう気持ちをもって、取り組んできました。
そうするうちに、授業を少しずつ聞けるようになってきたようで、予習をすることも少しずつ減ってきました。
算数に関しては、ほとんど必要ないほどに。
言語が苦手な娘は、国語が苦手。文章を読み取って問題に答える、文章問題や、文章を自分で構成しなければならない、感想文や作文は、まだまだです。ですが、徐々に、授業でやったプリントを、先生の指示を聞きながら、自分で丸付けできるようにもなりました。
1年生も、残り僅か。
4月には、娘も2年生になります。2年生になれば、勉強もより難しくなります。
宿題やテストの結果などから、娘の学習状況を確認しつつ、担任の先生に授業の様子を細かく聞きながら、予習を調整していきたいと思っています。
発達障害のある子どもが勉強についていけない……。どうすればいい?
勉強についていけないということに関しては、個々によってさまざまな状態の違いがありますので、一概にこれだけやればいいというような特効薬はありませんが、SAKURAさんのように予習をすることで、見通しが自信が得られ授業中の活動に集中できるということも一つになると思います。あるいは、字を書くことや計算など特定の学習活動が苦手な場合は、その活動の基礎となるスキル、例えば指先の巧緻性や視覚認知、記憶、数量概念などのどこにつまづきがあるのかをアセスメントし、本人にあったプログラムを作っていくことが必要となります。授業に参加するという活動を支援するには、個人の学力や努力だけでなく、授業中の声がけや席の位置、教材などに対して合理的配慮を行っていくことも含まれると思います。
(監修:井上先生より)
不注意や不安、やる気のなさなどが授業参加に影響している場合、SAKURAさんのように予習によって自信をつけたり予測性をあげたりすることはとても有効だと思います。コラムから、家庭での協同作戦のような感覚でお母さんと楽しみながら取り組まれたことが想像できます。自分の子どもに対して、追い込まれる感じでなく、勉強が好きになるよう、褒めながら教えていくことはとても難しいことだと思いますが、これが成功につながったのではないかと思います。
不注意や不安、やる気のなさなどが授業参加に影響している場合、SAKURAさんのように予習によって自信をつけたり予測性をあげたりすることはとても有効だと思います。コラムから、家庭での協同作戦のような感覚でお母さんと楽しみながら取り組まれたことが想像できます。自分の子どもに対して、追い込まれる感じでなく、勉強が好きになるよう、褒めながら教えていくことはとても難しいことだと思いますが、これが成功につながったのではないかと思います。

期待と不安の授業参観!広汎性発達障害の娘、学校生活の実態やいかに!?

授業中にぐらぐら揺れる…「常同行動」の理由を息子に聞いてみた

ASD小6息子の宿題事情。「機嫌が良くても悪くても手が止まる」問題の理由と対策
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています