幼稚園や保育園で行き渋り、集団行動できない、お友達に手が出る…対策を専門家が回答!
ライター:発達ナビ編集部
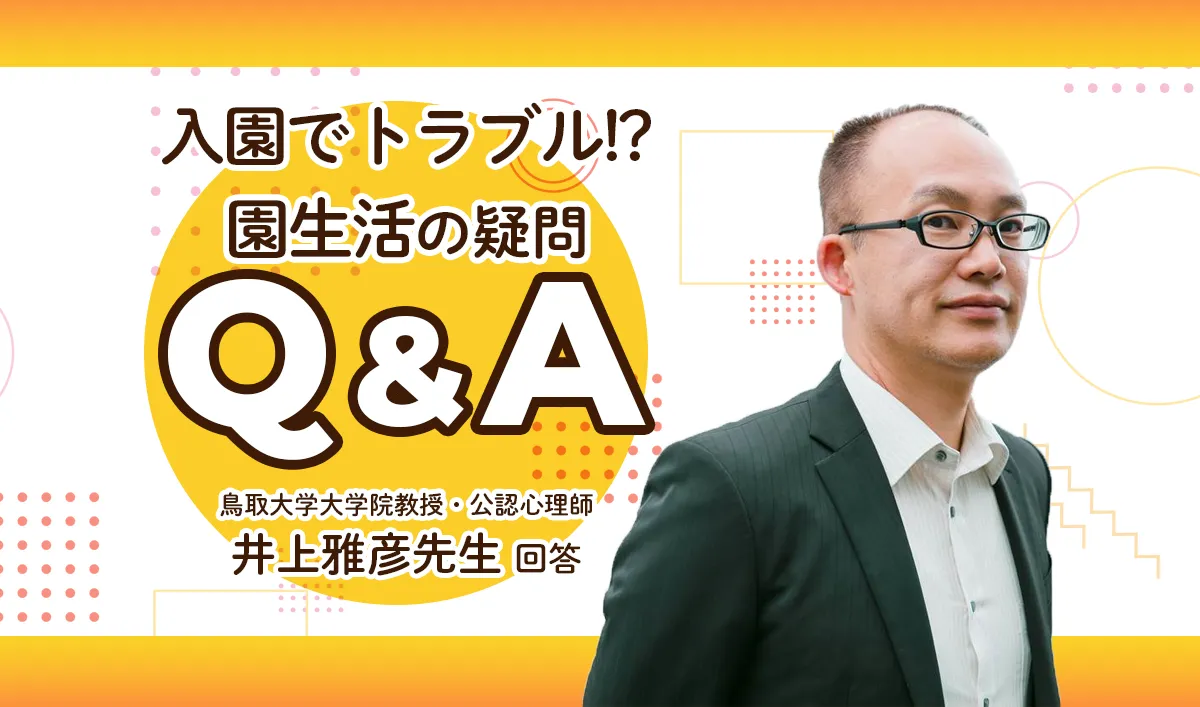
Upload By 発達ナビ編集部
この春からお子さんが幼稚園や保育園に入園した方も多いのではないでしょうか?登園を嫌がる、園での活動に参加できないなど、園生活に関するお悩みが多く聞かれる時期です。このコラムでは、園生活での困りごとやお悩みについて、鳥取大学大学院教授で発達障害を専門とする井上雅彦先生が分かりやすく教えてくれます。(取材/LITALICO発達ナビ編集部)

監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
入園でトラブル発生!?園への行き渋り、園での活動に参加できない…園生活の困りごとを紹介
発達ナビのQ&Aコーナーは、子育てに関する疑問や知りたいことなどを気軽に質問し相談し合える場所です。幼稚園や保育園での困りごとやお悩みも多く寄せられていますので、ここで一部をご紹介します。
4歳児の暴言暴力の相談です。
1歳半〜3歳過ぎまで癇癪が酷く療育に通ってます。癇癪は一時落ち着き、入園後は集団行動も問題なく、お友達もできて楽しく通っていました。3学期になり、家では怒りやすく行き渋りが酷くなり癇癪も再発しています。上手にできていた切り替えもできなくなりました。
息子はASD 軽度知的障害で、普段は週4幼稚園、週1で市の療育園と民間療育に通っています。
この生活が始まって約一年、息子の成長も多く感じましたが、同時に癇癪や他害自害も増え、このまま年中に進級して良いのか、療育園のみに変える方がよいのではと悩むようになりました。
2歳7ヶ月の娘がいます。新生児期よりなかなか寝付けずとても育てにくさを感じています。
言葉や身体の発達は遅れの指摘はないですが、むしろ流暢、喋りすぎる、こだわり、癇癪や衝動、多動などがあります。抱っこはツイストして解除、手繋ぎは座り込みや地面と同化してしまうタイプです(中略)基本的に朝車から降りて10m先の園玄関まで手を繋げません。帰りが特に手強く本当に困っており、玄関でさようならしてから車に乗るまで平均30分かかります。最大1時間かかったこともあります。ようやく車に乗ったあとはチャイルドシートに乗せるのに5〜10分泣き叫びプロレスのような状態です。
登園渋り、癇癪、他害、集団行動が苦手……どうすれば?園生活の悩みやギモンに専門家が回答!
幼稚園や保育園に行きたがらない、思い通りにならないと癇癪を起こす、お友達を叩いたり物を壊したりする、先生のお話を聞けないなど、園生活ではさまざまな困りごとが起こりがちです。特に、入園したばかりのお子さんにとっては、初めての集団生活に戸惑いや不安があることでしょう。
ここでは園生活での悩みやギモンについて、鳥取大学大学院教授で発達障害を専門とする井上雅彦先生にご回答いただきました。
ここでは園生活での悩みやギモンについて、鳥取大学大学院教授で発達障害を専門とする井上雅彦先生にご回答いただきました。
毎朝激しい登園渋り……休ませてもいいの?
Q:年少の男の子です。小さい時からこだわりが強い傾向がありました。幼稚園に入りましたが、毎朝登園時には激しく泣き、園に行きたがりません。こんな時は休ませてもよいのでしょうか?多少無理をしてでも行ったほうがいいのか、判断に悩んでいます。
A:登園時に泣いたり拒否したりされると親御さんもつらくなるかと思います。登園させても子どもと離れられないこともあるかもしれません。まず園の中の環境が苦手なのか、あるいは親御さんと離れることが苦手なのかなど、その原因に目を向けていく必要があるかと思います。
登園時の工夫としては、お気に入りのグッズを持っていく、園に行ったらすぐに好きな活動ができるようにしておくなどが考えられます。登園して好きな活動ができるようになると、登園時の抵抗は弱くなると思いますが、親と離れられる程度の好きな活動が見つからない場合、まずは親同伴で過ごすことから始め、少しずつ一人遊びや先生との遊びができるようにして徐々に離れていくなど、スモールステップで進めていくとよいでしょう。
登園時の工夫としては、お気に入りのグッズを持っていく、園に行ったらすぐに好きな活動ができるようにしておくなどが考えられます。登園して好きな活動ができるようになると、登園時の抵抗は弱くなると思いますが、親と離れられる程度の好きな活動が見つからない場合、まずは親同伴で過ごすことから始め、少しずつ一人遊びや先生との遊びができるようにして徐々に離れていくなど、スモールステップで進めていくとよいでしょう。
園での癇癪がひどく先生から連日電話……どうすればいい?
Q:活動の切り替えが苦手な年少の娘がいます。園でも思い通りにならないと泣いて癇癪を起こすので、先生から連日のように電話があり、精神的に参ってしまいました。このような時、どう対応すればよいのでしょうか?
A:癇癪の原因にはさまざまなものが考えられます。何かしたいことができなかったり、好きなことをやめさせたりする場合、あるいは嫌な刺激があったり体調が悪い場合などに癇癪が起こりやすくなります。
このケースでは、思い通りにならないという場面を具体的にし、環境を調整することで、その原因を取り除いたり、癇癪以外で意思を伝える方法を教えていくことが大切です。園の先生だけで対応できない場合は、巡回相談など外部の専門家を活用していくのも一つの手段ではないかと思います。
このケースでは、思い通りにならないという場面を具体的にし、環境を調整することで、その原因を取り除いたり、癇癪以外で意思を伝える方法を教えていくことが大切です。園の先生だけで対応できない場合は、巡回相談など外部の専門家を活用していくのも一つの手段ではないかと思います。
園で他害……手が出る子どもへの対応方法は?
Q:年中の男の子です。ことばが遅く、 気持ちを伝えることができないせいか、お友達を叩いたり、噛んでしまったりすることがあります。やってはいけないことだと家でも言い聞かせてはいますが、なかなか改善しません。すぐに手が出てしまう子どもへの対応方法はあるでしょうか。
A:まず、トラブルが起こらないような環境調整を工夫していく必要があります。例えば、スケジュールやルールを視覚的に示したり、遊具の与え方を工夫するなどです。また、やってはいけないことだけではなく、気持ちを伝えるための手段を教えていくことが大切です。ことばが表出できるお子さんにはことばで、ことばは難しいが動作の模倣ができそうなお子さんには身振りやサインで表現できるように教えていきましょう。
集団行動が苦手な理由は?どうしたらできるようになる?
Q:保育園に通っている年少の男の子です。教室から出て行ってしまう、先生の話を聞けない、一斉指示が通らないといった指摘を受けました。家では特に困りごとがなかったので驚きましたが、集団行動が苦手な理由はどんなことが考えられるでしょうか?どうしたら集団行動ができるようになるのでしょうか?
A:集団行動が苦手な理由は複数考えられます。例えば、自分の興味関心や好きなもの、マイルールや順番などに対するこだわりが強いことなどがあげられます。
また、不注意(注意がそれやすく集中しにくい)や、多動性や衝動性といった特性が関係している場合もあります。ほかにも、指示が理解できていない可能性もあるかもしれません。さまざまな苦手な理由について園の先生と話し合い、集団活動に子どもの好きな活動を入れる・役割を与えるなど、あてはまる原因を探りそれに沿った工夫をすることで、活動参加がしやすくなると思います。
また、不注意(注意がそれやすく集中しにくい)や、多動性や衝動性といった特性が関係している場合もあります。ほかにも、指示が理解できていない可能性もあるかもしれません。さまざまな苦手な理由について園の先生と話し合い、集団活動に子どもの好きな活動を入れる・役割を与えるなど、あてはまる原因を探りそれに沿った工夫をすることで、活動参加がしやすくなると思います。
もしかして発達障害?ASDやADHDなど、発達障害のある子どもの特徴
「園での様子を見ると、ほかの子どもとわが子は何かが違うような気がする……」「もしかして、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)など、発達障害があるのではないか?」と考えている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
まずは一つひとつの行動の原因に目を向け、子どもの視点に立って、苦手な環境や対応を工夫してみましょう。また、不適切な行動だけに目を向けるのではなく、できていることを認めたり褒めていくことで、行動全体が変わってくることもあります。園の先生や巡回相談の先生と話し合いながら、工夫に取り組んでいきましょう。
それでも多くの困難が生じている場合、発達障害などの相談が可能な機関に相談に行かれることをお勧めします。
発達障害の特性を以下に示します。
ASD(自閉スペクトラム症)は、「社会的なコミュニケーションの困難さ」「限定された行動や興味、反復行動」といった特性が幼少期からみられ、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。ASD(自閉スペクトラム症)の症状の表れ方には個人差がありますが、幼児期には以下のような行動がみられることがあります。
・お気に入りのおもちゃをひたすら並べる
・くるくるまわるものをずっと見ている
・水遊びが大好きで始めるとやめられない
・おもちゃなどを使う順番を待てない
・決まったおもちゃで遊びたがる
・道順が違うとパニックになる
・活動の切り替えが難しい
・マイルールや勝ち負けにこだわる
など
※上記は一例です
ADHD(注意欠如多動症)は、「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性により、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。特性の表れ方には個人差がありますが、主に、多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプの3つに分けられます。ADHD(注意欠如多動症)の特性がはっきりしてくるのは早くても2歳頃からと言われていますが、幼児期には以下のような行動がみられることがあります。
・物事に集中できず、忘れっぽい
・落ち着きがなく、じっとしていられない
・かんしゃくを起こすことが多い
・ものを壊したり、乱暴な遊びを好む
など
※上記は一例です
しかしながら、これらの行動は幼稚園や保育園に通う年頃の子どもにはよく見られるため、このような行動をとるからといって、必ずしも発達障害があると判断することはできません。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)などの診断は医師によってなされます。
お子さんの発達に不安があったり悩んだりしている場合、まずは発達相談などが可能な専門機関に相談されるとよいでしょう。
まずは一つひとつの行動の原因に目を向け、子どもの視点に立って、苦手な環境や対応を工夫してみましょう。また、不適切な行動だけに目を向けるのではなく、できていることを認めたり褒めていくことで、行動全体が変わってくることもあります。園の先生や巡回相談の先生と話し合いながら、工夫に取り組んでいきましょう。
それでも多くの困難が生じている場合、発達障害などの相談が可能な機関に相談に行かれることをお勧めします。
発達障害の特性を以下に示します。
ASD(自閉スペクトラム症)は、「社会的なコミュニケーションの困難さ」「限定された行動や興味、反復行動」といった特性が幼少期からみられ、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。ASD(自閉スペクトラム症)の症状の表れ方には個人差がありますが、幼児期には以下のような行動がみられることがあります。
・お気に入りのおもちゃをひたすら並べる
・くるくるまわるものをずっと見ている
・水遊びが大好きで始めるとやめられない
・おもちゃなどを使う順番を待てない
・決まったおもちゃで遊びたがる
・道順が違うとパニックになる
・活動の切り替えが難しい
・マイルールや勝ち負けにこだわる
など
※上記は一例です
ADHD(注意欠如多動症)は、「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性により、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。特性の表れ方には個人差がありますが、主に、多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプの3つに分けられます。ADHD(注意欠如多動症)の特性がはっきりしてくるのは早くても2歳頃からと言われていますが、幼児期には以下のような行動がみられることがあります。
・物事に集中できず、忘れっぽい
・落ち着きがなく、じっとしていられない
・かんしゃくを起こすことが多い
・ものを壊したり、乱暴な遊びを好む
など
※上記は一例です
しかしながら、これらの行動は幼稚園や保育園に通う年頃の子どもにはよく見られるため、このような行動をとるからといって、必ずしも発達障害があると判断することはできません。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)などの診断は医師によってなされます。
お子さんの発達に不安があったり悩んだりしている場合、まずは発達相談などが可能な専門機関に相談されるとよいでしょう。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています



















