特性のある子どもの進学先は?定期テスト、受験…実際どうだった?発達ナビの就学大調査【小学校高学年・中高生編】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
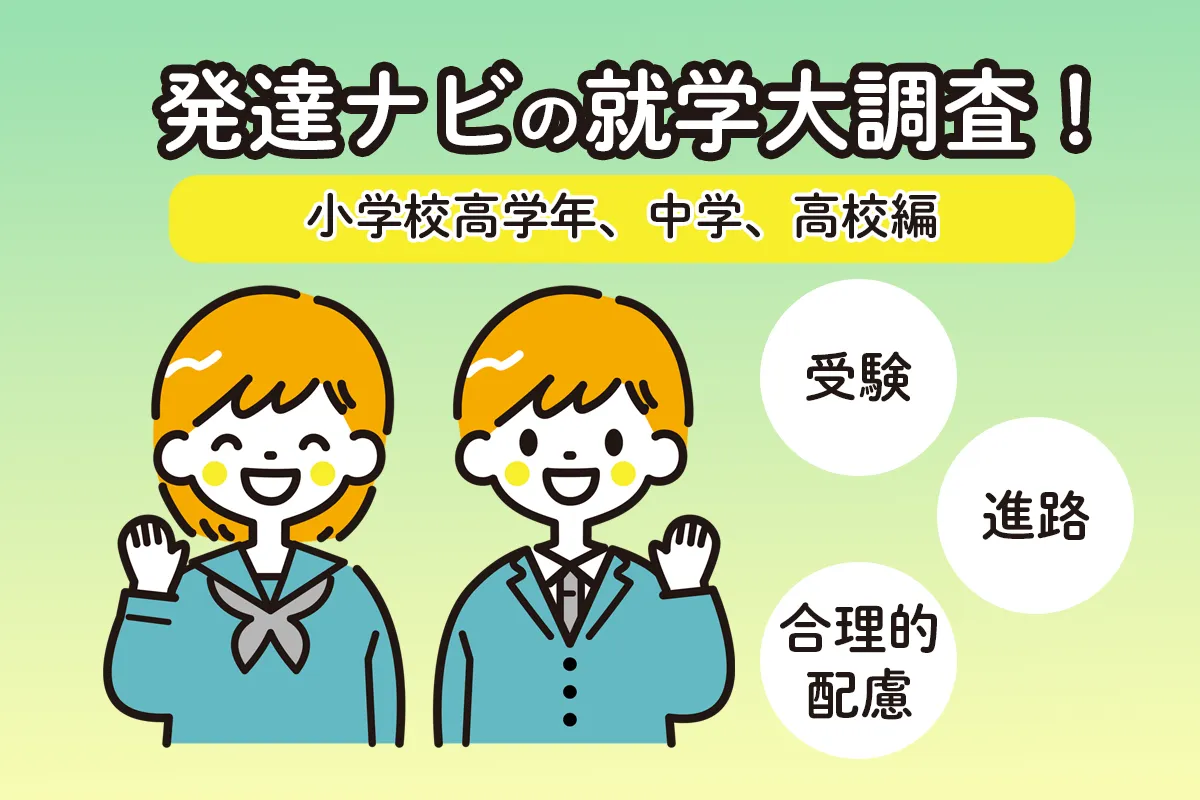
Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
2024年12月20日から2025年2月28日に、LITALICO発達ナビでは「就学・進学アンケート」を行い、発達障害のある子どもの保護者283名の声が寄せられました。アンケートへのたくさんのご回答、ありがとうございました。 今回は「小学校高学年、中学、高校編」として発達障害や特性のあるお子さんの選んだ進路、受験、進路先の合理的配慮などなど……アンケートの回答と併せて「就学・進学」にまつわる質問や思いなどもご紹介いたします。

監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
就学・進路の大調査!発達特性のある子どもの中高進学先、受験の割合は?【小学校高学年、中学、高校編】
LITALICO発達ナビにて行った「就学・進学」アンケート。小学校高学年、中学生、高校生の結果は……
2024年12月20日から2025年2月28日に、LITALICO発達ナビでは「就学・進学アンケート」を行い、発達障害のある子どもの保護者283名の声が寄せられました。アンケートへのたくさんのご回答、ありがとうございました。
2022年の文部科学省の調査によると、通常学級に通っている中で特別な支援が必要だと考えられるお子さんの割合は、小学校・中学校では8.8%、高等学校では2.2%という結果になっています。
2022年の文部科学省の調査によると、通常学級に通っている中で特別な支援が必要だと考えられるお子さんの割合は、小学校・中学校では8.8%、高等学校では2.2%という結果になっています。
このコラムでは発達障害や特性のあるお子さんの思春期での困りやトラブル、悩み、受験についてや合理的配慮など、アンケートの回答と併せて「就学・進学」にまつわる質問や思いなどもご紹介いたします。
今回は「小学校高学年(4.5.6年)、中学、高校編」のアンケート結果を紹介します。気になる中学・高校受験の割合についてや進学先の選び方など皆さんの参考にもなるはずです。
回答者や回答者のお子さんの情報については「未就学・小学校低学年編」で公開中です。こちらもぜひ合わせてご覧ください。
<調査対象について>
「LITALICO発達ナビ」コラムや会員へのメールから、アンケートフォームにて回答いただいた発達障害の子どもをもつ保護者:283名の回答を集計しました。(調査期間:2024年12月20日から2025年2月28日)
※設問によっては283名全員が回答していないもの、複数回答可のものがあります。
※調査結果の構成割合は四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。
今回は「小学校高学年(4.5.6年)、中学、高校編」のアンケート結果を紹介します。気になる中学・高校受験の割合についてや進学先の選び方など皆さんの参考にもなるはずです。
回答者や回答者のお子さんの情報については「未就学・小学校低学年編」で公開中です。こちらもぜひ合わせてご覧ください。
<調査対象について>
「LITALICO発達ナビ」コラムや会員へのメールから、アンケートフォームにて回答いただいた発達障害の子どもをもつ保護者:283名の回答を集計しました。(調査期間:2024年12月20日から2025年2月28日)
※設問によっては283名全員が回答していないもの、複数回答可のものがあります。
※調査結果の構成割合は四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

発達ナビの就学大調査!就学相談の時期、在籍クラス、合理的配慮…実体験エピソードも満載【未就学・小学校低学年編】
高学年になって振り返る……就学先は正解だった?合理的配慮についてのエピソードなども【小4以上のお子さんのいらっしゃる方へのアンケート】
ここからは小学校4年生以上のお子さんのいる保護者の方の回答とコメントをピックアップしてご紹介します。
小学校の在籍クラスを教えてください。
小学校4年生以上のお子さんの在籍クラスは通常学級が35%と一番多い結果となりました。その後自閉症・情緒障害特別支援学級(22%)、通常学級+通級指導教室(22%)、知的障害特別支援学級(12%)、特別支援学校(5%)と続きます。高学年になり転籍を考えるお子さんも多いのではないでしょうか。
決めた就学先は子どもに合っていたと感じましたか?
実際に決めた就学先については合っていたと感じた方が64%と一番多い結果となりました。どちらともいえない方は26%、合っていなかったと感じた方は7%でした。特別支援学級の縦割りクラスに支えられることもある一方で高学年になり同級生との差に悩むお子さんもいらっしゃるようです。
「合っていた」「合っていなかった」の理由を教えてください
アンケートに寄せられたコメントをご紹介します。
・合っていたと感じる(知的障害特別支援学級在籍)
入学当時は特別支援学級は1クラスしかなく、1~6年生まで全員の合同クラスでした。九九を覚えたり、宿泊行事があったり、それぞれの運動会の過ごし方など、小学校6年間の学校生活を、1年生のときに身近に見知ることができたのが、よい「予告」になったと思います。また、親としても、頼もしい高学年の先輩をこの目で見られたことは、大変心の支えになりました。(以下略)
・どちらとも言えない(知的障害特別支援学級在籍)
先生が学年が上がる度に変わるが、引き継ぎができていないので、子ども自身が先生のやり方に慣れないといけないので、苦労する。
・合っていたと感じる(知的障害特別支援学級在籍)
入学当時は特別支援学級は1クラスしかなく、1~6年生まで全員の合同クラスでした。九九を覚えたり、宿泊行事があったり、それぞれの運動会の過ごし方など、小学校6年間の学校生活を、1年生のときに身近に見知ることができたのが、よい「予告」になったと思います。また、親としても、頼もしい高学年の先輩をこの目で見られたことは、大変心の支えになりました。(以下略)
・どちらとも言えない(知的障害特別支援学級在籍)
先生が学年が上がる度に変わるが、引き継ぎができていないので、子ども自身が先生のやり方に慣れないといけないので、苦労する。
就学先の支援や合理的配慮に満足していますか?
就学先の支援や合理的配慮に満足をしている(22%)、おおむね満足している(47%)という結果となり、合わせて69%の方が満足をされていると回答しています。しかし、あまり満足していない(17%)、不満がある(6%)という方もいらっしゃいます。学年が上がるにつれて悩みも多様化してきますので、そのお子さんに合った支援が望まれます。
就学後のエピソード(手厚さ、合理的配慮内容、困ったことなども)など教えてください
・満足している(通常学級)
【中学年で困ったこと】
小3からは徐々に勉強で困ることが増えてきました。
算数はたし算・かけ算は何とかなるが、引き算・わり算の理解に苦戦。桁の概念の理解が弱く、計算問題は扱う数字が1000を超えると扱いが分からなくなりました。国語は小4の終わり頃に漢字を頑張らせることを捨てて、将来に向けてタイピングの練習をする方向に切り替えました。
【高学年(小5)で困ったこと】
算数は九九を覚えてもすぐ抜けていく対策が必要でした。図形問題は計算が比較的簡単なので得意ですが、通分と約分が必要な分数同士の計算、割る数に小数点を含むわり算の筆算など、手順が多く目線の複雑な移動が必要な問題は、途中で迷子になってどうしたらいいのか分からなくなりました。国語は、漢字を捨てたことで逆に安定したようです。
生活面では、友だちと夜遅くまでオンラインゲームで遊んでしまうことで入眠の困難さが増すなど、タイムスケジュールの乱れからくる情緒の不安定さ・気持ちの切り替えの鈍さが目に付くようになってきました。
・満足している(自閉症・情緒障害特別支援学級)
交流学級での失敗を、なぜダメだったか、どうすれば良かったのか等、特別支援学級で丁寧に教えてもらえた。学習もマンツーマンで丁寧に教えてもらえたので良かった。
・おおむね満足している(通常学級)
3年生から申し出て、なかなか思うような支援が受けられなかったが、5年生の途中から、専科の先生により、板書がタブレットにテストの時は補助がつくなどしてもらっていて、過ごしやすくなっていると思う。
※特定の就学先によって困り事が生じたり解決したりするわけではなく、あくまで子どもの状態と環境によって変わりますので注意が必要です。
【中学年で困ったこと】
小3からは徐々に勉強で困ることが増えてきました。
算数はたし算・かけ算は何とかなるが、引き算・わり算の理解に苦戦。桁の概念の理解が弱く、計算問題は扱う数字が1000を超えると扱いが分からなくなりました。国語は小4の終わり頃に漢字を頑張らせることを捨てて、将来に向けてタイピングの練習をする方向に切り替えました。
【高学年(小5)で困ったこと】
算数は九九を覚えてもすぐ抜けていく対策が必要でした。図形問題は計算が比較的簡単なので得意ですが、通分と約分が必要な分数同士の計算、割る数に小数点を含むわり算の筆算など、手順が多く目線の複雑な移動が必要な問題は、途中で迷子になってどうしたらいいのか分からなくなりました。国語は、漢字を捨てたことで逆に安定したようです。
生活面では、友だちと夜遅くまでオンラインゲームで遊んでしまうことで入眠の困難さが増すなど、タイムスケジュールの乱れからくる情緒の不安定さ・気持ちの切り替えの鈍さが目に付くようになってきました。
・満足している(自閉症・情緒障害特別支援学級)
交流学級での失敗を、なぜダメだったか、どうすれば良かったのか等、特別支援学級で丁寧に教えてもらえた。学習もマンツーマンで丁寧に教えてもらえたので良かった。
・おおむね満足している(通常学級)
3年生から申し出て、なかなか思うような支援が受けられなかったが、5年生の途中から、専科の先生により、板書がタブレットにテストの時は補助がつくなどしてもらっていて、過ごしやすくなっていると思う。
※特定の就学先によって困り事が生じたり解決したりするわけではなく、あくまで子どもの状態と環境によって変わりますので注意が必要です。
中学校の在籍クラスは?【中学生以上のお子さんの保護者アンケート結果】
中学校の在籍クラスを教えてください。
中学の在籍クラスは通常学級が55%と半数を占める結果となりました。続いて自閉症・情緒障害特別支援学級が17%、通常学級+通級指導教室が13%、知的障害特別支援学級が10%となっています。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています



















