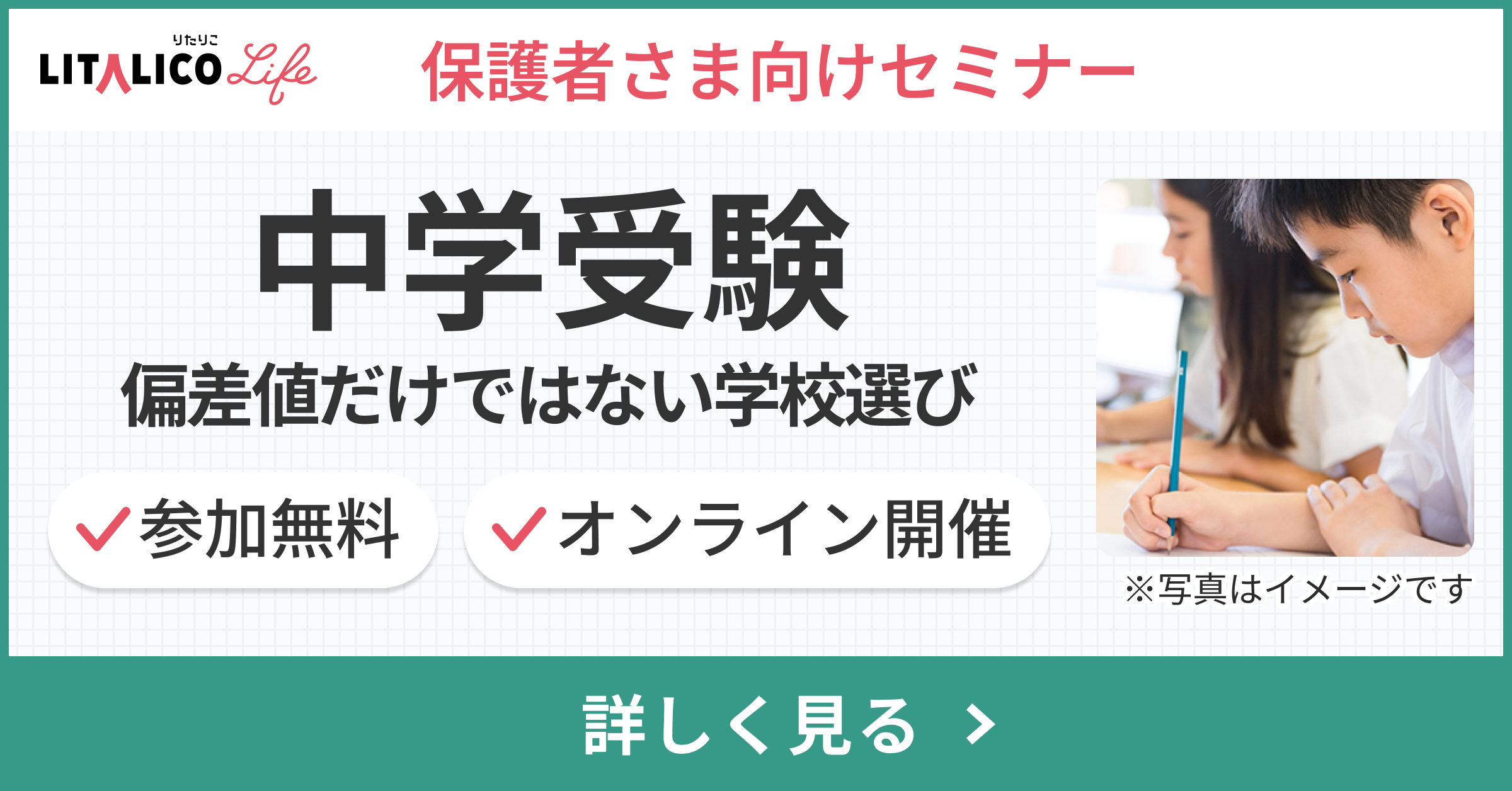小学校高学年の合理的配慮、発達障害でも受験は可能?特別支援学級だと内申点がつかないの?専門家が解説!
合理的配慮と転籍、どちらの選択がいいのか悩んでいます。
Q:小学校高学年になってきて低学年の時と違う合理的配慮の必要性を感じています。宿題やグループ学習時の配慮などをしてもらっていますが本人も勉強や周りについていけないようでつらそうです。特別支援学級への転籍も考えたほうがよいのでしょうか。
A:いきなり転籍を考えるのではなく、通級指導教室などの利用を行って、個別の学習でどの点を補完していくとよいのかをアセスメントしたうえで転籍の判断をされると良いと思います。転籍先の特別支援学級の人数やメンバー、個別のニーズにどれくらい合わせてもらえそうか、交流学級との授業との割合などによっても変わってきます。また、本人が特別支援学級を体験し、メリットを感じるかどうかも大切な要素になるでしょう。(回答:井上 雅彦先生(鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授))
A:いきなり転籍を考えるのではなく、通級指導教室などの利用を行って、個別の学習でどの点を補完していくとよいのかをアセスメントしたうえで転籍の判断をされると良いと思います。転籍先の特別支援学級の人数やメンバー、個別のニーズにどれくらい合わせてもらえそうか、交流学級との授業との割合などによっても変わってきます。また、本人が特別支援学級を体験し、メリットを感じるかどうかも大切な要素になるでしょう。(回答:井上 雅彦先生(鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授))
発達障害があっても中学や高校の受験は可能ですか?
Q:中学受験を考えていますがどのような配慮をしてもらえるのでしょうか?今後高校受験もすることを考えると学校側の迷惑にならないか不安です。
A:発達障害などの診断があれば合理的配慮を求めることで入試の際の個別的な配慮は可能になります。ただし受験前の在籍校での個別の教育支援計画の中に合理的配慮の事項が記載されていたり、テスト時などでの配慮の実績を求められることがあります。(回答:井上 雅彦先生(鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授))
A:発達障害などの診断があれば合理的配慮を求めることで入試の際の個別的な配慮は可能になります。ただし受験前の在籍校での個別の教育支援計画の中に合理的配慮の事項が記載されていたり、テスト時などでの配慮の実績を求められることがあります。(回答:井上 雅彦先生(鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授))
中学では自閉症・情緒障害特別支援学級に通っています。高校受験は不利になってしまうのでしょうか。
Q:中学では自閉症・情緒障害特別支援学級に通っています。特別支援学級だと内申点がつかないなどと聞きましたが高校受験が不利になってしまうのでしょうか。
A:障害があることや特別支援学級在籍であることによって入試が不利になることはありません。自治体や教育委員会によっても違いますが、内申書に代わる評価を行っているところもありますので在籍校や地域の教育委員会、私立であれば受験先の学校に訊ねてみてください。(回答:井上 雅彦先生(鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授))
A:障害があることや特別支援学級在籍であることによって入試が不利になることはありません。自治体や教育委員会によっても違いますが、内申書に代わる評価を行っているところもありますので在籍校や地域の教育委員会、私立であれば受験先の学校に訊ねてみてください。(回答:井上 雅彦先生(鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授))

【リアル体験談】中学受験で「学びの多様化学校(不登校特例校)」を選んだ不登校息子。メリットデメリットは?【読者92人が回答!中学進路アンケート結果も】

不登校の特別支援学校中3息子。「学校をあきらめたくない」の言葉に先生が薦めたのは…通信制高校!?

発達障害娘、公立中の特別支援学級へ。気になる内申点や卒業後の進路は?通学路チェックは親子で?【専門家によるアドバイスも】
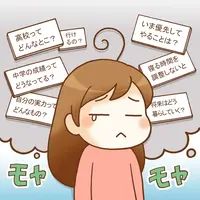
不登校のASD娘、高校受験塾へ!9月になったとたん「行きたくない」、そのワケは…

「進路どうする?」に無言…自閉症娘と悩み見つけた就労移行支援事業所、自分らしく働く道へ【読者体験談】
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
SLD(限局性学習症)
LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
SLD(限局性学習症)
LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています