気になったら遠慮せず、躊躇せず、セカンドオピニオン!
今はセカンドオピニオンを推奨している病院も多いですし、その辺を躊躇する必要は全くないと個人的には思っています。
とくに私の周りの病気や障害がある子どもの保護者は、積極的に県をまたぎ、色んな病院で診てもらっていますし、結果、良くなった、病気の原因が分かったという話もよく聞きます。
親にとったら、可愛いわが子のためには藁にもすがる気持ちですよね。
治してもらえるなら、どんなとこにも連れていってあげたいと思うのが親心だと思うのです。
ちなみに私自身の話ですが、咳が止まらず、咳喘息かと思い近所の呼吸器科に行ったら、問診のみでそんなの咳喘息なわけがないと医師に言われたのですが、その後1年経過してもよくならなかったので3駅先の評判のいい呼吸器科に行ったところ、徹底的に検査をしていただいた結果、咳喘息を通り越して、喘息(こちらのほうが咳喘息よりも重い)になってしまったのを発見してもらったのでした……。
病院の設備や医師もその病院によって違いますし、やはりセカンドオピニオンは必要だと思うのです。
とくに私の周りの病気や障害がある子どもの保護者は、積極的に県をまたぎ、色んな病院で診てもらっていますし、結果、良くなった、病気の原因が分かったという話もよく聞きます。
親にとったら、可愛いわが子のためには藁にもすがる気持ちですよね。
治してもらえるなら、どんなとこにも連れていってあげたいと思うのが親心だと思うのです。
ちなみに私自身の話ですが、咳が止まらず、咳喘息かと思い近所の呼吸器科に行ったら、問診のみでそんなの咳喘息なわけがないと医師に言われたのですが、その後1年経過してもよくならなかったので3駅先の評判のいい呼吸器科に行ったところ、徹底的に検査をしていただいた結果、咳喘息を通り越して、喘息(こちらのほうが咳喘息よりも重い)になってしまったのを発見してもらったのでした……。
病院の設備や医師もその病院によって違いますし、やはりセカンドオピニオンは必要だと思うのです。
可愛い子どものためならなおさら。
私たち親ができることであれば、なんでもしてあげたいですね。
私たち親ができることであれば、なんでもしてあげたいですね。
執筆/星きのこ
(監修:鈴木先生より)
私のクリニックでは約8%の患者さんが県外から通われています。神経発達症ともなると、きちんと診断や治療のできる病院は限られてしまいます。まして大人の神経発達症になればさらに診察できる精神科はほとんどないのが現状です。皆さん、ネットで調べて予約してきます。ダウン症であれば、本来経過を見ているこども病院の眼科がダウン症のお子さんにも慣れていて専門のはずなので、検査もできるはずなのですが……。しかし、それでも検査が困難なお子さんを受け入れてくれる病院があるだけでも親としては心強い味方になりえますね。私のクリニックでも、大学病院や神経発達症専門のクリニックから紹介されるケースも多く、可能な限り受け入れるようにしています。お子さんと相性が合えば検査や診察は可能なはずです。
(監修:鈴木先生より)
私のクリニックでは約8%の患者さんが県外から通われています。神経発達症ともなると、きちんと診断や治療のできる病院は限られてしまいます。まして大人の神経発達症になればさらに診察できる精神科はほとんどないのが現状です。皆さん、ネットで調べて予約してきます。ダウン症であれば、本来経過を見ているこども病院の眼科がダウン症のお子さんにも慣れていて専門のはずなので、検査もできるはずなのですが……。しかし、それでも検査が困難なお子さんを受け入れてくれる病院があるだけでも親としては心強い味方になりえますね。私のクリニックでも、大学病院や神経発達症専門のクリニックから紹介されるケースも多く、可能な限り受け入れるようにしています。お子さんと相性が合えば検査や診察は可能なはずです。
このコラムを書いた人の著書
きいちゃんはダウン症 完全版
小学館
Amazonで詳しく見る
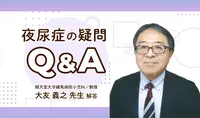
夜尿症の原因は?小学生のおねしょは病院に行くべき?/医師QA

いざ診察になると不安が強くなって泣いてしまう…そんなときに出来る工夫は?

予防接種がイヤ!発達障害息子が車道に向かって逃走!追いかけ転倒し失神した母。目覚めると息子は…/読者体験談

不登校の小4息子は解離性障害?児童精神科での違和感…追い詰められた母はセカンドオピニオンを決断して

Sponsored
発達障害の薬物療法、どのように向き合う? 薬に対する考え方、本人・周囲への伝え方ポイントまとめ【医師監修】
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

-
 1
1
- 2
















