これはこだわりだった
ついに児童精神科の診察の日がやってきました。先生に「これは強迫性障害でしょうか?」と尋ねると、「これはこだわりだね。手触りが気になって仕方ないんだね」と話してくれました。たしかに長男はとてもこだわりが強い方でしたが、このような形のこだわりもあるのだと私はとてもびっくりしました。その行為自体を無理やりやめさせようとすることよりも、そこから出てくる問題点(今回なら手荒れ)をケアしてあげることが大切だとアドバイスをもらいました。
今回は長男の行動が過剰になってしまっていることもあったのですが、何よりも私が長男を見ていてとてもしんどい旨を伝えると先生はとても親身になってくださり、長男に少量の飲み薬を落ち着くまで処方するのはどうかと提案してくれました。今まで薬は貰ったことがなかったので少し悩みましたが、何度も何度も洗う長男の姿が本当につらかったので処方してもらうことにしました。
今回は長男の行動が過剰になってしまっていることもあったのですが、何よりも私が長男を見ていてとてもしんどい旨を伝えると先生はとても親身になってくださり、長男に少量の飲み薬を落ち着くまで処方するのはどうかと提案してくれました。今まで薬は貰ったことがなかったので少し悩みましたが、何度も何度も洗う長男の姿が本当につらかったので処方してもらうことにしました。
現在の様子
薬を飲んでからしばらくして、気づいたら物洗いの行動が少し落ち着いてきたように感じました。精神科の先生とも相談して4ヶ月ほどで薬を飲むのをやめました。4年生の春から再登校し始めたのですが、学校に行き始めてからほとんど物洗いは見なくなりました。不登校と物洗いの関係性については分かりませんが、当時は本人なりにいろいろと葛藤していた時期だったのかもしれません。また、家にいる時間が長いので普段気にならないことが過剰に気になってしまったのかもしれません。
今はブロックを洗うという行為はほぼしなくなったのですが、手触りが気になるとタオルでよく拭いています。拭いたタオルをよくほったらかしにしているので洗濯かごへ入れるように毎日口うるさく言っています(笑)。よくよく考えると長男の行動には流行りのようなものもあり、一時期過剰であってもしばらくすると全くやらなくなったりすることがよくあります。食べ物にもあります。長い目で様子を見ながら今後も長男の気持ちを受け止めつつ、必要な時は医療機関を頼り、少しでも気持ちが楽になるようにサポートしていけたらと思います。
今はブロックを洗うという行為はほぼしなくなったのですが、手触りが気になるとタオルでよく拭いています。拭いたタオルをよくほったらかしにしているので洗濯かごへ入れるように毎日口うるさく言っています(笑)。よくよく考えると長男の行動には流行りのようなものもあり、一時期過剰であってもしばらくすると全くやらなくなったりすることがよくあります。食べ物にもあります。長い目で様子を見ながら今後も長男の気持ちを受け止めつつ、必要な時は医療機関を頼り、少しでも気持ちが楽になるようにサポートしていけたらと思います。
執筆/ねこじま いもみ
(監修:鈴木先生より)
洗いすぎはASD(自閉スペクトラム症)のこだわりだったり、強迫性障害だったりがあります。強迫性の場合は確認行為が多いのでブロックだけではなくスイッチの消し忘れや鍵の閉め忘れなど何度も確認するなどほかの症状も見られることがあります。また、友人から怒られることが増えたことで不登校になるお子さんが多く、今回のようなキックベースのルール変更がきっかけになっている場合以外では運動が苦手なお子さんの運動会後が多くみられています。
こだわりに関しては、こだわり保存の法則があり、一つのこだわりが減るとほかのこだわりが出てくることがあります。また、自分と同じ色の服を着せるなど他人を巻き込む「巻き込みこだわり」というのもあります。
長い目で様子を見守ってあげることも必要ですね。
洗いすぎはASD(自閉スペクトラム症)のこだわりだったり、強迫性障害だったりがあります。強迫性の場合は確認行為が多いのでブロックだけではなくスイッチの消し忘れや鍵の閉め忘れなど何度も確認するなどほかの症状も見られることがあります。また、友人から怒られることが増えたことで不登校になるお子さんが多く、今回のようなキックベースのルール変更がきっかけになっている場合以外では運動が苦手なお子さんの運動会後が多くみられています。
こだわりに関しては、こだわり保存の法則があり、一つのこだわりが減るとほかのこだわりが出てくることがあります。また、自分と同じ色の服を着せるなど他人を巻き込む「巻き込みこだわり」というのもあります。
長い目で様子を見守ってあげることも必要ですね。

「個と環境の相互作用」の視点、子どもの困りごと解決にどう役立てる?公認心理師・井上雅彦先生に聞きました
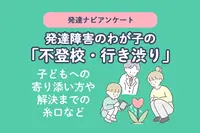
約9割が行き渋り、不登校を経験!?発達ナビのアンケート結果や実体験コラム5選

これは強迫性障害?チェックポイントや治るきっかけなど/医師QA

強迫性障害(強迫症)とは?症状や原因、治療法、相談先、周囲の対応も解説

出口の見えない自閉症息子の登校しぶり、仕事も家庭も限界に…救いになった「意外な存在」
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-
 1
1
- 2
















