きっかけは遠足!?特別支援学級の小2息子が「交流学級」を楽しめるようになるまで
ライター:プクティ

Upload By プクティ
ASD(自閉スペクトラム症)の傾向があり、小学校入学時から特別支援学級に在籍している長男。2年生になってもなかなか交流学級へ参加できずにいましたが、遠足の日をきっかけに大きな変化がありました。
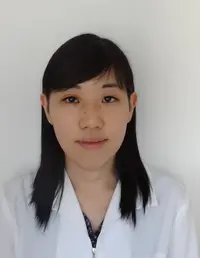
監修: 新美妙美
信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 特任助教
2003年信州大学医学部卒業。小児科医師として、小児神経、発達分野を中心に県内の病院で勤務。2010年信州大学精神科・子どものこころ診療部で研修。以降は発達障害、心身症、不登校支援の診療を大学病院及び一般病院専門外来で行っている。グループSST、ペアレントトレーニング、視覚支援を学ぶ保護者向けグループ講座を主催し、特に発達障害・不登校の親支援に力を入れている。
多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」の制作スタッフ。
交流学級に参加できないまま迎えた2年生の遠足
ASD(自閉スペクトラム症)の傾向があり、小学校入学時から特別支援学級に在籍している長男。2年生になって、クラスや担任の先生に変更がありました。進級から2ヶ月程経っても、長男は新しい環境に慣れることができず、交流学級にも行けない日が続いていました。そんなある日、2年生全員で行く遠足がありました!
1年生の時の遠足との比較
1年生の時も遠足があったのですが、特別支援学級の担任の先生が常に一緒についてくれていて、通常学級の子たちと絡むことはせず、一人で大好きな虫を探したり、お弁当も先生と一緒に食べたりして楽しんでいました。
しかし今回の遠足では、通常学級の子たちが積極的に長男に話しかけてくれて、みんなと一緒に遊んだり、お弁当を食べたりすることができました!担任の先生によると、長男は通常学級のお友だちに大人気で、みんな長男と遊びたがっていたとのことでした。そして、学校へ帰る時も、ずっと楽しそうに通常学級のお友だちとお話ししながら帰ってきたと聞いて、私もうれしい気持ちでいっぱいになりました。
学校生活での変化
その遠足をきっかけに、長男は通常学級の担任の先生とも仲良くなり、クラスで飼っている昆虫や爬虫類を観察しに、通常学級の教室へ度々行くようになりました。その結果、これまで廊下からのぞくだけだった交流学級の授業にも参加できるようになりました!
そして通常学級の教室へ行くと、たくさんのお友だちが長男のところへ来てくれて、みんなが話しかけてくれるとのことで、長男も帰宅すると「僕大人気なんだよ!」とうれしそうに教えてくれました。
特別支援学級はクラスの人数も少なく、お友だちとの関わりが少ないため、不安に感じていたところもあったのですが、遠足以降、同じ学年のお友だちがたくさんでき、交流学級への参加もできるようになりました。一時期は、このままずっと交流学級に行けないのではないか……と心配していたので、ほっとしました。きっと長男自身も、この出来事をきっかけに、交流学級が安心できる居場所になったのかな?と思います。夏休み明けも、長男がまた楽しく学校に行けることを願っています。
特別支援学級はクラスの人数も少なく、お友だちとの関わりが少ないため、不安に感じていたところもあったのですが、遠足以降、同じ学年のお友だちがたくさんでき、交流学級への参加もできるようになりました。一時期は、このままずっと交流学級に行けないのではないか……と心配していたので、ほっとしました。きっと長男自身も、この出来事をきっかけに、交流学級が安心できる居場所になったのかな?と思います。夏休み明けも、長男がまた楽しく学校に行けることを願っています。
執筆/プクティ
(監修:新美先生より)
特別支援学級に在籍する長男さんが、交流学級(※地域によっては原級、在籍学級、原籍学級などとも呼ばれる通常学級)に行きやすくなったきっかけについて、貴重なご経験を教えていただきありがとうございます。
ASD(自閉スペクトラム症)の傾向があるお子さんの中には、大人数や初めての人との関わりを負担に感じ、通常学級での活動に馴染みにくいことも少なくありません。交流学級との関係を深めることが必ずしも唯一の目標ではありませんが、多くのお友だちと関われる機会が生まれるとうれしいと感じるのも自然なことと思います。
1年生の時には、無理に交流を進めず、担任の先生が1対1で寄り添い、好きな虫探しを楽しめた経験が土台となり、2年生での遠足にも安心して参加できたのではないでしょうか。そのうえで、開放的な遠足の場でクラスメイトが積極的に声をかけ、一緒に遊ぶことができ、「楽しい」「うれしい」という体験を得られたことは大きな意味を持ちます。背景には、担任の先生がクラスの子どもたちにお子さんの好きなことや関わり方を伝えていてくれた可能性も考えられます。そうした積み重ねが、「通常学級=安心できる場所」へとつながっていったのでしょう。
発達特性をもつお子さんにとって、新しい環境や大人数の場に慣れるには段階的な関わりと「きっかけ」が必要です。学校生活では、まず無理をせずに安心を積み重ね、その次のステップで「得意なこと」「興味のあること」を介して友だちとつながることがよく見られます。これからも波はあるかもしれませんが、お子さん自身の思いを尊重しながら、楽しい体験や興味をきっかけに良い交流を重ねていけると良いですね。
(監修:新美先生より)
特別支援学級に在籍する長男さんが、交流学級(※地域によっては原級、在籍学級、原籍学級などとも呼ばれる通常学級)に行きやすくなったきっかけについて、貴重なご経験を教えていただきありがとうございます。
ASD(自閉スペクトラム症)の傾向があるお子さんの中には、大人数や初めての人との関わりを負担に感じ、通常学級での活動に馴染みにくいことも少なくありません。交流学級との関係を深めることが必ずしも唯一の目標ではありませんが、多くのお友だちと関われる機会が生まれるとうれしいと感じるのも自然なことと思います。
1年生の時には、無理に交流を進めず、担任の先生が1対1で寄り添い、好きな虫探しを楽しめた経験が土台となり、2年生での遠足にも安心して参加できたのではないでしょうか。そのうえで、開放的な遠足の場でクラスメイトが積極的に声をかけ、一緒に遊ぶことができ、「楽しい」「うれしい」という体験を得られたことは大きな意味を持ちます。背景には、担任の先生がクラスの子どもたちにお子さんの好きなことや関わり方を伝えていてくれた可能性も考えられます。そうした積み重ねが、「通常学級=安心できる場所」へとつながっていったのでしょう。
発達特性をもつお子さんにとって、新しい環境や大人数の場に慣れるには段階的な関わりと「きっかけ」が必要です。学校生活では、まず無理をせずに安心を積み重ね、その次のステップで「得意なこと」「興味のあること」を介して友だちとつながることがよく見られます。これからも波はあるかもしれませんが、お子さん自身の思いを尊重しながら、楽しい体験や興味をきっかけに良い交流を重ねていけると良いですね。

自閉症娘、小学校は特別支援学級へ。心配だった入学式、学校生活、友達関係…ありがたかった配慮は?

1日中大勢の中にいると疲れてしまう…そんなときに出来る学校での工夫は?

友だちに言い返せない…特別支援教室に通う小2息子、学校での「生き抜く術」が切なくて【臨床心理士の解説も】

周りには既にグループが…「小学校で友達つくるぞ!」幼稚園でウケた持ちネタ披露も大すべり!ASD息子が学んだ友達の輪への入り方

自閉症息子は誰にでも「マブダチ対応」!?人との距離感、空気が読めず交流学級で空回り…【専門家からのコメントも】
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています



















