正直合わないなー!と感じる人もいる、にんげんだもの
長い医療機関との付き合いの中で、医療機関は「診断される場所」ではなく、「一緒に考えてくれるパートナー」だと感じるようになりました。関わり方は成長とともに変化しますが、その時々で丁寧に向き合ってくれる先生、スタッフの皆さんに巡りあうことができ、本当に感謝しています。
その中でも、ほんのわずか、ちょっと代替で来られたりした先生の中には「ちょっと合わないな」と感じた方もいらっしゃいました。「期限を切って目標を立てて登校できるように頑張ろう」と強く促されたり、娘の話を頻繁に切り上げ「つまりこういうことが言いたいんだね?」とまとめて話を進めたりと、そういうところがあると、私たちはちょっとストレスを感じてしまうタイプです。
でも、子どもの進学や就職などの人生のステージを意識して励ましてくれる先生が悪い先生とも思いません。大人との会話のやり方を教えてくれる先生も、あとで考えたらありがたい指導だったと思う日も来るでしょう。むしろ、そういう先生のほうが良いという保護者の方もいらっしゃると思います。
娘、息子共に何度かの転院と担当変更を経験しましたが、医師の先生も病院も想像していたより個性がありました。もし今通っている医療機関が合わないかもと感じたら、ほかの医療機関に目を向けてみてもいいんじゃないかなと思います。
執筆/寺島ヒロ
(監修:鈴木先生より)
カウンセリングの基本は「聴くこと」です。親御さんがいて患児が話しづらい場合は親子別々に診察することも珍しくありません。それでもドクターとの相性が悪い場合は転院するケースもあります。
私の診察室は「チャットルーム」と名づけています。診察はもちろんですが、患者さんや親御さんからの相談がほとんどだからです。まずは雑談から入り、アイスブレークすることを心がけています。ここに出てくる先生も無理に話しかけず、その場をスルーしてくれたり、好きな絵のことに話題を換えたり、雑談のようなもので気分を落ち着かせて娘さんと向き合っていく気持ちが良かったのだと思います。ペアレントトレーニングと同じように「傾聴と承認」が重要なのです。ほかの病院から数年後に戻ってくるケースも珍しくありません。去る者追わず来る者拒まずの精神で日々診療を行っております。
カウンセリングの基本は「聴くこと」です。親御さんがいて患児が話しづらい場合は親子別々に診察することも珍しくありません。それでもドクターとの相性が悪い場合は転院するケースもあります。
私の診察室は「チャットルーム」と名づけています。診察はもちろんですが、患者さんや親御さんからの相談がほとんどだからです。まずは雑談から入り、アイスブレークすることを心がけています。ここに出てくる先生も無理に話しかけず、その場をスルーしてくれたり、好きな絵のことに話題を換えたり、雑談のようなもので気分を落ち着かせて娘さんと向き合っていく気持ちが良かったのだと思います。ペアレントトレーニングと同じように「傾聴と承認」が重要なのです。ほかの病院から数年後に戻ってくるケースも珍しくありません。去る者追わず来る者拒まずの精神で日々診療を行っております。

近づくタイムリミット…でも息子の視力をあきらめたくない!評判の病院にセカンドオピニオンを求めてみると

心療内科とは?精神科とは違うの?病院選びで大切にしたいこと、対象になる病気や治療の流れ、費用など【医師監修】
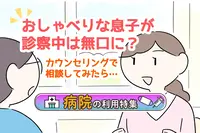
中1発達障害息子、診察室でいつも無口に…普段はおしゃべりなのになぜ?成人後の「1人で受診」に備えてできること

大げさ?と迷っていた児童精神科に障害者手帳取得を見据えて受診。ところが医師の診断は…【読者体験談】

【専門家監修】ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の違いは?こだわりはどちらの特徴?
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-
 1
1
- 2














