怒鳴り合いの日々から「怒らない子育て」へ!発達障害息子の自己肯定感は爆上がり!?高校生になった今は…
ライター:あき

Upload By あき
わが家の息子コチ丸は、小3の時にASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)と診断されています。生まれて間もない時期から、なんとなくほかの子と違うぞ?という違和感を抱きながら育てていた私。
たくさんある情報の中から、何を自分の子育てに取り入れるのが良いのか選択することは、コチ丸が大きくなった今でもとても難しい問題です。

監修: 初川久美子
臨床心理士・公認心理師
東京都公立学校スクールカウンセラー/発達研修ユニットみつばち
臨床心理士・公認心理師。早稲田大学大学院人間科学研究科修了。在学中よりスクールカウンセリングを学び、臨床心理士資格取得後よりスクールカウンセラーとして勤務。児童精神科医の三木崇弘とともに「発達研修ユニットみつばち」を結成し、教員向け・保護者向け・専門家向け研修・講演講師も行っている。都内公立教育相談室にて教育相談員兼務。
東京都公立学校スクールカウンセラー/発達研修ユニットみつばち
偶然入社した会社での仕事が子育ての教科書に!愛着関係や発達心理学を学ぶ日々。
わが家はコチ丸が保育園に入る前にすでに離婚をしていて、ひとり親家庭でした。私1人で落ち着きがないコチ丸を育てるのはなかなか大変でした。発達障害の診断がまだ出ていないグレーゾーンの時期(幼児~小学校低学年頃)は、コチ丸の成長をよその子と比べ、できないことを数えては、怒ったり喧嘩したりの連続でした。
私はコチ丸が生まれてしばらくしてから、育児関係の仕事に就きました。そこで私自身も乳幼児期の親子の愛着関係や子どもの発達について学ぶ機会がありました。おかげで、発達障害という言葉や対応の仕方も早い段階から知っていたので、コチ丸の困りごとが表れてきた時に「発達障害かもしれない」と考えられる知識を持っていたのは良かったなと思っています。しかしそんな知識はあっても実践となるとまた違うもの。やはり腹が立つときは立つのですが(笑)。
コチ丸の診断が出る頃には、私はその仕事を辞め、小学校での状況もずいぶん変わっていましたが、知識を持つということの大切さを学んでいた私は、その後も発達障害についてたくさんの本を読み漁りました。
もともと私が若い頃にうつや摂食障害で悩み、心理学を学んだことがあったり、カウンセリングを受けたりしていたので、子どもとの向き合い方を学ぶことは私にとっては楽しいことでした。また、本で読んだ知識をちゃんと実践していったら、どんな子に育つんだろう?と、もともとは苦手意識のあった子育てから、楽しみを見出すことができるようになりました。
私はコチ丸が生まれてしばらくしてから、育児関係の仕事に就きました。そこで私自身も乳幼児期の親子の愛着関係や子どもの発達について学ぶ機会がありました。おかげで、発達障害という言葉や対応の仕方も早い段階から知っていたので、コチ丸の困りごとが表れてきた時に「発達障害かもしれない」と考えられる知識を持っていたのは良かったなと思っています。しかしそんな知識はあっても実践となるとまた違うもの。やはり腹が立つときは立つのですが(笑)。
コチ丸の診断が出る頃には、私はその仕事を辞め、小学校での状況もずいぶん変わっていましたが、知識を持つということの大切さを学んでいた私は、その後も発達障害についてたくさんの本を読み漁りました。
もともと私が若い頃にうつや摂食障害で悩み、心理学を学んだことがあったり、カウンセリングを受けたりしていたので、子どもとの向き合い方を学ぶことは私にとっては楽しいことでした。また、本で読んだ知識をちゃんと実践していったら、どんな子に育つんだろう?と、もともとは苦手意識のあった子育てから、楽しみを見出すことができるようになりました。
「怒らない子育て」を実践した結果、息子の自己肯定感が爆上がり!?
本で読んで実践したことの中でも、特に一番わが家の子育てに影響したのは、多くの方が本やメディアでも見たり聞いたりしたことがあるだろう、「怒らない子育て」でした。
私とコチ丸は保育園の頃から、事あるごとに大喧嘩を繰り返していました。小学校入学を機に実家に戻った時には、激しい親子バトルを見たばぁばが「そのうち警察沙汰になるのでは」と心配していたほどでした(汗)。
そんな元来せっかちでイライラしがちな私の性格を、「怒らない」にシフトするのはかなり難しいことでした。が、もし私が怒るのをやめることで、コチ丸とのバトルの数が減り、コチ丸自身も変わっていくのだとしたら、自分のストレスも減って大きくいろんなことが変わるのでは?と思ったのです。
特に大きく変えたのは使う言葉でした。「ありがとう」「すごいね」「ごめんね」「頑張ったね」「まあいいか」という言葉を、普段から常に意識してかけるようにし、つい怒ってしまいそうな時も、一旦飲み込み、これらの言葉に置き換えるように努力をしました。
始めた頃は、小学生のコチ丸に「ママは目が笑っていない」と指摘をされるほど無理しているのがバレバレでした。実際、私自身も「怒らないこと」自体にイライラして、口の中に歯形がつくほど唇を噛み締めたり、歯を食いしばったりしていて、減らすはずのストレスが逆に溜まっていました(笑)。
とはいえ、時間をかければ慣れてくるもので、気がつくと私はコチ丸のことを怒らないようになっていました。毎日怒鳴り合いの親子バトルを繰り広げていた私が、数年経った頃には「甘やかしすぎなのでは?」と周りから思われてしまうほど怒らない親になっていました。
最初はあえて言葉に出していた「すごいね」は、コチ丸の学年が上がっていくにつれ、本心から「すごいね」と思えて言えるようになりました。そしてコチ丸も、楽観的で穏やかな性格に変わっていきました。それでいて周りに流されることもない、芯の強さもある、しっかりした子に育ちました。
私とコチ丸は保育園の頃から、事あるごとに大喧嘩を繰り返していました。小学校入学を機に実家に戻った時には、激しい親子バトルを見たばぁばが「そのうち警察沙汰になるのでは」と心配していたほどでした(汗)。
そんな元来せっかちでイライラしがちな私の性格を、「怒らない」にシフトするのはかなり難しいことでした。が、もし私が怒るのをやめることで、コチ丸とのバトルの数が減り、コチ丸自身も変わっていくのだとしたら、自分のストレスも減って大きくいろんなことが変わるのでは?と思ったのです。
特に大きく変えたのは使う言葉でした。「ありがとう」「すごいね」「ごめんね」「頑張ったね」「まあいいか」という言葉を、普段から常に意識してかけるようにし、つい怒ってしまいそうな時も、一旦飲み込み、これらの言葉に置き換えるように努力をしました。
始めた頃は、小学生のコチ丸に「ママは目が笑っていない」と指摘をされるほど無理しているのがバレバレでした。実際、私自身も「怒らないこと」自体にイライラして、口の中に歯形がつくほど唇を噛み締めたり、歯を食いしばったりしていて、減らすはずのストレスが逆に溜まっていました(笑)。
とはいえ、時間をかければ慣れてくるもので、気がつくと私はコチ丸のことを怒らないようになっていました。毎日怒鳴り合いの親子バトルを繰り広げていた私が、数年経った頃には「甘やかしすぎなのでは?」と周りから思われてしまうほど怒らない親になっていました。
最初はあえて言葉に出していた「すごいね」は、コチ丸の学年が上がっていくにつれ、本心から「すごいね」と思えて言えるようになりました。そしてコチ丸も、楽観的で穏やかな性格に変わっていきました。それでいて周りに流されることもない、芯の強さもある、しっかりした子に育ちました。
もしかすると違う育て方があったのかも?と現在もワクワクする日々を継続中!
もちろん、本に書いてあることが全ての人に当てはまるわけではありません。その子の個性もあれば、親との元々の相性もあると思うのです(そう思うと私とコチ丸はあまり相性は良くないほうかもしれません)。
なんにしても私は、とりあえず知識をどんどん仕入れ、その中から「こういう子育てをしたい」という自分の思いに合うものを選んで、比較的その理想に叶った育て方ができたのではないのかなと常々思ってきました。それはコチ丸が生まれる前に思い描いていた子育てとは全く違うものでしたが……。
発達障害があるならば、その特性を活かした生き方ができるといいな。すぐれた記憶力や集中力を活かせる仕事に就いたら、楽しく生きていけるんじゃないかな!もしかすると大物になる可能性があるかもしれない!と思うと、逆にすごくワクワクできる人生を送るチャンスをもらえたような気がしました。
思い返せば、自分自身が未熟で、心が病んでしまうほど子育てが大変な時期もありましたが、その時期すら今は愛おしい思い出です。「もし生まれ変わったら」なんていうこともない、本当に楽しい子育て期間を与えてくれたなと、コチ丸が私のところに生まれてきてくれたことには日々感謝してやみません。
そんな中、私は今でも気になっていることが一つあります。それは、コチ丸が中学3年生の時に受けたWISCの結果です。それまで何度かWISCを受けたことはありましたが、コチ丸は毎回全く落ち着かず、最後まできちんと受けることができていませんでした。中学3年生になったコチ丸は、最後までWISCを受けることができ、初めて正確な結果を得ることができたのですが……その時の結果が全ての項目において130超えだったのです。毎回常に苦手だったはずのワーキングメモリの項目まで全て……。もしかすると、コチ丸は今まで落ち着いてテストが受けられず正確な数値が測れなかっただけで、本来のIQは高かったのではないか?と思うようになりました。
もちろん今さらそれを言っても仕方ないことですし、先にも書いたように、この子育ては本当に楽しかったので、今となってはどちらでも良いことなのですが……。もし、もっと私に知識があって、違った視点をもってコチ丸を育てていたとしたら、さらに違った人生もあったのかもしれないなと、それもまた見てみたかった私です。
なんにしても私は、とりあえず知識をどんどん仕入れ、その中から「こういう子育てをしたい」という自分の思いに合うものを選んで、比較的その理想に叶った育て方ができたのではないのかなと常々思ってきました。それはコチ丸が生まれる前に思い描いていた子育てとは全く違うものでしたが……。
発達障害があるならば、その特性を活かした生き方ができるといいな。すぐれた記憶力や集中力を活かせる仕事に就いたら、楽しく生きていけるんじゃないかな!もしかすると大物になる可能性があるかもしれない!と思うと、逆にすごくワクワクできる人生を送るチャンスをもらえたような気がしました。
思い返せば、自分自身が未熟で、心が病んでしまうほど子育てが大変な時期もありましたが、その時期すら今は愛おしい思い出です。「もし生まれ変わったら」なんていうこともない、本当に楽しい子育て期間を与えてくれたなと、コチ丸が私のところに生まれてきてくれたことには日々感謝してやみません。
そんな中、私は今でも気になっていることが一つあります。それは、コチ丸が中学3年生の時に受けたWISCの結果です。それまで何度かWISCを受けたことはありましたが、コチ丸は毎回全く落ち着かず、最後まできちんと受けることができていませんでした。中学3年生になったコチ丸は、最後までWISCを受けることができ、初めて正確な結果を得ることができたのですが……その時の結果が全ての項目において130超えだったのです。毎回常に苦手だったはずのワーキングメモリの項目まで全て……。もしかすると、コチ丸は今まで落ち着いてテストが受けられず正確な数値が測れなかっただけで、本来のIQは高かったのではないか?と思うようになりました。
もちろん今さらそれを言っても仕方ないことですし、先にも書いたように、この子育ては本当に楽しかったので、今となってはどちらでも良いことなのですが……。もし、もっと私に知識があって、違った視点をもってコチ丸を育てていたとしたら、さらに違った人生もあったのかもしれないなと、それもまた見てみたかった私です。
執筆/あき
(監修:初川先生より)
コチ丸くんの子育てを振り返ってのコラムをありがとうございます。読んでいてなるほどなと思ったのは、あきさんが本から知識を得るのが好き(得意)で、そして得た知識を実践してみようと思えるタイプで、さらにやってみようと決めたことをすぐに投げ出すことなくしばらく頑張って続けてみる力があるということでした(口の中に歯形が残るほどストレスを抱えながらも、よくぞ耐えましたね!と思いました)。このあたりは、かなり個人差があるというか、保護者の方の得意不得意や性格的な面なども影響するだろうと思います。人によっては、本(文字)から情報を取り込むのが得意ではない方もいらっしゃると思いますし、一人で取り組むのが苦手だという方もいらっしゃるかもしれません。そういう場合は、相談機関や医療・福祉機関などに相談しながら知識を得て、時々相談・報告しながら(つまりどなたかに間接的にではあれ伴走してもらいながら)やっていくこともできるかなと思いました。
さて、「怒らない子育て」ですが、そのやり方に限らず、何かしら取り組んでみたい子育て方法や親子のコミュニケーションがある場合、そのやり方を信じて邁進するというよりも、大事なことは、そのやり方をやってみて、お子さんはどう反応しているか、そしてやっている保護者の方の気持ちやストレスはどうかということです。どんなやり方であれ、合う合わないはあります。そういう意味で、何かしら働きかけ方を変えてみた際には、その後の反応をよく見ていく(観察する)ことが大事です。どんなやり方をやる際にも、「試しにやってみる」「実験としてやってみる(だから結果や効果をしっかり観察して吟味する)」という視点は大事です。あまりに短期間だとその効果も見えてこないかもしれませんが、しばらく取り組んでみた際に、お子さんや保護者の反応や状態が良くない際には、やり方を変える(あるいは修正する)決断が必要です。やり方そのものに固執することはおすすめしません。ご自身での決断が難しい場合には担任の先生はじめ相談できそうな人に相談してみるのも1つの方法です。
「怒らない子育て」に関して言えば、いつもいつも親子で喧嘩になる展開は望ましくない(喧嘩そのものに注意が向いてしまい、本来お子さんに取り組んでもらいたいものからどんどん注意がそれていくことが気になります。何より親子関係にひびが入っていいことはありません)ので、「何を注意する(指摘する)か」といったあたりを厳選する必要はあります。そのあたりについては「ペアレントトレーニング」についてまとまった本などを一度眺めてみていただければと思います。
最後のWISCに関してですが、コチ丸くんは注意集中の持続に課題が大きく、検査中最後まで集中して取り組むことが難しかったのだろうと思います。中学3年生だったということを考えると成長によって集中が続くようになることもありますし、人によっては服薬によってそのあたり下支えしていく方もいます。確かに、これまでの検査時に本来持ちうるすべての力が発揮されなかったというのはあるかもしれません(そういう意味で、検査結果は数値のみならず、「検査時の様子」の記述もよく読んでいただければと思います)。また、そもそも検査は検査室という特殊な(刺激の少ない)環境で実施するものなので、日常生活でのパフォーマンスとイコールではないことも多いです。中3時の検査結果に関していえば“何らかの要因によって、集中の持続ができると、高いパフォーマンスを発揮できるということが分かった”ということです。もっと前に何かができていたら……ということを考えたくなるのは自然なことではありますが、そこにばかりとらわれず、コチ丸くんの持っている力がなかなか素晴らしいこと、そしてそれを発揮できる土台が整ってきたことが分かってきて、そしてご本人ももう青年期に入られて自己理解を進め自立も視野に入ってくる年頃。これから、どうしていくか。そこが大事なのだろうと思います。
(監修:初川先生より)
コチ丸くんの子育てを振り返ってのコラムをありがとうございます。読んでいてなるほどなと思ったのは、あきさんが本から知識を得るのが好き(得意)で、そして得た知識を実践してみようと思えるタイプで、さらにやってみようと決めたことをすぐに投げ出すことなくしばらく頑張って続けてみる力があるということでした(口の中に歯形が残るほどストレスを抱えながらも、よくぞ耐えましたね!と思いました)。このあたりは、かなり個人差があるというか、保護者の方の得意不得意や性格的な面なども影響するだろうと思います。人によっては、本(文字)から情報を取り込むのが得意ではない方もいらっしゃると思いますし、一人で取り組むのが苦手だという方もいらっしゃるかもしれません。そういう場合は、相談機関や医療・福祉機関などに相談しながら知識を得て、時々相談・報告しながら(つまりどなたかに間接的にではあれ伴走してもらいながら)やっていくこともできるかなと思いました。
さて、「怒らない子育て」ですが、そのやり方に限らず、何かしら取り組んでみたい子育て方法や親子のコミュニケーションがある場合、そのやり方を信じて邁進するというよりも、大事なことは、そのやり方をやってみて、お子さんはどう反応しているか、そしてやっている保護者の方の気持ちやストレスはどうかということです。どんなやり方であれ、合う合わないはあります。そういう意味で、何かしら働きかけ方を変えてみた際には、その後の反応をよく見ていく(観察する)ことが大事です。どんなやり方をやる際にも、「試しにやってみる」「実験としてやってみる(だから結果や効果をしっかり観察して吟味する)」という視点は大事です。あまりに短期間だとその効果も見えてこないかもしれませんが、しばらく取り組んでみた際に、お子さんや保護者の反応や状態が良くない際には、やり方を変える(あるいは修正する)決断が必要です。やり方そのものに固執することはおすすめしません。ご自身での決断が難しい場合には担任の先生はじめ相談できそうな人に相談してみるのも1つの方法です。
「怒らない子育て」に関して言えば、いつもいつも親子で喧嘩になる展開は望ましくない(喧嘩そのものに注意が向いてしまい、本来お子さんに取り組んでもらいたいものからどんどん注意がそれていくことが気になります。何より親子関係にひびが入っていいことはありません)ので、「何を注意する(指摘する)か」といったあたりを厳選する必要はあります。そのあたりについては「ペアレントトレーニング」についてまとまった本などを一度眺めてみていただければと思います。
最後のWISCに関してですが、コチ丸くんは注意集中の持続に課題が大きく、検査中最後まで集中して取り組むことが難しかったのだろうと思います。中学3年生だったということを考えると成長によって集中が続くようになることもありますし、人によっては服薬によってそのあたり下支えしていく方もいます。確かに、これまでの検査時に本来持ちうるすべての力が発揮されなかったというのはあるかもしれません(そういう意味で、検査結果は数値のみならず、「検査時の様子」の記述もよく読んでいただければと思います)。また、そもそも検査は検査室という特殊な(刺激の少ない)環境で実施するものなので、日常生活でのパフォーマンスとイコールではないことも多いです。中3時の検査結果に関していえば“何らかの要因によって、集中の持続ができると、高いパフォーマンスを発揮できるということが分かった”ということです。もっと前に何かができていたら……ということを考えたくなるのは自然なことではありますが、そこにばかりとらわれず、コチ丸くんの持っている力がなかなか素晴らしいこと、そしてそれを発揮できる土台が整ってきたことが分かってきて、そしてご本人ももう青年期に入られて自己理解を進め自立も視野に入ってくる年頃。これから、どうしていくか。そこが大事なのだろうと思います。

息子の癇癪に毎日イライラ!カッとなり自己嫌悪…私を変えた「怒りのコントロール法」

苦手なことが多くて取り組むのにも一苦労…そんなときに出来る工夫は?

通常学級でトラブル多発、小4で自閉症とADHDの診断。服薬とペアトレを開始して見られた変化とは【息子から校長先生への手紙/マンガ専門家体験】
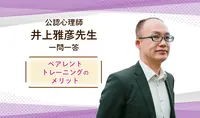
ペアレントトレーニング(ペアトレ)のメリットは?【公認心理師・井上雅彦先生にきく】

「こんな困った子見たことない」脱走、癇癪…幼稚園で怒られてばかりの息子に変化が!?児童発達支援とペアトレに出合って【読者体験談】
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

















