専門家コラムで悩みを深掘り/こだわりが学びの原動力に
――専門家の先生方のコラムも、読み物としてボリュームがあり実践的だと感じました。読者に伝えたいポイントとして、コラムの知識や情報はどのような基準で選ばれたのですか。
モンズースー:個人的に、専門家の先生に聞きたかったことを書いていただきました。特に知りたかったのは、お薬についてです。わが家は息子たちが低学年の頃に発達外来に通っていたのですが、長男のときは薬の話は出ず、次男が通い始めたらすぐに「この子は将来お薬が効くタイプかもしれない。困ったら相談してください」と先生に言われました。私には未だに2人の違いが分からないけれど、本当に困ったときにその言葉を思い出しては「今困っていることはお薬で解決するのか」と何度も迷いました。結局うちは一度も使いませんでしたが、お薬で解決するかもと考えている家庭は多いと思います。
――コトハちゃんは自分に合うお薬と出合えて生活が楽になりましたが、みなさんそれぞれ違いますよね。
モンズースー:あそこまでうまくいくパターンは珍しいかもしれません。情報を見て簡単に手を出してほしくはないですが、手段を知るのはいいことじゃないかと思い、描かせていただきました。お薬については「LITALICO発達ナビ」の記事から図表を引用して解説を入れつつ、気軽ではないという方向性や、ずっと使い続けるのかという視点も注意深く扱いました。漫画内でも何度も書き直したところです。
モンズースー:個人的に、専門家の先生に聞きたかったことを書いていただきました。特に知りたかったのは、お薬についてです。わが家は息子たちが低学年の頃に発達外来に通っていたのですが、長男のときは薬の話は出ず、次男が通い始めたらすぐに「この子は将来お薬が効くタイプかもしれない。困ったら相談してください」と先生に言われました。私には未だに2人の違いが分からないけれど、本当に困ったときにその言葉を思い出しては「今困っていることはお薬で解決するのか」と何度も迷いました。結局うちは一度も使いませんでしたが、お薬で解決するかもと考えている家庭は多いと思います。
――コトハちゃんは自分に合うお薬と出合えて生活が楽になりましたが、みなさんそれぞれ違いますよね。
モンズースー:あそこまでうまくいくパターンは珍しいかもしれません。情報を見て簡単に手を出してほしくはないですが、手段を知るのはいいことじゃないかと思い、描かせていただきました。お薬については「LITALICO発達ナビ」の記事から図表を引用して解説を入れつつ、気軽ではないという方向性や、ずっと使い続けるのかという視点も注意深く扱いました。漫画内でも何度も書き直したところです。
――入学後の子どもたちは、新たな環境で一歩を踏み出しています。中学受験の経験が彼らの人生にどのような力をもたらしてくれたと考えますか。
モンズースー:努力して入学できたことで、自己肯定感がすごく高まったと思います。それまで「できないこと」ばかりを気にしていた本人が、「自分は努力もできる」と気づけた。これは、とてもいい成功体験になったと思います。
――自己肯定感が上がる経験として、中学受験がうまく作用できるといいですよね。受かればいいのではなく、その先の人生も長いですから、受験が成長のきっかけになるといいなと個人的には思いました。それからジンくんのように、入学初期は疲れや不安が出ても、自由で理解のある学校環境があれば徐々に適応できるのだなとも感じました。
モンズースー:ジンくんは幼少期から運動面での発達遅延があり、「運動部に絶対に入りたくないから中学受験をやりたい」と言っていたそうです。地元の学校は地域的に運動部の種類も少なく、男子は運動部に入らなきゃいけない文化があったらしく……。勉強も、もともとできるタイプではなかったけれど、中学受験をきっかけに通いはじめた塾の先生との相性がよく、成績もぐんぐん伸びた。自分で学ぶことが楽しくなったそうです。特性であるこだわりの強さが、勉強へと向かったのもよかったのでしょうね。
本の中でも触れていますが、制服の代わりに夏は指定のポロシャツ登校ができるという感覚過敏にも嬉しい制度や、給食ではなく、カフェテリア利用やお弁当の持参OKというのが「好きなメニューを自由に食べられる」喜びになっていたそうです。
モンズースー:努力して入学できたことで、自己肯定感がすごく高まったと思います。それまで「できないこと」ばかりを気にしていた本人が、「自分は努力もできる」と気づけた。これは、とてもいい成功体験になったと思います。
――自己肯定感が上がる経験として、中学受験がうまく作用できるといいですよね。受かればいいのではなく、その先の人生も長いですから、受験が成長のきっかけになるといいなと個人的には思いました。それからジンくんのように、入学初期は疲れや不安が出ても、自由で理解のある学校環境があれば徐々に適応できるのだなとも感じました。
モンズースー:ジンくんは幼少期から運動面での発達遅延があり、「運動部に絶対に入りたくないから中学受験をやりたい」と言っていたそうです。地元の学校は地域的に運動部の種類も少なく、男子は運動部に入らなきゃいけない文化があったらしく……。勉強も、もともとできるタイプではなかったけれど、中学受験をきっかけに通いはじめた塾の先生との相性がよく、成績もぐんぐん伸びた。自分で学ぶことが楽しくなったそうです。特性であるこだわりの強さが、勉強へと向かったのもよかったのでしょうね。
本の中でも触れていますが、制服の代わりに夏は指定のポロシャツ登校ができるという感覚過敏にも嬉しい制度や、給食ではなく、カフェテリア利用やお弁当の持参OKというのが「好きなメニューを自由に食べられる」喜びになっていたそうです。
情報よりも子自身に答えが。中学受験は新しい道への選択肢
――中学受験だけが選択肢ではないですが、公立中学がお子さんの特性に合わない可能性がある場合、こういう道もあると知ることは、気持ちが楽になったり前向きになれるかもしれませんね。最後に、読者のみなさまへメッセージをいただきたいです。
モンズースー:中学受験や私立中学が絶対的にいいわけではなく、お子さんそれぞれに合う場所があると思います。ただ、私立中学という選択肢を知らなかったり、知っていても「私立なんて一部のすごい子だけでしょ」と思われている方も多いように感じます。なので、中学受験はそこまでハードルが高くないことを、まずは伝えたかった。小学校の時点で地元の環境が合わず、その後の人生にまで影響してしまう子もいると思うんですよね。ひょっとしたら、公立以外の道を選ぶほうがその子に合うかもしれない。この本が、そうした進路を選ぶ一つのきっかけになればと願っています。
――受験だけに限らず、子育てに関する情報があふれる中でどうやって自分の子どもに合った情報を厳選できるのか、モンズースーさんなりのコツがあれば伺いたいです。
モンズースー:やはり「発達障害」というカテゴリーよりも、「その子に合ったやり方」でしょうか。情報を集めすぎないのも結構大事だと思っていて。情報を集めすぎると逆にうまくいかないこともあるので、もし訳が分からなくなってきたら、本人を見てほしいです。意外と本人に答えが隠れていたりするんですよ。情報に振り回されず、その子を見て答えを導き出すことが大切ではないかなと思います。
モンズースー:中学受験や私立中学が絶対的にいいわけではなく、お子さんそれぞれに合う場所があると思います。ただ、私立中学という選択肢を知らなかったり、知っていても「私立なんて一部のすごい子だけでしょ」と思われている方も多いように感じます。なので、中学受験はそこまでハードルが高くないことを、まずは伝えたかった。小学校の時点で地元の環境が合わず、その後の人生にまで影響してしまう子もいると思うんですよね。ひょっとしたら、公立以外の道を選ぶほうがその子に合うかもしれない。この本が、そうした進路を選ぶ一つのきっかけになればと願っています。
――受験だけに限らず、子育てに関する情報があふれる中でどうやって自分の子どもに合った情報を厳選できるのか、モンズースーさんなりのコツがあれば伺いたいです。
モンズースー:やはり「発達障害」というカテゴリーよりも、「その子に合ったやり方」でしょうか。情報を集めすぎないのも結構大事だと思っていて。情報を集めすぎると逆にうまくいかないこともあるので、もし訳が分からなくなってきたら、本人を見てほしいです。意外と本人に答えが隠れていたりするんですよ。情報に振り回されず、その子を見て答えを導き出すことが大切ではないかなと思います。
発達障害っ子の中学受験
KADOKAWA
Amazonで詳しく見る
発達障害っ子の中学受験
KADOKAWA
楽天で詳しく見る
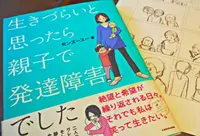
「生きづらいと思ったら親子で発達障害でした」の著者、モンズースーさんに会ってきた!
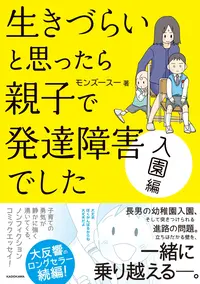
『生きづらいと思ったら親子で発達障害でした 入園編』モンズースーさん待望の新刊発売!

子どもの偏食、どうしてる? 発達障害との関係は?原因と工夫、みんなの体験談を一挙にご紹介!
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-
 1
1
- 2

















