配慮でひらいた息子の「見える」世界
さまざまな困難がありましたが、一つひとつ手に入れてきた配慮は、確実に息子の世界を変えていきました。
現在お願いしている配慮の以下の4つです。
拡大教科書と遮光眼鏡を使うようになって、日本語の「。」と「、」、英語の「.」と「,」などこれまで曖昧だった記号の違いが、はっきりと認識できるようになりました。
耳で聴いて覚えていたピアノの楽譜も、自分の目で追えるようになり、読書を避けていた息子が、本を手に取るようになったのも嬉しい変化です。一時期は「学校に行くと頭が痛くなる」と登校できなくなったこともありましたが、眼鏡のレンズの色を濃くすることで症状が和らぎ、再び学校に通えるようになりました。
ルビの存在さえ知らなかった息子が、今は自分の力で文字を追い、世界を広げています。その姿を見ることが、私にとって何よりの喜びです。
現在お願いしている配慮の以下の4つです。
- 教科書は、拡大教科書や、タブレットで使えるPDF版拡大図書を使う
- プリントや教材の拡大コピー、ルーペの併用
- 遮光レンズの眼鏡の使用
- 耳栓やイヤーマフの使用
拡大教科書と遮光眼鏡を使うようになって、日本語の「。」と「、」、英語の「.」と「,」などこれまで曖昧だった記号の違いが、はっきりと認識できるようになりました。
耳で聴いて覚えていたピアノの楽譜も、自分の目で追えるようになり、読書を避けていた息子が、本を手に取るようになったのも嬉しい変化です。一時期は「学校に行くと頭が痛くなる」と登校できなくなったこともありましたが、眼鏡のレンズの色を濃くすることで症状が和らぎ、再び学校に通えるようになりました。
ルビの存在さえ知らなかった息子が、今は自分の力で文字を追い、世界を広げています。その姿を見ることが、私にとって何よりの喜びです。
記録と連携、そして愚痴をこぼせる場所の大切さ
「うるさい親だと思われても仕方ない」そんな覚悟で交渉を続けてきましたが、やはり精神的に疲れることもありました。
今までの経験から、学校へのお願いは電話ではなく、記録に残るメールや手紙で行うことをお勧めします。後から見返すことができ、支援者の方と共有する際にも正確に状況を伝えられます。そして、いざという時に頼れる医療機関や支援機関と繋がっておくことも大切です。
何より、一人で抱え込まないこと。気心の知れた友人や親の会など、安心して愚痴をこぼせる場所が、私を何度も救ってくれました。気持ちを吐き出す中で、心が軽くなったり、思わぬヒントがもらえたりもします。
これからも、さまざまな壁にぶつかるのだと思いますが、息子のために、私にできることを続けていきたいなと思います。
今までの経験から、学校へのお願いは電話ではなく、記録に残るメールや手紙で行うことをお勧めします。後から見返すことができ、支援者の方と共有する際にも正確に状況を伝えられます。そして、いざという時に頼れる医療機関や支援機関と繋がっておくことも大切です。
何より、一人で抱え込まないこと。気心の知れた友人や親の会など、安心して愚痴をこぼせる場所が、私を何度も救ってくれました。気持ちを吐き出す中で、心が軽くなったり、思わぬヒントがもらえたりもします。
これからも、さまざまな壁にぶつかるのだと思いますが、息子のために、私にできることを続けていきたいなと思います。
イラスト/keiko
エピソード参考/まなり
(監修:新美先生)
息子さんの感覚の偏りに関する、学校での合理的配慮を求めたエピソードについて詳しく聞かせていただきありがとうございます。
発達障害のあるお子さんの「見えない困難」は、周囲からは気づかれにくく、本人さえもなかなか気づきにくいものです。今回の体験談では、聴覚や視覚といった感覚面の課題に気づき、少しずつ合理的配慮を整えていかれたお母さまの歩みが丁寧に描かれていました。これは、発達障害支援の現場でも非常に大切なプロセスです。
耳栓やイヤーマフ、拡大コピーなどは、発達特性に合わせた合理的配慮としてごく一般的であり、他の児童に迷惑をかけるものではありません。それにもかかわらず、こうした配慮を実現するために何度も交渉を重ねなければならなかった筆者さんのご苦労には、深い敬意とねぎらいの気持ちを覚えます。
また、せっかく「許可」を得ても、実際に使える雰囲気がなければ、子ども本人が遠慮してしまうことも少なくありません。先生が「どうしてもの場合は特別に認める」という姿勢ではなく、「必要な道具として積極的に使っていい」と勧めてくださることが、本人の安心につながります。感覚の違いを理解し、合理的配慮を当たり前に受けられる学校文化が広がっていくことを願ってやみません。
感覚の違いを理解し、本人が安心して学べる環境を共につくっていく――それこそが、合理的配慮の本当の意味だと感じました。
エピソード参考/まなり
(監修:新美先生)
息子さんの感覚の偏りに関する、学校での合理的配慮を求めたエピソードについて詳しく聞かせていただきありがとうございます。
発達障害のあるお子さんの「見えない困難」は、周囲からは気づかれにくく、本人さえもなかなか気づきにくいものです。今回の体験談では、聴覚や視覚といった感覚面の課題に気づき、少しずつ合理的配慮を整えていかれたお母さまの歩みが丁寧に描かれていました。これは、発達障害支援の現場でも非常に大切なプロセスです。
耳栓やイヤーマフ、拡大コピーなどは、発達特性に合わせた合理的配慮としてごく一般的であり、他の児童に迷惑をかけるものではありません。それにもかかわらず、こうした配慮を実現するために何度も交渉を重ねなければならなかった筆者さんのご苦労には、深い敬意とねぎらいの気持ちを覚えます。
また、せっかく「許可」を得ても、実際に使える雰囲気がなければ、子ども本人が遠慮してしまうことも少なくありません。先生が「どうしてもの場合は特別に認める」という姿勢ではなく、「必要な道具として積極的に使っていい」と勧めてくださることが、本人の安心につながります。感覚の違いを理解し、合理的配慮を当たり前に受けられる学校文化が広がっていくことを願ってやみません。
感覚の違いを理解し、本人が安心して学べる環境を共につくっていく――それこそが、合理的配慮の本当の意味だと感じました。
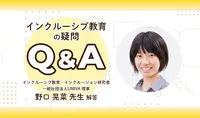
インクルーシブ教育とは?実践例や合理的配慮の求め方【専門家QA】

ひらがなが読めない!?小学校入学で気づいた学習の困り。学校で受けている5つの合理的配慮は【読者体験談】

通常学級を選んだ発達障害グレー息子。就学準備、合理的配慮の求め方は?自閉症長男との違いも

境界知能の娘、学校での合理的配慮は?診断から高校までの歩みと困難【読者体験談】

発達特性のある息子、大学進学で「合理的配慮」は受けられる?就活まで役立った自作の"特性説明台本"を紹介
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-
 1
1
- 2















