必要不可欠なのは「本人側からの相談」と「対話」
では、どうすればこのような配慮を受けられるのでしょうか。
どのような時に困難さを感じ、その困難さに対しどのような配慮が必要かを関係者が話し合うことが大切です。
どのような時に困難さを感じ、その困難さに対しどのような配慮が必要かを関係者が話し合うことが大切です。
ステップ
① 本人や保護者・介助者から、必要な配慮に関する意思表明をすること、もしくは周りの人(学校の先生など)が必要な配慮を提案すること
② 学校と本人・保護者が話し合いをし、実施すべき配慮や実施可能な配慮について話し合うこと ※個別の指導計画に記載することが望ましい
③ どんな場面でどんな配慮ができるか、お互いに合意したうえで実施すること
④ 配慮を実施したあとも、定期的にその内容や程度について見直し・改善をすること
② 学校と本人・保護者が話し合いをし、実施すべき配慮や実施可能な配慮について話し合うこと ※個別の指導計画に記載することが望ましい
③ どんな場面でどんな配慮ができるか、お互いに合意したうえで実施すること
④ 配慮を実施したあとも、定期的にその内容や程度について見直し・改善をすること
どんな場合も、本人を含めた関係者同士の「対話」が必要不可欠です。
困っていることに対し、具体的な解決策を共に考え、合意をした上で進んでいきます。
しかし、申し出た解決策が、金銭的な事情や人員的な事情で難しい場合もあるでしょう。その場合は、今できる解決策を一緒に考えることになります。
困っていることに対し、具体的な解決策を共に考え、合意をした上で進んでいきます。
しかし、申し出た解決策が、金銭的な事情や人員的な事情で難しい場合もあるでしょう。その場合は、今できる解決策を一緒に考えることになります。
4月から「合理的配慮」と言えば先生に伝わるの?
法律は4月の時点で施行されますが、社会全体の認識が4月1日から一斉に変わるわけではありません。徐々に浸透していくのだろうと思っています。
そして、先生方は現時点で全員「合理的配慮」という言葉や、具体的な方法を把握しているかというと、残念ながら、この法律の改変にあたって先生方へ向けた研修等はまだまだ充実していないのが現状です。
私自身、いくつかの学校にお声かけいただき研修をさせていただきましたが、全国各地の学校に伺ったわけではありません。
株式会社LITALICOが2015年3月に独自でおこなった、小中学校の教員300名向けのアンケートでは、内容まで詳しく知っているという方は全体の24%でした。
そして、先生方は現時点で全員「合理的配慮」という言葉や、具体的な方法を把握しているかというと、残念ながら、この法律の改変にあたって先生方へ向けた研修等はまだまだ充実していないのが現状です。
私自身、いくつかの学校にお声かけいただき研修をさせていただきましたが、全国各地の学校に伺ったわけではありません。
株式会社LITALICOが2015年3月に独自でおこなった、小中学校の教員300名向けのアンケートでは、内容まで詳しく知っているという方は全体の24%でした。
もちろん、個人で勉強されている先生方も多いですが、全ての先生に具体的な実践方法まで詳しく知らされているわけではありません。
だからこそ、子ども自身の困りごとや特性をよく把握している保護者からの、丁寧な相談や提案が大切になってくるのです。
だからこそ、子ども自身の困りごとや特性をよく把握している保護者からの、丁寧な相談や提案が大切になってくるのです。
「子ども主語」で調整をしていこう。両者が対立しては意味がない
合理的配慮は原語でいうとreasonable accommodation.リーズナブルアコモデーションです。
「配慮」というと「してもらうもの」「してあげるもの」というイメージを持ちますが、原語のアコモデーションは「調整・便宜」という意味を含みます。
つまり個々のニーズに応じて必要な工夫や配慮をできるように「調整」するということになります。
そのため、合理的配慮を当然である環境や文化を作っていきながら、子ども自身がゆくゆくは自分の特性を理解し、「こういう工夫・配慮があるとこういうことができる」と周りに働きかけられるようになることも大切です。
「配慮」というと「してもらうもの」「してあげるもの」というイメージを持ちますが、原語のアコモデーションは「調整・便宜」という意味を含みます。
つまり個々のニーズに応じて必要な工夫や配慮をできるように「調整」するということになります。
そのため、合理的配慮を当然である環境や文化を作っていきながら、子ども自身がゆくゆくは自分の特性を理解し、「こういう工夫・配慮があるとこういうことができる」と周りに働きかけられるようになることも大切です。
4月から施行されるこの法律によって、「うちの学校はやってくれない」「保護者の要求が高すぎる」と、両者が対立してしまっては、何1つ子どものためになりません。
合理的配慮は誰のためにあるか、を忘れないようにしていきたいです。
「子どもの学ぶ環境を整える」という同じ目的にむかって、学校と保護者が手を取り合い、合理的な調整を考えていける「チーム」になることが何よりも大切です。
この新しい法律を対立するための武器として使うのではなく、子どもが今と未来を幸せに生きるために活用していきましょう。
合理的配慮は誰のためにあるか、を忘れないようにしていきたいです。
「子どもの学ぶ環境を整える」という同じ目的にむかって、学校と保護者が手を取り合い、合理的な調整を考えていける「チーム」になることが何よりも大切です。
この新しい法律を対立するための武器として使うのではなく、子どもが今と未来を幸せに生きるために活用していきましょう。

まだ知らない人も多い「合理的配慮」を社会の当たり前にするには
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
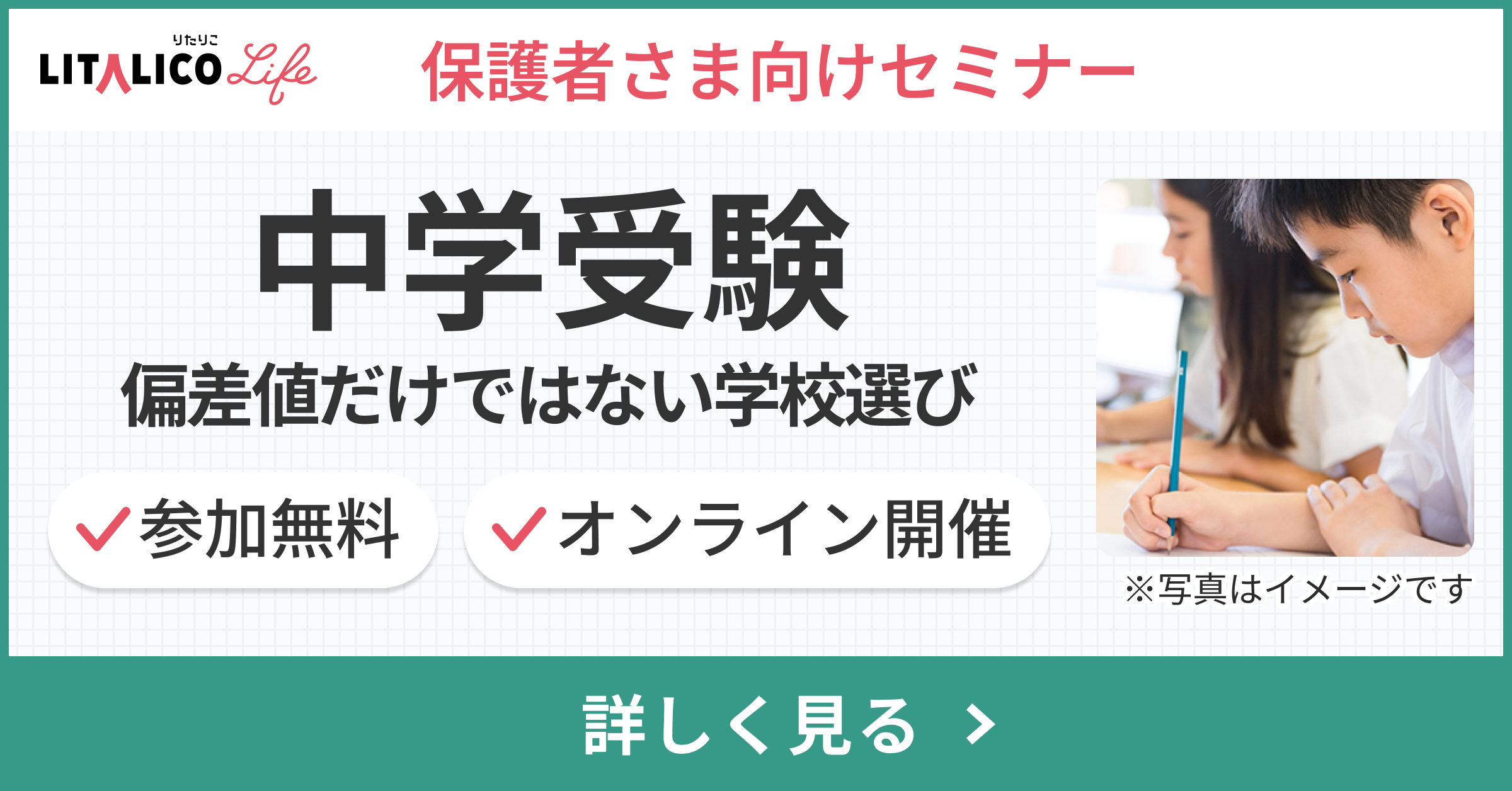
-
 1
1
- 2

















