子どもの睡眠障害の症状や対処法、発達障害との関係【医師監修】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
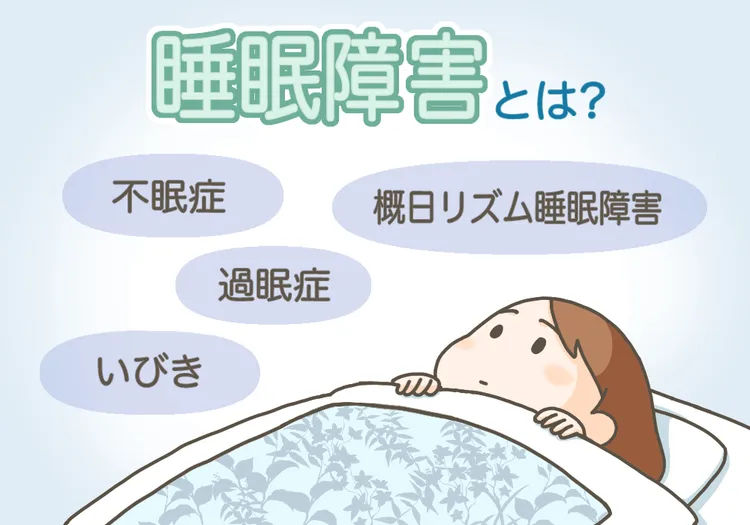
Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
睡眠障害(不眠障害)は、なかなか寝付けない入眠困難、中途覚醒などが頻回におきたり、覚醒後に寝つけなくなる睡眠維持困難、早朝覚醒のいずれか1つ以上の睡眠に関する問題を呈し、苦痛や社会的な困難を伴います。また、睡眠障害はASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)などの発達障害のある子どもに併存することが多いといわれています。今回は子どもの睡眠障害について、症状や原因、対処法などを紹介します。

監修: 藤井明子
小児科専門医
小児神経専門医
てんかん専門医
どんぐり発達クリニック院長
東京女子医科大学大学院修了。東京女子医科大学病院、長崎県立子ども医療福祉センターで研鑽を積み、2019年よりさくらキッズくりにっく院長に就任。2024年より、どんぐり発達クリニック院長、育心会児童発達部門統括医師に就任。お子様の個性を大切にしながら、親御さんの子育ての悩みにも寄り添う診療を行っている。 3人の子どもを育児中である。
小児神経専門医
てんかん専門医
どんぐり発達クリニック院長
睡眠障害とは?子どもがなかなか眠らないのは睡眠障害なの?
睡眠障害(不眠障害)は、なかなか寝付けない入眠困難や中途覚醒などが頻回に起きたり、覚醒後に寝つけなくなる睡眠維持困難や早朝覚醒のいずれか1つ以上の睡眠に関する問題が週に3日以上あり、3ヶ月以上続いている状態で、苦痛や社会的な困難を伴います。
なお、診断にあたっては、このような不眠が、ナルコレプシーや概日リズム睡眠‐覚醒障害などそのほかの睡眠‐覚醒障害によるものでないこと、医薬品など物質の影響でないこと、併存する精神疾患によるものではないことの確認が必要となります。
子どもの心身の育ちにとって睡眠はとても重要です。子育て中の保護者の方にとって、子どもの睡眠は大きな悩みの一つであるかもしれません。「子どもが夜ちゃんと寝てくれなくて…」、「たびたび夜中に起きて騒ぐので、家族みんな寝不足で…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
子どもがぐっすり寝てくれないと、お世話をする保護者のほうも寝不足になり、体力的にも精神的にもつらいと思います。夜泣きしたり騒いでしまったりすると、近所迷惑になっていないかというストレスを感じる方もいらっしゃるでしょう。また、うまく眠れない日が続くと、何かの病気ではないか、発育に影響はないのか、不安になったりするかもしれません。
子どもは、新生児期には昼夜を問わず短い睡眠・覚醒を繰り返しますが、幼児期(3歳から6 歳ごろ)までに浅い眠りと深い眠りのサイクルが大人と同様のリズムに移行していきます。そのため、幼児期になっても睡眠に何らかの問題がある場合、改善の必要があるといえます。
特に、発達障害のある子どもは、睡眠障害を経験する場合が多いといわれています。睡眠リズムのシステムづくりになんらかの問題が生じたり、発達障害の二次障害として睡眠障害があらわれたりする可能性もあります。睡眠障害が長く続くと、日常生活に更なる影響が出ることもあるため、早めに対処や治療をおこなっていくことが重要です。
なお、診断にあたっては、このような不眠が、ナルコレプシーや概日リズム睡眠‐覚醒障害などそのほかの睡眠‐覚醒障害によるものでないこと、医薬品など物質の影響でないこと、併存する精神疾患によるものではないことの確認が必要となります。
子どもの心身の育ちにとって睡眠はとても重要です。子育て中の保護者の方にとって、子どもの睡眠は大きな悩みの一つであるかもしれません。「子どもが夜ちゃんと寝てくれなくて…」、「たびたび夜中に起きて騒ぐので、家族みんな寝不足で…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
子どもがぐっすり寝てくれないと、お世話をする保護者のほうも寝不足になり、体力的にも精神的にもつらいと思います。夜泣きしたり騒いでしまったりすると、近所迷惑になっていないかというストレスを感じる方もいらっしゃるでしょう。また、うまく眠れない日が続くと、何かの病気ではないか、発育に影響はないのか、不安になったりするかもしれません。
子どもは、新生児期には昼夜を問わず短い睡眠・覚醒を繰り返しますが、幼児期(3歳から6 歳ごろ)までに浅い眠りと深い眠りのサイクルが大人と同様のリズムに移行していきます。そのため、幼児期になっても睡眠に何らかの問題がある場合、改善の必要があるといえます。
特に、発達障害のある子どもは、睡眠障害を経験する場合が多いといわれています。睡眠リズムのシステムづくりになんらかの問題が生じたり、発達障害の二次障害として睡眠障害があらわれたりする可能性もあります。睡眠障害が長く続くと、日常生活に更なる影響が出ることもあるため、早めに対処や治療をおこなっていくことが重要です。
発達障害のある子どもの睡眠障害
実際に発達障害のある子どもに睡眠障害もあり、困っているという体験談を紹介します。
■悪夢が怖い!発達障害むっくんの「眠れない」問題、どうしたら?母も入眠障害に…親子で向き合った睡眠問題の年長から小2現在
ADHD(注意欠如多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の診断のあるむっくんは元々入眠困難がありましたが、6歳になったころ悪夢を見るようになりました。悪夢を見ると泣きながら起きあがり、再度入眠するのを怖がるため、お母さんは朝までアニメなどを見て一緒に過ごすこともありました。そうしているうちに、お母さんも「今日も眠れなかったらどうしよう」と悩むようになり、一時は自身も入眠困難に陥ってしまいました。
ADHD(注意欠如多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の診断のあるむっくんは元々入眠困難がありましたが、6歳になったころ悪夢を見るようになりました。悪夢を見ると泣きながら起きあがり、再度入眠するのを怖がるため、お母さんは朝までアニメなどを見て一緒に過ごすこともありました。そうしているうちに、お母さんも「今日も眠れなかったらどうしよう」と悩むようになり、一時は自身も入眠困難に陥ってしまいました。

悪夢が怖い!発達障害むっくんの「眠れない」問題、どうしたら?母も入眠障害に…親子で向き合った睡眠問題の年長から小2現在
■0歳から4歳になった今も続く自閉症息子の睡眠の悩み。低年齢のうちは薬に頼りたくないと思っていたけれど
かさはらあやこさんの息子さんはASD(自閉スペクトラム症)の診断があり、生後100日を過ぎたあたりからは夜泣きが始まりました。毎日23時ごろから2~3時間ほぼ決まった時間に泣くようになり、落ち着くまで時間を有しました。さらに昼間は癇癪も激しく、睡眠不足のなか対応することで夫婦ともに消耗し、肉体的にも精神的にも辛い状況だったといいます。この状況は一旦3歳になったころに収まりましたが、幼稚園の行事が増えたころから再発。そこで、4歳になるころに医師のすすめで投薬を開始し、少しずつ落ち着いてきました。
かさはらあやこさんの息子さんはASD(自閉スペクトラム症)の診断があり、生後100日を過ぎたあたりからは夜泣きが始まりました。毎日23時ごろから2~3時間ほぼ決まった時間に泣くようになり、落ち着くまで時間を有しました。さらに昼間は癇癪も激しく、睡眠不足のなか対応することで夫婦ともに消耗し、肉体的にも精神的にも辛い状況だったといいます。この状況は一旦3歳になったころに収まりましたが、幼稚園の行事が増えたころから再発。そこで、4歳になるころに医師のすすめで投薬を開始し、少しずつ落ち着いてきました。

0歳から4歳になった今も続く自閉症息子の睡眠の悩み。低年齢のうちは薬に頼りたくないと思っていたけれど
■睡眠障害のあるASD娘、高校受験を前に投薬開始!「眠れるけど起きる時間は…」本人の下した決断、そして進路は
ASD(自閉スペクトラム症)のあるいっちゃんは非24時間睡眠覚醒症候群といって、毎日寝る時間が1時間から2時間遅れていく病気もありました。通っていた幼稚園からは「生活リズムを整えるように」と言われていましたが、規則正しい生活をしてもどうしても寝る時間にずれが出ていました。
実はお母さんにも睡眠障害があったため、もしかしてと3歳になるころにいっちゃんの睡眠日記を付けはじめた結果、「概ね26時間周期、睡眠時間は10時間のロングスリーパー」ということが判明。朝型の生活をするのは難しいと感じ、高校は通信制を選び、無理のない学校生活を送っています。
ASD(自閉スペクトラム症)のあるいっちゃんは非24時間睡眠覚醒症候群といって、毎日寝る時間が1時間から2時間遅れていく病気もありました。通っていた幼稚園からは「生活リズムを整えるように」と言われていましたが、規則正しい生活をしてもどうしても寝る時間にずれが出ていました。
実はお母さんにも睡眠障害があったため、もしかしてと3歳になるころにいっちゃんの睡眠日記を付けはじめた結果、「概ね26時間周期、睡眠時間は10時間のロングスリーパー」ということが判明。朝型の生活をするのは難しいと感じ、高校は通信制を選び、無理のない学校生活を送っています。

睡眠障害のあるASD娘、高校受験を前に投薬開始!「眠れるけど起きる時間は…」本人の下した決断、そして進路は
子どもの発育に睡眠が重要な理由は?
睡眠リズムは成長につれて確立します
子どもの睡眠のメカニズムは、脳の成長につれ変わっていきます。生まれてすぐのころは短い周期で昼夜の区別なく眠りと覚醒を繰り返します。生後6ヶ月ごろまでには昼間に長めに起きて夜に集中して眠る、約24時間の生体リズムが形成されます。その後、午前中の昼寝、午後のお昼寝の順に必要がなくなり、3歳~6歳くらいまでに夜間にまとまって寝るようになります。
睡眠量だけでなく、睡眠の質(睡眠構造)も年齢・成長にともない変化します。人間の睡眠は、レム睡眠(浅い眠りで身体は眠っているのに、脳が活発に動いている状態)とノンレム睡眠(脳も身体が休んでいる深い眠りの状態)の2つに分けられますが、生後間もなくはレム睡眠に似た浅い動睡眠が睡眠全体の約半分を占めます。
生後3ヶ月ごろにはレム睡眠が減少し、入眠もノンレム睡眠から始まるようになります。3歳から6歳ごろまでにはノンレム睡眠とレム睡眠を90分ほどの周期で繰り返す、大人とほぼ同じ睡眠リズムができてきます。そのために睡眠のシステムが形成される時期に良質な睡眠をとることは、大切であるといわれています。
また、1歳ごろまでにメラトニンという体内時計を調整する役割をもつホルモンの分泌が急速に始まり、最終的には10歳頃までメラトニン分泌の高い状態が続き、睡眠と覚醒のリズムが確立されていくといわれています。メラトニンは、覚醒と睡眠を切り替えて眠りをうながしますが、日中に光をたくさんあびることで分泌されるので、早寝早起きの生活リズムを続けることでより分泌量が増え、より眠れるようにもなります。
乳児期はこれらの睡眠のシステムが形成される途中であるため、睡眠が浅かったり、細切れになりますが、3歳以降になってもこのシステムがうまくできていない場合、対策を考えたほうがよいかもしれません。
睡眠量だけでなく、睡眠の質(睡眠構造)も年齢・成長にともない変化します。人間の睡眠は、レム睡眠(浅い眠りで身体は眠っているのに、脳が活発に動いている状態)とノンレム睡眠(脳も身体が休んでいる深い眠りの状態)の2つに分けられますが、生後間もなくはレム睡眠に似た浅い動睡眠が睡眠全体の約半分を占めます。
生後3ヶ月ごろにはレム睡眠が減少し、入眠もノンレム睡眠から始まるようになります。3歳から6歳ごろまでにはノンレム睡眠とレム睡眠を90分ほどの周期で繰り返す、大人とほぼ同じ睡眠リズムができてきます。そのために睡眠のシステムが形成される時期に良質な睡眠をとることは、大切であるといわれています。
また、1歳ごろまでにメラトニンという体内時計を調整する役割をもつホルモンの分泌が急速に始まり、最終的には10歳頃までメラトニン分泌の高い状態が続き、睡眠と覚醒のリズムが確立されていくといわれています。メラトニンは、覚醒と睡眠を切り替えて眠りをうながしますが、日中に光をたくさんあびることで分泌されるので、早寝早起きの生活リズムを続けることでより分泌量が増え、より眠れるようにもなります。
乳児期はこれらの睡眠のシステムが形成される途中であるため、睡眠が浅かったり、細切れになりますが、3歳以降になってもこのシステムがうまくできていない場合、対策を考えたほうがよいかもしれません。
睡眠が発達をうながします
細胞組織の生成と新陳代謝を促す成長ホルモンは、身長を伸ばしたり、筋肉をつくったりするのに欠かせません。また、脳の発達や記憶などにも関係するホルモンです。この成長ホルモンは、睡眠中、特に入眠後最初に訪れるノンレム睡眠中に多く分泌されるといわれています。つまり睡眠中に成長ホルモンが分泌されることで、身体の組織や脳が構築され発達するのです。
このように、子どもにとって睡眠は日中の疲労を回復するだけではありません。乳幼児から思春期の睡眠は、心身が大きく成長する時期に必要なホルモンが分泌される、発達に欠かせない大切な時間といえるでしょう。
そのため、子どもの睡眠の問題には早期に対処することが重要です。睡眠障害が改善されることで発達障害にもよい影響を与えると考える医師や研究者もおり、さまざまな研究も進められています。
このように、子どもにとって睡眠は日中の疲労を回復するだけではありません。乳幼児から思春期の睡眠は、心身が大きく成長する時期に必要なホルモンが分泌される、発達に欠かせない大切な時間といえるでしょう。
そのため、子どもの睡眠の問題には早期に対処することが重要です。睡眠障害が改善されることで発達障害にもよい影響を与えると考える医師や研究者もおり、さまざまな研究も進められています。
子どもの睡眠障害とは?どんな場合に疑われる?
眠りになんらかの問題がある状態を睡眠障害といいます。「眠れない」不眠症をイメージする人が多いのですが、眠りすぎやいびきなども含め、眠りの質と量にまつわるさまざまな問題を広く含みます。
以下の様子が見られるときは睡眠障害が原因の可能性もあります。
以下の様子が見られるときは睡眠障害が原因の可能性もあります。
・夜中に突然大声で叫び、パニックを起こす
・手足のムズムズ感や違和感、痛みで眠れない
・夜中に歩き回る
・夜普通に寝ているが、日中眠そうにしていたり居眠りしたりする
・寝る時間が遅くて不規則な生活が続き、直せない
・睡眠が十分に取れなくて頭痛や体調不良が続いている
・落ち着きがなく、衝動性がある
睡眠時間や睡眠中に起きる問題のほか、一見睡眠と関係なさそうなことも睡眠障害が原因かもしれません。子どもが良質な睡眠ができているか、普段の様子や生活をチェックし、心配なことがあれば医師に相談しましょう
・手足のムズムズ感や違和感、痛みで眠れない
・夜中に歩き回る
・夜普通に寝ているが、日中眠そうにしていたり居眠りしたりする
・寝る時間が遅くて不規則な生活が続き、直せない
・睡眠が十分に取れなくて頭痛や体調不良が続いている
・落ち着きがなく、衝動性がある
睡眠時間や睡眠中に起きる問題のほか、一見睡眠と関係なさそうなことも睡眠障害が原因かもしれません。子どもが良質な睡眠ができているか、普段の様子や生活をチェックし、心配なことがあれば医師に相談しましょう

発達障害がある子どもの不眠、どんな対処法がある?【医師監修】
















