発達障害がある子どもの不眠、どんな対処法がある?【医師監修】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
発達障害がある子どもは、睡眠に何らかの問題を抱えることがあるといわれています。原因として、感覚の過敏さ、睡眠リズムに必要なホルモンとの関係、不安症状などがあるのではないかと考えられています。
発達障害がある子どもの不眠について、原因や対処法、相談先まで紹介します。

監修: 藤井明子
小児科専門医
小児神経専門医
てんかん専門医
どんぐり発達クリニック院長
東京女子医科大学大学院修了。東京女子医科大学病院、長崎県立子ども医療福祉センターで研鑽を積み、2019年よりさくらキッズくりにっく院長に就任。2024年より、どんぐり発達クリニック院長、育心会児童発達部門統括医師に就任。お子様の個性を大切にしながら、親御さんの子育ての悩みにも寄り添う診療を行っている。 3人の子どもを育児中である。
小児神経専門医
てんかん専門医
どんぐり発達クリニック院長
発達障害と不眠の関係
発達障害のある子どもは、睡眠に何らかの問題を抱えることがあるといわれています。自閉スペクトラム症児では50〜80%、ADHDでは25〜50%に睡眠障害が合併するとの報告があります。
発達障害のある子どもが寝ないのはなぜ?
発達障害のある子どもが不眠に悩む場合は、その原因として、感覚の過敏さなどの特性や睡眠リズムのシステムづくりの問題、不安症状との関連などが考えられるといわれています。例えば、感覚の過敏さについては、音や光などに対する感覚が過敏である場合、覚醒しやすいといわれています。
※現在、自閉症は自閉スペクトラム症(ASD)という診断名に統一されています。

【専門家監修】感覚過敏・鈍麻への対応ガイド。発達障害の子どもが「嫌がる・気づかない」理由
ADHD(注意欠如多動症)のある子どもと睡眠障害の関係
ADHD(注意欠如多動症)の場合、25〜50%に睡眠障害が合併するとの報告があります。
調査ではADHDのある子どもの入床への抵抗、入眠の困難、中途覚醒、起床の困難、日中の過剰な眠気がある子どもが多い傾向があるという結果があります。これは、ADHDの特徴である不注意・多動性・衝動性との関連があるのではないかと考えられています。
調査ではADHDのある子どもの入床への抵抗、入眠の困難、中途覚醒、起床の困難、日中の過剰な眠気がある子どもが多い傾向があるという結果があります。これは、ADHDの特徴である不注意・多動性・衝動性との関連があるのではないかと考えられています。
脳内の神経伝達物質の偏りによる影響
・セロトニン・メラトニンなど睡眠に関連するホルモンの不足
発達障害がある人は、メラトニンの量や、セロトニン・メラトニンといったホルモンの元となるトリプトファンの量が、極端に多すぎたり少なすぎたりするのではないかと考えられています。体内時計をコントロールする、これらのホルモンの不足があると、不眠や概日リズム睡眠障害になりやすくなると考えられています。
発達障害がある人は、メラトニンの量や、セロトニン・メラトニンといったホルモンの元となるトリプトファンの量が、極端に多すぎたり少なすぎたりするのではないかと考えられています。体内時計をコントロールする、これらのホルモンの不足があると、不眠や概日リズム睡眠障害になりやすくなると考えられています。
うつ
発達障害の二次障害であるうつなどを発症することで、不眠につながる場合もあります。
上記をはじめとして、発達障害がある子どもの不眠には、いくつかの原因が考えられていますが、まだはっきりとは解明されていません。
上記をはじめとして、発達障害がある子どもの不眠には、いくつかの原因が考えられていますが、まだはっきりとは解明されていません。
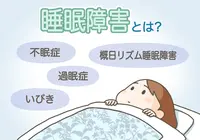
子どもの睡眠障害の症状や対処法、発達障害との関係【医師監修】
家庭でできる不眠の対処法
生活リズムを整える
早寝早起き、朝食をしっかりとる、昼寝させ過ぎない、日中体を動かす、夕飯やお風呂の時間を見直すなど、まずは生活リズムを整えてみましょう。
入眠儀式をつくる
特性などによって、睡眠への切り替えが難しい場合は、入眠儀式をつくることでスムーズに眠れるようになる場合もあります。寝る前に着替えて歯を磨く、絵本を読むなどの決まりごとをつくります。毎日同じ習慣や手順で眠りにつくことで、寝るモードに気持ちが変わりやすくなることがあります。親子のスキンシップにもなるマッサージを、入眠儀式として取り入れてみるのもよいかもしれません。
子どもがどんなことをすると眠りやすいか探しながら、合うものがあれば毎日繰り返して「入眠儀式」にしていきましょう。
子どもがどんなことをすると眠りやすいか探しながら、合うものがあれば毎日繰り返して「入眠儀式」にしていきましょう。
気分転換
どうしても寝つきが悪いときには無理に寝かせようとせず、思い切って起きるという方法もあります。一度部屋を明るくして布団の外に出てみたり、音楽をかけてみるのもよいでしょう。眠れないことで不安になり、寝ようと意識しすぎるとかえって興奮してしまい眠れなくなってしまう場合もあるからです。
寝る環境を整える
寝室の環境も睡眠に影響します。落ち着いて眠りにつける空間づくりと、朝起きやすくなる工夫をしましょう。
ベッドは日当たりのよい場所に置きましょう。遮光性のあるカーテンをして、朝決まった時間に開け、起床時に日光を浴びるようにします。インテリアは、淡い青や黄色、アースカラーなどの穏やかで落ち着いた色を選ぶというのもよいかもしれません。不安を感じやすい場合や光に敏感な場合は、天井から布などを吊って高さを抑えた空間にしたり、照明を和らげたりもできます。眠る時間には静かな環境をつくるとよいでしょう。
また、重みのある寝具や、ぴったりと体に添う寝具などを取り入れると、安心して眠れるようになる場合というもあります。北欧のスウェーデンやデンマークの病院では、作業療法士によってチェーンブランケットという掛け布団が保険処方されています。
ベッドは日当たりのよい場所に置きましょう。遮光性のあるカーテンをして、朝決まった時間に開け、起床時に日光を浴びるようにします。インテリアは、淡い青や黄色、アースカラーなどの穏やかで落ち着いた色を選ぶというのもよいかもしれません。不安を感じやすい場合や光に敏感な場合は、天井から布などを吊って高さを抑えた空間にしたり、照明を和らげたりもできます。眠る時間には静かな環境をつくるとよいでしょう。
また、重みのある寝具や、ぴったりと体に添う寝具などを取り入れると、安心して眠れるようになる場合というもあります。北欧のスウェーデンやデンマークの病院では、作業療法士によってチェーンブランケットという掛け布団が保険処方されています。
家庭での対処が難しいときの相談先
生活リズムの改善や、環境調整、寝具の工夫などでも不眠が解消しない場合は、家族だけで抱え込まずに、かかりつけの小児科や地域の保健センターに相談しましょう。専門的な治療が必要な場合は、専門機関や対処を教えてくれるでしょう。
医療機関では、不眠の原因の確認を行い、必要に応じて治療が行われます。医療機関で行われる代表的な治療法には、次のようなものがあります。
医療機関では、不眠の原因の確認を行い、必要に応じて治療が行われます。医療機関で行われる代表的な治療法には、次のようなものがあります。
生活指導
子どもの睡眠障害は、保護者の生活習慣の影響を受けやすいため、家庭の生活習慣の見直しや、子どもがうまく眠れないときのかかわり方などについての指導など、行動療法的なアプローチが有効です。
そこで、保護者の睡眠に関する知識を正し、睡眠環境や生活リズムを整えることで適切な睡眠が得られるようにします。睡眠リズムを記録する睡眠表をつけることもあります。
そこで、保護者の睡眠に関する知識を正し、睡眠環境や生活リズムを整えることで適切な睡眠が得られるようにします。睡眠リズムを記録する睡眠表をつけることもあります。
薬物療法
子どもの薬物治療については、医師による治療方針やケースにもよりますが、生体リズムの改善のため、メラトニンやドーパミンを薬で調整する治療法があります。また、緊張や不安が原因の場合、それを和らげるための薬が処方されることもあります。薬物治療を行う際には主治医と相談の上、用法や用量を守って進めることが重要です。
高照度光療法
朝に強い光を浴びることで体内時計がリセットされる仕組みを使い、朝、身体の中心部の体温が上昇し始める時間に、人工的につくった明るい光を浴びる治療法です。
不眠の原因によっても対処法は異なってきますが、まずはご家庭でできることを試し、それでも改善が難しいようであれば、早めに相談機関につながるようにしましょう。

【専門家監修】図解で分かる発達障害。3つのタイプと原因、診断など

お昼寝失敗で癇癪、寝かしつけに数時間。眠れないASD息子に効果的だったのは?正論アドバイスに傷ついた乳幼児期

睡眠障害のあるASD娘、高校受験を前に投薬開始!「眠れるけど起きる時間は…」本人の下した決断、そして進路は

Sponsored
発達障害がある子の不眠、寝具で解消!? 体と心に「ぴったり」寄り添うチェーンブランケットを紹介!

悪夢が怖い!発達障害むっくんの「眠れない」問題、どうしたら?母も入眠障害に…親子で向き合った睡眠問題の年長から小2現在

子どもの癇癪(かんしゃく)とは?癇癪を起こす原因や発達障害との関連は?しんどいときの対応方法、相談先まとめ【専門家監修】















