「年齢より3割幼いと思ってね」医師の言葉通り息子を見守るも…
ライター:かなしろにゃんこ。
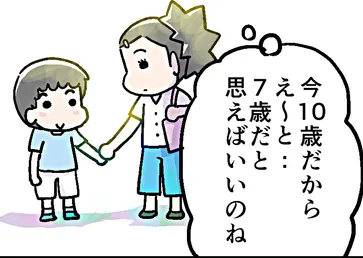
Upload By かなしろにゃんこ。
ADHDがある高校生3年生の息子の母です。ドタバタ育児マンガをつづっていきますので、よろしくお願いします。今回は、子どもの発達と実年齢の違いのお話です。
専門家による“発達障害のある高校生への対応”と共にご覧ください。

監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
発達障害の高校生への保護者の対応は?
発達障害における特徴の表れ方は、年齢によって変化してきます。まだ幼いと思っていても高校生になると自分と周囲の違いを強く意識するようになり、これまでと違った困り事を抱えることも出てきます。そんな時保護者はどのように対応すればいいのでしょうか。
友逹関係で悩んでいた時
家族より友逹との世界が重要になってくる時期ですが、発達障害のある子どもはグループでの行動が苦手だったり、話の内容についていけない、相手との間で誤解が生じるなどして孤立する場合もあります。また過度に友逹の意見に合わせたり誘いに応じてしまうことで、強いストレスを感じている子どもも少なくありません。
そんな時保護者はあれこれ聞き出すよりも、お子さんに「困ったときにはいつでも相談にのるからね」と伝えておくとよいでしょう。また、例えば相手の誘いを断れず困っている場合は、相手が不快になりにくい具体的な断り方などを教えて、だんだんと本人が対処できるようにしていくという方法もあります。
そんな時保護者はあれこれ聞き出すよりも、お子さんに「困ったときにはいつでも相談にのるからね」と伝えておくとよいでしょう。また、例えば相手の誘いを断れず困っている場合は、相手が不快になりにくい具体的な断り方などを教えて、だんだんと本人が対処できるようにしていくという方法もあります。
自己肯定感が低下している時
自分の特性に気づき、友逹との違いや苦手なことがある劣等感から、自分のことを否定的に捉えてしまうことがあります。これが続くとうつ状態や不登校などの二次障害を引き起こす可能性もあります。
この場合、保護者は「子どもの意見を聞く・認める」ことが大切です。本人が対応を間違えた時も、まずは子どもの言い分をしっかり聞きましょう。「ちゃんとやりなさい」といった否定の言葉はかけず「私はこう考えるけれど、あなたはどう考える?」などと本人が考えていることを聞いてできるところを褒め、子どもが安心するように「次はうまくいくよ。応援しているよ」と伝えてみてください。
まだ幼く感じられるようであっても、子ども自身成長しています。大人が考えたことを「正解」としてアドバイスするよりも、選択肢や判断基準を伝え本人に最終的に決定させる形の支援が必要になってきます。本人の自立したいという気持ちを尊重しながらも、サポート自体はやめず、これまでとは違う声かけ・サポート方法を心がけましょう。
この場合、保護者は「子どもの意見を聞く・認める」ことが大切です。本人が対応を間違えた時も、まずは子どもの言い分をしっかり聞きましょう。「ちゃんとやりなさい」といった否定の言葉はかけず「私はこう考えるけれど、あなたはどう考える?」などと本人が考えていることを聞いてできるところを褒め、子どもが安心するように「次はうまくいくよ。応援しているよ」と伝えてみてください。
まだ幼く感じられるようであっても、子ども自身成長しています。大人が考えたことを「正解」としてアドバイスするよりも、選択肢や判断基準を伝え本人に最終的に決定させる形の支援が必要になってきます。本人の自立したいという気持ちを尊重しながらも、サポート自体はやめず、これまでとは違う声かけ・サポート方法を心がけましょう。
以下は、ADHD(注意欠如多動症)のお子さんが高校生になって保護者さまが感じられていることをご共有いただいた体験談です。専門家のコメントと併せてご覧ください。
実年齢より3割幼い?
かかりつけの児童精神科医に、「発達障害のある子は、実年齢より3割幼いと思って向き合ってください」
とのアドバイスをもらったことがあります。
息子は18歳なので、そろそろこの「3割幼い」の見方を改めたい気持ちもありますが、続けています。
人間関係の問題が起こると考え方が幼いと感じることがあるからです。
とのアドバイスをもらったことがあります。
息子は18歳なので、そろそろこの「3割幼い」の見方を改めたい気持ちもありますが、続けています。
人間関係の問題が起こると考え方が幼いと感じることがあるからです。
心の発達がゆっくりなのは?
以前、大人の発達障害の『当事者会』をされている大先輩に
発達障害のことをお聞きした際にこんなことをおっしゃっていました。
「集団生活の中で発達する機会に恵まれなかった人もいます。
発達に障害があるのではなく、発達する機会に障害があると思うんです」と。
発達に遅れがあることでお友だちとの関わりが減り、心や考えを成長させる機会が少なくなるということなんでしょうね。
この当事者会では、コミュニケーションスキルを学ぶワークショップを、毎回開催しています。
成人向けですが、私のように保護者として参加している方もたくさんいらっしゃいました。
参加するたびに、発達障害のある大先輩とたくさんお会いします。
当事者の方とのお話はいつも参考になり、私にたくさんのことを教えてくださるので、とても貴重な時間です。
発達障害のことをお聞きした際にこんなことをおっしゃっていました。
「集団生活の中で発達する機会に恵まれなかった人もいます。
発達に障害があるのではなく、発達する機会に障害があると思うんです」と。
発達に遅れがあることでお友だちとの関わりが減り、心や考えを成長させる機会が少なくなるということなんでしょうね。
この当事者会では、コミュニケーションスキルを学ぶワークショップを、毎回開催しています。
成人向けですが、私のように保護者として参加している方もたくさんいらっしゃいました。
参加するたびに、発達障害のある大先輩とたくさんお会いします。
当事者の方とのお話はいつも参考になり、私にたくさんのことを教えてくださるので、とても貴重な時間です。
執筆/かなしろにゃんこ。
(監修:井上先生より)
発達障害のあるお子さんの思春期の特性として、「両価性」という相反する感情などを同時に持つということがあります。例えば、幼い面もあれば反対に自立しすぎる面もある、また、この前は積極的な意見を言っていたのに、今日は否定的なことを言うなど、言葉と行動に一貫性がないことです。保護者は混乱してしまうかもしれませんが、お子さんの理不尽だったり極端な行動についても、ゆっくり話を聞いてあげることが大事です。お子さんの考えの中の矛盾点、社会的常識との乖離については、お子さんの考えを理解しながら客観的に言語化して、解決方法を一緒に考えていくような関わりができるといいでしょう。
保護者の方も、お子さんが10代後半になると『成人になるまでになんとかしなければ』と焦ってしまうかもしれません。ですが、感情的、否定的にならず、引き続きできないことに注目するより、望ましいことをやったときは年齢にあわせて上手に褒めるようにしましょう。
(監修:井上先生より)
発達障害のあるお子さんの思春期の特性として、「両価性」という相反する感情などを同時に持つということがあります。例えば、幼い面もあれば反対に自立しすぎる面もある、また、この前は積極的な意見を言っていたのに、今日は否定的なことを言うなど、言葉と行動に一貫性がないことです。保護者は混乱してしまうかもしれませんが、お子さんの理不尽だったり極端な行動についても、ゆっくり話を聞いてあげることが大事です。お子さんの考えの中の矛盾点、社会的常識との乖離については、お子さんの考えを理解しながら客観的に言語化して、解決方法を一緒に考えていくような関わりができるといいでしょう。
保護者の方も、お子さんが10代後半になると『成人になるまでになんとかしなければ』と焦ってしまうかもしれません。ですが、感情的、否定的にならず、引き続きできないことに注目するより、望ましいことをやったときは年齢にあわせて上手に褒めるようにしましょう。

【ADHD(注意欠如多動症)】幼児期から成人期まで、年齢別の特徴や症状の現れ方を解説します【専門家監修】

子どもの「見せたくない理由」を聞いたら、大人はどんな風に対応する?
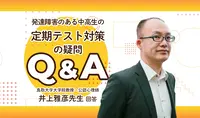
ケアレスミス、字が汚い…発達障害中高校生、定期テスト対策は【専門家QA】

ASD(自閉スペクトラム症)の特徴は?0歳から学齢期、成人期までの年齢別に紹介【専門家監修】
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
















