発達障害とモロー反射の関連は?
先ほどもご紹介したように、モロー反射をはじめとする原始反射は発達状態のバロメーターです。この点から、原始反射が強く残存している場合、脳機能への問題が考えられます。そしてそれが発達障害の兆候である可能性もあるのです。
モロー反射が長く続くということは、外からの刺激に毎回反応してしまう、つまり刺激に対して敏感な状態が続くと解釈できます。そのため、以下の発達障害のような傾向が見られることがあります。
・音や光をはじめとする刺激に対する感覚過敏
・社会的未熟さ(新しい状況・環境への参加対応が難しい)
必ずしもモロー反射が長く続く=発達障害である、というわけではありません。しかし、モロー反射をはじめとする原始反射が長く続けば続くほど何らかの問題がある可能性が高まります。いざというときのために、日頃から子どもの動作をよく観察したり、場合によっては記録したりすることが大切です。
モロー反射が長く続くということは、外からの刺激に毎回反応してしまう、つまり刺激に対して敏感な状態が続くと解釈できます。そのため、以下の発達障害のような傾向が見られることがあります。
・音や光をはじめとする刺激に対する感覚過敏
・社会的未熟さ(新しい状況・環境への参加対応が難しい)
必ずしもモロー反射が長く続く=発達障害である、というわけではありません。しかし、モロー反射をはじめとする原始反射が長く続けば続くほど何らかの問題がある可能性が高まります。いざというときのために、日頃から子どもの動作をよく観察したり、場合によっては記録したりすることが大切です。
モロー反射が激しいときはどうすればいいの?
では、子どものモロー反射で不安を感じる場合、どうすればよいのでしょうか。多くのパパ・ママが子どものモロー反射に不安を感じることとして、モロー反射が激しく、子どもが泣きだすというケースが挙げられます。
これは、大きな刺激に対して大きな動きで反応した赤ちゃんが、刺激と自分の動きに対してびっくりしてしまい、その衝撃で泣く、というメカニズムで起こります。モロー反射は刺激に対する無意識の反応のため、パパ・ママにできることとしては赤ちゃんに不要な刺激を与えないように環境を整えてあげることが必要です。
・大きな音をなるべく立てない
・赤ちゃんが極端な熱さ、冷たさに触れないようにする(冷たい風や指でも赤ちゃんはびっくりしてモロー反射を起こすことがあります。)
・こまめなスキンシップで赤ちゃんを安心させてあげる
また、寝かしつけの際に赤ちゃんがモロー反射を起こし、なかなか寝てくれなくて悩んでいる...というパパ・ママもいるかもしれません。この場合、寝かしつけるとき、特に赤ちゃんをだっこしている腕の中からベッドへ移すときがポイントです。赤ちゃんにとって刺激となる要因をできるだけ少なくする、以下のような工夫をすることが大切です。
・ベビーベッド・赤ちゃんの寝具を、だっこされている腕の中の体温くらいにあたためておく
・だっこから腕を抜くときに、赤ちゃんの首の角度や体勢が大きく変わらないようにする
・扇風機の風やヒーターの光が赤ちゃんに直接当たらないようにする
このように、モロー反射が激しく、一度起こるとしばらく泣き続けてしまうなどという場合、まずは子どもに余計な刺激を与えないような環境づくりをすることが重要です。また、モロー反射から泣きだす子どもの大半はびっくりして泣いています。パパ・ママがこまめにスキンシップをとることで赤ちゃんを安心させてあげることも一つの方法です。
これは、大きな刺激に対して大きな動きで反応した赤ちゃんが、刺激と自分の動きに対してびっくりしてしまい、その衝撃で泣く、というメカニズムで起こります。モロー反射は刺激に対する無意識の反応のため、パパ・ママにできることとしては赤ちゃんに不要な刺激を与えないように環境を整えてあげることが必要です。
・大きな音をなるべく立てない
・赤ちゃんが極端な熱さ、冷たさに触れないようにする(冷たい風や指でも赤ちゃんはびっくりしてモロー反射を起こすことがあります。)
・こまめなスキンシップで赤ちゃんを安心させてあげる
また、寝かしつけの際に赤ちゃんがモロー反射を起こし、なかなか寝てくれなくて悩んでいる...というパパ・ママもいるかもしれません。この場合、寝かしつけるとき、特に赤ちゃんをだっこしている腕の中からベッドへ移すときがポイントです。赤ちゃんにとって刺激となる要因をできるだけ少なくする、以下のような工夫をすることが大切です。
・ベビーベッド・赤ちゃんの寝具を、だっこされている腕の中の体温くらいにあたためておく
・だっこから腕を抜くときに、赤ちゃんの首の角度や体勢が大きく変わらないようにする
・扇風機の風やヒーターの光が赤ちゃんに直接当たらないようにする
このように、モロー反射が激しく、一度起こるとしばらく泣き続けてしまうなどという場合、まずは子どもに余計な刺激を与えないような環境づくりをすることが重要です。また、モロー反射から泣きだす子どもの大半はびっくりして泣いています。パパ・ママがこまめにスキンシップをとることで赤ちゃんを安心させてあげることも一つの方法です。
まとめ
モロー反射とは0~4ヶ月で見られる原始反射の一種です。大きな刺激を受けた時に身体をびくっとさせ、両手を広げてしがみつくようにする動作は赤ちゃんならではのとても可愛らしい動作です。
また、ただかわいい動作であるだけでなく、モロー反射をはじめとした原始反射は子どもの発達状態の一つの重要な指標となります。原始反射の始まりと終わりの時期や動作の特徴などで子どもの発達状態に問題がないか気づくきっかけになることがあります。
モロー反射とさまざまな疾患・発達障害との関係についてもご紹介しましたが、実際パパ・ママにとって、モロー反射と他の疾患の症状を区別することは難しいケースが多いです。モロー反射などの原始反射を通して、少しでも不安を感じたときは乳幼児健診の際に保健士や医師に相談したり、行きつけの小児科へ相談したりすることをおすすめします。
また、ただかわいい動作であるだけでなく、モロー反射をはじめとした原始反射は子どもの発達状態の一つの重要な指標となります。原始反射の始まりと終わりの時期や動作の特徴などで子どもの発達状態に問題がないか気づくきっかけになることがあります。
モロー反射とさまざまな疾患・発達障害との関係についてもご紹介しましたが、実際パパ・ママにとって、モロー反射と他の疾患の症状を区別することは難しいケースが多いです。モロー反射などの原始反射を通して、少しでも不安を感じたときは乳幼児健診の際に保健士や医師に相談したり、行きつけの小児科へ相談したりすることをおすすめします。
はじめてママ&パパの育児―0~3才赤ちゃんとの暮らし 気がかりがスッキリ!
主婦の友社
Amazonで詳しく見る

モロー反射とは?新生児から生後何ヶ月くらいまで見られる?激しいときの対処法やてんかんとの違い、脳性麻痺や発達障害との関係についても解説【小児科医監修】

【医師監修】低緊張(筋緊張低下)とは。低緊張の赤ちゃんの症状、原因疾患、発達障害との関連、治療法を解説
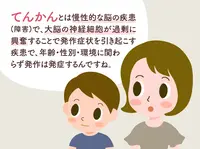
てんかん(癲癇)とは?原因や発作のパターンをイラストで詳しく解説。4つの診断の種類なども【医師監修】

てんかん(癲癇)を起こしたら?小児(子ども)の場合は?てんかんの診断や検査、治療方法をイラスト付きで分かりやすく解説【医師監修】

熱性痙攣(けいれん)とは?原因や対応方法、てんかんとの違い、救急車を呼ぶべき状態の見極めかたなどについて詳しく解説します【医師監修】

子どもの癇癪(かんしゃく)とは?癇癪を起こす原因や発達障害との関連は?しんどいときの対応方法、相談先まとめ【専門家監修】

-
 1
1
- 2














