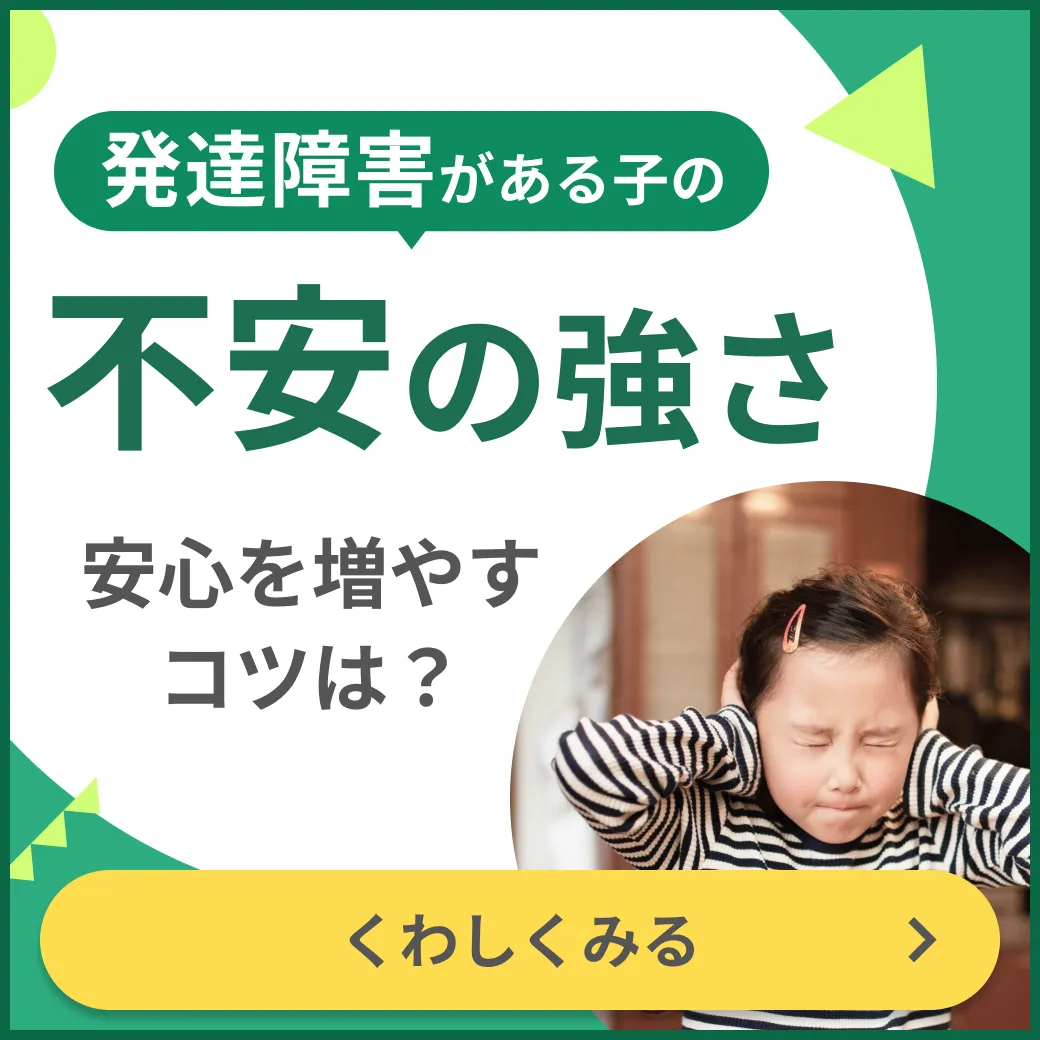子どもが起立性調節障害と診断されたら、どんなことに気をつけたらいい?
平常心を保つ
もしもご自身の子どもが起立性調節障害と診断された場合、まず気をつけたいのが「平常心を保つ」ことです。起立性調節障害の治療には時間がかかるため、「どのくらいで良くなるのか」「学校に行けるようになるのか」など、保護者が不安になってしまうことも少なくありません。起立性調節障害は体の病気であると分かっていても、不安を感じることはあると思います。
しかし、不安から子どもを叱ってしまったり、イライラした気持ちを表に出したりしてしまうと、子どもとの関係が悪くなってしまうかもしれません。まずは平常心を保つという心構えを大切にした上で、日常生活のサポートをしていきましょう。
しかし、不安から子どもを叱ってしまったり、イライラした気持ちを表に出したりしてしまうと、子どもとの関係が悪くなってしまうかもしれません。まずは平常心を保つという心構えを大切にした上で、日常生活のサポートをしていきましょう。
生活リズムを保つようにする
毎日の生活の中では、起立性調節障害の治療の中で説明した、「非薬物療法(日常生活における注意点)」を工夫して行っていくことが大切です。起立性調節障害の子どもは朝起きるのが苦手なので、生活リズムの改善は難しいことが多いです。すぐに改善することはできないと理解した上で、子どものサポートを行っていきましょう。
また、家族全体でルールを共有し、一定の生活パターンを送ることも有用です。テレビを見る時間を決める、夕食は全員で食べるなど、家族と話し合って可能なものからルールを作ってみると良いでしょう。それらの生活パターンが、子どもの体のリズムにも良い影響を与えてくれます。
また、家族全体でルールを共有し、一定の生活パターンを送ることも有用です。テレビを見る時間を決める、夕食は全員で食べるなど、家族と話し合って可能なものからルールを作ってみると良いでしょう。それらの生活パターンが、子どもの体のリズムにも良い影響を与えてくれます。
勉強の遅れをサポートする
起立性調節障害を持つ子どもは、脳の血流量が少なくなっているため、授業に集中できずに学力が低下したり、欠席が続くと授業に遅れてしまうこともあります。
起立性調節障害の場合、夕方から夜は比較的元気に過ごせることも多いです。学業面が心配な場合、学校に放課後の補習をお願いしたり、塾や家庭教師を活用したりしても良いでしょう。
起立性調節障害の場合、夕方から夜は比較的元気に過ごせることも多いです。学業面が心配な場合、学校に放課後の補習をお願いしたり、塾や家庭教師を活用したりしても良いでしょう。
無理をせず、家族でよく話し合う
起立性調節障害の子どもをサポートする上で、子どもに無理をさせないこと、家族でしっかりと話をすることも大切なポイントです。保護者が良かれと思って、朝無理に起こしたり登校を促したりすることが、反対に子どものストレスとなってしまうことも考えられます。
また、保護者が心配しすぎないようにしましょう。起立性調節障害の治療には時間がかかりますし、考えすぎると保護者も精神的に疲れてしまいます。治療やサポートは、子どものペースに合わせて進めていくことが大切です。
また、保護者が心配しすぎないようにしましょう。起立性調節障害の治療には時間がかかりますし、考えすぎると保護者も精神的に疲れてしまいます。治療やサポートは、子どものペースに合わせて進めていくことが大切です。
まとめ
起立性調節障害は、気持ちの問題だと誤解されやすい病気ですが、体の病気です。人によっては治療が必要なこともあり、回復するまでに時間を要することも少なくありません。病気そのものの認知度もまだ低いため、起立性調節障害と診断されずに、苦しい思いをしている子どもや保護者も多くいると考えられています。
適切な治療をすることで、起立性調節障害の症状は改善する可能性があります。もし該当する症状や心配な症状があるようであれば、診断が可能な小児科のある医療機関を受診してみてはいかがでしょうか。
適切な治療をすることで、起立性調節障害の症状は改善する可能性があります。もし該当する症状や心配な症状があるようであれば、診断が可能な小児科のある医療機関を受診してみてはいかがでしょうか。
参考
改訂 起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応
中央法規出版
Amazonで詳しく見る
改訂 起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック
中央法規出版
Amazonで詳しく見る
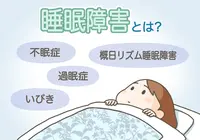
子どもの睡眠障害の症状や対処法、発達障害との関係【医師監修】
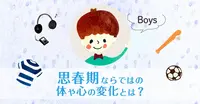
発達障害の男の子、思春期はどんな時期?変化の内容や大人の関わり方のポイントを解説!

女の子の発達障害、思春期に起こる身体と心の変化とは?【専門家監修】