自閉症息子のこだわりと、親の障害受容。段階を踏んで関わり方を変えた結果…!?【読者体験談】
ライター:ユーザー体験談

Upload By ユーザー体験談
【発達ナビでは読者からのエピソードを募集中!今回は「こだわり」「障害受容」」についてのエピソードをご紹介します。】現在小学3年生の息子は、2歳の時に知的障害(精神発達遅滞)、自閉スペクトラム症(非定型自閉症)の診断を受けています。息子のこだわりは赤ちゃんの頃から始まり、いまも絶好調。ですが、私の息子のこだわりへの対応は、障害受容の度合いによって変わってきました。

監修: 鈴木直光
筑波こどものこころクリニック院長
1959年東京都生まれ。1985年秋田大学医学部卒。在学中YMCAキャンプリーダーで初めて自閉症児に出会う。同年東京医科歯科大学小児科入局。
1987〜88年、瀬川小児神経学クリニックで自閉症と神経学を学び、栃木県県南健康福祉センターの発達相談で数々の発達障がい児と出会う。2011年、茨城県つくば市に筑波こどものこころクリニック開院。
遠回り、マンホール観察…自閉症息子のこだわりは私の体力を削り続け…
現在小学3年生の息子は、2歳の時に知的障害(精神発達遅滞)、自閉スペクトラム症(非定型自閉症)の診断を受けています。
息子のこだわりに気づき始めたのは9ヶ月、離乳食後期の頃でした。それまで私がスプーンで食べさせていたのですが、これを急に拒否!自分の手で食べるようになり、それからはクリームシチューや餡かけなどのトロッとした物は一切受け付けなくなりました。トロッとしたものが本当に嫌だったんでしょうね…。
息子のこだわりはここからはじまり、いまも絶好調!行きたい場所、やるべきことにこだわりまくり、私の体力を遠慮なく削っていきます。
例えば……
・駅までまっすぐ歩いたら徒歩5分のところを、わざわざ遠回りをして2~3倍の時間と距離をかけて移動。
・電車で帰れば10分のところなのに、バスで1時間近くかけて帰る。しかも最後列右側の席限定!
・髪の毛が地面についてもおかまいなし。マンホールがある度に中をのぞいたりにおいをかぐ。マンホールは数メートルごとにあるので、全然進まない……。
・目の前の信号が青なのに拒否し、遠い場所にある決まった信号からしか渡らない!
・エレベーターに乗ったら、僕は右側、ママは左側のボタンの横で立ってという指示。満員だから無理だよと伝えても、ママは左側へ行けと妥協なし……。
大雨や大荷物でクタクタのときも、暑すぎる真夏でも、寒すぎる冬でも容赦なく発動されるこれらのこだわり。腰痛もちの私はもう限界に近いです……。
息子のこだわりに気づき始めたのは9ヶ月、離乳食後期の頃でした。それまで私がスプーンで食べさせていたのですが、これを急に拒否!自分の手で食べるようになり、それからはクリームシチューや餡かけなどのトロッとした物は一切受け付けなくなりました。トロッとしたものが本当に嫌だったんでしょうね…。
息子のこだわりはここからはじまり、いまも絶好調!行きたい場所、やるべきことにこだわりまくり、私の体力を遠慮なく削っていきます。
例えば……
・駅までまっすぐ歩いたら徒歩5分のところを、わざわざ遠回りをして2~3倍の時間と距離をかけて移動。
・電車で帰れば10分のところなのに、バスで1時間近くかけて帰る。しかも最後列右側の席限定!
・髪の毛が地面についてもおかまいなし。マンホールがある度に中をのぞいたりにおいをかぐ。マンホールは数メートルごとにあるので、全然進まない……。
・目の前の信号が青なのに拒否し、遠い場所にある決まった信号からしか渡らない!
・エレベーターに乗ったら、僕は右側、ママは左側のボタンの横で立ってという指示。満員だから無理だよと伝えても、ママは左側へ行けと妥協なし……。
大雨や大荷物でクタクタのときも、暑すぎる真夏でも、寒すぎる冬でも容赦なく発動されるこれらのこだわり。腰痛もちの私はもう限界に近いです……。
息子のこだわりへの対応は、私の障害受容レベルによって変化してきました
そんな息子のこだわりへの私の対応は、だんだんと変化してきました。それは、私自身の障害受容のレベルとも深く関係していると思います。いまに至るまで、3段階を経てきました。
1段階目、まだ障害受容ができていなかったころは、同じことの繰り返しに親のほうが飽きてしまってイライラすることが多く、止めさせようとしたこともありました。ですが、止めさせようとすると子どもが癇癪を起こすなどお互いにストレスをためてしまい、デメリットが多くあったと思います。
そして2段階目、障害受容していたつもりでただ自分が我慢していただけの頃、全て好きなようにやらせて、私がそれに合わせて行動するという期間がありました。いま思い返すと、思考停止になることで楽になりたかった時期です。
その後、海外で生活をした際に幼稚園の先生がとても広い気持ちで受容・対応してくれているのを目の当たりにし、自分自身がどこかでまだ障害を受容し切れていなかったことに気づきました。それからは周りの人に子どもの障害についてオープンにし、積極的に助けてもらうようになりました。これが3段階目です。
1段階目、まだ障害受容ができていなかったころは、同じことの繰り返しに親のほうが飽きてしまってイライラすることが多く、止めさせようとしたこともありました。ですが、止めさせようとすると子どもが癇癪を起こすなどお互いにストレスをためてしまい、デメリットが多くあったと思います。
そして2段階目、障害受容していたつもりでただ自分が我慢していただけの頃、全て好きなようにやらせて、私がそれに合わせて行動するという期間がありました。いま思い返すと、思考停止になることで楽になりたかった時期です。
その後、海外で生活をした際に幼稚園の先生がとても広い気持ちで受容・対応してくれているのを目の当たりにし、自分自身がどこかでまだ障害を受容し切れていなかったことに気づきました。それからは周りの人に子どもの障害についてオープンにし、積極的に助けてもらうようになりました。これが3段階目です。
海外に住んでいた頃、まだ学習できていないものなのか(未学習)、間違ったことを正しいと誤って学習してしまったものなのか(誤学習)を意識しつつ、子どもの個性を大事にしていくことの大切さを学びました。
いまは、ただ好きにやらせるのではなく、子どもに対しては基本的には本人の意向に沿いつつ、こだわり、ルールを完全に定型化しないよう、たまに「揺らし」を入れて妥協を覚えさせるように練習しています。
例えば、息子が、放課後等デイサービスの送迎で覚えた電車の見えるスポットに連れて行ってくれるとき。目的地も分からず「こっち」といってひたすら歩かされ、だいたい1万~1万2千歩くこともざらだったのですが、息子にどんなところに行こうとしているのか、そこで何がしたいのかを先に伝えてもらうように練習しました。それを聞いた上で、行けるときは行く、行けないときは理由を伝えて、次にこういう条件になったときに行こうという約束と、本日の代替プランBを提案して選択してもらっています。
また、遠回りをする、決まった道を通ろうとするときは、「こっちは草がいっぱい生えてるから、ここから先は歩道に出ようか」、「今日はゴミが落ちてるからそっちは通らないよ」などと正当な理由を伝えて、別の道に勧めるようにしています。最初は「こっち!」と嫌がっていましたが、実際に歩いてみて「ほらね、草がいっぱいでしょ?」「あそこに犬の糞がある」などと経験することで納得してくれ、ちょっとずつ妥協を覚えてくれるようになりました。
このように対応できるようになって、私も精神的に楽になりました。
いまは、ただ好きにやらせるのではなく、子どもに対しては基本的には本人の意向に沿いつつ、こだわり、ルールを完全に定型化しないよう、たまに「揺らし」を入れて妥協を覚えさせるように練習しています。
例えば、息子が、放課後等デイサービスの送迎で覚えた電車の見えるスポットに連れて行ってくれるとき。目的地も分からず「こっち」といってひたすら歩かされ、だいたい1万~1万2千歩くこともざらだったのですが、息子にどんなところに行こうとしているのか、そこで何がしたいのかを先に伝えてもらうように練習しました。それを聞いた上で、行けるときは行く、行けないときは理由を伝えて、次にこういう条件になったときに行こうという約束と、本日の代替プランBを提案して選択してもらっています。
また、遠回りをする、決まった道を通ろうとするときは、「こっちは草がいっぱい生えてるから、ここから先は歩道に出ようか」、「今日はゴミが落ちてるからそっちは通らないよ」などと正当な理由を伝えて、別の道に勧めるようにしています。最初は「こっち!」と嫌がっていましたが、実際に歩いてみて「ほらね、草がいっぱいでしょ?」「あそこに犬の糞がある」などと経験することで納得してくれ、ちょっとずつ妥協を覚えてくれるようになりました。
このように対応できるようになって、私も精神的に楽になりました。
「こだわりはいつか必ず強みになる」息子の人生が楽しいものであるように心から願っています
息子が2歳のときに通っていた体操教室の先生が「こだわりはいつか必ず強みになる」と言ってくださったのが強く記憶に残っています。
息子には強い好奇心、記憶力、研ぎ澄まされた色彩感覚、卓越した運動能力、ソムリエ並みの味覚があります。これらを生かして「好き」から「得意」を見つけ自己肯定感を得て、もしその得意なことから将来仕事に繋がるものを見つけられたら最高だなと思っています。もし職業に繋がらなくても、これから生きていく中での毎日の楽しみや生き甲斐になれば充分です。
ひとりっ子で、ママ命の甘えたがり。注意されると全否定されたと感じるようで、素直に聞き入れられずつい文句を言ってしまう……そんな息子に、これからも体力の限界までつき合っていきたいと思います!
ひとりっ子で、ママ命の甘えたがり。注意されると全否定されたと感じるようで、素直に聞き入れられずつい文句を言ってしまう……そんな息子に、これからも体力の限界までつき合っていきたいと思います!
エピソード参考/おかんレベル8
イラスト/カタバミ
(監修:鈴木先生より)
ASDには、こだわり保存の法則というのがあります。あるこだわりが減ると、ほかののこだわりが増えるということです。ある道に興味がなくなっても、ほかの道にまた興味がわくかもしれません。
また、自分だけではなく、他人、特に親をこだわりを巻き込むことがあります。これを「巻き込みこだわり」と言います。自分が青い服を着たら親にも同じ色の服を着せるなど、自分以外の人にもこだわりを巻き込ませるのです。
ASDの子どもは予定の変更が苦手です。こだわりがASDの子どもの「予定」の中に既に入っているので、それを変更することは困難になります。可能ならば、なるべく早めに予定の変更を提示してあげることも重要です。誰でも突然変更されると嫌なものです。これからもこういうASDの特性を理解してつき合っていきましょう。
イラスト/カタバミ
(監修:鈴木先生より)
ASDには、こだわり保存の法則というのがあります。あるこだわりが減ると、ほかののこだわりが増えるということです。ある道に興味がなくなっても、ほかの道にまた興味がわくかもしれません。
また、自分だけではなく、他人、特に親をこだわりを巻き込むことがあります。これを「巻き込みこだわり」と言います。自分が青い服を着たら親にも同じ色の服を着せるなど、自分以外の人にもこだわりを巻き込ませるのです。
ASDの子どもは予定の変更が苦手です。こだわりがASDの子どもの「予定」の中に既に入っているので、それを変更することは困難になります。可能ならば、なるべく早めに予定の変更を提示してあげることも重要です。誰でも突然変更されると嫌なものです。これからもこういうASDの特性を理解してつき合っていきましょう。

ASD(自閉スペクトラム症)の子どもへの接し方は?子育ての困難と対処法、ペアトレ・レスパイトの活用まで【専門家監修】

ASD(自閉スペクトラム症)とは?専門機関や診断基準を解説【専門家監修】
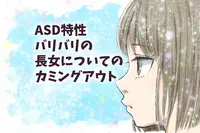
わが子の障害、実母や義実家、ママ友にどう伝える?それぞれの反応と私の考え【専門家アドバイスも】

わが子二人は発達障害、横断歩道で固まりあわや事故⁉「悪い人!」と電車内でいきなり他人を注意…。外出はいつも疲労困憊【読者体験談】

子どもの癇癪(かんしゃく)とは?癇癪を起こす原因や発達障害との関連は?しんどいときの対応方法、相談先まとめ【専門家監修】
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。



















