座席選びは戦略的に
実践されてる方も多いかもしれませんが、新幹線などでは、最前列か最後列の座席を取るのが鉄則です(わが家調べ)。理由はシンプル。デッキにすぐ出られること、トイレやゴミ箱が近いこと、これらはとても重要なポイントです。特にデッキに出られるのは、子どもがぐずったときの大きな助けになります。
また、「ちょっとゴミを捨てに行こうか」と、おやつなどで出たゴミ捨てに行くだけで、子どもが気分転換できるうえ、少し時間稼ぎもできます。
また、「ちょっとゴミを捨てに行こうか」と、おやつなどで出たゴミ捨てに行くだけで、子どもが気分転換できるうえ、少し時間稼ぎもできます。
ヘルプマークで事情をさりげなく伝える
普段はあまりつけないヘルプマークも、お出かけ時には目立つようにつけています。座席周りの人には「うるさくするかもしれませんが、すみません」と一言声をかけることで、直接の配慮を心がけていますが、当然、話しかけられない距離にいる方や、移動中以外の場所でも、ヘルプマークが「この家族には何か事情があるのかもしれない」と周囲に察してもらう役割を果たしてくれます。これだけでも心に余裕が生まれ、気持ちが少し楽になります。
わが家流の「小さな工夫」が生む大きな安心
これらはあくまでわが家の場合の工夫なので、すべてのご家庭に当てはまるわけではありません。それぞれのお子さんやご家族に合った方法がきっとあると思います!無理をせず、少しずつ試してみながら、ストレスを軽減できるお出かけや旅行を楽しめるといいですね。「みんなで楽しく過ごせたらいいな」という気持ちを大切にしながら、肩の力を抜いて取り組んでみてください。何か一つでもヒントになればうれしいです!
執筆/スパ山
執筆/スパ山
(監修:新美先生より)
お出かけ時の工夫について、具体的にたくさん教えてくださりありがとうございます。個性の強いお子さんを連れて長時間の移動を伴うお出かけは、とっても大変です。さらに公共交通機関を使う場合は、場所の制約、運行時間に合わせた行動、持っていける荷物の制限などもあり難易度は高いですよね。コラムでたくさん教えていただけたように、まずは暇つぶし対策です。長時間じっとしていないといけない状況なので、とにかく気を紛らわす暇つぶしを複数用意しておくことは必須です。お子さんによって、慣れた好きなことに集中するほうがいい、飽きないように手を変え品を変え目新しいもので次々興味をひいたほうがいいなど、さまざまかと思います。また、スケジュールなどが具体的に示されたほうが安心できるお子さんの場合は、スケジュールも示しておくこともおすすめします。座席選びやヘルプマークの使い方までいろいろ聞かせてくださりありがとうございます。皆さんの参考になったのではないでしょうか。
お出かけ時の工夫について、具体的にたくさん教えてくださりありがとうございます。個性の強いお子さんを連れて長時間の移動を伴うお出かけは、とっても大変です。さらに公共交通機関を使う場合は、場所の制約、運行時間に合わせた行動、持っていける荷物の制限などもあり難易度は高いですよね。コラムでたくさん教えていただけたように、まずは暇つぶし対策です。長時間じっとしていないといけない状況なので、とにかく気を紛らわす暇つぶしを複数用意しておくことは必須です。お子さんによって、慣れた好きなことに集中するほうがいい、飽きないように手を変え品を変え目新しいもので次々興味をひいたほうがいいなど、さまざまかと思います。また、スケジュールなどが具体的に示されたほうが安心できるお子さんの場合は、スケジュールも示しておくこともおすすめします。座席選びやヘルプマークの使い方までいろいろ聞かせてくださりありがとうございます。皆さんの参考になったのではないでしょうか。

これも自閉症の特性?「目の前にあるのに見えてない」息子が帰省で持ち帰った大荷物の中身にビックリ!
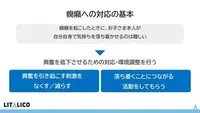
癇癪のお悩み、対応方法と減らしていくヒントは?作業療法士・野田遥さんが解説!

4歳のASD長男連れで帰省!不安な長距離移動、義実家滞在。偏食対策や移動対策で荷物がいっぱい、親は大忙しだったけれど…

自閉症息子との帰省!長距離バスで奇声、癇癪どうする?離れて暮らす祖父母の理解は?関わり方のコツも

長時間移動はパニック必至…!?ASD息子に合わせた「総崩れ回避」策で、帰省を乗り切る…!
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。


-
 1
1
- 2
















