発達支援施設での面談。支援員さんから言われた言葉が支えになって。
通っている発達支援施設では、半年に一度の面談があります。このまま通い続けるか悩んでいた私は、初めての面談で率直に「プレ幼稚園では難しかったことが、ここではできているように見えました。幼稚園や家庭では気になる点はまだあるのですが、児童発達支援を続けるか悩んでいる」と相談してみました。
支援員さんは、「発達支援施設でのたーちゃんはとっても頑張っていますよね」と褒めてくれた上で、
・「目立った困りごとがなさそうに見えても、周りにヘルプを出せなかったり、コミュニケーションが難しかったりと、気づかれにくい課題もある」
・「発達支援施設で“できる”という成功体験を積むことも、たーちゃんのプラスになるかもしれない」
・「発達について相談できる場や、保護者どうしの交流の場としても使ってほしい」
と言ってくれました。支援員さんのその言葉が支えになったことと、たーちゃんが楽しそうに通っていたこともあり、通い続けることに決めました。
支援員さんは、「発達支援施設でのたーちゃんはとっても頑張っていますよね」と褒めてくれた上で、
・「目立った困りごとがなさそうに見えても、周りにヘルプを出せなかったり、コミュニケーションが難しかったりと、気づかれにくい課題もある」
・「発達支援施設で“できる”という成功体験を積むことも、たーちゃんのプラスになるかもしれない」
・「発達について相談できる場や、保護者どうしの交流の場としても使ってほしい」
と言ってくれました。支援員さんのその言葉が支えになったことと、たーちゃんが楽しそうに通っていたこともあり、通い続けることに決めました。
発達支援施設に通って2年。通い続けて良かったこと。
児童発達支援を続けるか悩んだ時期もありましたが、年長になった現在もその施設にお世話になっています。
2年間通い続けて良かったと思うことは
・できることが増え、たーちゃんの自信に繋がったこと
・たーちゃんが困ったとき、周りにヘルプを発信できるようになったこと
・私も分かっていなかった、たーちゃんの困りごとに気づけたこと
・支援員さんや保護者の方と情報交換や相談ができたこと
です。
児童発達支援に通えるのは小学校入学前までです。あと1年間、安心してのびのび活動できる児童発達支援で、たーちゃんの個性を伸ばし、苦手なことは練習していきたいと思います。そして、たーちゃんの生きづらさを軽くできたら良いなと思っています。
同じ発達支援施設でも、障害や課題はお子さんによってさまざまです。児童発達支援を続けるか迷った時には、一度支援員さんに相談してみることをおすすめします。
2年間通い続けて良かったと思うことは
・できることが増え、たーちゃんの自信に繋がったこと
・たーちゃんが困ったとき、周りにヘルプを発信できるようになったこと
・私も分かっていなかった、たーちゃんの困りごとに気づけたこと
・支援員さんや保護者の方と情報交換や相談ができたこと
です。
児童発達支援に通えるのは小学校入学前までです。あと1年間、安心してのびのび活動できる児童発達支援で、たーちゃんの個性を伸ばし、苦手なことは練習していきたいと思います。そして、たーちゃんの生きづらさを軽くできたら良いなと思っています。
同じ発達支援施設でも、障害や課題はお子さんによってさまざまです。児童発達支援を続けるか迷った時には、一度支援員さんに相談してみることをおすすめします。
執筆/みかみかん
(監修:森先生より)
みかみかんさん、お子さんのサポートに悩まれた体験談をありがとうございます。たーちゃんの成長を見守りながら、決断を重ねてきたのですね。プレ幼稚園での苦労やメンタル的につらかった時期を乗り越え、「できた!」を一つひとつ見つけながら支えてきたその姿は、本当に素晴らしいと思います。たーちゃんが楽しそうに通い、自信をつけていく姿に勇気づけられる読者の方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
さて、ASD(自閉スペクトラム症)の傾向のあるお子さんには、コミュニケーションや社会的な相互作用の困難さ、限定された興味や反復行動などが見られることがあります。ところが、知的障害(知的発達症)を伴わないケースでは、困りごとが目立たずに、見過ごされてしまいがちです。支援員さんが指摘されたように、「気づかれにくい課題」が存在することがあるのです。感情の調整が難しい、自分の気持ちを言葉にするのが苦手、環境の変化に適応しづらい、といった点が挙げられます。一見「問題ない」ように見えても、本人にとっては大きなストレスや生きづらさに繋がることがあるのです。特性があったとしても、適切なサポートや環境調整によって、生活の質を大きく向上させることが可能です。たーちゃんのように、発達支援施設での成功体験が自信に繋がったり、ヘルプを出す力が育ったりしているのは、サポートが功を奏しているということです。「安心できる場所」や「予測可能なルーティン」が、自己肯定感や社会性の発達を助けるのです。
発達支援施設での「できる」が増える一方で、幼稚園や家庭での困りごとが残っているとのことですが、これは「場面依存性」といって、環境によって得意・不得意が分かれることがあるのです。支援機関や医療機関と情報共有をして、たーちゃんの成長に合わせて支援を調整していくと良いでしょう。発達障害の傾向のあるお子さんは、音や光、触覚などの感覚に敏感だったり鈍感だったりする「感覚処理の特性」がある場合があります。たーちゃんが立ち歩くなどの行動は、もしかすると感覚的な調整が関係しているかもしれません。支援機関や医療機関に相談して、感覚統合療法などを検討するのも一つの手です。小学校の入学の時には、学校の先生や支援員さんと早い段階で連携して、得意なことや苦手なことを伝えておくとスムーズなスタートが切れる可能性が高まります。
たーちゃんがヘルプを出せるようになったのは素晴らしい成長ですね。これをさらに伸ばすために、家でも「手伝って」「待って」などの言葉を練習する遊びを取り入れてみてください。例えば、おもちゃでごっこ遊びをしながら「助けて!」と言う場面をつくってみると、自然に身につくかもしれません。迷った時には周りに相談しながら、これからもお子さんの個性を伸ばしていけるよう、応援しています。
みかみかんさん、お子さんのサポートに悩まれた体験談をありがとうございます。たーちゃんの成長を見守りながら、決断を重ねてきたのですね。プレ幼稚園での苦労やメンタル的につらかった時期を乗り越え、「できた!」を一つひとつ見つけながら支えてきたその姿は、本当に素晴らしいと思います。たーちゃんが楽しそうに通い、自信をつけていく姿に勇気づけられる読者の方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
さて、ASD(自閉スペクトラム症)の傾向のあるお子さんには、コミュニケーションや社会的な相互作用の困難さ、限定された興味や反復行動などが見られることがあります。ところが、知的障害(知的発達症)を伴わないケースでは、困りごとが目立たずに、見過ごされてしまいがちです。支援員さんが指摘されたように、「気づかれにくい課題」が存在することがあるのです。感情の調整が難しい、自分の気持ちを言葉にするのが苦手、環境の変化に適応しづらい、といった点が挙げられます。一見「問題ない」ように見えても、本人にとっては大きなストレスや生きづらさに繋がることがあるのです。特性があったとしても、適切なサポートや環境調整によって、生活の質を大きく向上させることが可能です。たーちゃんのように、発達支援施設での成功体験が自信に繋がったり、ヘルプを出す力が育ったりしているのは、サポートが功を奏しているということです。「安心できる場所」や「予測可能なルーティン」が、自己肯定感や社会性の発達を助けるのです。
発達支援施設での「できる」が増える一方で、幼稚園や家庭での困りごとが残っているとのことですが、これは「場面依存性」といって、環境によって得意・不得意が分かれることがあるのです。支援機関や医療機関と情報共有をして、たーちゃんの成長に合わせて支援を調整していくと良いでしょう。発達障害の傾向のあるお子さんは、音や光、触覚などの感覚に敏感だったり鈍感だったりする「感覚処理の特性」がある場合があります。たーちゃんが立ち歩くなどの行動は、もしかすると感覚的な調整が関係しているかもしれません。支援機関や医療機関に相談して、感覚統合療法などを検討するのも一つの手です。小学校の入学の時には、学校の先生や支援員さんと早い段階で連携して、得意なことや苦手なことを伝えておくとスムーズなスタートが切れる可能性が高まります。
たーちゃんがヘルプを出せるようになったのは素晴らしい成長ですね。これをさらに伸ばすために、家でも「手伝って」「待って」などの言葉を練習する遊びを取り入れてみてください。例えば、おもちゃでごっこ遊びをしながら「助けて!」と言う場面をつくってみると、自然に身につくかもしれません。迷った時には周りに相談しながら、これからもお子さんの個性を伸ばしていけるよう、応援しています。

学習メインと生活メイン、タイプが違う2か所の発達支援施設に通った息子。行き渋り、癇癪…就学までの変化は?

禁止はせずに◯◯をしよう

「発達相談で様子見に」「小学生になって困りごとが増えた」発達支援の疑問を専門家が解説【発達ナビアンケート結果も】

3歳で無発語、多動だった自閉症娘。成人した今思う、児童発達支援で育てた「成長の種」【読者体験談】
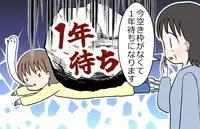
2歳息子、発達の遅れで児童発達支援をすすめられたけど…受給者証発行に3ヶ月、事業所に入れるのは…1年先!?
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-
 1
1
- 2















