打ちのめされた企業の息子に対する評価
しかし、待っていたのは企業からの厳しい評価でした。
「集中力がないので、来年の実習は受けることはできません」
「高等部3年生での実習を受け入れられない」ということは、採用を見極めるための実習への参加ができないということ。つまり「うちの会社では採用はできません」という意味です。
確かに、実習日誌の実習先からのコメントには「手が止まっていたりキョロキョロすることが多かった」「少しずつ集中が途切れてしまい、失敗してしまうはがきの枚数が増えた」「大きなあくびを3回した」と書かれていました。
このコメントを読んだとき、正直ショックでした。私が見た息子の頑張っている姿と、企業が見た息子の姿に大きなギャップがあったからです。
「障害者には単純作業を」「決まったルーティンのほうが、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは落ち着いて仕事ができる」——そういった考え方があることは理解しています。
けれども、息子の場合は少し違っていて、ずっと同じ作業を続けることがかえって難しい。むしろ、合理的配慮として「30分作業したら内容を変える」といった工夫が必要だと感じていました。
たとえば、「30分ハンコを押す作業をしたら、次は袋詰めに切り替える」といったように、単調さを避けて目先を変えていく。そうした柔軟な配慮が、息子には合っているからです。
そう考えると、この企業の対応では息子に合わないと感じました。
息子には「不合格だったよ」とは言わず「来年また違う場所で実習しようね」と伝えました。
「集中力がないので、来年の実習は受けることはできません」
「高等部3年生での実習を受け入れられない」ということは、採用を見極めるための実習への参加ができないということ。つまり「うちの会社では採用はできません」という意味です。
確かに、実習日誌の実習先からのコメントには「手が止まっていたりキョロキョロすることが多かった」「少しずつ集中が途切れてしまい、失敗してしまうはがきの枚数が増えた」「大きなあくびを3回した」と書かれていました。
このコメントを読んだとき、正直ショックでした。私が見た息子の頑張っている姿と、企業が見た息子の姿に大きなギャップがあったからです。
「障害者には単純作業を」「決まったルーティンのほうが、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは落ち着いて仕事ができる」——そういった考え方があることは理解しています。
けれども、息子の場合は少し違っていて、ずっと同じ作業を続けることがかえって難しい。むしろ、合理的配慮として「30分作業したら内容を変える」といった工夫が必要だと感じていました。
たとえば、「30分ハンコを押す作業をしたら、次は袋詰めに切り替える」といったように、単調さを避けて目先を変えていく。そうした柔軟な配慮が、息子には合っているからです。
そう考えると、この企業の対応では息子に合わないと感じました。
息子には「不合格だったよ」とは言わず「来年また違う場所で実習しようね」と伝えました。
3年生での実習は就労移行支援事業所を考えるように
息子は実習を頑張っていましたが、企業が求めるレベルは想像以上に高いものでした。そして、息子の状態では、高等部卒業後すぐに企業に就労することは難しいと感じる出来事でした。
そこで、就労移行支援事業所で高等部卒業後もスキルを学ぶことを希望し、就労移行支援事業所を本格的に探すようになったのです。
次回は、就労移行支援事業所を選ぶ際の見学体験などについてお話しさせていただきます。
そこで、就労移行支援事業所で高等部卒業後もスキルを学ぶことを希望し、就労移行支援事業所を本格的に探すようになったのです。
次回は、就労移行支援事業所を選ぶ際の見学体験などについてお話しさせていただきます。
執筆/立石美津子
(監修:渡部先生より)
特別支援学校卒業後については、一般企業や福祉的就労といったカテゴリーにこだわるより、本人の特性に合った進路を選択してほしいと思います。でも、企業就労を目指す子たちの中にいて、実際に就職が決まった情報などが聞こえてくると、親はどうしても「うちの子もできれば一般就労してほしい」と思いがちですよね。もしかしたら生徒さん本人も、同じ気持ちになることが多いのかもしれません。
ただ、実習に行った先で厳しい評価をされてしまうことはよくあるようです。そんな場合にも、立石さんのように「来年また違う場所で実習しようね」と本人に伝えるということは、とても参考になると思います。本人としては慣れない場所に通って、頑張って実習に取り組んだのに、「不合格」という結果だけ聞いたら傷ついてしまいます。言い方を工夫して、次のステップに進めるようにしてあげるのは、大切なことですね。
(監修:渡部先生より)
特別支援学校卒業後については、一般企業や福祉的就労といったカテゴリーにこだわるより、本人の特性に合った進路を選択してほしいと思います。でも、企業就労を目指す子たちの中にいて、実際に就職が決まった情報などが聞こえてくると、親はどうしても「うちの子もできれば一般就労してほしい」と思いがちですよね。もしかしたら生徒さん本人も、同じ気持ちになることが多いのかもしれません。
ただ、実習に行った先で厳しい評価をされてしまうことはよくあるようです。そんな場合にも、立石さんのように「来年また違う場所で実習しようね」と本人に伝えるということは、とても参考になると思います。本人としては慣れない場所に通って、頑張って実習に取り組んだのに、「不合格」という結果だけ聞いたら傷ついてしまいます。言い方を工夫して、次のステップに進めるようにしてあげるのは、大切なことですね。
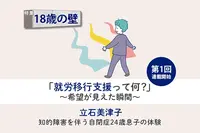
知的障害息子も企業で働けるかもしれない…希望を持てた「就労移行支援」との出合い【18歳の壁/立石美津子 第1回】

就労移行支援とは?就労継続支援との違い、対象者や利用期間、利用料などを解説

活動に最後まで取り組めなくて困る…そんな時はどうすればいい?

大学中退後分かった発達障害。障害者雇用、就労移行支援、就労継続支援A型、B型を経験し、目標へ向けて進む今【読者体験談】

「進路どうする?」に無言…自閉症娘と悩み見つけた就労移行支援事業所、自分らしく働く道へ【読者体験談】

障害福祉サービスとは?介護保険との違いは?支援の対象者、申請の手続き、審査基準、利用費を解説!
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-
 1
1
- 2














