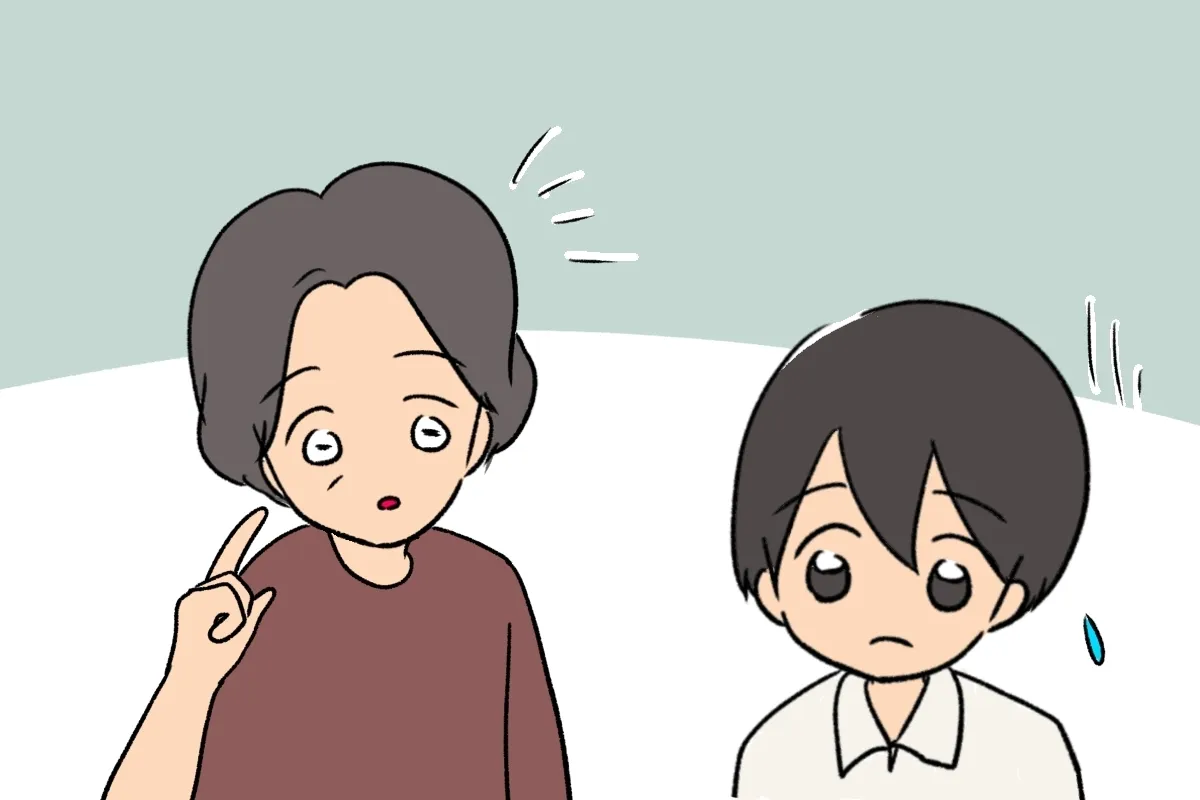「ズボンのチクチク」から始まった、発達障害息子の「中1の壁」。制服、勉強、先生との関係…どう乗り越えた?
ライター:メイ

Upload By メイ
こんにちは。メイです。
息子のトールは現在中学1年生。ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の診断を受けています。今回は小学校とは環境が大きく変わる中学校に入学し、親子で直面したいくつかの「壁」と、それを乗り越えるために工夫した1学期の様子についてお話ししたいと思います。

監修: 藤井明子
小児科専門医
小児神経専門医
てんかん専門医
どんぐり発達クリニック院長
東京女子医科大学大学院修了。東京女子医科大学病院、長崎県立子ども医療福祉センターで研鑽を積み、2019年よりさくらキッズくりにっく院長に就任。2024年より、どんぐり発達クリニック院長、育心会児童発達部門統括医師に就任。お子様の個性を大切にしながら、親御さんの子育ての悩みにも寄り添う診療を行っている。 3人の子どもを育児中である。
小児神経専門医
てんかん専門医
どんぐり発達クリニック院長
最初の壁は「制服」。着慣れない衣服の感触への対策
この春、小学校から中学校に進学したわが家の息子のトール。慣れ親しんだ環境から新しい環境に変わり、最初に直面したのは「制服」という生活スタイルの変化でした。トールが通う中学校は制服を着て通学する決まりになっており、小学校では毎日私服だった息子にとっては、幼稚園以来の経験です。
新品の制服が家に届き、袖を通したトールは、開口一番「ズボンがチクチクして気になる」と訴えました。トールにとって、少し硬い生地のチクチク感が想像以上のストレスだったようです。試しに私も履いてみましたが、確かに少しごわつきを感じます。しかし、ほかのお母さんや制服販売店に聞いてもそのような声はなく、私たちだけが直面している困りごとのようでした。入学前に何度か洗濯をしても違和感は消えず、最終的にズボンの下にインナーを履くことで乗り切ることにしました(暑い夏場でもインナーなしではズボンを履くことができなかったので、熱中症にならないか心配でした……)。
新品の制服が家に届き、袖を通したトールは、開口一番「ズボンがチクチクして気になる」と訴えました。トールにとって、少し硬い生地のチクチク感が想像以上のストレスだったようです。試しに私も履いてみましたが、確かに少しごわつきを感じます。しかし、ほかのお母さんや制服販売店に聞いてもそのような声はなく、私たちだけが直面している困りごとのようでした。入学前に何度か洗濯をしても違和感は消えず、最終的にズボンの下にインナーを履くことで乗り切ることにしました(暑い夏場でもインナーなしではズボンを履くことができなかったので、熱中症にならないか心配でした……)。
また、制服を着る際には、これまでほとんど使ったことのないベルトの着用も必須でした。バックル式のベルトを買って練習したものの、うまく着脱できません。着慣れない制服の感触に、ただでさえストレスを感じていたようだったので、1学期の間は簡単に着脱できるゴム製のベルトを使うことにしました。このゴムベルトは、トイレのたびに外す必要がないため、トールにとって負担軽減になったようです。夏休みが明けて、少しずつ学校生活にも慣れてきた今、頃合いを見計らってバックル式のベルトの練習もできたらいいなと思っています。
「どう勉強すれば……?」初めての定期テストで計画性の課題も
制服問題の次に現れたのが「勉強の壁」でした。1学期には中学校に入って最初の定期テストがありましたが、1年生は誰もが初めての経験ということで、学校で学習予定表をつくり、それに沿って学習を進めるよう指導がありました。
トールは自分から進んで課題を進めているようだったので、私は口出しをせずに見守っていました。しかし、テスト直前に勉強の進み具合や理解度を確認してみたところ、暗記などがあまり進んでいないことが判明したのです。
今まで「テストのために計画的に勉強する」という経験がなかったので、どのように勉強すればいいのか、見通しを立てることが難しかったようです。テスト直前の数日は、私も一緒に勉強に付き合い、問題を出すなどするようにしていました。
トールは自分から進んで課題を進めているようだったので、私は口出しをせずに見守っていました。しかし、テスト直前に勉強の進み具合や理解度を確認してみたところ、暗記などがあまり進んでいないことが判明したのです。
今まで「テストのために計画的に勉強する」という経験がなかったので、どのように勉強すればいいのか、見通しを立てることが難しかったようです。テスト直前の数日は、私も一緒に勉強に付き合い、問題を出すなどするようにしていました。
提出物など「いつまでに行う」というゴールが明確な課題は、日付をメモしておけば自分でこなせることが分かったのは、親として少し安心した点です。
ただ、自分で計画を立てて実行に移す難しさは、今回のテストで浮き彫りになりました。この経験を活かし、2学期はまず一緒に勉強の計画を立てるところからサポートしていく予定です。
ただ、自分で計画を立てて実行に移す難しさは、今回のテストで浮き彫りになりました。この経験を活かし、2学期はまず一緒に勉強の計画を立てるところからサポートしていく予定です。
最大の変化は「人」。4年間お世話になった先生との違いに戸惑う息子へかけた言葉
そして、トールにとって最も大きな変化は、特別支援学級の担任の先生が変わったことでした。小学校では3年生から6年生までの4年間、ずっと同じ担任の先生にお世話になっていたトール。トールの特性を深く理解し、ときには見守り、ときには分かりやすいようにサポートしてくれた先生は、私たち親子が信頼を寄せていた支援者の1人でした。
中学校の先生も非常に熱心で、何度かお話ししただけでも、一生懸命トールに向き合ってくださっていることが伝わってきました。しかし、まだ関係性を築いている最中で、お互いに少し気持ちがすれ違ってしまうこともあるようでした。
中学校の先生も非常に熱心で、何度かお話ししただけでも、一生懸命トールに向き合ってくださっていることが伝わってきました。しかし、まだ関係性を築いている最中で、お互いに少し気持ちがすれ違ってしまうこともあるようでした。
1学期の終わり頃に、トールが「今の特別支援学級の先生は……」と少し不満げな様子を見せていたことがありました。口には出さなかったけれど、小学校の時の先生を懐かしんでいるようでした。その時、私はこう話しました。
「小学校の時の先生は4年以上トールのことを見てくれていたから、トールのことをすごくよく分かってくれていたね。でも今の中学校の先生はまだ出会って3、4か月。だから、仲良くなれるのはこれからだよ」
私の言葉に、トールは「そうか。まだちょっとしか一緒にいないもんね」と納得した表情を見せてくれました。
夏休みが明け、2学期が始まりました。これから、定期テストや学校行事も本格化していきます。
先生との関係や、中学卒業後の進路のことも含め、考えるべきことはたくさんありますが、トールが「楽しい」と感じる瞬間を一つでも多く重ねられるよう、私もサポートしていきたいなと思っています。
「小学校の時の先生は4年以上トールのことを見てくれていたから、トールのことをすごくよく分かってくれていたね。でも今の中学校の先生はまだ出会って3、4か月。だから、仲良くなれるのはこれからだよ」
私の言葉に、トールは「そうか。まだちょっとしか一緒にいないもんね」と納得した表情を見せてくれました。
夏休みが明け、2学期が始まりました。これから、定期テストや学校行事も本格化していきます。
先生との関係や、中学卒業後の進路のことも含め、考えるべきことはたくさんありますが、トールが「楽しい」と感じる瞬間を一つでも多く重ねられるよう、私もサポートしていきたいなと思っています。
執筆/メイ
(監修:藤井先生より)
新しい環境は楽しみもありますが、発達特性のあるお子さんにとっては大きな負担にもなり得るため、メイさんの支えはとても大きな意味を持っていると思います。感覚過敏で制服が着慣れない場合には、学校と相談して素材を工夫することもあります。学習面では、親や先生と少しずつ一緒に立てて、見守りながら自分なりの方法を身につけていけると安心です。また、中学校生活では先生や友人と関わる中で、うれしいことも大変なことも経験しますが、そうした積み重ねが社会の中での生き方を広げていく大切な機会にもなります。メイさんがここまでトールさんのペースを大切にしながら支えてこられたこと、トールさんにとって安心できる基盤になっていると感じました。
(監修:藤井先生より)
新しい環境は楽しみもありますが、発達特性のあるお子さんにとっては大きな負担にもなり得るため、メイさんの支えはとても大きな意味を持っていると思います。感覚過敏で制服が着慣れない場合には、学校と相談して素材を工夫することもあります。学習面では、親や先生と少しずつ一緒に立てて、見守りながら自分なりの方法を身につけていけると安心です。また、中学校生活では先生や友人と関わる中で、うれしいことも大変なことも経験しますが、そうした積み重ねが社会の中での生き方を広げていく大切な機会にもなります。メイさんがここまでトールさんのペースを大切にしながら支えてこられたこと、トールさんにとって安心できる基盤になっていると感じました。

「通常学級に戻れたら」と願った日も…それでも発達障害息子が小中とも特別支援学級で学んだ理由

Sponsored
勉強・学校生活・進路…思春期に悩む保護者へ!『発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方』井上雅彦先生インタビュー

特別支援学級からの中学進学準備。発達障害息子が順調に過ごせた理由と将来への「自立」に向けて【読者体験談】

部活の先輩にタメ口!?「暗黙の了解」が苦手な自閉症娘への敬語の伝え方

小6ADHD息子の担任は子育ての大先輩!教わった中学でのトラブル把握、家庭での関わり方のコツが役立って
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています