親としてできること
次女も話していましたが、修学旅行自体はとても楽しめた様子。もともと次女自身は、こういったイベント自体は嫌いじゃないし、好奇心旺盛でやってみたいこともたくさんあるし、楽しむこともできる。ただ、とても疲れてしまう。だから、次女にとってはやりたいことをやるためにも「慣れる」というのがとても大事で、負担がかかるからやめる・休むばかりが正解じゃなくて、いろいろボロボロになりながらもスモールステップで経験を積んで慣れていくしかないのかなと思いました。
私ができることは、そんな次女がゆっくり休める場をつくっていくことなんだろうなと改めて思ったのでした。
私ができることは、そんな次女がゆっくり休める場をつくっていくことなんだろうなと改めて思ったのでした。
執筆/まりまり
(監修:新美先生より)
場面緘黙がある娘さんの、修学旅行についての保護者の立場からの思いについて聞かせて下さりありがとうございます。修学旅行という大きなイベントを楽しんでこられた娘さんの成長と、それを支え見守られたお母様の思いの変化が、とても素敵でした。
場面緘黙のあるお子さんは、初めての事柄や見通しが持てない場面、人から注目を集める場面に、強い緊張や不安を抱きやすいものです。その場では何とかやり過ごせても、ずっと気を張って緊張していると、疲弊して後から動けなくなってしまうことは珍しくありません。特に宿泊学習は、多くの小学校で初めて行う行事であり、長丁場でもあることから、心身ともに疲弊してしまうのは無理もないことですね。5年生の時の宿泊学習では、楽しいこともあったかもしれませんが、疲弊がキャパシティを超えてしまい、それまでの疲労も相まって、しばらく学校に行けなくなるほどの状態になってしまったのかもしれません。
そのような経験があると保護者としては「もう、修学旅行なんて行かなくてもいいよ」という気持ちになっていたかもしれません。それでも積極的に止めることもできずハラハラしながらも送り出されたのかなと思います。そして、思いのほか元気な顔で帰ってきてくれて、その後も休まず登校できているとのこと、本当に良かったですね。
まりまりさんが分析されているように、宿泊行事2回目で、5年生の経験を踏まえて見通しが持てたことで、修学旅行では疲弊度が軽くなったのかもしれません。そう考えると、5年生の宿泊行事はその後しばらく休むほどの大変さがあったとしても、その経験が蓄積されて6年生の修学旅行を楽しめることにつながったと思えば、大きな意味があったと言えるのではないでしょうか。
こういったことで気をつけたいのは、お子さん自身に「行きたい」という気持ちがあるか、そして「楽しい」と感じられる行事か、という点です。ともすると「何事も経験」「経験を積めば慣れる」と無理やり行事に参加させるような風潮もありますが、まりまりさんの娘さんが大変でも良い経験にできたのは、本人におそらくは行きたい気持ちがあったんじゃないかと思われますし、そして大変でも楽しめる行事だったからだと推察します。
「行きたい」という気持ちを尊重し、それを実現するために、学校と家庭が連携してスモールステップで準備を進めていく。そして、疲弊したときに「いつでも安心して休める場所」を家庭で用意する……お子さんの気持ちに寄り添い、適切なサポートを行うことの重要性を確認させていただきました。これからも、娘さんの成長と挑戦を温かく見守ってください。
(監修:新美先生より)
場面緘黙がある娘さんの、修学旅行についての保護者の立場からの思いについて聞かせて下さりありがとうございます。修学旅行という大きなイベントを楽しんでこられた娘さんの成長と、それを支え見守られたお母様の思いの変化が、とても素敵でした。
場面緘黙のあるお子さんは、初めての事柄や見通しが持てない場面、人から注目を集める場面に、強い緊張や不安を抱きやすいものです。その場では何とかやり過ごせても、ずっと気を張って緊張していると、疲弊して後から動けなくなってしまうことは珍しくありません。特に宿泊学習は、多くの小学校で初めて行う行事であり、長丁場でもあることから、心身ともに疲弊してしまうのは無理もないことですね。5年生の時の宿泊学習では、楽しいこともあったかもしれませんが、疲弊がキャパシティを超えてしまい、それまでの疲労も相まって、しばらく学校に行けなくなるほどの状態になってしまったのかもしれません。
そのような経験があると保護者としては「もう、修学旅行なんて行かなくてもいいよ」という気持ちになっていたかもしれません。それでも積極的に止めることもできずハラハラしながらも送り出されたのかなと思います。そして、思いのほか元気な顔で帰ってきてくれて、その後も休まず登校できているとのこと、本当に良かったですね。
まりまりさんが分析されているように、宿泊行事2回目で、5年生の経験を踏まえて見通しが持てたことで、修学旅行では疲弊度が軽くなったのかもしれません。そう考えると、5年生の宿泊行事はその後しばらく休むほどの大変さがあったとしても、その経験が蓄積されて6年生の修学旅行を楽しめることにつながったと思えば、大きな意味があったと言えるのではないでしょうか。
こういったことで気をつけたいのは、お子さん自身に「行きたい」という気持ちがあるか、そして「楽しい」と感じられる行事か、という点です。ともすると「何事も経験」「経験を積めば慣れる」と無理やり行事に参加させるような風潮もありますが、まりまりさんの娘さんが大変でも良い経験にできたのは、本人におそらくは行きたい気持ちがあったんじゃないかと思われますし、そして大変でも楽しめる行事だったからだと推察します。
「行きたい」という気持ちを尊重し、それを実現するために、学校と家庭が連携してスモールステップで準備を進めていく。そして、疲弊したときに「いつでも安心して休める場所」を家庭で用意する……お子さんの気持ちに寄り添い、適切なサポートを行うことの重要性を確認させていただきました。これからも、娘さんの成長と挑戦を温かく見守ってください。

修学旅行「ほんとに行くの?」登校渋りの多い発達グレー長男、当日朝まで心配は続き…

行事の練習が始まる前に、お家で出来ることって?

ASD小6コウの修学旅行「迷子になる?持ち物は探せる?」母の立てた渾身の対策とは

特別支援学校の息子、高2で不登校に。「体調不良アピール」で病院受診も原因不明…学校からの提案は【読者体験談】
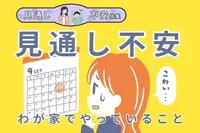
学校行事は「怖い」「イヤ」小6自閉症娘の見通し不安、無理強いで失敗も。「参加できた」自信を積み重ねるために…
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-
 1
1
- 2















