発達障害の子どもがつまずきがちな学習の悩みは?発達ナビアンケート結果と家庭でできる工夫【体験談まとめ】
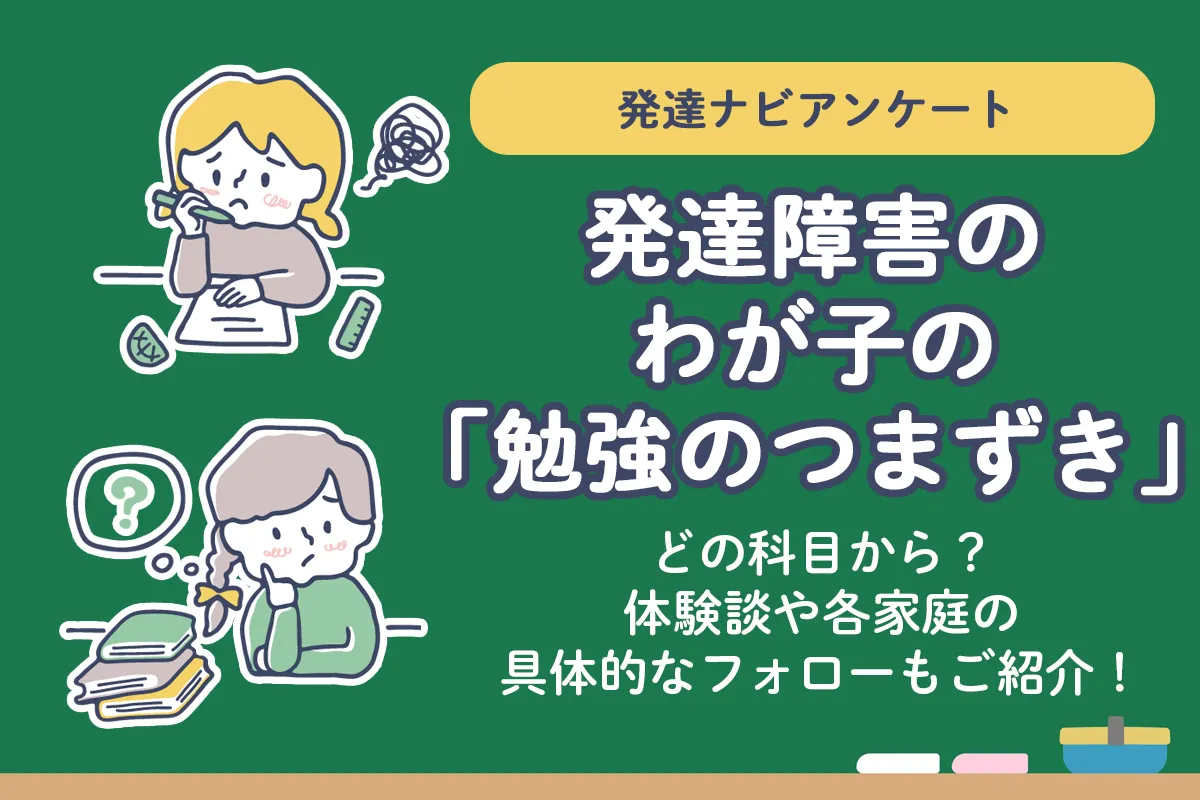
発達ナビでは、会員のみなさまに『【勉強などのつまずきアンケート】どの科目でつまずいた?体育、算数、国語などへの取り組み、どう工夫した?』を実施、64名から回答をいただきました。この記事では国語、算数などどの科目が苦手だったかのアンケート結果、そして寄せられた「勉強のつまずき」に関するリアルな体験談をご紹介します。
勉強の苦手さに気づき、支援・合理的配慮の実施、そしてその後の変化までをたどった具体的なお話をたくさんいただきました。同じような悩みを抱えるご家庭のヒントになりますように。
発達障害の子どもの「勉強のつまずき」アンケート結果は?
算数(数学)…36%
国語…28%
理科(生活)…3%
社会(生活)…0%
体育 …11%
図工(美術)…5%
英語 …6%
その他 …11%
問題文の意味が理解できなかったり、自己流解釈してしまうので解けずにパニック。(解説すれば解ける)応用力がないので「工夫をして計算しよう」が鬼門中の鬼門。
計算は数をこなせば慣れると思っていたので、何度も繰り返し解かせていましたが、すぐ気が散り間違いも増えました。逆に1〜3問だけ集中して解くということにしたら終わりが見えるので頑張ってくれてます。
息子は、筆圧が弱く、又、文字のバランスが悪くて困りました。
音読も、行を飛ばしたり、「は」と「わ」を間違えて読んだり、「ば」と「ぱ」等の読み間違いが多かったです。
注意すると癇癪を起こし…。
本当に親子で疲弊していました。
支援級になってからは、クラスでは使用出来なかった、読み上げのタブレット等を使い大分軽減しましたが…。
空間把握が苦手で、かけ算・わり算の桁数が増えた時に筆算のケタを縦に揃えて書くのが難しかったので、家では大きいマスに計算記号や線を予め書きこんでおくなどの支援をしていました。また、ワークは最初の方の問題だけ答えを薄く書いてあげると(子どもはなぞるだけ)、やり始めの敷居を下げることができるようでした。
九九の6の段~9の段がまともに使えるようになってきたのは、小5の後半(つい最近)です。
現在は引き算は指を使わなくても暗算できる、割り算は割る数が1ケタなら解ける、かけ算は2桁の暗算もまあまあいけるくらいにはなりました。そのため、図形の面積や角度、単位あたりの量の計算のような具体性が高い単元については、思ったよりも追いついてきてるかなという印象です。
英語だけはどうにもなりません。
アルファベットも鏡文字で書いたりします。
LDだろうと言われているのに、先生には「勉強不足」と言われてしまいます。
個別指導の塾を勧めても、何がどうあってもイヤだと言って行きません。
お医者さんには「今は翻訳ソフトとかあって困らないから、英語は捨てていい」と言われました。
教科書、問題集だけでは理解できないので、AIにわからないところを聞いて一生懸命勉強しています。
ひらがな、漢字、書字への困難……配慮の具体例も。3家庭の体験談をご紹介
ひらがなが読めない!?小学校入学で気づいた学習の困り。学校で受けている5つの合理的配慮は【読者体験談】

ひらがなが読めない!?小学校入学で気づいた学習の困り。学校で受けている5つの合理的配慮は【読者体験談】
漢字と文章読解に苦戦!学習障害とは違う自閉症の特性?苦手克服の工夫と学校での合理的配慮【読者体験談】

漢字と文章読解に苦戦!学習障害とは違う自閉症の特性?苦手克服の工夫と学校での合理的配慮【読者体験談】
小学校入学直後から国語につまずき書くことが恐怖に。パニック、手の震え…。学校の配慮と大学生になった今【読者体験談】
この体験談では、小、中、高、そして大学合格にいたるまでの国語への取り組みの変化を共有いただきました。

小学校入学直後から国語につまずき書くことが恐怖に。パニック、手の震え…。学校の配慮と大学生になった今【読者体験談】
お子さん一人ひとりのペースで、無理のない学びの形を
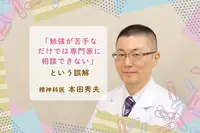
【精神科医・本田秀夫】「勉強が苦手なだけでは専門家に相談できない」は誤解。気づきにくい軽度知的障害と境界知能の子どもの困難
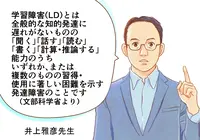
学習障害・限局性学習症とは?読み・書き・計算に困難?チェックシートつきで紹介ーーマンガで学ぶLD・SLD【専門家監修】

頑張る時期が周りより5年ズレてた!?中高時代、成績最悪だったADHD息子が18歳でようやくみつけた勉強法

「授業で上の空…」を回避!?発達外来ドクターおすすめの予習勉強法

勉強のつまずきは、感覚過敏や鈍麻が原因?発達障害との関係、学習困難の理由や支援方法も解説【専門家監修】
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
SLD(限局性学習症)
LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています















