安心できる情報にすがる日々。それでも不安は消えず、頼った先は
この頃の私はインターネットで自分の安心する記事ばかり見ていました。「3歳から話しはじめました」「不安だったけど話し出したら2語文、3語文あっという間に話しています」などの記事を見て、「りーは今その時期じゃないだけ」「発達がゆっくりだけどすぐに追いつくはずだ」と自分を無理やり安心させていました。
こうして無理やり自分自身を安心させている半面、「この子は何かあるのかもしれない」という気持ちがなくなったわけではありませんでした。私たちの住んでいる地域には児童発達支援の施設が多くありません。万が一のことを考え、知り合いの児童発達支援施設の先生へ連絡しました。
その先生はこちらの事情を話すと温かく迎えてくれ、りーが利用することになるかも、ということも快諾してくれました。
この先生との関わりで、私とりーの世界が大きく広がっていくことになったのですが、りーのその後についてはまた別の機会に書かせていただきます。
こうして無理やり自分自身を安心させている半面、「この子は何かあるのかもしれない」という気持ちがなくなったわけではありませんでした。私たちの住んでいる地域には児童発達支援の施設が多くありません。万が一のことを考え、知り合いの児童発達支援施設の先生へ連絡しました。
その先生はこちらの事情を話すと温かく迎えてくれ、りーが利用することになるかも、ということも快諾してくれました。
この先生との関わりで、私とりーの世界が大きく広がっていくことになったのですが、りーのその後についてはまた別の機会に書かせていただきます。
執筆/かしりりあ
(監修:初川先生より)
長男りーくんの幼少期のエピソードをありがとうございます。発達や様子に気になるところはありつつも、それが何であるか、そしてどうやって「やりとり」をしていくかが見えない。そんな時期のお話でした。
ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんには感覚の過敏などがあることは昨今よく知られていますが、過敏と同様に鈍麻もあります。熱が出ていることに気づかない、痛みに鈍感である。感覚としての鈍感さを呈するものがあるということです。あるものは過敏で、あるものは鈍くて。そうしたこともあるでしょう。感覚鈍麻がみられる場合は、体調の変化やケガがみられた時にお子さん本人から訴えが出づらいこともあり、周囲の大人はそのあたり気を配ることが必要です。
お子さんへの療育は早期であるほうがよいとされていますが、仕事の状況や地域的な課題などで実際療育を受けられるかどうかはご家庭で判断してゆくことになります。夫婦で話し合って決められたとのこと、よかったです。話し合える家族や親族、地域の支援者がいることは何よりです。
インターネットでさまざまな経験談がシェアされる時代。実際にはお子さんの状況やお子さんの周辺状況はかなりケースバイケースなのですが、不安から検索してしまうこと、また自分にとって救いとなるような情報ばかり見てしまうこと。よくあると思います。ただ、本当にこうしたことはケースバイケースで、目の前にいるお子さんがどのような発達経過をたどるかはインターネットを見ていてもどうにも分からないものです。継続的に相談でき、お子さんの様子を見て介入(療育など)してくださる、いわば子育ての伴走相手としての支援職が近くにいるといいなと感じます。かしさんにはお知り合いの児童発達支援施設の先生がいらしたこと、何よりです。近くに相談相手がいない、という場合には自治体の子育て支援センターや療育センターなどにそのあたり相談いただけると、さまざまな情報を集めることができると思います。
長男りーくんの幼少期のエピソードをありがとうございます。発達や様子に気になるところはありつつも、それが何であるか、そしてどうやって「やりとり」をしていくかが見えない。そんな時期のお話でした。
ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんには感覚の過敏などがあることは昨今よく知られていますが、過敏と同様に鈍麻もあります。熱が出ていることに気づかない、痛みに鈍感である。感覚としての鈍感さを呈するものがあるということです。あるものは過敏で、あるものは鈍くて。そうしたこともあるでしょう。感覚鈍麻がみられる場合は、体調の変化やケガがみられた時にお子さん本人から訴えが出づらいこともあり、周囲の大人はそのあたり気を配ることが必要です。
お子さんへの療育は早期であるほうがよいとされていますが、仕事の状況や地域的な課題などで実際療育を受けられるかどうかはご家庭で判断してゆくことになります。夫婦で話し合って決められたとのこと、よかったです。話し合える家族や親族、地域の支援者がいることは何よりです。
インターネットでさまざまな経験談がシェアされる時代。実際にはお子さんの状況やお子さんの周辺状況はかなりケースバイケースなのですが、不安から検索してしまうこと、また自分にとって救いとなるような情報ばかり見てしまうこと。よくあると思います。ただ、本当にこうしたことはケースバイケースで、目の前にいるお子さんがどのような発達経過をたどるかはインターネットを見ていてもどうにも分からないものです。継続的に相談でき、お子さんの様子を見て介入(療育など)してくださる、いわば子育ての伴走相手としての支援職が近くにいるといいなと感じます。かしさんにはお知り合いの児童発達支援施設の先生がいらしたこと、何よりです。近くに相談相手がいない、という場合には自治体の子育て支援センターや療育センターなどにそのあたり相談いただけると、さまざまな情報を集めることができると思います。

2歳で発語、指さしなし。激しい癇癪、ベビーカー拒否で母も涙…自閉症娘の子育て奮闘記【新連載】

楽しく言葉をつかうには、どんな場面で促してみるのが良いのかな…?そんなときは

自閉症息子、2歳過ぎても手づかみ食べ、スプーンは握れず…6歳の今も続く食事の悩み

知的障害、0歳での兆候は?「泣かない」などの特徴や遺伝、相談先について解説【医師監修】

逆さバイバイ、つま先歩き、光や洋服の感触が苦手…もしかして特性だった?5歳息子の乳幼児期
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
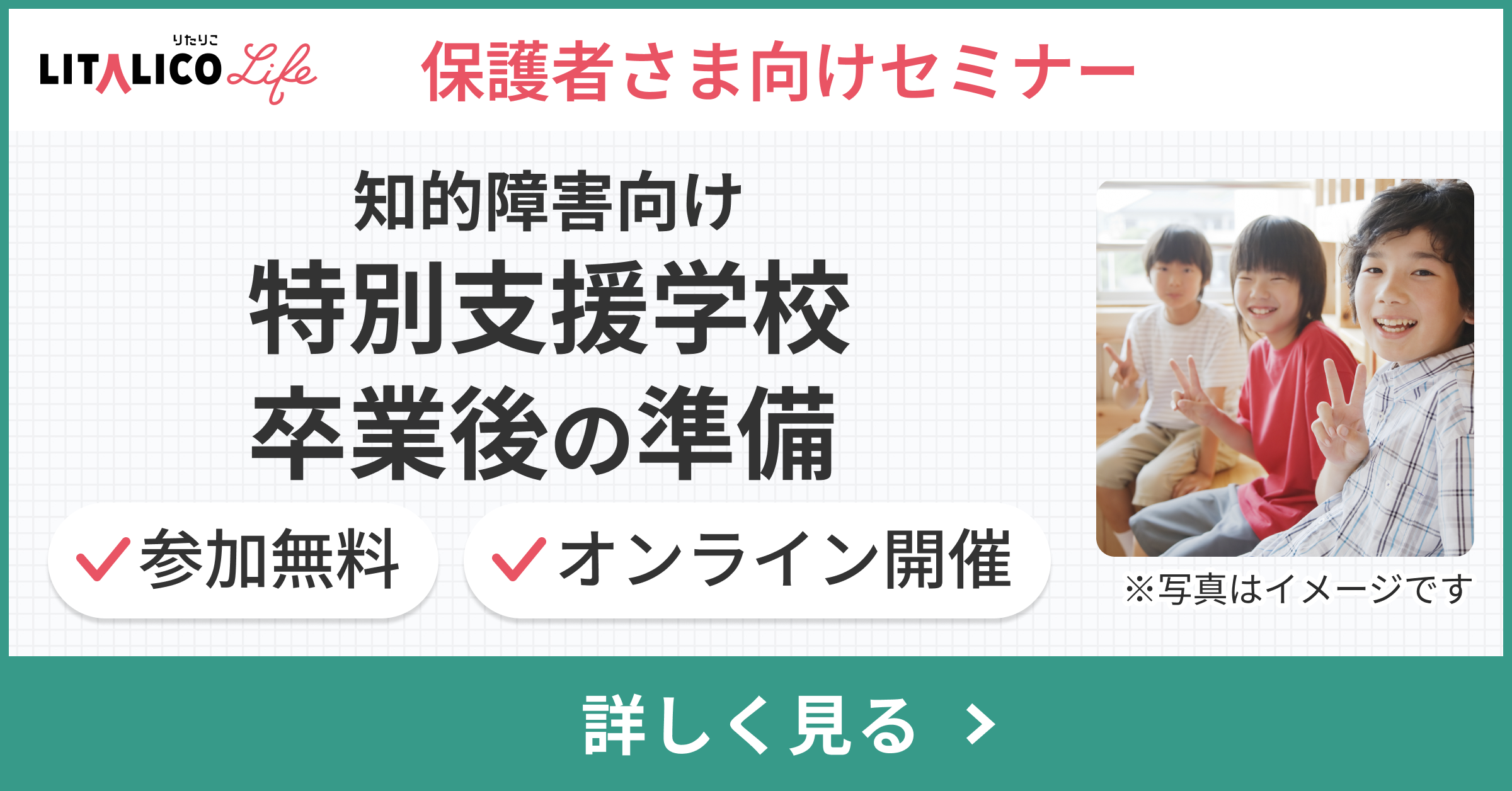
-
 1
1
- 2















