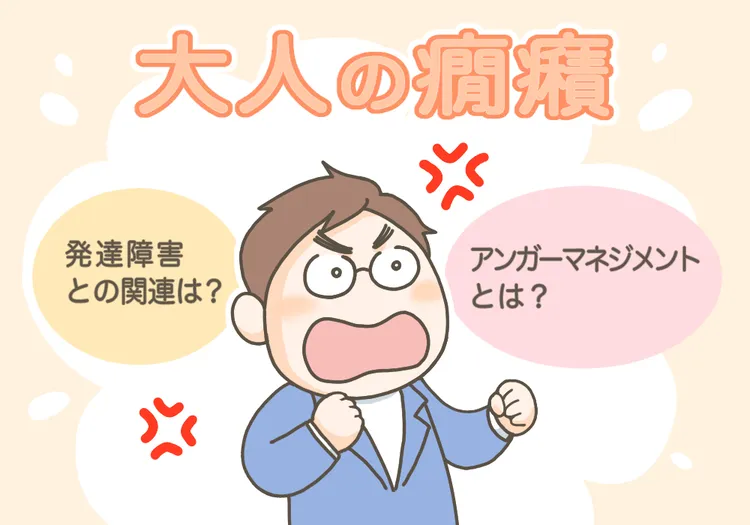大人の癇癪(かんしゃく)とは?感情のコントロールができない…発達障害との関連は?【専門家監修】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
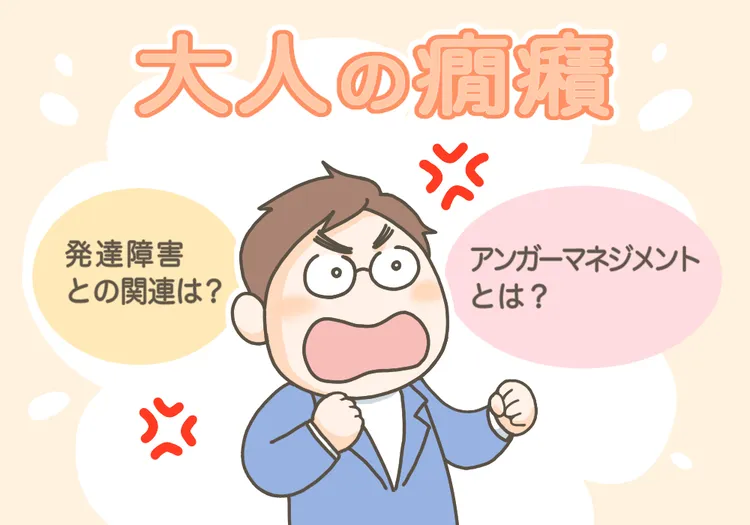
Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
癇癪(かんしゃく)は、医学的な診断名ではありませんが、一般的には怒りの気持ちを抑えたり、怒りからくる突発的な行動をコントロールしたりすることができない状態を指します。イライラしたら止まらない、家族にだけイライラする、キレる、人や物に激しく当たる、攻撃的な言動をとる、仕事や勉強が手につかないなどの行動がみられることがあります。ここでは、怒りとの付き合い方や、強い怒り(癇癪)の対処法「アンガーマネジメント」、癇癪の原因、関係する病気や障害、相談先についてご紹介します。

監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
大人の癇癪とは?
この記事で分かること
- 大人の癇癪(かんしゃく)の原因と、ついカッとなってしまう怒りの感情のメカニズム
- 自分でできる怒りのコントロール方法「アンガーマネジメント」の具体的なテクニック
- 大人の癇癪と発達障害(ASD・ADHD)の関連性、その特性が与える影響について
- 悩みを抱え込まないための専門機関への相談先と、癇癪を起こす人の周りの人の関わり方
癇癪って?
癇癪(かんしゃく)とは、怒りの感情を抑えられなかったり、怒りからくる突発的な行動をコントロールしたりすることができない状態を指します。子どもだけでなく、大人も癇癪を起すことがあります。癇癪を起しているときには、周囲の人や物に激しく当たる、攻撃的な言動をとる、仕事や勉強が手につかないなどの行動がみられることがあります。
ここでは大人の癇癪について、詳しく見ていきたいと思います。
ここでは大人の癇癪について、詳しく見ていきたいと思います。
ネガティブな感情をコントロールできないのはなぜ?
人が生活するなかで、ポジティブ・ネガティブ問わずさまざまな感情や情動が湧き起こること自体は、自然な現象です。私たちは、時には気持ちをぐっと抑え、実際に相手とのやりとりでは柔らく表現するなど、工夫をしながら生活しています。
専門的には、ぐっと気持ちを抑えることを「情動調整」、「本当は怒りたいのだけれど、やわらかく言おうとする」ことを「行動制御」ともいいます。
しかし、感情のコントロールがうまくできないと、冷静に判断をすることができず、怒りの感情にまかせて体が衝動的に動いてしまうことがあります。
また、逆にストレスをため込みすぎると身体症状が生じたり、抑うつなどの二次的な問題が起こったりすることもあります。
怒りが起こるきっかけはさまざまで、例えば、人とのかかわりの中で相手から投げられた言葉や態度、また物事に対するうまくいかなさなどがあります。いずれにせよそれらのきっかけは、冷静に考えたらささいなものであり、それほど怒るようなことでもない場合が大抵です。
癇癪を起こしてしまう原因は、その場にある刺激や出来事、相手の態度だけではなく、もっと別のところにも問題があるとも考えられます。この点については後の章でご紹介します。
専門的には、ぐっと気持ちを抑えることを「情動調整」、「本当は怒りたいのだけれど、やわらかく言おうとする」ことを「行動制御」ともいいます。
しかし、感情のコントロールがうまくできないと、冷静に判断をすることができず、怒りの感情にまかせて体が衝動的に動いてしまうことがあります。
また、逆にストレスをため込みすぎると身体症状が生じたり、抑うつなどの二次的な問題が起こったりすることもあります。
怒りが起こるきっかけはさまざまで、例えば、人とのかかわりの中で相手から投げられた言葉や態度、また物事に対するうまくいかなさなどがあります。いずれにせよそれらのきっかけは、冷静に考えたらささいなものであり、それほど怒るようなことでもない場合が大抵です。
癇癪を起こしてしまう原因は、その場にある刺激や出来事、相手の態度だけではなく、もっと別のところにも問題があるとも考えられます。この点については後の章でご紹介します。
そもそも、怒りとは何か?
感情は、人が自分がどのような状況に置かれているかについて知らせるシグナルの役目をもっています。例えば、恐れの感情がその代表といえるでしょう。自分の生命を脅かすようなものに出くわしたときに、「怖い!」と感じることにより、危険を回避することができます。
また、感情表出や共有によって、周りの人との関係を作ってゆくことができます。例えば、「楽しい」気持ちによって出てきた笑顔が周りの人とのかかわりを生み出して、友好的なコミュニケーションを引き出すということは、誰しも経験があることなのではないかと思います。
このように生命を維持したり、人とのかかわりをつくるのに感情は役に立っています。
では、まず「怒り」について詳しく考えていきましょう。
ひと言で「怒り」といっても、認知の介在しない怒りと認知の介在する怒りがあります。
認知の介在しない怒りは、目の前にある対象に対して瞬間的に起こる怒りの感情です。いやなことをされて瞬間的に怒鳴るなどがこれに当たります。この怒りは脳の大脳辺縁体が働いて起こります。
認知の介在する怒りは、目の前にある対象に対しての場合と、目の前にない過去の出来事に対して怒りの感情が湧いてくる場合もあります。きっかけとなる他者の態度に対して、「私の悪口を言っている」「あのときは馬鹿にしていたのだ」などと考えたことが引き金となって怒りの感情になるのです。これは前頭葉、大脳皮質の反応による感情です。
コントロールされた怒りの感情の表出は、そのきっかけがあったときに、多くは以下のプロセスをとります。
1.きっかけとなる出来事が起こる
2.怒りの感情が起こる
3.感情を調整する
4.行動・表現する
癇癪を起こしてしまう人は、上記のプロセスを経る中で「過剰に反応してしまう」「感情を調整することができない」「行動の調整をすることができない」などの状況に陥っていると言えます。
では、そのような困った状況で、私たちは怒りをどのように抑えていけばよいのでしょうか。
また、感情表出や共有によって、周りの人との関係を作ってゆくことができます。例えば、「楽しい」気持ちによって出てきた笑顔が周りの人とのかかわりを生み出して、友好的なコミュニケーションを引き出すということは、誰しも経験があることなのではないかと思います。
このように生命を維持したり、人とのかかわりをつくるのに感情は役に立っています。
では、まず「怒り」について詳しく考えていきましょう。
ひと言で「怒り」といっても、認知の介在しない怒りと認知の介在する怒りがあります。
認知の介在しない怒りは、目の前にある対象に対して瞬間的に起こる怒りの感情です。いやなことをされて瞬間的に怒鳴るなどがこれに当たります。この怒りは脳の大脳辺縁体が働いて起こります。
認知の介在する怒りは、目の前にある対象に対しての場合と、目の前にない過去の出来事に対して怒りの感情が湧いてくる場合もあります。きっかけとなる他者の態度に対して、「私の悪口を言っている」「あのときは馬鹿にしていたのだ」などと考えたことが引き金となって怒りの感情になるのです。これは前頭葉、大脳皮質の反応による感情です。
コントロールされた怒りの感情の表出は、そのきっかけがあったときに、多くは以下のプロセスをとります。
1.きっかけとなる出来事が起こる
2.怒りの感情が起こる
3.感情を調整する
4.行動・表現する
癇癪を起こしてしまう人は、上記のプロセスを経る中で「過剰に反応してしまう」「感情を調整することができない」「行動の調整をすることができない」などの状況に陥っていると言えます。
では、そのような困った状況で、私たちは怒りをどのように抑えていけばよいのでしょうか。

癇癪を自分でコントロールしたい…怒りを抑えるには?
感情が生じること自体は生物学的に自然なものです。ですから、感情の生起自体をコントロールすることは難しく、その感情が起こった後に、どのように対処するかが重要になります。
また対処法は、その怒りに認知が介在しているかどうか、今目の前に対象がいるかによっても変わってきます。
ここでは怒りが起こったときに、どのような対処法が有効かをご紹介します。
また対処法は、その怒りに認知が介在しているかどうか、今目の前に対象がいるかによっても変わってきます。
ここでは怒りが起こったときに、どのような対処法が有効かをご紹介します。
生理的なアプローチ
瞬間的に反応して起きる怒りについては、主として生理的なアプローチが有効です。
誰でも疲れていたり、眠れないときにはイライラしたり、ちょっとしたことでカッとなってしまいがちです。
そんなときはまず、よく寝る、体を緩めるなどして体調を整えてみましょう。
誰でも疲れていたり、眠れないときにはイライラしたり、ちょっとしたことでカッとなってしまいがちです。
そんなときはまず、よく寝る、体を緩めるなどして体調を整えてみましょう。
アンガーマネジメント
認知の介在する怒りに関しては、アンガーマネジメントや認知の修正をするとよいといわれています。
アンガーマネジメントとは、アメリカで開発された怒りを予防し制御するための心理プログラムです。プログラムの開発当初は、軽犯罪者に対する矯正プログラムとして確立されていましたが、今では企業や教育現場などにも取り入れられています。
怒りの感情と上手に向き合うことで「あのとき、あんなふうに怒らなければよかった」と後悔することが少なくなるでしょう。
アンガ―マネジメントはトレーニングですので、すぐには怒りを抑えることができなくても、意識をして何度も行動に移すことで効果が現れてきます。
諸説あるものの、怒りが頭にのぼるピークは6秒ほどといわれています。短時間で怒りをやり過ごす例として、5つの方法を挙げます。
1.怒りを数値化する
2.その場から離れる
3.深呼吸をする
4.意味づけを行う
5.いまに意識を集中させる
1.怒りを数値化する
怒りは目に見えないものです。だからこそ、振り回されてしまいます。怒りを数値化することによって、感情を客観的に評価することができ、怒り任せの行動を防ぐことができます。
ここでは10点満点中、0~10までの数字を思い浮かべます。
アンガーマネジメントとは、アメリカで開発された怒りを予防し制御するための心理プログラムです。プログラムの開発当初は、軽犯罪者に対する矯正プログラムとして確立されていましたが、今では企業や教育現場などにも取り入れられています。
怒りの感情と上手に向き合うことで「あのとき、あんなふうに怒らなければよかった」と後悔することが少なくなるでしょう。
アンガ―マネジメントはトレーニングですので、すぐには怒りを抑えることができなくても、意識をして何度も行動に移すことで効果が現れてきます。
諸説あるものの、怒りが頭にのぼるピークは6秒ほどといわれています。短時間で怒りをやり過ごす例として、5つの方法を挙げます。
1.怒りを数値化する
2.その場から離れる
3.深呼吸をする
4.意味づけを行う
5.いまに意識を集中させる
1.怒りを数値化する
怒りは目に見えないものです。だからこそ、振り回されてしまいます。怒りを数値化することによって、感情を客観的に評価することができ、怒り任せの行動を防ぐことができます。
ここでは10点満点中、0~10までの数字を思い浮かべます。
0 まったく怒りを感じていない状態
1~3 イラッとするが、すぐに忘れてしまえる程度の軽い怒り
4~6 時間がたっても心がざわつくような怒り
7~9 頭に血が上るような怒り
10 絶対にゆるせないと思うくらいの激しい怒り
戸田久美/著『アンガ―マネジメント 怒らない伝え方』2015年/刊/かんき出版
点数をつけることで、怒りの対象から意識がそらされ、怒りの気持ちにストップがかかります。また、点数をつけることを習慣にすることで、自分が怒りを感じるパターンが把握できるようになります。
2.その場から離れる
目の前に怒りの対象がいる場合で、自分が感情をコントロールできなくなったときに有効です。怒りの気持ちがおこった環境を変えることにより、攻撃的な気持ちをリセットすることができます。
怒りを感じたときに相手がいる場合には、「ちょっとお手洗いにいくので席をはずしますね」などと一言断ってから場を離れるようにしましょう。
3.深呼吸をする
怒りを感じたら深呼吸をするという対処法はよく聞きますが、生理学的にも効果が証明されています。深呼吸をすることによって、副交感神経という心をリラックスさせる自律神経のはたらきが高まります。
怒りが湧いてきたら、鼻から大きく息を吸い、いったん呼吸を止めます。そして、口からゆっくりと息を吐きます。これを2~3回行っていきます。「4秒吸って、8秒吐く」など吐くことに時間をかけると効果的です。
4.意味づけを行う
問題のある状況に意味を見出すこと、またその状況に対してポジティブな解釈をすることです。
例えば就職活動の面接に来た場合を例として考えてみましょう。
面接官から非常に難しい質問をされたとします。その状況を「意地悪な面接で嫌だなあ」と思うかもしれません。しかし「面接官も好きで意地悪をやっているのではない。業務の一環なんだ」ととらえることもできます。
そして面接官がした質問の捉え方によって、私たちの反応は変わってきます。おそらく前者では恐怖を感じる、自信をなくしてそのあとの質問にもうまく答えられないかもしれないですが、後者では、質問に何とか対応しようと冷静さが保てるかもしれません。
このように、状況や相手の言葉や態度を見る視点を変えることを心理学では「認知的再評価」といいます。
5.いまに意識を集中させる
怒りを感じたシーンではないにもかかわらず、頭の中で認知的に意味づけをしてしまうことで、怒りの感情が増幅したり、何度も繰り返されてしまって持続してしまうような場合があります。この方法は怒りが頭に湧き起こってきたときにも有効ですが、他の方法と異なるのは、以下のように怒りの対象が目の前に存在しないときに生じる怒りにも効果が見られることです。
・怒りが長く続いているとき
・過去に起こった怒りにとらわれているとき
・よくない未来を想像しがちなとき
目の前にあるものを観察したり、目を閉じて聞こえてくる音を心の中で描写します。例えば「紙がこすれるカサカサという音がする」「足音がする」「電気がチリチリと鳴る音がする」などです。
これはマインドフルネスという瞑想プログラムでも用いられている方法で、今ここに意識をもってくることで、とらわれている感情から解放されることが目的とされます。
2.その場から離れる
目の前に怒りの対象がいる場合で、自分が感情をコントロールできなくなったときに有効です。怒りの気持ちがおこった環境を変えることにより、攻撃的な気持ちをリセットすることができます。
怒りを感じたときに相手がいる場合には、「ちょっとお手洗いにいくので席をはずしますね」などと一言断ってから場を離れるようにしましょう。
3.深呼吸をする
怒りを感じたら深呼吸をするという対処法はよく聞きますが、生理学的にも効果が証明されています。深呼吸をすることによって、副交感神経という心をリラックスさせる自律神経のはたらきが高まります。
怒りが湧いてきたら、鼻から大きく息を吸い、いったん呼吸を止めます。そして、口からゆっくりと息を吐きます。これを2~3回行っていきます。「4秒吸って、8秒吐く」など吐くことに時間をかけると効果的です。
4.意味づけを行う
問題のある状況に意味を見出すこと、またその状況に対してポジティブな解釈をすることです。
例えば就職活動の面接に来た場合を例として考えてみましょう。
面接官から非常に難しい質問をされたとします。その状況を「意地悪な面接で嫌だなあ」と思うかもしれません。しかし「面接官も好きで意地悪をやっているのではない。業務の一環なんだ」ととらえることもできます。
そして面接官がした質問の捉え方によって、私たちの反応は変わってきます。おそらく前者では恐怖を感じる、自信をなくしてそのあとの質問にもうまく答えられないかもしれないですが、後者では、質問に何とか対応しようと冷静さが保てるかもしれません。
このように、状況や相手の言葉や態度を見る視点を変えることを心理学では「認知的再評価」といいます。
5.いまに意識を集中させる
怒りを感じたシーンではないにもかかわらず、頭の中で認知的に意味づけをしてしまうことで、怒りの感情が増幅したり、何度も繰り返されてしまって持続してしまうような場合があります。この方法は怒りが頭に湧き起こってきたときにも有効ですが、他の方法と異なるのは、以下のように怒りの対象が目の前に存在しないときに生じる怒りにも効果が見られることです。
・怒りが長く続いているとき
・過去に起こった怒りにとらわれているとき
・よくない未来を想像しがちなとき
目の前にあるものを観察したり、目を閉じて聞こえてくる音を心の中で描写します。例えば「紙がこすれるカサカサという音がする」「足音がする」「電気がチリチリと鳴る音がする」などです。
これはマインドフルネスという瞑想プログラムでも用いられている方法で、今ここに意識をもってくることで、とらわれている感情から解放されることが目的とされます。

イライラ予防に効果あり!ADHDな私の「ネガティブイメトレ」法とは

大人にもおススメ!すぐキレる6歳の息子が考えたイライラ対処法
大人の癇癪と発達障害(自閉スペクトラム症(ASD)やADHD(注意欠如多動症)など)との関係は?
大人の癇癪には、障害や疾病が関連していることもあります。例えば自閉スペクトラム症(ASD)については、その特性の一つである臨機応変な対応が苦手な傾向から、予想外の事態に直面したときなどに、怒りや感情をコントロールできず癇癪につながることがあります。ADHD(注意欠如多動症)においては、不注意、多動、衝動性といった特性から、カッとなったらすぐに手が出てしまうこともあります。また発達障害の二次障害から、攻撃性がさらに高まってしまうことも考えられます。
もちろん睡眠不足やストレスなどの日常生活上の習慣は怒りの要因として大いに関係していますが、関連が考えられる障害や疾病について以下で解説します。
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症(ASD)は、ほかの人との気持ちの共有や会話のやりとりが難しい、表情から気持ちが読み取れないなどの「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」、および常同的な行動や、活動が切り替えられなかったり同じ行動を反復したりするなどの「特定のものや行動における反復性やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」などの特性が幼少期から見られ、日常生活に困難を生じる発達障害のひとつです。知的障害(知的発達症)を伴うこともあります。
自閉スペクトラム症(ASD)の特性として、決められた手順やスケジュールに強くこだわり、新しい人や状況、臨機応変な対応などが苦手な傾向があります。そのため、予想外の事態に直面すると不安にかられたり、癇癪を起こしてしまうことがあります。
自閉スペクトラム症(ASD)の特性として、決められた手順やスケジュールに強くこだわり、新しい人や状況、臨機応変な対応などが苦手な傾向があります。そのため、予想外の事態に直面すると不安にかられたり、癇癪を起こしてしまうことがあります。

ASD(自閉スペクトラム症)の診断・検査の内容は?【専門家監修】

ASD(自閉スペクトラム症)とは?専門機関や診断基準を解説【専門家監修】

ASD(自閉スペクトラム症)の特徴は?0歳から学齢期、成人期までの年齢別に紹介【専門家監修】
ADHD(注意欠如多動症)
発達障害のひとつであるADHD(注意欠如多動症)は、不注意、多動、衝動性を主な症状としています。これらの特性から行動のコントロールの障害が生じ、カッとなったらすぐに手が出てしまうことがあります。これは刺激と反応の間にワンクッションを入れることが苦手な傾向が影響しています。
また、ADHD(注意欠如多動症)の二次障害として、素行障害や反抗挑戦性障害を引き起こすことがあります。幼少期、就学期のころに、周囲から叱責や注意を多く受け、自分の行動が理解されないことから自尊心が下がることなどにより、こうした二次障害につながると、反抗的な態度を取ることとなります。
幼い頃は反抗的な態度をとるにとどまっていても、年齢があがってくると徐々に攻撃性がエスカレートし、また周囲からの理解が得られず、攻撃性がさらに高まり、暴力行為や非行問題に走ってしまうことがあります。このような負の連鎖をDBDマーチともいいます。
また、ADHD(注意欠如多動症)の二次障害として、素行障害や反抗挑戦性障害を引き起こすことがあります。幼少期、就学期のころに、周囲から叱責や注意を多く受け、自分の行動が理解されないことから自尊心が下がることなどにより、こうした二次障害につながると、反抗的な態度を取ることとなります。
幼い頃は反抗的な態度をとるにとどまっていても、年齢があがってくると徐々に攻撃性がエスカレートし、また周囲からの理解が得られず、攻撃性がさらに高まり、暴力行為や非行問題に走ってしまうことがあります。このような負の連鎖をDBDマーチともいいます。

【専門家監修】ADHD(注意欠如多動症)の3つのタイプとは?「不注意」「多動・衝動性」「混合」それぞれの特徴を解説

素行障害(素行症)とは?症状や原因、発達障害との関連は?【専門家監修】

「大人のADHD」普段は何に困ってる?二児の母である私の場合
幼少時の養育環境によるもの
保護者が役割を放棄していたり、虐待にあっているなどの過酷な家庭環境にさらされている場合には、情動制御の弱さが見られるケースが多く報告されています。
というのも気持ちのコントロールは、他者とのあいだにある多様なやりとりによって、その方法を学ぶという要素が強いからです。
人は相手との愛着的関係の中で、「気持ちをなだめてもらう」「気持ちをコントロールしてうまくいく」という経験を経て学習していくものです。しかし、虐待や育児放棄といった、養育環境の中で適切なやりとりが行われなかった場合、過剰に感情を表出したり、あるいは抑制したりしてしまう子どももいます。そしてそれが大人になっても続いていくことがあります。
人に危害を加えてしまうことがある、また対人関係が上手くいかないなどの具体的な悩みごとがあり、自覚できることがある場合、カウンセラーなどの専門家に相談してみることをおすすめします。
というのも気持ちのコントロールは、他者とのあいだにある多様なやりとりによって、その方法を学ぶという要素が強いからです。
人は相手との愛着的関係の中で、「気持ちをなだめてもらう」「気持ちをコントロールしてうまくいく」という経験を経て学習していくものです。しかし、虐待や育児放棄といった、養育環境の中で適切なやりとりが行われなかった場合、過剰に感情を表出したり、あるいは抑制したりしてしまう子どももいます。そしてそれが大人になっても続いていくことがあります。
人に危害を加えてしまうことがある、また対人関係が上手くいかないなどの具体的な悩みごとがあり、自覚できることがある場合、カウンセラーなどの専門家に相談してみることをおすすめします。