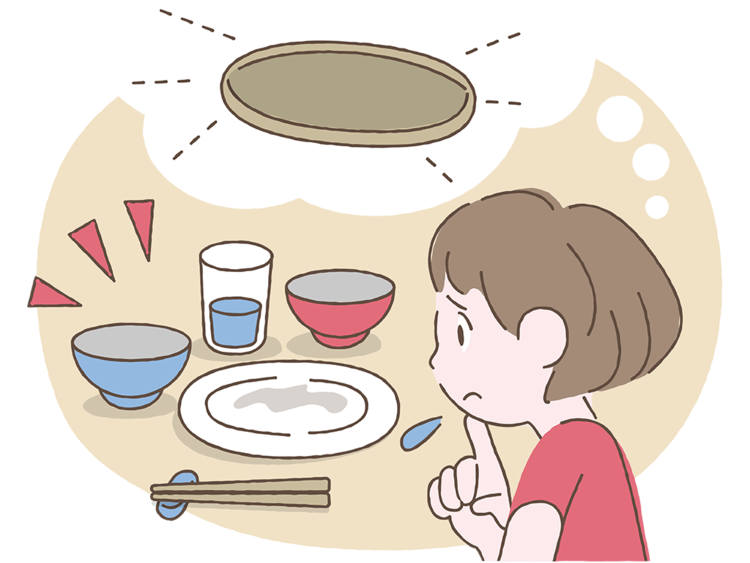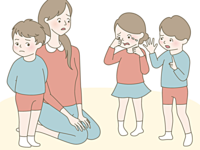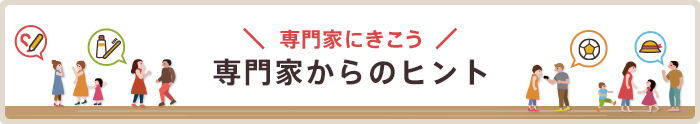よく嘘をつく


すぐにばれるよう嘘をついたり、「やってない!」「知らない!」とごまかしたりするのは、どうしてでしょうか。
お子さんが嘘をつかなくてもすむ対応、嘘をついてしまったときの対応について考えてみましょう。
18568
view
できていないのに「できた!」と言ったり、分かっていないのに「分かった」と言ったりするのは、決して嘘をついているのではありません。
ここでは、できたとき、できないときにどうすればよいか具体的に教える方法を紹介します。
1
お子さんに簡単な作業をしてもらい、できたら教えてもらいます
食器運び、積み木、型はめ、着替えなど
普段からできている活動を選ぶと
練習はスムーズにできそうですね。 2 「できました!」が言えたらまずは褒めましょう きちんと報告できた、ということを褒めましょう。 3 報告が出来るようになったら、お子さんの困る場面を用意しましょう 着替えるときにくつ下が片方ない、
型はめのピースが1つ足りない、
などお子さんが困ってしまう場面をつくっていきます。 4 困ったときの伝え方を教えてあげましょう 「ちょっと助けて」
「困った」
「教えて」
などお子さんがすぐに覚えられそうなフレーズにしましょう。 困っていること、分からないということを伝えられたら、褒めましょう。
 ワンポイント
簡単な遊びの中で取り組むのも良いでしょう。 まず、「できました」という報告からはじめ、 自尊心を大切にしながら大人に事実を報告する練習をしましょう。 そのときは、「できたこと」を褒めるのではなく 「困っていること、分からないということを素直に伝えられたこと」を中心に褒めましょう。 そうすることで、質問や困ったことを正直に言いやすくしていきます。
ワンポイント
簡単な遊びの中で取り組むのも良いでしょう。 まず、「できました」という報告からはじめ、 自尊心を大切にしながら大人に事実を報告する練習をしましょう。 そのときは、「できたこと」を褒めるのではなく 「困っていること、分からないということを素直に伝えられたこと」を中心に褒めましょう。 そうすることで、質問や困ったことを正直に言いやすくしていきます。
ここでは、できたとき、できないときにどうすればよいか具体的に教える方法を紹介します。
普段からできている活動を選ぶと
練習はスムーズにできそうですね。 2 「できました!」が言えたらまずは褒めましょう きちんと報告できた、ということを褒めましょう。 3 報告が出来るようになったら、お子さんの困る場面を用意しましょう 着替えるときにくつ下が片方ない、
型はめのピースが1つ足りない、
などお子さんが困ってしまう場面をつくっていきます。 4 困ったときの伝え方を教えてあげましょう 「ちょっと助けて」
「困った」
「教えて」
などお子さんがすぐに覚えられそうなフレーズにしましょう。 困っていること、分からないということを伝えられたら、褒めましょう。

井上 雅彦
先生
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
公認心理師
専門行動療法士
自閉症支援士エキスパート
LITALICO研究所 客員研究員
当サイトに掲載されている情報、及びこの情報を用いて行う利用者の行動や判断につきまして、正確性、完全性、有益性、適合性、その他一切について責任を負うものではありません。また、掲載されている感想やご意見等に関しましても個々人のものとなり、全ての方にあてはまるものではありません。