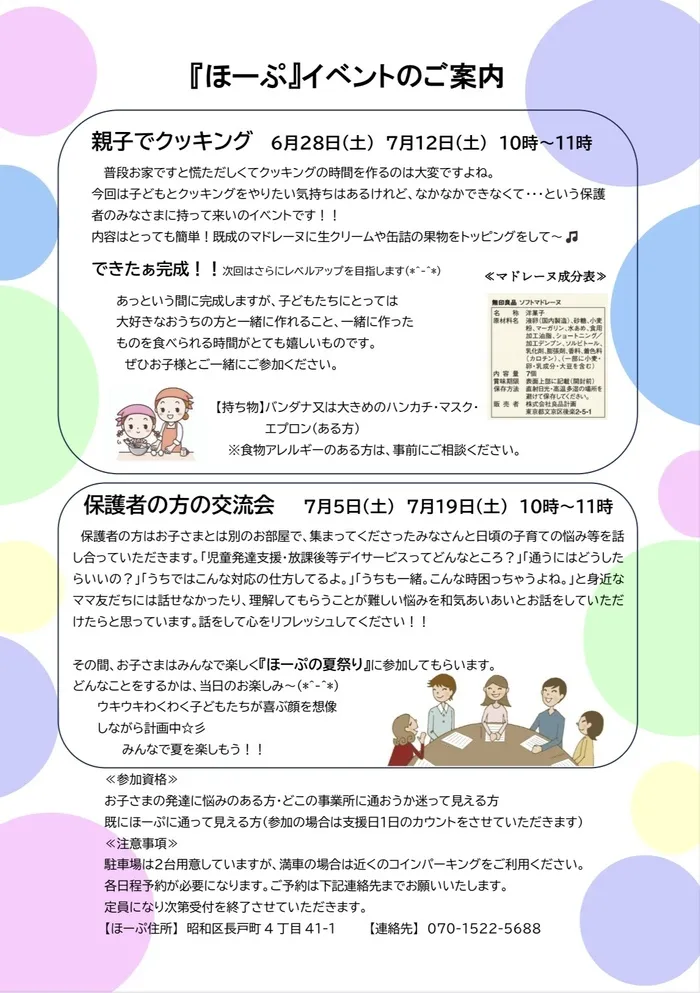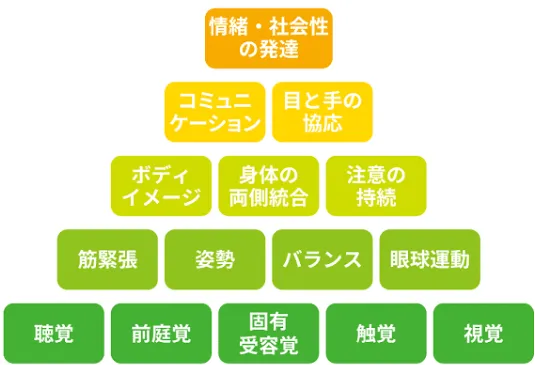ブログ一覧
(42件)
※営業・調査を目的としたお問い合わせはご遠慮ください
掲載情報について
施設の情報
施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。
利用者の声
利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
施設カテゴリ
施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。