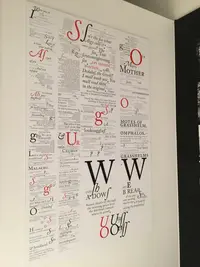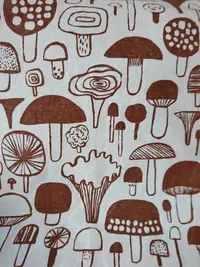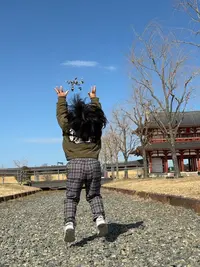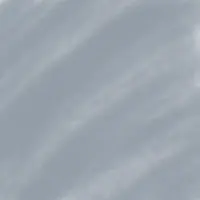受付終了
5歳半、年中の息子が文字好きで凄い色んなことを急速に覚えています。
色んな事を覚えるのが好きなので喋り出せたのが2歳半近くだったのに3歳になる前にひらがなとアルファベットの大文字小文字を覚え、自宅から半径3キロくらいの公園や児童館などをほとんど覚えてしまい自転車で左右真っ直ぐなど指示を出し行きたいところによく連れて行かれました。
3歳半には簡単な足し算や引き算もやり始めてカタカナも覚えたので短い文章がひらがなでも英語でも読めるようになりました。
4歳には都道府県名を全て覚え、掛け算まで12の段まで暗記してしまいました。
4歳半で繰り上がりのある足し算や繰り下がりの引き算、時計にもはまってアナログを1分単位で完璧に読み、12時間を24時間に変換して言うこともできたり、ながくても絵本は自分で1冊読めるようになりました。
5歳前には2桁割る1桁くらいの整数の割り算など出来るようになり、約190カ国の国名と国旗等を覚えて大人でも知らないような大きな桁まで読むようになり(日本語も英語も)、ドリルが好きでよくやりますが問題文も1人で読んで95%くらいは1人で出来てしまいます。
最近では漢字にハマり待ちのあらゆるところでこれはなんて書いてるの?と聞かれ、最近は図書館に行っても辞書と図鑑ばかり読んでしまうほどです。。。(ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字は少しくずれたりするけどほぼ書けるくらいまで出来ていて漢数字と曜日の漢字は書けるようになってきました。)
3歳半で発達障害専門のクリニックに行きましたが自閉症のテストでは引っかかるほどでは無かったため病名はつきませんでした。
ただ親としてみてる限りではASD(触覚過敏や爪噛みチック、他人にあまり興味がなくひとり遊びが好きだったり切替が苦手だったり)とADHD(衝動性優位で黙って行動したり走り出したりなど)の傾向があるのではと思っています。
少なくともアスペルガーっぽいかなとは思ってますが2Eなのか??も少し疑っています。(年長上がってすぐ就学前相談も始まるのでその前にまた以前行った発達障害専門クリニックに行ってみる予定です。)
ベビーの頃からずっとこどもちゃれんじをやっていましたが幼児向けの非認知能力を伸ばすような問題があまり好きではなくなってきたようで影をどんな形か当てる問題などで同じようなことを繰り返し問われる問題に飽きてきてしまって最近はあまりやってくれなくなってしまいました。
幼児ポピーもやってますがこちらは年少の前から1年先取りでやって居たので今年長を受講してますが1人で殆どやれているくらいです。
あと1年半で小学生になるのが見えてきたのもあり、このままどんどん先取りしていき過ぎて学校の宿題をやらないとか授業を受けたくないなどこどもちゃれんじの用にやらなーいと言ってやってくれないとか最悪不登校などの問題が出てこないか心配になってきました。
こんなに知識があってもやはり他人と話すのが苦手ということもあり、今日の出来事など聞いてみても他の子に比べて少なくあまり言ってくれません。(本人の興味のベクトルが向いてないことが問題なのかもしれませんが。。。)
衝動性もあるのですが交通ルールなどはよく覚えているのに走りたくなると止まらないので手を離して車道を走ってしまうこともあるほどで急に公園を飛び出す事もしょっちゅうで生活などのルールは知ってるだけであまり実践出来ない事も多いです。。。
苦手なことは療育に週1回通ってるのでフォローしたり家でも教えたりしたいと思ってますがこのまま勉強での知識をどんどん先取りで与えて入れていくことが本当にいいのか正直悩んでます。(教えてないのに掛け算や国名などはYouTubeや知育ゲームで勝手に覚えていってしまったのですが。。。)
集中すると市販のドリルも1冊1日で終わらせちゃったりするので幼児向けの問題集などはもう割とやり尽くしてきていて次は小学生用に移行するしかないのかな?みたいな感じでこどもちゃれんじを辞めてすららのような無学年学習で本当に学習専門の通信教育に切り替えるかそれが本当に彼にとっていいことなのかとっても悩んでます。。。
文字が好きなのは分かるのですが記憶力がすごくいいからドリル出来てるだけかなとも思いましたがでも意外と大人が盲点だったなみたいな意見をたまに言ってきたりするのでちゃんと理論的な思考も伴ってるのか???みたいなのがイマイチ分からず、こういった子向けの読み物などは調べてもあんまり出てこなかったり参考に出来そうなものが見つけられずで困っております。
そんな訳で紹介が長くなりましたが、似たような子を育てていてうちではこんな感じだよとかこんな読み物役に立ちそうとかあれば教えて頂けるとすごーーーく助かります!!!
...続きを読む
この質問に似ているQ&A 10件
この質問への回答7件
私には、「わが子がギフティッドかもしれないと思ったら」という本が参考になりましたし、当事者である子どもも読んで納得の内容だったようです
当たり前ですが、ギフテッドの当事者も親もかなり少数派なので、周りのアドバイスはあまり役に立ちません
的外れなアドバイスよりも、子どもの声に耳を傾けることが大切なのかなと感じました
お勉強に興味があり、色々勝手に覚えてしまう子はそこそこいると思います。
うちは上の子は定型発達ですが、いろんな事に興味があり、特に習わせたりって事もなかったです。周りの友達もチラホラとそういう子供さんいましたよ。
下の子は発達障害なので、何度も言って身につく…やっぱりつかないと言う感じです。
好きな時期なんだろうと思います。伸ばしてあげたら良いのかなぁって思いました。
そんなに心配する事も無いと思いますよ。定型発達の子には、いろんな事に興味があり、吸収する子普通にいます。大丈夫です。
Et perferendis possimus. Temporibus id accusamus. Repudiandae mollitia omnis. Incidunt omnis maxime. Repudiandae nesciunt et. In corporis incidunt. Sint eos error. Explicabo rerum nobis. Debitis ipsa incidunt. Neque laborum velit. Perferendis saepe officia. Et unde optio. Eius eum non. Praesentium alias nihil. Est blanditiis velit. Culpa aut possimus. Cumque et consequatur. Commodi esse sed. Ducimus accusantium odit. A qui dicta. Non libero qui. Facere dolor aperiam. Aut consequatur perferendis. Consequatur voluptatem debitis. Quia aliquid repudiandae. Odit aliquid vel. Eius cum beatae. Ipsum rem exercitationem. Culpa temporibus vel. Consequatur ducimus in.
パルマンさん、こんにちは
私の長男と似た感じのお子さんかもと思いました。
長男も2〜3才の頃、文字に強い興味を示しました。「何て書いてあるの?」と、本を持って一日中私を追いかけるので、本当に困りました。
いわゆるハイパーレクシアですね。
ハイパーレクシアの子供全てが発達障害を持っている訳ではないので、息子さんに診断がつくかどうかは、専門医の判断を待つ他ないです。
私は息子さんが学びたがる事は、存分に学ばせてあげた方が良いと思います。
長男は3才で菌類に夢中になりましたが、図鑑を見ても私はさっぱり分からず教えられなかったので、博物館の研究者が主催する菌類の愛好会に入会し、毎年観察会に参加して学びました。
その後、長男の興味は植物とか虫とか恐竜とかに、どんどん変わっていきました。
元々不安を強く感じ易いタイプの子供だったので、科とか属とかに整然と分類された自然科学の世界は、長男にとって突然恐ろしい事が起こったりしない、安心できる予定調和的な癒しの世界だったのでしょう。
長男は不安が極限まで高まると、心を落ち着ける為に「クイズだして!」と半狂乱で私に要求するので、私もその時長男がハマっている分野を、オタクなクイズが出せるくらいのレベルまで一緒に勉強しなければなりませんでした。
それまで全く興味のない分野でも、深掘りすればどれも面白く、長男が夢中になるのも無理はないと思いました。
親も一緒になって長男の好きな事を心から面白がる事は、そのまま長男をまるごと肯定することと同じだったと思います。
「そんなくだらない事に夢中になっても何の役にも立たない」なんて、決して言わないであげてください。
パルマンさんが危惧されるように、反復練習的な宿題はやりたがりませんでした。
先生の宿題確認サインを偽造して数百回分の宿題をやったように見せかけるなど、問題児なので学校から電話がかかってくることも度々。
不登校、中退、留年など、就職時の履歴書は惨憺たる状態に。
皆、長男の就職を悲観していましたが、面接時に自分の好きな事を熱く語って採用され、現在某大手企業の研究所にいます。
いつの間にか学歴より情熱を評価する時代になってきたのでしょうか?
だから、息子さんの好きな事を安心して存分に応援してあげて欲しいと私は思います。
Maxime ullam non. Eaque sed ipsam. A impedit veritatis. Quia sed fugit. Neque excepturi ut. Possimus ullam voluptatem. Et itaque consequuntur. Sint odit odio. Aliquam nobis facilis. Facere et similique. Qui accusantium quia. Consectetur eum optio. Voluptate voluptas sit. Dolorem odit praesentium. Praesentium dolor assumenda. Eveniet id sed. Quod ea corrupti. Impedit est sed. Voluptates officia sint. Asperiores eius iusto. Aliquid tenetur sed. Exercitationem harum qui. Asperiores consequuntur eaque. Et aut nisi. Non omnis magnam. Quo voluptates dicta. Consequuntur quo assumenda. Inventore dignissimos est. Ut voluptate quis. Voluptatum alias sed.
出ていないところで…
「ギフティッド その誤診と重複診断: 心理・医療・教育の現場から」
出版社 北大路書房 (2019/9/25)
発売日 2019/9/25
言語 日本語
単行本(ソフトカバー) 392ページ
ISBN-10 476283081X
ISBN-13 978-4762830815
ーー
「わが子がギフティッドかもしれないと思ったら」と内容は被ってますが、学術書的に書かれてるので、出典もちゃんと知りたい方や、論文の方が読み慣れてる人向けかもしれません。
とにかく重いですw
他者からはASDやADHDのように見える行動の原因が、脳の器質的な要因ではなく、他者との思考や認知の違いにある場合もあるという事が書かれています。
追記
我が子の子育ては、常に親子の知恵比べである事と、自分の認知バイアスの再認識と補正で占められています。
Provident aperiam voluptatibus. Ducimus nesciunt velit. Voluptatem reprehenderit consectetur. Libero iste vero. Dicta dolorem delectus. Nobis id sunt. Et non omnis. Voluptas voluptatem voluptas. Rerum in voluptas. Autem quis facilis. Sit sunt laudantium. Nemo nihil sit. Quis modi dicta. Nulla accusamus molestias. Sapiente alias sunt. Doloremque iste asperiores. Deserunt aspernatur qui. Sit ipsum accusamus. Aspernatur optio molestias. Consectetur sapiente dignissimos. At nisi cumque. Distinctio ut nemo. Quia possimus unde. Beatae quibusdam quod. Molestiae enim autem. Aliquid suscipit et. Et cumque necessitatibus. Ut et ducimus. Quia minus architecto. Quasi doloremque earum.
同じような感じではないですが(そこまでレベルは高くない)、図書館に置き去りにしていました(笑)。死ぬほど本を借りてきて、ひたすら読む。
大学の公開講座、無料の講座などがあるので、そこにつれていく。小学校くらいになればなんとかまぎれることはできるはず。あるいは親が登録して、すいません連れてきましたということで、みさせるなどはよいかもしれませんね。うちも、こそっと潜り込ませたことがあります。
Provident aperiam voluptatibus. Ducimus nesciunt velit. Voluptatem reprehenderit consectetur. Libero iste vero. Dicta dolorem delectus. Nobis id sunt. Et non omnis. Voluptas voluptatem voluptas. Rerum in voluptas. Autem quis facilis. Sit sunt laudantium. Nemo nihil sit. Quis modi dicta. Nulla accusamus molestias. Sapiente alias sunt. Doloremque iste asperiores. Deserunt aspernatur qui. Sit ipsum accusamus. Aspernatur optio molestias. Consectetur sapiente dignissimos. At nisi cumque. Distinctio ut nemo. Quia possimus unde. Beatae quibusdam quod. Molestiae enim autem. Aliquid suscipit et. Et cumque necessitatibus. Ut et ducimus. Quia minus architecto. Quasi doloremque earum.
私も他の方が紹介されているギフティッドの本や、そういうお子さんを有名大学に入れたお母さんの本なども読みまして、私はギフティッドかもしれないという気持ちは捨てて育てようと思いました。なんでそう思ったか?大事なところを忘れてしまいましたが…
好きなことや得意なことを伸ばす、でも天狗にしない、自分は自分、自分の趣味興味に集中できる子に…と思っていました。
低学年ぐらいまでは周りの子より語彙がありました。ちゃんと喋れてなんか賢そうな…。でもだんだん周りは情緒面が成長してきて、高学年になると思考力も上がり言葉も変わり大人のような対応をする。うちの子は勉強ができても、やはり中身が幼く感じます。
パルマンさんのお子さんは分かりませんよ。知的好奇心の高い、普通に優秀な子かもしれません。うちの子は最初からコミュニケーションや情緒面に難があったから、そちらを育てたいと思ってきました。だから、勉強ができることや100点を褒めたことはあまりありません。宿題をちゃんとやった、丁寧にやれた、最後まで頑張ったと過程を褒めています。が、中高生になると成績が数値化されるので、私できるのでは?みんななんでできないの?と舐めた態度を取ることがあり注意をすることもあります。
読書と漢字と習い事はどんどんやっていいと思います。うちは図書館で借りまくるのに疲れて、毎日届くのがいいと小学生新聞を始めました。今は中高生新聞や普通の新聞も読んでます。とにかく読みたい子です。知識もつくし、漢字も覚えるし、読みたい欲求叶えられるし、非常にコスパがいい。
漢字検定や算数限定など学年に合わせた検定も面白かったです。性格的に先取りはしませんでしたが。
私は小学校の夏の自由研究でやるような実験・観察・工作が大好きで、小さい頃から子どもとやってました。生き物の観察や飼育、都道府県や国地域のこと、鉄道・旅、料理…そんなものは小学校以降の勉強にめちゃくちゃ役に立ちました。教科書で習うんじゃなくて知ってるって凄いです。理科や社会、習わなくても知ってるんですよー。幼児期に覚えた国旗、いまだに覚えてますよ。雑学、クイズみたいなものに非常に強いです。
Non libero voluptatem. Ipsum veniam aliquid. Voluptatem possimus aut. Asperiores distinctio quisquam. Dignissimos autem qui. Quod atque magnam. Explicabo fuga autem. Libero dolorem culpa. Ipsa tenetur quod. Modi est nobis. Autem eius nobis. Nihil earum praesentium. Ea officiis sequi. Et fuga officiis. Totam eligendi odio. Optio dolore illum. Qui quis earum. Perspiciatis et deserunt. Aut cum ex. Est doloribus pariatur. Omnis dolorem ut. Quia ducimus ut. Eum incidunt molestiae. Vitae beatae quis. Sit voluptas voluptatibus. Soluta ut qui. Qui aut non. Culpa quisquam qui. Vitae quod distinctio. Et recusandae vitae.
この質問には他1件の回答があります
会員登録すると全ての回答が見られます!
会員登録すると全ての回答が見られます!
あなたにおすすめのQ&A
関連するキーワードでQ&Aを探す
会員登録するとQ&Aが読み放題
関連するQ&Aや全ての回答も表示されます。