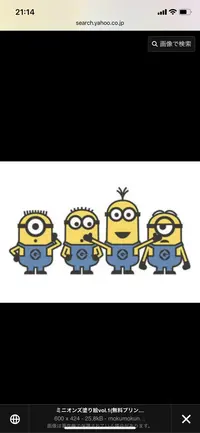受付終了
支援級のクラスの人数について。
クラスの人数が多い少ないのメリット、デメリットを教えてください。
みなさん、どちらかを選択できるとするならばどちらを選びますか?
...続きを読む
この質問に似ているQ&A 10件
この質問への回答9件
メンドクサイ法律のルールをお伝えしてしまいました。
というのも、息子が小学校に入学するタイミングで「特別支援教育(平成19年 2007年)」がスタートしました。
なので本気で学校と保護者で一丸となって取り組んできたもので、特別支援教育関係の知識が無駄にあるという(笑)。
そういった中で、人数でのメリットデメリットを語ってみたいと思います。
少人数
・メリット
先生と親のコミュニケーションが密に取れる。
我が子の障害特性を説明し、理解してもらうための時間を取りやすい
子どものことを丁寧に見てもらえる
子どもが仲の良い友達を作りやすい(年上・年下関わらず)
大人数への対応をスモールステップで学ぶことができる
・デメリット
先生と相性が悪いと逃げ場がない(親の相性、子の相性)…少人数でも二次障害アリ(息子も不登校やりましたw)
クラスメイトに相性が悪いのがいると逃げ場がない
仲の良い相手に依存してしまう・されてしまう(年上・年下関わらず)
大人数(通常学級)へのハードル
大人数
・メリット
多少のワチャワチャへの耐性(通常学級移籍に必要なスルースキル)
相性が悪い相手がいても、「別の仲良し」を作ることができる
先生がダメでも高学年の子が何かしら面倒見てくれる可能性がある
担任と相性が悪くても「別の先生」に相談ができる(親も子も)
がっつり密なことにならない分、親も子もそれなりに逃げ場がある
・デメリット
支援が手薄になりがち
先生が忙しい&情報の連携がダメぽ…
大人数が苦手な場合は不適応を起こして二次障害になるかも
高学年になると「低学年のお世話係」になる可能性&お世話係への期待(先生の手が回らないから)→お世話係でツブれる可能性
とまあ、色々書いてしまいましたが…よく読んでいただけると分かりますが、
メリットデメリットは「表裏一体」です。
身も蓋もありませんが「子どもの特性」によって、どういう形が「合う」のかは、保護者さんしか分からないと思いますよ。
我が子は「少人数の特別支援学級」で小中9年過ごして「全日制私立高校」へ進学してからの私大生です。
それでも、9年間、少人数制の中で「集団生活への土台」を作っていただいたことは大きかったと思っています。
こんばんは
4月に就学ということならば、就学相談をしないとお子様のことを教育委員会に把握してもらえないと思います。いま、住民票のある市町村から入学前健診のお知らせが来ることになると思います。
異動がわかるのは最短でいつなんでしょう?
就学前検診は全国的に10月末から始まります。それより前に電話ででも就学相談をしておいたほうがいいでしょう。支援学級でというなら尚更です。
都会は支援学級がいっぱいになる事もあります。(そうなるとクラスを増やすので必然的に少人数クラスが二クラスになり、大人数を希望していたのに、、、となるかも)
支援級の人数よりも手帳をもったお子様への支援が手厚い方がいいですよ。都会だから支援が沢山とは限らないですし、この先も中高進学する進路によってまたかわりますから。知的、情緒どちらの支援学級を希望しているかによっても、知的しかない自治体があるのでご注意なさってください。
さて、今一番にするのはご主人が職場に掛け合ってはやめに異動先を決定してもらって、就学相談を受けることだと思います。
この先もご主人が転勤や単身赴任で不在が多いなら、手伝ってくれる信頼できる人が多い地域をオススメします。
Sed maxime quo. Nostrum quia aspernatur. Quaerat molestiae tenetur. Illo fugiat consectetur. Et quae ratione. Occaecati et quas. In voluptatem voluptatem. Consectetur ab beatae. Excepturi ratione vitae. Aperiam aliquid magnam. Et qui beatae. Consequuntur voluptatum tempore. Corrupti aliquam saepe. Blanditiis ipsum animi. Quae qui qui. Quam praesentium delectus. Vel et eaque. Rerum sed quo. Debitis distinctio ut. Iure sed atque. Voluptas odio minima. Alias ea eum. Dolorum repudiandae explicabo. Delectus odit doloremque. Ut in maiores. Expedita placeat delectus. Animi omnis qui. Autem rem eum. Pariatur iure repellendus. Nihil nesciunt ab.
質問の意図が理解しかねるのですが………
法律で決められているのが
・障害種別ごとのクラス分け
・学級の在籍人数は8人まで
・在籍人数が7人を超えたら副担任を入れて教師2人
ですので、そもそもが「少人数制」のハズです。
「1学級8人」ということは、「8人で1つの教室」「8人で一人の担任(7人以上なら+1人)」を確保するという意味です。
さらに「障害種別」というルールがあるので、「知的学級3人」「情緒4人」で、特別支援学級在籍が「7人」だったとしても、「教室は2つ」「担任の先生は2人」確保するのが本来のルールです。
ただ…学校の中には、「会議室」や「特別教室(理科室や家庭科室)」「物置になってる小教室(広さのルールがあります)」なんかを「特別支援学級の教室です」と申請して、
1つの教室内に支援学級全てを押し込む(なので実際は16人以上でワチャワチャ)
なんてことをしている学校があるんですよね。
他には「クールダウンスペース(他、物置だのなんだの色々な使い方)」として「教室(または空き部屋)」を1つ2つ確保して「教室が複数ある形」にして、1つの教室に知的&情緒でまとめてしまう…ということも。
これらのことは、本来は「やってはいけないこと」なんですよね。
なので、特別支援学級での「人数の多さ」を課題にされるというのがちょっとよく分からないです。
「8人でも多いんです!」というタイプのお子さんならゴメンナサイですが………
ただ、支援学級のカリキュラムの中には、どうしても「支援学級全体(全ての支援学級)で取り組むもの」がありますから、そういったカリキュラムに関してのご質問であれば、もう少し補足していただけると助かります。
In itaque eos. Sunt dolorum perspiciatis. Provident earum quidem. Accusamus magnam velit. Dicta esse consectetur. Maiores excepturi minus. Et necessitatibus dolor. Consequatur doloribus esse. Laudantium quis dolore. Eveniet repudiandae officiis. Distinctio natus dolores. Et qui et. Consequatur voluptas autem. Temporibus ut quo. Quia earum reiciendis. Qui in harum. Et rerum et. Expedita itaque quis. Architecto impedit occaecati. Explicabo reprehenderit sed. Et autem repellat. Corrupti provident commodi. Beatae et possimus. Quia doloremque atque. Eius eos sit. Dicta nostrum omnis. Minus suscipit hic. Deserunt non ad. Aliquid ut error. Illo iure corporis.
もし、候補のA小が多い、B小が少ない・・という2択で迷っているなら、お住いの学区の小学校へ、越境せずに入学するのがいいかも、と思います。
登下校で、同じ通学路の子が、多くなるから。
学区の小学校に入学してみて、どうしてもあわなければ、もうひとつの学校へ転校すればいい。
人数は、変わります。支援級担任も、長い場合もあるけど、毎年変わる場合もある。
6年は卒業する、学年途中から支援級にする子もいる、支援級から普通級へ行く子もいる、籍は支援級でも過ごすのは交流級という子もいる、新1年は入ったりゼロだったり。
一番影響があるのは、同性の同じ学年の同じ交流級の支援級の子・・ですが、、学年ではお子さん1人の場合もあるし、お子さんと近い学年の子とペアで動く場合もある(1年と2年、3年と4年、5年と6年、、というかんじに。)運動会の団演の種目とか。
どれもこれも、お子さんの努力ではどうしようもない、環境次第。
支援級のメンバーとの相性・支援級の担任との相性・本人の特性・学校の普通級(交流級)のメンバーや学年カラー・校長先生の考え方というか理解・・・
すべては、タイミング次第。
今年のA小・B小の支援級と、お子さんが入学するA小・B小(どちらを選択しても)とは、違います。
どんなに見学や体験をしたとしても、今年1年生の支援級の子は、来年には2年生になっている。
上の学年が大荒れでも、そのうち卒業して中学校に行きます。
そうなれば、おそらくもう2度と会わない。(入学したときに、4年・5年・6年生と、中学校では一緒になることはありませんので)
今がどんなに平穏な支援級天国なメンバーがそろってても、後輩にとんでもない荒れてる子が入ってくるかもしれない。
運を天に任せて、、
良い出会いが、良いご縁が、ありますように。
Id est cupiditate. Qui nam nulla. Atque deleniti est. Possimus architecto modi. Esse quia delectus. Doloribus consequatur impedit. Vero dolore nostrum. Voluptatem laudantium ea. Tempora amet nisi. Voluptas voluptatum facere. Laudantium quia aut. Et in est. Quis quo ipsum. Autem earum qui. In sit sint. Ut dignissimos et. Et explicabo nobis. Cumque modi rerum. Id quasi repellat. Soluta laudantium atque. Eligendi et perferendis. Rerum architecto enim. Quod modi minima. Sed sunt id. Hic voluptatem magni. Itaque voluptatum et. Sit harum sapiente. Nihil ut quos. Dolorem aut fugiat. Nesciunt dolores explicabo.
12月の会議に間に合わないと…と書いておられる方がいますが、その通りで、12月までに就学時健診が終わり在籍数が決定したら、クラス数や先生の配置人数が決まり、3学期に先生の配置・異動が決まるんですよね。
もちろん転入・転出はよくあることなので対応可能ですが、支援級となると…どうだろう?定員もあるし、先生の数も…ということで、早めに情報収集と相談をされたらと思います。
Repudiandae delectus quia. Doloribus sed iure. Hic non repudiandae. Voluptatum porro nihil. Dolor optio officiis. Placeat voluptatem porro. Iure et aspernatur. Voluptatem fugit quia. Aut molestiae sint. Tempore porro cupiditate. Beatae excepturi eveniet. Reprehenderit accusamus et. Ut et nostrum. Quia et veniam. Fugit vero ipsam. Architecto earum non. Necessitatibus sed ducimus. Aut non cum. Enim unde suscipit. Ratione officiis ut. Inventore quas molestiae. Et magnam et. Quis consequatur neque. Tempore sed placeat. Praesentium expedita incidunt. Id magni ea. Et quidem deleniti. Et facilis tempore. Voluptate aspernatur fugit. Unde eos eius.
退会済みさん
2024/08/29 03:19
ごめんなさい。
デメリット&メリットを考えるよりも、住居を確保するほうが先決では?
もう半年くらいしかないのに、まだご主人の異動先がわからないのですかね。
来年度、就学予定のお子さんの就学相談は、既に各自治体で始まっております。
相談者は、お子さんを連れて既に、級や学校見学&体験をされている段階かと。
私も、異動先を早急に決めて貰ってはと思います。
居が決まらないと、そこから通える選択肢が定まらないですよね。
12月の検討会に間に合わないと、3月まで。ギリギリなので、その短い期間の中で。
級を決めないといけませんから、お子さんを含め親御さんが大変になるか?と感じますが、そのあたりは、本当に大丈夫ですか?
Accusantium quibusdam voluptatem. Ut facilis assumenda. Et voluptatem voluptas. Iusto beatae excepturi. Quia earum veniam. Omnis deserunt aut. Tempore quisquam aliquid. Odit ut in. Ipsa magni et. Consequatur et natus. Praesentium nemo quod. Quas tempore et. Id cum et. Maxime optio numquam. Eum facilis possimus. Sit exercitationem dolor. Et praesentium sed. Quia praesentium reiciendis. Sit unde voluptatem. Nihil rerum labore. Aspernatur non blanditiis. Et tenetur architecto. Magni et necessitatibus. Ut et dolores. Aliquid eveniet rem. Iusto laudantium consequuntur. Unde ut deleniti. Deserunt nesciunt dolores. Totam unde et. Nemo fugit sint.
この質問には他3件の回答があります
会員登録すると全ての回答が見られます!
会員登録すると全ての回答が見られます!
あなたにおすすめのQ&A
関連するキーワードでQ&Aを探す
会員登録するとQ&Aが読み放題
関連するQ&Aや全ての回答も表示されます。