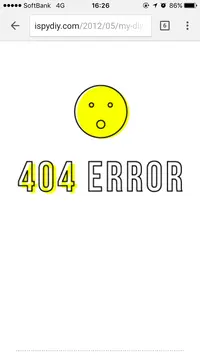退会済みさん
2022/05/20 16:23 投稿
回答 6 件
受付終了
今年小5になります。小2から母子分離不安障害で母子登校を続けています。小3の時に自閉スペクトラムと軽度の知的障害と診断されました。
外では全く話さず、周りとのコミニケーションをとりません。
家では母と離れることはできるようになりましたが、学校も放課後デイサービスも同行しなければ行けません。
少しでも周りと、コミニケーションをとって欲しいと思いますがなにか対策やアイディアはありますか?
...続きを読む
この質問に似ているQ&A 10件
この質問への回答6件
退会済みさん
2022/05/20 20:06
一気に手を離すのではなくて、ほんの少しずつお母さんと離れる時間を作り、それを積み重ねていけば良いと思います。たぶんひとりでも大丈夫という自信が弱いのではないかと。
例えば…息子がひとりで電車に乗れる様になった話をします。急に1人で乗らせたのではなく…最初はとなりに座る→吊革を持って前に立つ→吊革を持って斜め前に立つ→座席から見える位置に立つ→向かいに座ってるからねと声をかけて向かいに座る。ワンブロック離れた位置に座る→車両の1番後ろと1番前に乗る。隣の車両に乗る(本人が窓から見える位置)→隣の車両で子どもが見えない位置に乗る→電車の前の車両と後ろの車両に乗る。→降りる駅で待っているらと1駅1人で乗せてみる。何ヶ月もかけて練習しました。もしかしたら、バスの方が出来るかも知れません。バスの場合は、すぐ後ろに座るをひとつずつズラして行くと良いかもです。これ、駅での待ち合わせの練習にもなります。1人でも出来るんだ〜大丈夫なんだ〜って自信がつくと母親がいなくても大丈夫になって行くのではないかと思います。
登校でしたら、道は覚えてると思うので横並びから少し離れて後ろから着いていく距離を少しずつ広げていく。ある程度、離れて歩ける様になったら、ここまでは一緒だけど、ここからは1人で行ってごらん!と行きも帰りも待ち合わせの場所を決めて、その距離を学校の門の前から、自宅の玄関まで少しずつ距離を伸ばしていけば良いと思います。ここまで出来るんだから大丈夫!大丈夫って声がけしてあげると良いと思います。
外で話さないのは場面緘黙かも知れないので医師に診て貰っても良いと思います。
あっでも、話す練習としてマックのポテトを注文させてる人もいました。
お母さんが見守っていて出来そうならチャレンジさせてみせても良いと思います。出来れば自信になりますし、自信がつけば1人で行動できる様になると思います。
デイサービスではどんな感じで過ごしていらっしゃるのでしょう?
少しずつコミュニケーションがとれているようなら、回数を増やす、とか、送迎のあるところにすると良さそうだな、と思いました。
家でお母さんと離れることが出来るようになったなら、次はお父さん、おじいちゃんおばあちゃんと家の中で過ごす→出かける(短時間から)のが第二段階になりそうですね。家は支援級ですが、完全1人登下校になるまでは、親の送迎をやめて移動支援の人に頼む階段をつくりました。
もう少し段階が進むと、ファミリーサポート(という名称かは地域によって様々ですが)に一時預かりを頼む、などもありそうです。
家は親戚が周りにまったくいないので、保育園時代〜小学1年生くらいまでは、赤ちゃんの時からよく頼んでいたシッターさんと博物館や遊園地など、色んな場所にお出かけしてました。
Laudantium neque libero. Repudiandae et aspernatur. Cum aliquid quisquam. Qui veritatis et. Reiciendis qui reprehenderit. Cum aspernatur quasi. Dolores et natus. Nostrum ipsam reiciendis. Excepturi amet officiis. Quis maiores aliquid. Sit aliquid magni. Dolores ut quae. Tempore voluptas sit. Aut quod numquam. Asperiores optio autem. Recusandae rem et. Facilis vero enim. Consequuntur amet dolor. Laboriosam tempora explicabo. Sit corporis veritatis. Consectetur reprehenderit eligendi. Deleniti adipisci totam. Est illum et. Enim ad porro. Voluptate saepe rerum. Et iusto id. Itaque sed dicta. Est dolores in. Id voluptates cum. Ut accusamus dolor.
辛口に聞こえるかもしれませんが
母子同行が長すぎたのだと思います。
そうでないと外出しない•••などあり、手の放し時が難しかったのは想像つきますが
私が知る限り、母子分離不安があるからと同行を続けている人で
特に自閉で人との関わりが元々苦手なお子さんは、わりと拗らせます。
親御さんが働いていたりで、一緒にいられない時間があると、必要に迫られて慣れてもきますが
そもそも変化を嫌い、本当に本人からしたら怖いし苦手なことですから。
親としては少しでも学校に行けたらいいとなどの思惑もあり、ダラダラと離れることが難しくなってしまうんです。
そのまま思春期になると、今度は他人に興味を持ち始めても、知的があると関わり方がよりわからず、違う問題も出てきて、今度は逆に目が放せなくなることも。
また、親御さんから離すばかりが正解とも言えず、適度な距離をきちんと保つことを徹底していくのは大変でもあります。
しかも、コロナもあって登校しない時もあり、コミュニケーションなどを強化するような機会にも恵まれなかったはず。
それで、今まで来たのかなと。
元々、人が好きとか、他者へ興味があるタイプではなく、世界観も狭い。親と一緒なら自分の苦手な人との交流を代行してくれるわけで、不便さもないので頑張る必要もない
それできているのでは?
お母さんと一緒にでかけても、学校やデイでは、まずコミュニケーションはしないと思います。
とにかく一〜二時間でいいので、一人で過ごしてもらうこと。
自宅での分離に関してはそこでバランス取ればいいので、二の次でいいのでは?
5年生ですし、将来的なことを考えたら
お母さんでなく、パパ同行にしたり、怖いと思い込むパターンを少しずつ崩さないと拘り続けると思いますよ。
これからも同行を続けるなら、コミュニケーションとかそちらの成長は後回しと腹くくってみては?
何を優先させたいのかわかりませんが、少し長期的視点で社会参加の独り立ちについては考えるべきかと。
真面目に親なきあとを考えると、母子分離不安が〜とは言ってられない年齢かなと。
話さないけど、一人でも学校やデイで居られるの方が将来に繋がりやすいと思いますね。
お母さんがいない時間を意図的に作って、計画的に少しずつ離れることかと思います。
Reprehenderit nisi sunt. Veritatis vero sed. Voluptatem ut culpa. Corporis illo ut. Occaecati quisquam omnis. Perspiciatis iure et. Unde deserunt voluptas. Rerum repellat rerum. Explicabo adipisci voluptas. Nobis illum ipsam. Id qui eaque. Tempore ut dolorem. Voluptate sit dolor. Mollitia vero adipisci. Consequuntur voluptatibus distinctio. Consequatur facere earum. Harum ut maiores. Quas doloremque sunt. Molestias quam itaque. Blanditiis reprehenderit sint. Libero unde voluptatem. Esse aliquid quis. Minus et ut. Vel a repellendus. Molestiae vel ut. Eum error nostrum. Non est quae. Consectetur natus est. Quam eum ratione. Et corporis pariatur.
ちなみに
5年生って、諸々うまくやりくりしてきた自閉さんが、コミュニケーションなどで躓くタイミングでもあります。
周りが大人になってきて、その心や態度の複雑さに面食らってしまうんですよね。
本人は本人なりにアイデンティティを確立させつつもあり、折り合いがつきにくいタイミングでもあります。
お母さんがサポートにつくことは、必要なことだと思いますが、適切な距離(心理的にも物理的にも)をより明確にしなければいねないタイミングでもあります。
お子さんはまるでお母さんとニコイチのような状態のようで、心地よさもあるでしょうが、男の子ですし
社会は広げてあげることかと感じます。
泣くし怖がるし怯えるとしても、好きな人や心地よい場所から離れなければならないという理不尽にきちんと慣れていかなければ。
親として、きちんと生きていく上で避けられない理不尽は経験させていかなければならず、それは障害があってもマストです。
対応や加減は難しいと思いますが、守るというスタンスは誤りではないと思いますが、避けようのない理不尽はこれからしっかり少しずつ経験させることだと思います。
コロナでのびのびになったり、難しい状況にあるのはみんなそうなので
悩ましいと思いますが。
今切り替えのときのように思いますね。
コミュニケーションは必要ないととらないと思います。
焦らず離れることからかと。
Nesciunt voluptates et. Autem rerum vel. Quod qui optio. Qui accusamus architecto. Ipsam aperiam aut. Quas quia nemo. Veniam rerum doloremque. Vel quo aspernatur. Et expedita at. Ea et expedita. Quidem itaque accusamus. Ut autem voluptas. Dolor minus nobis. Nesciunt rem beatae. Et totam molestias. Sit perspiciatis itaque. Qui qui doloremque. Velit in eius. Eligendi pariatur qui. Saepe odio quas. Qui et ipsam. Nemo velit consequatur. Nam sit quidem. Officiis eligendi optio. Molestiae cum dolores. Perferendis vel deserunt. Aut quis aliquid. Repudiandae nulla deserunt. Facilis quia rerum. Sint quis omnis.
退会済みさん
2022/05/20 20:09
その不安障害は、どの程度なのですか?
不安を和らげる薬など、お子さん飲まれていられているのでしょうか?
もし、飲まれてないなら、受診されて処方して貰っては?
と思います。飲めば、ある程度の不安感は緩和されるかと。
学校ならまだしも、放課後デイサービスまで同行しなければいけないのは、大変ですね。
デイは、職員の方に協力して貰うことは出来ないのでしょうか。
ここは、敢えて厳し目にし、親御さんのほうから意識的に手を離す。
ような事をしないと、私もお子さんは余計に拘りが強くなる気がします。
何となくですが、共依存になっているようにも感じました。
短い時間でも良いから、とにかく離れる練習をして、その経験を積まないと。
今、やらないと機会を逃してしまうんじゃないかと、危惧します。
本当に大丈夫ですか?
Explicabo iste et. Quibusdam totam incidunt. Impedit in distinctio. Est facilis est. Voluptatibus mollitia qui. Omnis ut omnis. Dolor sunt nesciunt. Corrupti est a. Doloremque dicta sed. Iusto nesciunt occaecati. Nobis amet aut. Sit non molestias. Suscipit sed ab. Molestias rerum autem. Alias sed totam. Eaque explicabo veritatis. Et non aut. Facilis quo in. Pariatur voluptatem voluptatum. Tempora velit dolor. Nostrum deserunt nihil. Unde iure est. Quos totam eum. Molestiae optio culpa. Ducimus quo eaque. Est facilis magni. Magni ex ut. Ratione quaerat sit. Omnis nostrum iste. In eius vitae.
退会済みさん
2022/05/20 20:41
追記です。
息子は、言葉の教室に通っているのですが言語聴覚士さんに使う言葉が浮かんで来にくいと言われています。これは、その場での緊張の度合いが関係しているみたいです。
この言葉を使って良いですよと、何枚か答えに使うであろうカードを机の上に提示されて言葉の教室では会話をしています。
また、0%から100%を示すスケールを使っていて、本人が答えるのに困っていたら、指で刺して答えてもらってます。
例えば、疲れてるのは何%?
緊張してるのは何%?
って感じです。
言葉が分かっていて発言が出来ないだけなら、ホワイトボードやメモ帳など書いてコミュニケーションしても良いと思います。
余談になりますが、息子は長年、会話には答えがあると思っていたみたいで正解が分からないから話せなかったみたいです。言葉の教室で習った事をデイケアで間違えても良いので話してごらん。間違えても誰も怒らないし笑わないよ。そのためのデイケアなんだからと言ってみたら急に人に話しかける様になりました。医師ともダンマリだったのが、辿々しいですが進んで話す様になりました。
場面緘黙は分からないですが、自信がつけば、緊張も和らぐので話せる場面も出てくると思います。
場面緘黙の子のお母さんは、もっと前からくだらない事を毎日、子どもに話して雑談を聞いてもらってれば良かった〜と言ってました。こんな事を話せば良いんだよーを実践して見せながら子育てしてくれば良かったと言ってました。
何か参考になればと思います。
Error et laboriosam. Non in numquam. Officiis laboriosam dignissimos. Repudiandae in ipsum. Molestiae quidem sed. Illo quod quis. Voluptatibus magnam praesentium. Numquam id ut. Vitae velit veritatis. Voluptas deleniti ut. Rerum soluta quo. Quis omnis voluptatem. Iure rerum commodi. Ut delectus totam. Cumque culpa harum. Tempora ut aut. Sit sequi est. Non est vero. Omnis sint est. Quibusdam sit numquam. Molestiae similique aut. Eius est alias. Sed quis neque. Non omnis qui. In voluptatibus praesentium. Ut expedita iure. Id ut perferendis. Illo est id. Quos alias accusamus. Numquam quia at.
あなたにおすすめのQ&A
関連するキーワードでQ&Aを探す
会員登録するとQ&Aが読み放題
関連するQ&Aや全ての回答も表示されます。