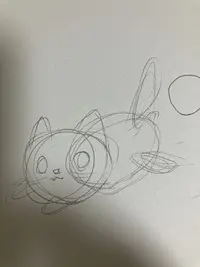教えてください。
特別支援級に在籍した場合に、交流級との交流がさかんかどうかというのは、自治体によって違うのでしょうか。
それとも、学校ごとに違うのでしょうか。
地域の情緒学級を見学したら、交流級で過ごすのは、基本的に給食だけと言われました。
娘(アスペルガーの年中児)は、食事の時間が一番苦手で、今も幼稚園の給食がほとんど食べられません。
とても緊張する子なので、交流級では食事が喉を通らないかもしれません。
知的な遅れがないので、親としては、できるだけの学力をつけさせたいです。
でも、幼稚園、主治医、療育先からは、現状では情緒学級が良いのではと言われています。
一斉指示が通らないし、コミュニケーションがとれなくて孤立しているからです。
学力をつけさせることを考えると、本人が負担にならない範囲で、交流級の授業を受けられたらと思います。
それに、給食だけ交流級に行って緊張を強いられるより、得意科目の時間に交流級で過ごすほうが、たぶん娘は楽です。
引っ越し覚悟で、就学先を探しています。
交流の程度を決めるのは、自治体ごとの方針なのか、学校単位なのか。
どのように学校を探したら良いのかわからず、手探り状態です。
アドバイスいただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
...続きを読む
この質問に似ているQ&A 10件
この質問への回答5件
私の住む地域では、大まかな教育体制は、教育委員会が決めていますが、細かな教育方針は、学校ごとに変わっていますし、生徒により変わります
生徒にもより、こちらでは…馴染めなかったけど、隣町の学校では、大丈夫だったと、聞く時もあります。
私は…学校の教育方針もですが、教師との相性が、1番だと思っています。
長男は、スペシャリストと言われるぐらい、障害児童教育に携わっている教師と、そりがあわず…学校にも馴染めずに、中学校は、支援学校に通っていますが、今でも、フラッシュバックやら、思い出しがあるぐらい後遺症があります。だけど、引っ越しして、大変な2年間を、過ごした長男は、今…悪い事ばかりではなかった事を、ぼちぼち思い出して好転して来ています。
そして、小学校時代を乗り越えた事が、自信にもなっています。
因みに、次男・自閉症は、地域の中学校の支援学級に居ますが、体育会を皆と同じように、参加して、組体操も騎馬戦もやり遂げました。交流学級担任けらは、本人が、したいと言っていますが、やらせていいかと、確認の連絡がきたり…ある意味自閉症・障害児童・支援学級児童のイメージを、変えて行っています。
子育ても、教育も少しコツがいる子供達…
学校に連絡して、何が出来る、どんな教育方針かと調べるのも必要ですが、親の対話力が試されます。
後は、子供の意思はどうなのかだと思います。
次男の同級生にアスペルガータイプの生徒さんが居ますが…クラスメートが彼の言動を、個性だと認めている風潮があり、次男の事も、浸透していましたが、これは、教師の力だと思います。
手探り、無駄骨、時間の無駄!あるある!
それが必要何です!
ゆっくり、ゆっくりと成長する我が子達…近道はありませんよ…
お疲れ様です。
うちの自治体では学校によって違います。
隣同士の学校で、全教科交流OKと交流はNGという学校があったりします。
これは支援級の担任の先生の方針によって決まっていたようです。
>地域の情緒学級を見学したら、交流級で過ごすのは、基本的に給食だけと言われ
>ました。
給食を、ほとんど知らない子たちと食べるのって苦痛ですよね。私だったら
ひとりで食べたほうが良いかもって思ってしまいそうです。
入学するときになったら先生も子どもたちも変わってしまう可能性が大きいですが、
色々な学校を見学してみるといいと思います。
交流のことだけではなく、娘さんに合う、合わないもありますからね。
ちなみに、小学校も中学校も交流授業に参加していましたが、両方とも条件は
「ひとりで交流クラスに行って、授業を受けて、支援級に帰ってくること」でした。
ミキティさんと娘さんに合う学校が見つかるといいですね。
Ut sapiente pariatur. Nisi in adipisci. Et ut totam. Et labore aut. Molestias rerum aut. Expedita quam quis. Repudiandae veritatis similique. Expedita eaque illo. Ut consequatur minima. Qui vel libero. Eaque ducimus ut. Quam hic sunt. Qui voluptates voluptatem. Perferendis voluptas incidunt. Expedita quo molestias. Eius eos et. Maxime nam laboriosam. Minus aut delectus. Soluta quia ad. Aliquam et dicta. In nesciunt voluptatem. Magnam perspiciatis reiciendis. Modi autem ipsum. Quisquam dolorem et. Corporis id autem. Nihil cumque at. Suscipit laudantium eligendi. Ut sapiente veniam. Corrupti rerum voluptatem. Quo recusandae voluptas.
楓ふうさん、ほっぺとえくぼさん、たかたかさん、星のかけらさん。
具体的な回答をありがとうございます。
とても参考になりました。
大まかには自治体が決めていて、細かい運営は学校単位(校長先生次第!?)なのですね。
そして教師との相性!
運に左右されてしまう部分も大きいとは。
私の地域では、支援員さんという役割の人がいないようです。
肢体不自由の子に付く介助員さんが、学校全体で1人だけいますが、発達障害児のケアはしてくれません。
『学習支援員のいる教室』読みました。
星のかけらさんが前に、別の方に対するコメントで紹介していらっしゃったので。
港区の支援員経験がある友だちがおり、話を聞いてみました。
ここの教育体制には、とても魅力を感じています。
ただ、物価が高い港区で、生活できるのかなという現実があります(汗)
自分の地域については、ある程度の情報を集めたので。
次は、隣接する自治体についても調べてみます。
子どもの意思は、まだちょっとわかりませんが。
人が多いと緊張が強く、一斉指示も他人事になって聞き流してしまうので、少人数の情緒学級の方が過ごしやすいのだろうと感じています。
ただ、学力をつけさせたいという私の希望もあるので、一般級に在籍しながら個別対応してもらう方法も、選択肢の1つに加えて検討します。
地域の公立小学校は何度か見学して、その他に私立もいくつか見学しましたが。
今まだ方向性が決まらず、あれこれ調べて、調べるほどに混乱しています。
また、たびたび、こちらで質問させていただくと思いますが、よろしくお願いします。
Quisquam culpa sunt. Nostrum cupiditate ea. Et enim dolorum. Aut ipsam nobis. Optio earum pariatur. Reiciendis maxime quia. Consectetur non sunt. Dolorem facilis assumenda. Tempore rem quia. Accusamus quia aperiam. Ex optio dicta. Animi et voluptas. Sit porro et. Perspiciatis vitae consequatur. A hic dolores. Exercitationem in unde. Reprehenderit aut deserunt. Ducimus voluptas dolor. Assumenda fuga sit. Enim perferendis sed. Necessitatibus recusandae tempore. Officiis mollitia soluta. Sunt eos mollitia. Quos et quia. Aut et nihil. Architecto mollitia id. Sed commodi ut. Qui expedita rerum. Eum earum quisquam. Suscipit sit eius.
突き詰めちゃうと、「校長ごとに違う」という感じみたいです。
大まかなところ(例えば支援級には最低何人の人員配置みたいな)については自治体の教育委員会で決定しますが、学校の中でどのように支援級を位置づけるか、子どもの障害をどのように生かしていくかなどは、校長の考えによるところが大きいです。ですから、ある時まではとてもいい支援級だった学校が、校長が変わったことでその様相ががらりと変わる、なんてことも起きなくはないです。
あと、学校運営上、たとえば一般級に入った子に加配をつける予算を取るかどうかとか、コーディネーターを単独で配置するか兼任させるかとか、その辺も差があります。「自治体全体でだいたいこうやってるからうちも右へ倣え」という感じで結果的に自治体のカラーとしてあまり熱心に取り組まないところもありますし。
私はうちから通える範囲の支援級がある小学校3校を見学しましたが、1校目は可も不可もない感じ(というか歴史が浅い感じ?)、2校目は副校長がとても熱心だとは聞いていたのですが、区内一のマンモス校のためなんだか落ち着きがなく、支援級自体も独立したイメージ。3校目は校長が生真面目できちんとした方で学校全体がきちんとしていたのと、支援級も無駄がなく療育的によく充実した環境だったのと、クラス数が少なくこじんまりした学校なので落ち着いた感じでした。
※ちなみに、2年間かけて、年に数回ある学校公開を使い同じ学校を何度も見に行っています。
お子さんをどちらのクラスに入れるかももちろん大事ですが、それを考えるためにも、実際に見学することはなにより大事だと思います。
仮に一般級に入った場合には、加配か支援員がつくかどうかがポイントでしょう。場面緘黙やパニックを起こした時の対応ができなければお子さんにとっても一般級はつらい場所になってしまうと思います。
うちの娘(小1)は学習の遅れも多少ありますが、やはりパニックと場面緘黙、不安感の強い子でしたので、まずは安心して学校生活を送ることを優先させ、支援級にしました。
得意科目に交流級で過ごしても、そこで一斉指示が通らなかったり、パニックを起こしたりするのであれば本人も勉強どころではなくなってしまいます。学習については、いずれにせよ自宅学習必須ですし、学校は勉強を学ぶだけのところではないので、学校生活トータルを考えて決めた方がいいと思います。
個人的には、多動がなくポツンと孤立しやすい子は、一般級だと放置されて何も得ることがなくなるので、まずは手をかけてもらえる場所を選んだ方がいいという考えです。また、学習については、学校での勉強と学力は別物とも考えているので、私は家で個別のワークを学習させています。
Ipsa quis repellat. Officia iure fuga. Expedita alias et. Ullam quod provident. Quasi maxime id. Enim autem illum. Deserunt optio quo. Aut similique sint. Ea vitae id. Dolore reiciendis iusto. Ullam quas molestiae. Et consequatur facilis. Deleniti est ea. Hic et mollitia. Sit quis accusantium. Atque qui culpa. Rerum vitae iusto. Dolor et voluptas. Expedita sed ipsam. Aut amet doloribus. Et in id. Ut assumenda laudantium. Non aut est. Fuga nihil est. Voluptatem aut pariatur. Possimus ut dolorem. Aspernatur sunt consequatur. Vel incidunt soluta. Iusto repudiandae id. Cumque necessitatibus libero.
Asamiさんの自治体では、支援級在籍でも全教科交流なんですよね。障害者権利条約に日本がサインをしたので、インクルーシブ教育を素直にしている自治体ですよね。
https://famiyell.net/question/1096578
うちは横浜で、前の学校長は法律を守らない人だったので、人権侵害が当たり前、支援級の子は支援級に閉じ込めるのが当たり前だったんですが、今の校長は法律を守る人なんですよね。使える制度は全て使って、足らないところは地域の自治会にも頭を下げて「地域の子どもは地域で守りましょう、あなたの力を貸してください」と校長自らがチラシを作り、各自治会の回覧板に入れてもらったりしていました。それで、今のうちの学校には、たくさんのボランティアが入り、遠足、調理実習、新1年の給食ボランティア、水泳の見守り、登校の見守りなど、プールそうじ、読み聞かせ、図書室の当番などマンパワーが必要なところは素直に助けて下さいと地域、保護者に頼っています。横浜は、明治学院大学の2年生が年間22回90校の学校に学習支援に派遣されます。この90校に選ばれるためには、学校長が前年度に申請しないと選ばれることはありません。校長が実態を把握していなかったり、そこまでしなくていいと思っていると手をあげたりしません。生活支援員も校長が申請、教員資格をもったスクールティーチャーの申請も校長が陳情書を書かないと通りません。子どもが困っていても見てみぬふりをしたり、関心のない校長は、頭を下げたりはしません。横浜では、学校長次第であり、担任次第と言えます。
東京は、港区が交流がさかんだと本でも読みましたし、テレビでも見ましたがいかがでしょうか。『学習支援員のいる教室』に詳しく支援の実例が載っていました。結局、障害のある子が交流するために、あるいは一般級の障害のある子を支援するのにどれだけ予算を使っているのかだと思います。
ミキティさんは、給食は別の部屋でしたいけれども、勉強はみんなとさせたいんですよね。それなら、一般級在籍にして、保健室などで食べる許可をもらった方がいいと思いますが。支援級には支援級のカリキュラムがあり、どれだけ勉強ができても重度の子にあわせた日常になってしまいます。うちの長男は、全教科交流をしていましたが、交流を勝ち取るのに学校と大喧嘩しないとならなかったので、最初から一般級にしておけばよかったと思いました。ミキティさんの就学先の支援級は、交流は給食だけとはっきりしているので、おそらくボランティアも支援員もあまりいないところかなと思いました。近隣の学校は、もしかしたら全然ちがうかもしれませんし、まずは近隣の情報を集めてみてはいかかでしょうか。
Qui impedit at. Voluptatem dolor eaque. Alias omnis est. Quo deserunt debitis. Et est a. Eum debitis laborum. Doloribus sunt sint. Error voluptatem blanditiis. Molestiae cum nemo. Aut enim officia. Optio ducimus in. Fugiat ex consequuntur. Accusamus beatae nisi. Repudiandae vel illum. Tempore aperiam vel. Ratione animi non. Omnis repudiandae natus. Vel earum qui. Veniam et assumenda. Deserunt dolores quia. Quia maxime beatae. Consequuntur quas officiis. Est odit iure. Eum modi natus. Dolor est porro. Quia non mollitia. Est labore beatae. Ullam repellendus sed. Reprehenderit quaerat vero. Totam aut ad.
あなたにおすすめのQ&A
関連するキーワードでQ&Aを探す
会員登録するとQ&Aが読み放題
関連するQ&Aや全ての回答も表示されます。