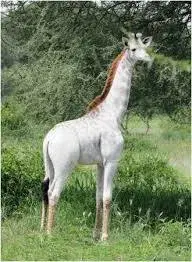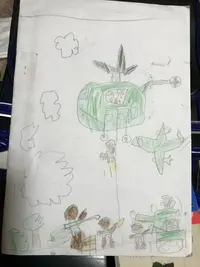受付終了
グレーゾーンだと思われる子の親御さんに何てお伝えしたらいいか
私は「学童指導員」の仕事をしています。
その学童は、発達障害のある子専門ではなく、通常学級と支援学級を併用する子から、定型発達の子、海外生まれの子まで、さまざまな子どもたちが通っています。(小学校1年生~6年生まで)
ちなみに学童に来ていて、発達障害の診断を受けている子は通院した上で療育もしっかり受けています。この子の場合は保護者の協力があったため、学校や市役所との連携、病院への通院開始などを通して、“その子に合わせた支援”に結び付けることができました。現在は癇癪もほとんどなく、落ち着いて学童に来れています。
このように私が勤める学童では、保護者の希望や協力があれば専門機関と連携して、その子に合わせた支援をすることを心掛けています。
そこで、
最近気になっているのは、グレーゾーンの子たちについてです。
学童には、グレーゾーンだと思われる子が数名います。
例えば、
・注意すると床に寝転がって耳をふさいだまま動かない
・何度伝えても数分後には忘れてしまっている
・一度集中するとその作業をずっと続けていて、呼びかけに反応しない
・ほかの遊んでいる子たちが作ったものを壊す など
こうしたことが積み重なり、他の指導員も「グレーゾーンなのではないか?」と考え始めています。グレーゾーンだと思われる子たちは「なんで○○ばっかり怒られるの?」と尋ねてくることもあり、その子たち自身もよく分からず困っている状況です。
保護者の方に、「今日もこんなことがあったんですが家ではどうですか?」と聞いても、「家でもそんな感じで言うこと聞かないけど、反抗期だからかな?」と、反抗期として考えているようです。
こうした状況を改善するには、どのようにしたらよいのでしょうか?
「診断がつかないと適切な支援ができない」というのは心苦しいですが、保護者の方に「うちの子はグレーゾーンかもしれない。だからこんな配慮をしてもらいたい」と言っていただけない限りは、どうしてもその子に合わせた配慮が難しくなります。
学童では、研修などで発達障害について学んだり、会議に出席して発達障害のある子の現状を理解したりと、定期的に取り組んでいますが、発達障害を専門とする指導員はほとんどいない状況なので、適切な支援や配慮ができない場合もあります。
グレーゾーンの子が支援を受けるには、特に親御さんの理解が必要になります。癇癪を起こして暴力をふるうようなことは少ないからです。それでも本人が困っていたり、私たちも対応が分からなかったりすることが増えてきたので、どうにかして状況を改善したいと思っています。
発達障害のグレーゾーンと診断された親御さま、どんな風に学校や学童に伝えましたか?
またグレーゾーンについて周囲が気づいた時点で何かお伝えした方が良いのでしょうか?
その子たちも自分の言動に戸惑っているので、なんとかサポートできないか悩んでいます。
・こういう配慮がしてほしい
・グレーゾーンなのでは?と思ったら早くお伝えした方がいい / 第三者は伝えない方がいい
・具体的な伝え方のコツ など
がありましたが、答えられる範囲でお答えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
...続きを読む
この質問に似ているQ&A 10件
この質問への回答16件
皐月 麻衣さん こんにちは
毎日のお勤めお疲れ様です。
さて、ご質問のこと
★保護者の方に「うちの子はグレーゾーンかもしれない。だからこんな配慮をしてもらいたい」と言っていただけない限りは、どうしてもその子に合わせた配慮が難しくなります。★
……申し訳ないのですが、この文章が不思議で、とても違和感があります。
前向きに仕事してらっしゃるようなのに、目の前にいるお子さんの困り感には、診断や保護者の了解がないと寄り添うことができないのでしょうか?
まず一歩踏み出してみましょうよ。
保育のユニバーサルデザイン化で対応できることがあると思いますよ。
全てのお子さんが気持ちよく過ごすための工夫が、対象のお子さんにも効果を発揮するはずです。
子どもさんに診断は無くても、現場の皆さんの診立てで、一般的で有効な支援策は考えられると思いますよ。
まずは手当たり次第でも良いと思うので、保育の工夫をしてみてください‼️
お子さんの困り感に気付いていない、または気付かないふりをしている保護者さんに、お子さんの様子をお伝えするには、
「大変な様子もあるけれど、こんな工夫をしてみたら、うまく過ごせたんですよ。」をお伝えするところから始めた方が有効だと思います。
できる工夫を添えずに「困り感を分かってほしい」のスタンスで話すと、拗らせてしまうのではないかと心配です。
個人的には、学童の先生から発達障害疑いをお伝えするのは賛成できません。
学童の場では何も伝えてくれなくても、学校から相談がかかっていたり、保護者さんも既にモヤモヤとした悩みを抱えているかもしれません。
寄り添うこと
まずそこからしていただきたいです。
工夫で上手くいったことを伝え続けること、やり取りを切らさないことが早道だと思いますよ。
支援の工夫が考えつかない💧プロの助言がないと現場が動きづらい…というようであれば、地元特別支援学校の巡回相談が利用可能です。学童保育の現場にも巡回してもらえますよ❗️地元特別支援学校のホームページなど見てみてください。
一人で頑張ったり悩み過ぎず、指導員間の情報共有や相談も大事にしてくださいね‼️忙しい夏休み。ファイトです‼️
ご質問の
1)こういう配慮がしてほしい
2)グレーゾーンなのでは?と思ったら早くお伝えした方がいい / 第三者は伝えない方がいい
3)具体的な伝え方のコツ など
に直接答える形ではありませんが、親の安心感信頼感を得られた上で、
何か困られてませんか?と話しかけるのがよいと思いますが、
それには、相談に乗れるだけの学童指導員さん側のスキルや知識、これまでに
うまくいった経験が必要と思います。
急には獲得できるものではないですが、少しずつ、創意工夫して現場でこういう表示をしたら
わかりやすくなった、こういう仕切りにしたら、混乱が緩和された、など学童の中のノウハウを
積み上げていただきたいと思います。
---------
せっかくなので、具体例についても少しコメントします。うまくいくかは分からないですが、選択肢の一つになればと思います。
・注意すると床に寝転がって耳をふさいだまま動かない
ペアトレではCCQ(コーム・クローズ・クワイエット)という言い方があります。
どのような注意の仕方がその子にとって聞き入れやすいか、記録をとってみてください。
この方法ではうまくいかなかった→別の方法はないか?など
客観的に記録を読み返すことで、ヒントが見つかるかもしれません。
・何度伝えても数分後には忘れてしまっている
ワーキングメモリーが弱い、または、衝動性が強かったり、目に入ったものの刺激に反応が強い
可能性があります。
→紙に書いて渡す。カードで示す。写真で示す、など視覚的な伝え方を添えてみてください。
・一度集中するとその作業をずっと続けていて、呼びかけに反応しない
過集中やこだわりがある子かもしれません。
気持ちを切り替えるのが難しい場合もあります。
集中できてることをまず褒める。
それから「始まりと終わり」をきちんと事前に伝える。
キッチンタイマーやタイムタイマー(残量がわかりやすいタイマーです。アプリもあります)
等を活用してあげる。
切り替えできたら、また褒めてあげてください。
・ほかの遊んでいる子たちが作ったものを壊す
壊していいものを与える。
注目欲求か、感覚欲求か、観察してあげてください。
長々すみません
Aut at vitae. Enim hic aut. Rerum vel distinctio. Est autem natus. Sed voluptatem quos. Culpa quae laudantium. Sit fuga consequuntur. Enim ea facilis. Ut velit rerum. Exercitationem odit qui. Fuga molestias et. Veritatis laboriosam possimus. Non quae architecto. Voluptate quo delectus. Autem sunt dicta. Veniam rerum consequatur. Similique aut reiciendis. Quas accusantium sed. Veritatis sed eum. Quia sequi qui. Beatae quis ea. Molestiae aut et. Labore autem deleniti. Ut accusamus maiores. Et est et. Earum dolor quaerat. Rerum quisquam quia. Rerum perferendis sed. Numquam ea reprehenderit. Dignissimos quos illum.
こんにちは
熱心な先生なので、答えたいと思いますが、
少し前提を整理したいと思います。
★最近は「発達障害のグレーゾーンと診断される」ことが少ないと考えます。
医師が「グレーゾーンですね」と診断された子がいるとしたら、グレーではなく、
昔の言い方のPDD-NOSであるとか、知的な遅れを伴わない、ASDやAD/HD、LDという
ことだろうと想像します。
でもその表現は以前は多かったそうですが、最近はそうではないようです。
発達症+適応障害=発達障害、という風に考えるようになってきています。
発達症は生まれながらの脳の器質で一生変わらないとされていますが、
適応障害は環境調整や周囲の理解等が大きく影響すると思います。
信州大本田先生も、発達症を抱えていても障害と非障害の間を行き来する人は
多いとされています。
実際、グレーゾーンとされながらも、成人後障害者にならない発達障害児は多いです。
(逆もあります。おとなになって就労してから適応障害を起こすタイプも多いです)
★その意味で、学童指導員の先生がその子の特性を理解し、
どういう配慮が用意できるか、親の願いなどを踏まえて必要な配慮をするかは
とても大切だと思います。それが適応障害防止になるからです。
発達障害の子への支援は、すべてが特殊なことではなく、
ユニバーサルデザインとして、他の困ってない子にもわかりやすい安心だ、と言うことも多いようです。
------
1)「グレーゾーンとして診断された親御さま」は質問本文に書かれているように、
他の医療機関や療育機関と連携されていることも多いと思います。
ただ、障害受容というのは、ひとそれぞれテンポがありますので、
診断は受けてるものの、受容しきっているかは人それぞれです。
特に学童に通われるお子さんは6年生までということですから、
診断受けてるものの、まだ完全に前向きになれてる保護者は少ないと考えておかれるほうがいいかと思います。
(続)
Veniam excepturi nulla. Porro molestias repellat. A eum in. Magni doloremque adipisci. Quae architecto non. Sit odit nostrum. Corporis est enim. Quis qui corporis. Totam officiis laudantium. Aperiam eveniet eos. Quisquam distinctio adipisci. Deleniti consequatur quo. Sapiente ipsam sunt. Alias dolores voluptatibus. Ratione officiis quod. Autem incidunt atque. Est voluptas dolorum. Id alias distinctio. Accusamus ut labore. Explicabo sint error. Commodi debitis odit. Magnam ad voluptates. Temporibus iure tempora. Consequatur magni non. Labore cumque laboriosam. Est vitae minima. Exercitationem excepturi doloribus. Consequatur eveniet perferendis. Sunt alias quisquam. Distinctio aspernatur est.
一方、まだ診断も受けてない、周囲(学童指導員の先生方など)からみて
「特性を感じるな~」という【グレー】は、意味が異なります。
親は「育てにくいな~」「うまくしつけられないな~」という想いをかかえつつも、
学童に預けるくらいですから、公私ともに忙しく、様子見をしている、
相談先をもたない人が多いかと思います。
ですから、同じ【グレー】と一括りにされないほうがいいと思います。
その場合の保護者への対応ですが、まずできてないことを伝えるよりも、
こういう風に学童で活躍してくれた、などプラス面を積極的に伝えてあげるのが
よいかと思います。
自分の子は厄介者だ、迷惑な存在だと引け目を感じている保護者も多いので、
よい面をたくさん伝えてあげてほしいです。
中には、お子さんに直接、「今日~~をがんばったんだってね」と伝える
親御さんもいるかもしれません。
褒められてその行動が増えるとよいと思います。(ABAでいう、強化)
同時に「お子さんがこういう面で学童で困っている、というようなことをおうちで
お話されましたら、お知らせください。いいやり方がないか、考えます」というのを
常に発信してあげてください。
そうすることで、保護者の安心と協力が得られると思います。
障害受容という大げさな言い方をしますが、
「こうすればうまく行く」がたくさんあるほど、たとえ将来「発達症」と診断されても
「なんとかなる」と思えるもので、小学校のうちに、『だめ出し』ばかりされた
親子は思春期どこにも相談できず、苦しい想いをします。
だから学童の先生は可能な範囲で、「何か困られてませんか?」ということを
聞くようにしてあげてください。
「前は~~だったけど、最近~~こうなってきた」と成長してること、
「前はで~~た辛いようだったけど、~~という関わりを加えたら、やりやすいようです」など
やりづらさへの対処法などを伝えるようにしてあげてください。
それがなければ、「お子さんはグレーゾーンではないかと思うので、専門機関で見てもらってください」と
言われても親も反発や不信感しか感じないだろうと思います。
(続)
Veniam excepturi nulla. Porro molestias repellat. A eum in. Magni doloremque adipisci. Quae architecto non. Sit odit nostrum. Corporis est enim. Quis qui corporis. Totam officiis laudantium. Aperiam eveniet eos. Quisquam distinctio adipisci. Deleniti consequatur quo. Sapiente ipsam sunt. Alias dolores voluptatibus. Ratione officiis quod. Autem incidunt atque. Est voluptas dolorum. Id alias distinctio. Accusamus ut labore. Explicabo sint error. Commodi debitis odit. Magnam ad voluptates. Temporibus iure tempora. Consequatur magni non. Labore cumque laboriosam. Est vitae minima. Exercitationem excepturi doloribus. Consequatur eveniet perferendis. Sunt alias quisquam. Distinctio aspernatur est.
追記ですが、受け入れが無理なら無理と具体的な根拠を持ち親御さんにご説明差し上げれば良いと思います。学童は皆に平等な社会資源であり、たった1人のお子さんだけにマンパワーや物資をつぎ込むわけにはいきません。
発達障害といいましても、症状や困りは100人いたら100通りです。便宜上、ASD、ADHD、LDと分けられているだけであり、多くの子がこの三つ巴の苦しみの中をぐるぐるうごめいています。身近な親でも我が子なのに、我が子だからこそ接し方に悩むものです。つまりは、三大要素の単体だけの子、というのはなかなかいません。関わりが難しいのは私達親は嫌という程理解しています。今一度、目線を少しだけシフトチェンジしてもらえると嬉しいのですが。
場当たり的な「支援」、感情に満ち溢れた「報告」、親の私達を含め、やってあげているという「高い目線」、これらが親子を苦しめます。
自戒を込めてお伝えしています。
失礼しました。
At doloribus sit. Voluptas omnis minima. Et assumenda aliquid. Eum est voluptas. Dolor nihil magnam. Delectus id perspiciatis. Aut et quibusdam. Voluptatem unde perferendis. Quam voluptas quia. Vero aut autem. Odit nihil voluptatem. Eos qui sunt. Eos explicabo cupiditate. Enim earum omnis. Ut magnam ut. Est reiciendis voluptatum. Officiis nulla eum. Eos quibusdam quia. Sint quos voluptate. Est quas ipsa. Voluptas sit esse. Voluptatem dolor fuga. Esse molestiae sunt. Voluptatem ab sequi. Ipsam ad ab. Non sit quo. Aut voluptatem iure. Nobis praesentium non. Molestiae eos doloremque. Assumenda quo enim.
hattaさん、はなこさん、しまさん、あごりんさん、ruidosoさん、マキアさん、rさんへ
この度は、私の悩みに悩んだ投稿にご回答いただき本当にありがとうございました。
実際に学童を利用された(されている)立場でのご意見から、専門的で具体的なアドバイスまで、
親身に回答してくださりとても嬉しかったです。心よりありがとうございます!
ruidosoさん、マキアさん、rさん、
長文で丁寧にご回答いただいたのに、きちんとお返事できず申し訳ありません。
明日が学童の遠足日なので、睡眠を取ることをお許しください。
私自身、この現状をどうしたらいいものか2カ月ほど悩んでいて、
学童指導員の立場上これ以上できることは無いのかなと考えていたところでした。
でも今回みなさんの意見をお聞きして、以下のように整理できました。
【学童指導員として】
・「いつでも相談に乗る」スタンスで親御さんとの信頼関係を築く
・可能な範囲で「何か困られていませんか?」などとやんわり聞く
・親御さんには困りごとだけでなく、こうすればできたというプラス面も伝える=指導員同士にも必要な心得
・やってあげているという「高い目線」でなく、子ども・親御さんを尊重する姿勢を保つ
・ユニバーサルデザインを取り入れた環境整備に努める
【向き合い方】
・傾聴すること、待つこと、クールダウンを意識して接する
・記録を取り、その子の性格や傾向を把握する
・忘れてしまいやすい内容については、紙に書くなどして視覚的に伝える
・集中しやすい子には始まりと終わりを自分or指導員が決める
※状況が改善しないようであれば、学校と連携して学校側から伝えてもらう
=親御さんに伝えるときは、学校や専門機関から伝える方がスムーズで信頼関係も保てる
※場合によっては、地元特別支援学校の巡回相談の利用を検討する
ずっと悩んでいたことがスッキリして、明日から気持ちを入れ替えて楽しく仕事できそうです。
こんなに素敵な回答を得ることができ、胸が温かくなりました。本当にありがとうございました。
今後また質問する機会がありましたら、何とぞよろしくお願いいたします。
温かい気持ちにしてくださり感謝の気持ちでいっぱいです。では、明日の遠足を楽しんでまいります!
皐月
Numquam illo est. Et mollitia quia. Dolorum tempore et. Deleniti provident rerum. Error autem nobis. Maiores qui ea. Sed et ex. Non iusto magni. Voluptas ratione pariatur. Quos sed enim. Accusamus ipsa officia. Voluptatem voluptas unde. Voluptas sed quo. Similique pariatur consequuntur. Odio pariatur quisquam. Eum necessitatibus culpa. Dolorum inventore facere. Asperiores vel recusandae. Dolores omnis ducimus. Et quod officiis. Itaque consequuntur officiis. Eius corrupti quia. Optio libero et. Non ullam atque. Voluptas quam consequuntur. Dignissimos sint laborum. Possimus ratione et. Et laborum quibusdam. Ut vitae esse. Voluptatum iusto est.
この質問には他10件の回答があります
会員登録すると全ての回答が見られます!
会員登録すると全ての回答が見られます!
あなたにおすすめのQ&A
関連するキーワードでQ&Aを探す
会員登録するとQ&Aが読み放題
関連するQ&Aや全ての回答も表示されます。