
相談支援専門員の役割と仕事内容とは?児童発達支援との関わりについて
相談支援専門員とは?
相談支援専門員とは、障害児や障害者の相談に対し、本人や保護者の意向を踏まえて自立した日常生活や社会生活が送れるように障害福祉サービスの利用にサポートや定期的な振り返りなどを行う職種のことです。基本的には相談支援事業所で働いています。
業務内容として、本人、保護者などからの生活や仕事などの困りごとに対する相談への対応や、利用できるサービスの情報提供、利用する際の計画の作成、関係機関との連絡調整、利用手続きなどのサポートなど幅広く行います。また、利用後もモニタリングといって定期的に利用状況の振り返り面談を行い、必要に応じて計画の変更なども実施します。
また、相談支援専門員は誰でも名乗れるわけではなく、福祉に関する実務が3年~10年あり、相談支援者従事初任者研修を終了した人がつくことができる職種です。実務経験は職場や役職、持っている資格などによって必要な年数が変わってきます。
研修は都道府県が実施しているので、詳しいことはWebサイトを確認しておくとよいでしょう。
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
児童発達支援とはどのように関わるの?「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」について
ここでは、相談支援専門員が児童発達支援を利用する際にどのように関わってくるかを紹介します。
まず、障害のある子どもに関する相談支援には「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」の二種類があります。障害児支援利用援助は支援計画の作成や実際に利用する際のサポートなどを行い、継続障害児支援利用援助では実際に支援を受けた後の振り返りや計画の変更などを行います。
ただ、相談支援専門員だけで支援が完結するわけではありません。そこで、実際の児童発達支援の利用の流れに沿って、具体的な仕事内容やほかの職種との関係性などを紹介します。
児童発達支援を利用する際の大まかな流れと主に関わるスタッフは以下になります。
1 アセスメント:相談支援専門員
2 障害児支援利用計画の作成:相談支援専門員
3 個別支援計画の作成:児童発達支援管理責任者
4 実際の支援:児童指導員など
5 モニタリング:相談支援専門員
この中で相談支援専門員は主にアセスメント、障害児支援利用計画、そしてモニタリングに関わるので、それぞれ紹介します。
アセスメント
まずはアセスメントといって聞き取りなどをもとに子どもの状態の把握を行います。
相談に来た子どもや保護者から、成育歴や現在困っていること、今後の意向をヒアリングするとともに、子どもの発達段階や障害の特性、おかれている環境などさまざまな情報を集めていきます。そして、その情報をもとにして、どのような支援を行っていくか方針の提案を行います。
障害児支援利用計画の作成
障害児支援利用計画を作成し、事業所で支援が始まってからも相談支援専門員の仕事はあります。モニタリングといって、定期的に子どもや保護者と面談を行って、事業所の支援内容や子どもの変化、満足度などの聞き取りを行います。
モニタリングは6ヶ月に一度が標準的ですが、大きな変化があった際はそれより短い期間で行われます。
モニタリングの結果、支援に満足していなかったり、新たなニーズが生じた際には必要に応じて担当者会議を開いて障害児支援利用計画の見直しを行います。
障害児支援利用計画の見直しが行われた場合は、それに合わせて利用している事業所の個別支援計画も子どもにとってより良い支援になるよう調整することも仕事の一つです。
そのほかの仕事内容
障害のある子ども向けの支援を利用している場合、18歳になるタイミングで成人向けの支援に切り替える必要が出てきます。利用できる支援や利用料の負担などさまざまな点で変更がありますが、その手続きも相談支援専門員が対応することがあります。
具体的な流れは状況により異なりますが、計画の作成やほかの機関との連携などを行い、18歳になって以降も切れ目のない支援が提供できるよう働きかけていきます。
このように、相談支援専門員は子ども本人だけでなく、保護者、関係機関、実際利用する事業所の担当者などさまざまな人と関わり、本人にとって最適な支援が提供できるように働きかけていく役割を担っています。
障害児相談支援事業所は自治体のWebサイトで一覧が掲載されている場合がありますので、相談を希望する方はお住まいの地区のWebサイトで確認するか、自治体の障害福祉窓口などに問い合わせてみるとよいでしょう。
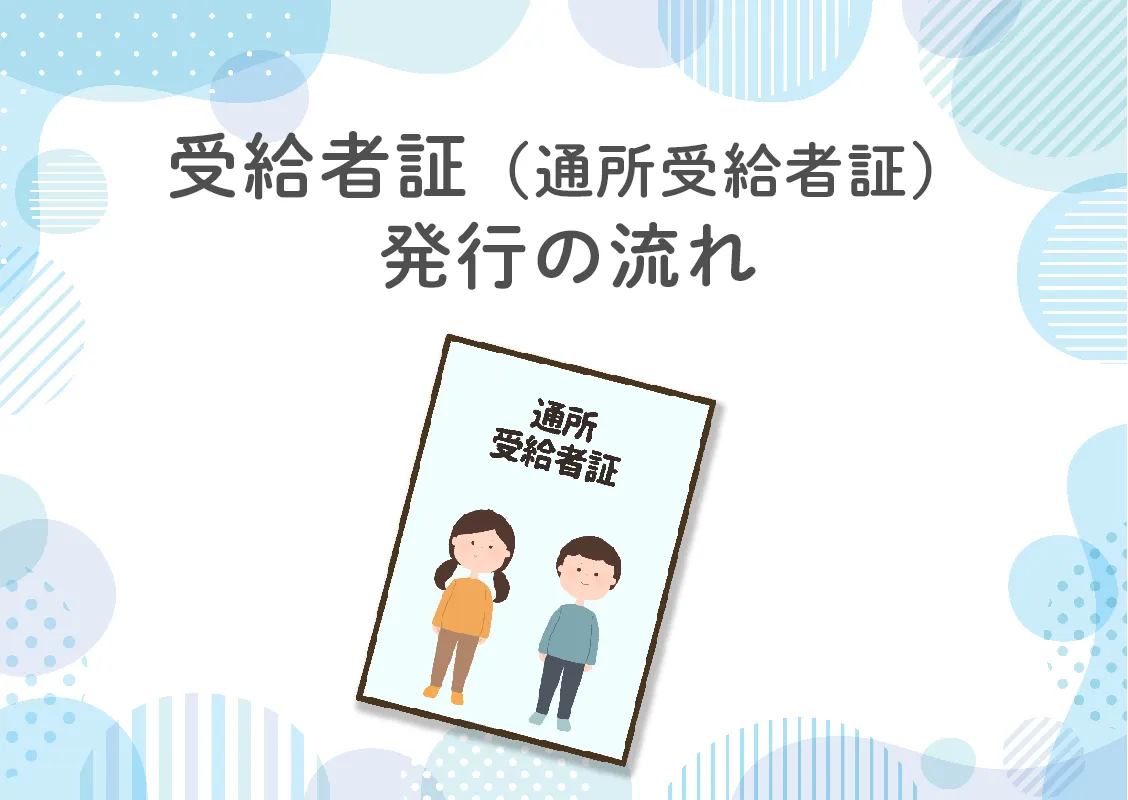


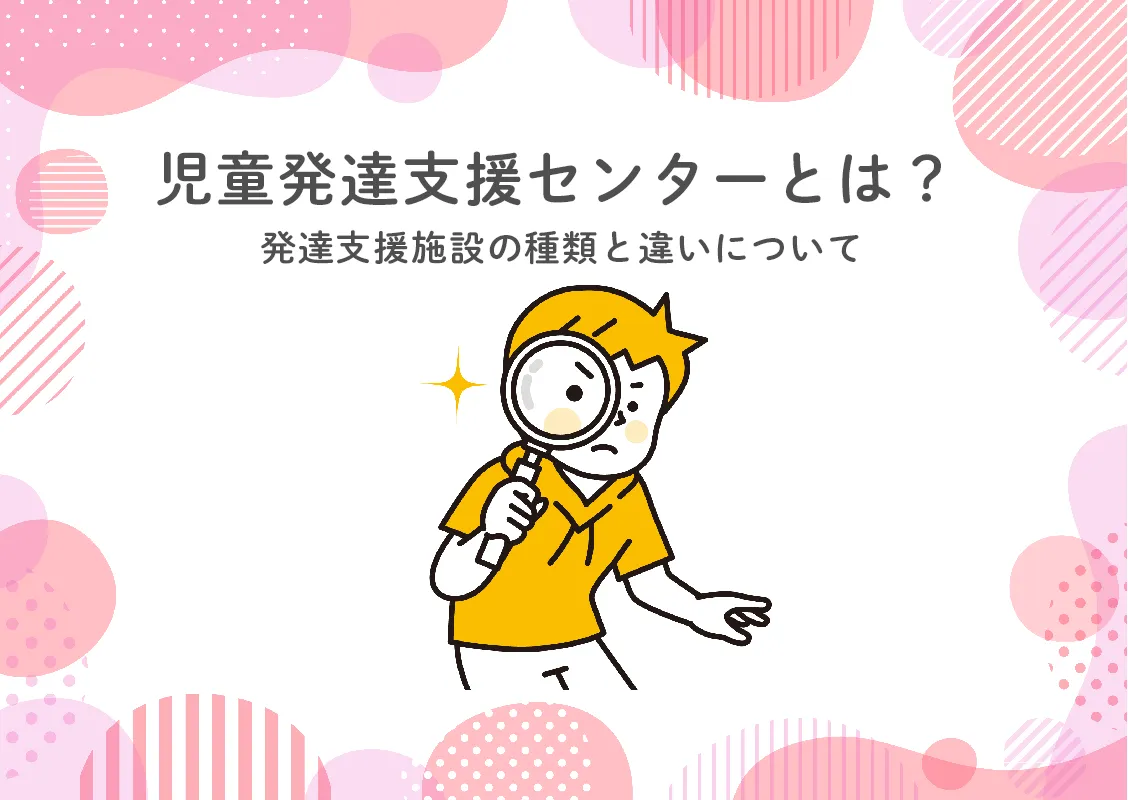
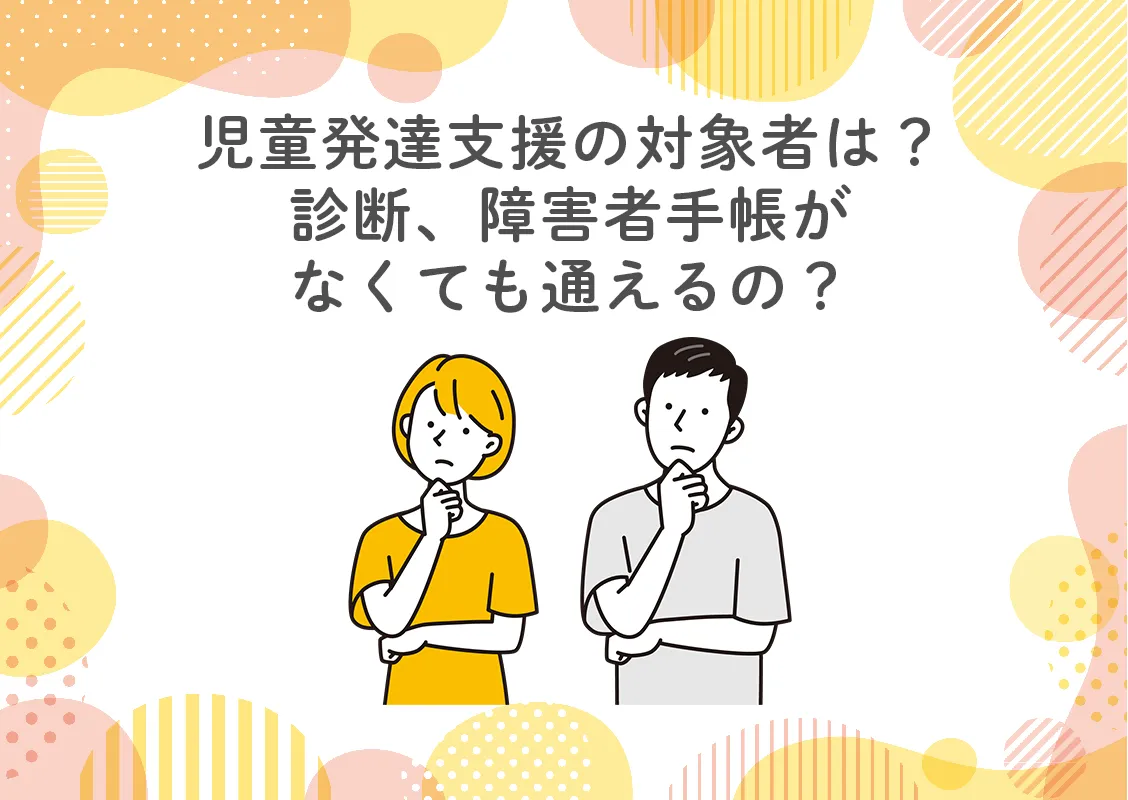

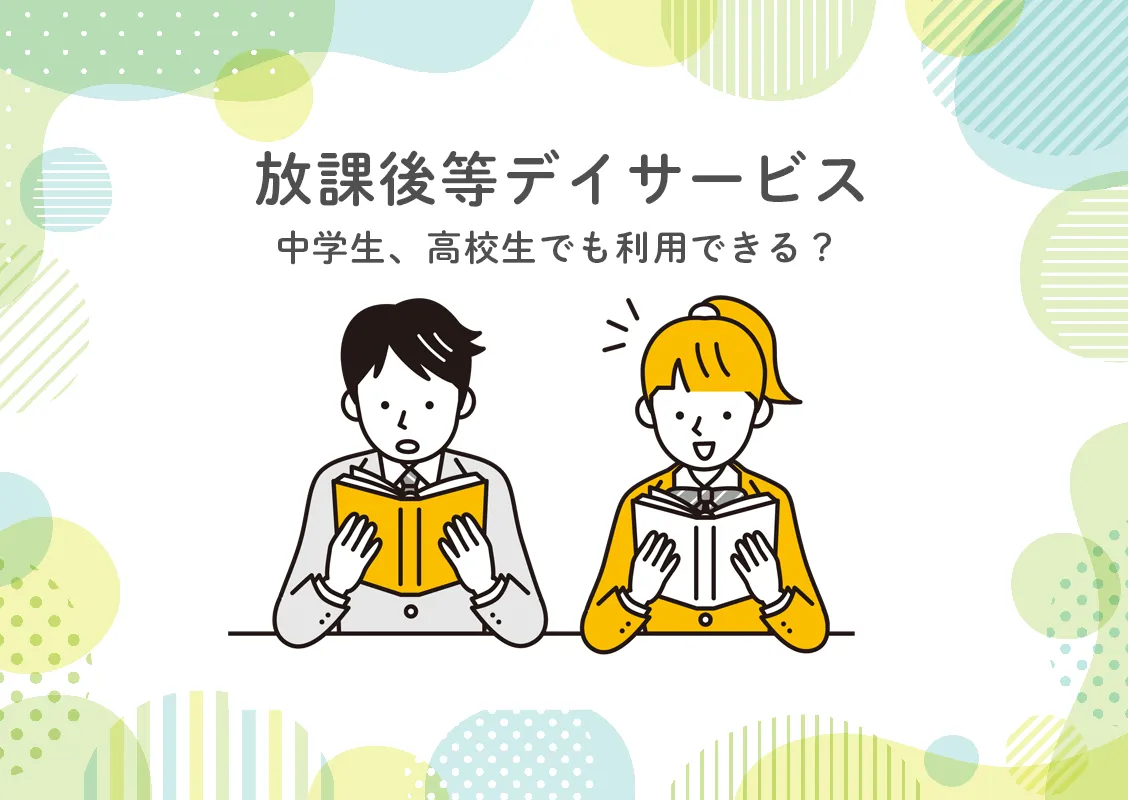
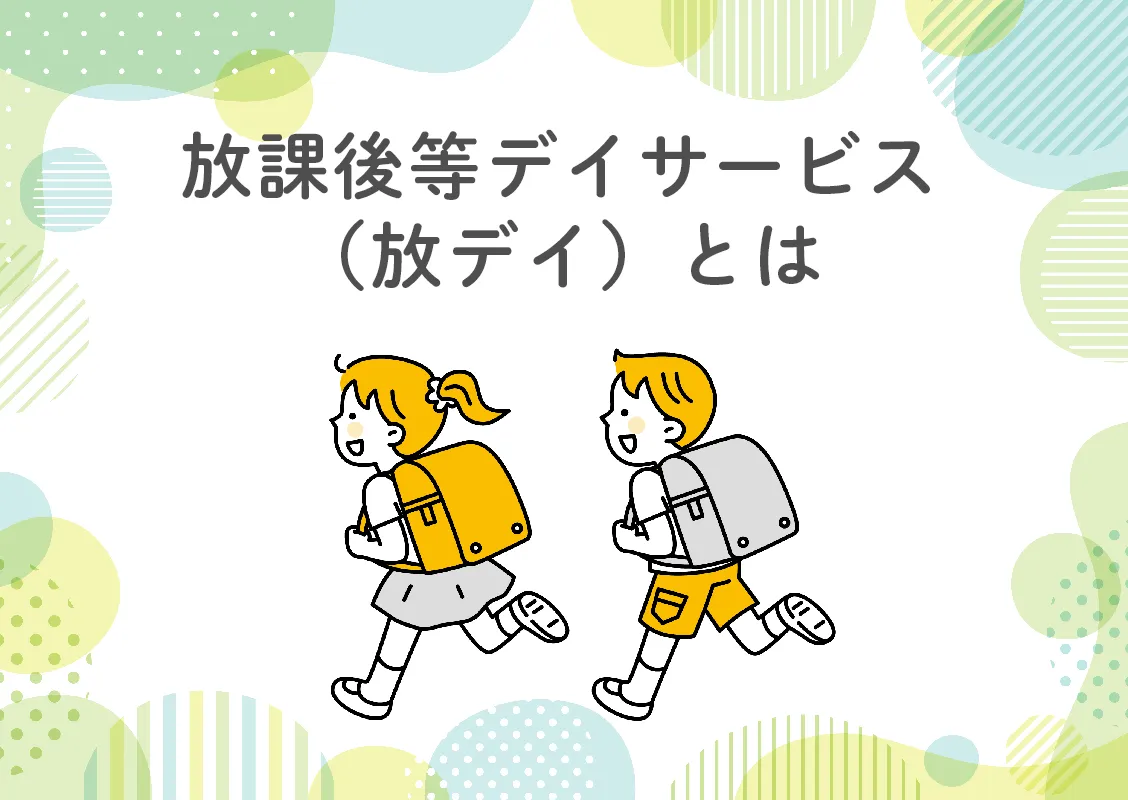




年長の息子の相談支援専門員が非常に多忙なのか、今年7月に担当の依頼をしてから、放デイ見学1ヵ所目が10月、2ヵ所目が12月となりました。勿論途中で催促もしましたが、なかなか動いてもらえませんでした。結果的に空いている事業所を押さえてはもらえたのですが、今後ずっとこの人に担当してもらう自信がありません。就学後、相談支援専門員の出番はどれくらいあるのでしょうか?放デイ利用に関する場面のみであれば我慢できるかもしれませんが、小学校に関しても出番がありますか?元々私の仕事関係で知っていた相談員で、その関係から夫の相談員を先にしてもらっているのですが、正直夫に関しては受給者証の更新さえしてくれればどうでもいいです。しかし子供のこととなると話は別です。こんな仕事をする人とは知らないまま、息子の担当をこちらから頼んでしまった手前、他の相談員に変えたいとはとても言いにくく、大変悩んでいます。就学に向けて相談員を変えた方がいいのか、変える場合も角が立たない方法はないのか、アドバイスいただけると幸いです。


現在利用しているのですが、うーん…と思うことが多く、セルフでやってた時とそこまで変わらないというか…という感じです。他の相談支援事業所はどのようなことをやっているのか?相談支援事業所の仕事はなんなのか?と思い質問させてもらいます。利用契約書やネットも見たのですが、具体的にはよくわからなくて…初質問なので、至らない点があったらすみません。ちなみに今契約してる相談支援事業所は年中の時に契約して、放デイ探しや地域の情報が欲しいと思い契約しました。(そういう話は伝えてます)そして来年度一年生なのですが相談支援事業所は半年に一度、我が家に訪問して親の話を聞き取り利用計画を作成してもらってます。相談員さんが療育園に子供の様子を見に行くということはしてないと思います(少なくとも行ったという報告は無い)リハビリや放デイの情報は聞いても毎回「空きがない」としか回答がなく、リストに載ってない新設の放デイなども教えてもらえないので、結局はリハも放デイも全部自力でしらみつぶしに探して契約してます。以前はセルフプランでやっていたので書類も自分で書いていたのですがあの書類の為だけに相談支援事業所を利用してるならお金がもったいない気がします(自分では払ってませんが)この相談員さんは2年前の契約時にしか我が子にあったことがないと思うのですが、そんなもんなのでしょうか?


りないのですが、我が家は放課後ディは利用せず、悩み相談や、アドバイス頂けたらと思い利用をしたいなと思っています。利用されている方おりますか?放課後ディより、認知されてなかったり、話題にならないのは何故かなと疑問でした。周りにあまりいないので教えてください。


ほとんど知識無いのですが、よろしくお願いします。3歳8ヶ月の男の子です。3歳児検診で、発達相談してみましょうとなり、保健所でk式?の発達検査をしました。そこで発達支援ルームに行ってみませんか?と言われました。見学に行った際、相談支援専門員をつけるか、セルフでするかと聞かれました。皆さんは、相談支援専門員さんをつけて良かった事、んー?って事、また、セルフでしてて困った事なども良かったら教えてください。


2ヶ月前に発達検査を受検したところ、軽度から中度の知的障害です。今後、障害を持つ子を育てるので、夫婦のストレスが多くたまり、また将来について不安で一杯です。質問をさせて頂きます。1、皆さんは、気負いなく相談出来る方をどのように作られているか。2、どのような方を相談相手としているか。3、同じ障害を持つ方に相談相手がいるかどうか。教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。


皆さんは相談支援事業所を正式に福祉スービスとして契約し、利用されたことがありますか?私は自分に合った相談機関を探そうかどうか迷っている際中です。私は就労移行支援センターに通っています。ただ、二度目の利用なので、また失敗して仕事をやめられるのではないかと市役所でその他相談支援機関を勧められました(この時点で職員さんの心配するというより、経費を気にしているような態度でメンタルダメージくらいましたが)三件ほど回り、一件自宅から近いところで一度契約しました。ですがなかなか連絡がつかない、相談しようにもできないことや相性の問題で頼ることが難しかったです。電話だけの相談なら他に親身にきいてくれる相談機関がありますが、正式に契約となると私としてはしっくりときません。発達だけでなく、家庭環境や仕事のトラウマ、フラッシュバックする性質、気難しい私がしっくりくる相談機関なんてないのではと思っています。皆さんはちゃんと信頼できて気軽に相談できる相談機関はありますか?それともカウンセリングですか?当事者の方にききたいです。
気持ちになります。私が考えた勉強サポート方法を話したら「WISCスコアだと難しい」と断定され、「お母様が良ければ行ってみたら」と基本丸投げ、あちこちの機関(4箇所)に通い始めたら「色々やられて大変ですね〜、でも(今のままでは)この部分解決できていませんよね(⇨アドバイスはなし)」と他人事。相談員て何のためにいるのでしょう?母親としてまだ足りないと言われているような気がします。どこに行けばアドバイスって頂けるのでしょう。途方に暮れています。

に相談会に参加してくださいと強く推されて学校について相談できるのは相談会でしか出来ないからと言われたのでもし電話で予約取れれば来週だめなら7月参加予定ですが正直わからないことがわからない状態なのだと言うとそこの旨も含めて伝えればなんでも話してくれるしあらゆる機関に繋げてくれるとのことだったのですが3月の相談会では支援学校の学級の種類や内容を簡単にですか教えて貰ってるのですがそれ以外だとなにを聞いたらいいのかわかってませんみなさん相談会でどんなことを聞きましたか?毎回相談会には参加してましたか?浅はかな質問ですみません💦


その児童発達支援についてなんですが、療育の計画書や進捗状況などを事業所は親に提示する必要はないのでしょうか?家族と保育園、事業所との連絡ノートを使用して連携を図ってるのですが、そもそも療育の進捗状況や何を目的に介入を行なっているのかなどを載せた計画書などを作成する義務?必要は制度的にはないのでしょうか?うちのところは見学に行ったり親が参加したりすることができないところなんですが皆さんのところはそういった情報共有などはいかがでしょうか?

らっしゃいますか?県教委や、市町村教委で作られて、希望者が使える、支援ツールの一つです。支援が必要な幼児、児童、生徒が使うことができて、早期療育から就学、就労まで一貫したサポートが受けられるように、成長歴や支援内容をファイリングしていくものです。私の町では、6年前に支援ファイルが完成し、教育委員会から配布が始まりました。自閉症次男の小学校就学に向けて、使用しました。そのときは、支援ファイルの構築に携わった療育センターの発達障害児コーディネーターの先生ががサポートしてくださり、ファイルの中身を書くことができ、さらに、息子の支援の関係者(主治医、保育園の加配の先生、療育センターの担任の先生、就学予定の小学校の特別支援コーディネーターの先生、町教委の学校担当者、町保健師、療育先の指導員の先生)を招いて、ケース会を行いました。ただ、発達障害児コーディネーターの先生がいらっしゃらなければ、書くことはできなかったと思います。支援ファイルを使っている方、どのように作成していますか?
掲載情報について
施設の情報
施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。
利用者の声
利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
施設カテゴリ
施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。


