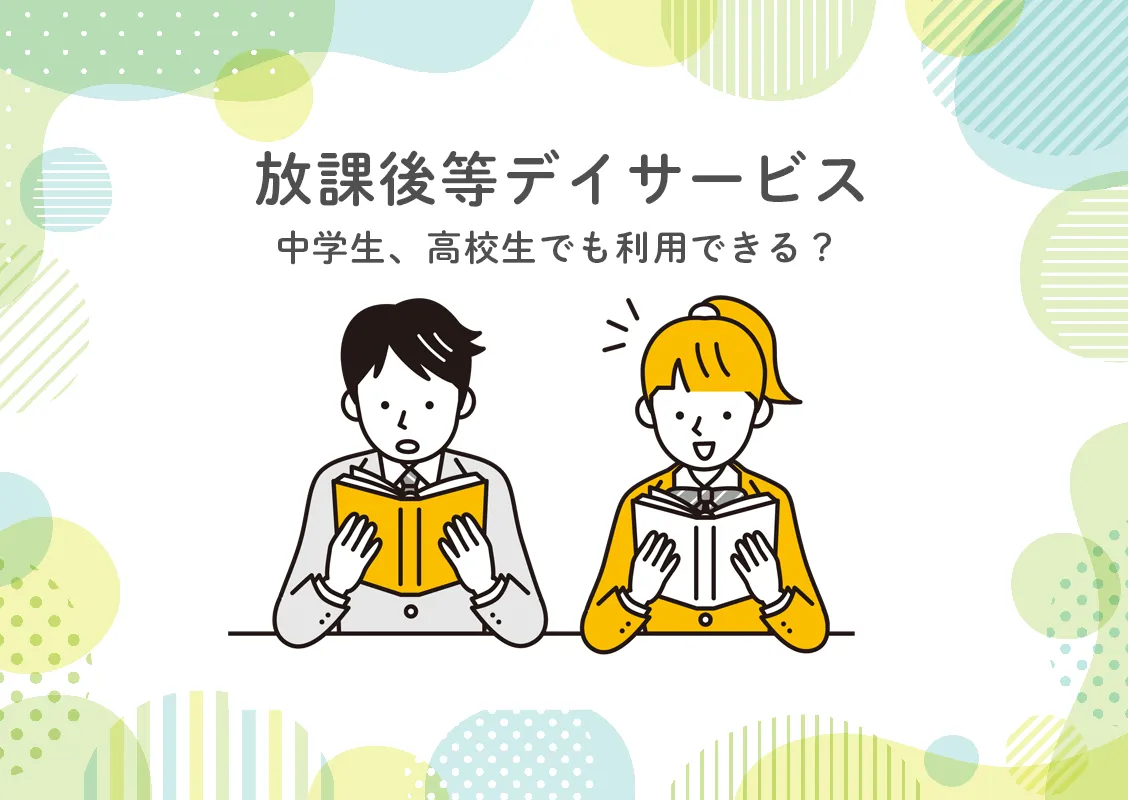
放課後等デイサービス、中学生、高校生でも利用できる?支援内容や活動例をご紹介
中学生、高校生も放課後等デイサービスを利用可能
放課後等デイサービスは障害のある就学児への福祉サービスです。就学児とはここでは小学校~高等学校までの学校に通っている人を指しており、幼稚園や大学に通っている場合は対象となりません。
また、該当する学校に在籍していれば不登校の状態でも利用可能ですが、退学した場合は対象外となります。
なお、令和6年4月からは専修学校に通っている場合も対象に含まれると明記されました。
放課後等デイサービスというと小学生が通うものとイメージする方もいるかもしれませんが、中学生や高校生の利用者も多くいます。厚生労働省が実施した令和元年度障害者総合福祉推進事業の調査では、1ヶ月の平均利用者で小学生が約18人に対し、中学生は約5人、高校生は約4人という割合で利用しているというデータもあり、決して少ない人数ではありません。
参考:厚生労働省|令和元年度障害者総合福祉推進事業放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書 令和2年3月 みずほ情報総研株式会社
中学生や高校生で放課後等デイサービスを利用する理由はさまざまですが、小学校では表面化しなかった困りごとが、中学生、高校生と環境が変わったために顕在化したことで利用を検討したという方もいます。また、不登校の状況で放課後等デイサービスを居場所として利用するという場合もあるようです。
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
どのような支援内容がある?
放課後等デイサービスでは障害のある子どもの日常生活や学校生活での困りごとを解消するために、一人ひとりに合わせてコミュニケーション、学習の進め方、身体の使い方、自己管理などに関するさまざまな支援が行われています。
大まかな支援の考え方はどの年齢でも共通ですが、具体的な困りごとは中学生、高校生と学年が上がるにしたがって変わってきて、それによって支援内容も変わってきます。
例えば、中学生になってから定期テストのためにスケジュールを組んで勉強することが難しいという困りごとが出てきた場合に、その人の特性に合わせたスケジュール管理方法を身につけるための支援が行われる、といった具合です。
中学生、高校生向けの支援として特徴的なものに、自立支援と就労支援があります。
自立支援は社会生活を送るうえで必要になるスキルの取得などの支援です。
主なものとして、
・生活全般のスケジュール管理
・思春期に合わせた人との付き合い方
・お金の管理
・交通機関の使い方
・SNSやゲームとの付き合い方
などがあります。
就労支援は社会に出ることを見越したさまざまな支援です。
主なものとして、
・職場体験実習
・業務スキルの訓練
・就職準備
・ストレスコントロール方法の取得
などがあります。
このあとは、中学生、高校生で自立支援と就労支援がどのように行われているのか紹介します。
中学生
中学生になると関わる生徒、先生が変わるほか、思春期になり異性を意識するなど内面的な変化もある時期です。それに従って、人との距離感がわからなくなるなどの困りごとも出てくるため、コミュニケーションの支援も思春期を想定した内容が加わります。
また、定期テストが実施されるなど自主性が求められることが増えるため、タスク管理、スケジュール管理方法を身につけるための支援も行われます。行動範囲も広がり友だちと街に遊びに行く機会も増えてくるため、金銭管理やバスや電車の乗り方などの方法を学ぶ支援を行っている事業所も多いようです。
ほかにも、スマートフォンやゲーム機を持つようになり、SNSやゲームにのめりこんでしまうという場合は、適度に楽しめるようにするための支援などもあります。
高校生
高校生になると中学生までの支援に加えて、進路や就労を意識した支援が多くなっている傾向があるようです。
仕事をイメージする機会として、さまざまな職場に出向いて実際の仕事を体験させてもらう職場体験実習や、事業所内でパソコンを使った模擬業務などの支援を実施している事業所があります。
また、仕事のスキルだけでなく名刺交換や上司や同僚への言葉遣いなど、ビジネスマナーを学ぶプログラムなどの支援もあります。
それと同時に、社会に出た後のことも想定して、家事やストレスコントロール、余暇の過ごし方などを学ぶワークなどを提供している事業所もあるようです。
不登校への支援
放課後等デイサービスでは不登校児の支援も行っています。
不登校児への支援としては、自己肯定感を高めていくことが大事とされており、放課後等デイサービスでの活動を通して成功体験を積んでいけるように意識して行われます。支援は不登校になった背景を踏まえて学校、家庭とも連携しながら計画を作成して実施されます。
具体的には、学習やコミュニケーションなど不登校になった要因を解消する支援や、居場所や同年代との交流の場として放課後等デイサービスで過ごせるようにするなどの支援があります。
本人だけでなく保護者向けの支援もあり、子どもが不登校になった要因の分析や社会参加へのステップの把握、子どもとの関わり方、活用できる支援などが学べるプログラムを提供している事業所もあるようです。
また、放課後等デイサービスの利用が在籍校の出席扱いとなる場合もありますが、その可否については放課後等デイサービスでの活動内容や各学校の裁量によって判断されます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
参考:不登校の子どもも放課後等デイサービスを利用できる?支援内容は?【放課後等デイ(放デイ)】
ここまで放課後等デイサービスで行われる中学生、高校生向けの支援内容について紹介してきました。支援内容は学年で決まっているわけではなく、子どもの特性や置かれている状況、今後の希望などでも変わってきます。
また、放課後等デイサービスは中学生、高校生も対象に含まれていますが、実際の利用判断は自治体が行います。利用を検討している方は自治体の障害福祉窓口や障害児相談支援事業所などに相談することから始めるとよいでしょう。
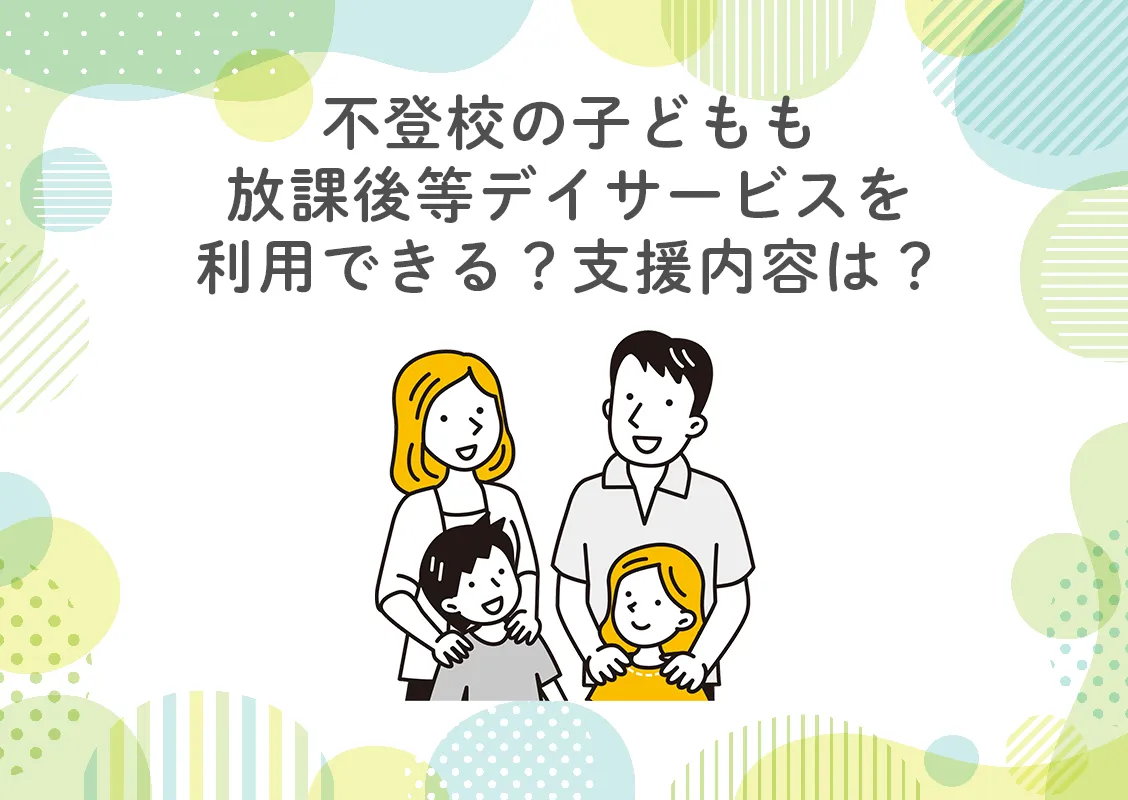

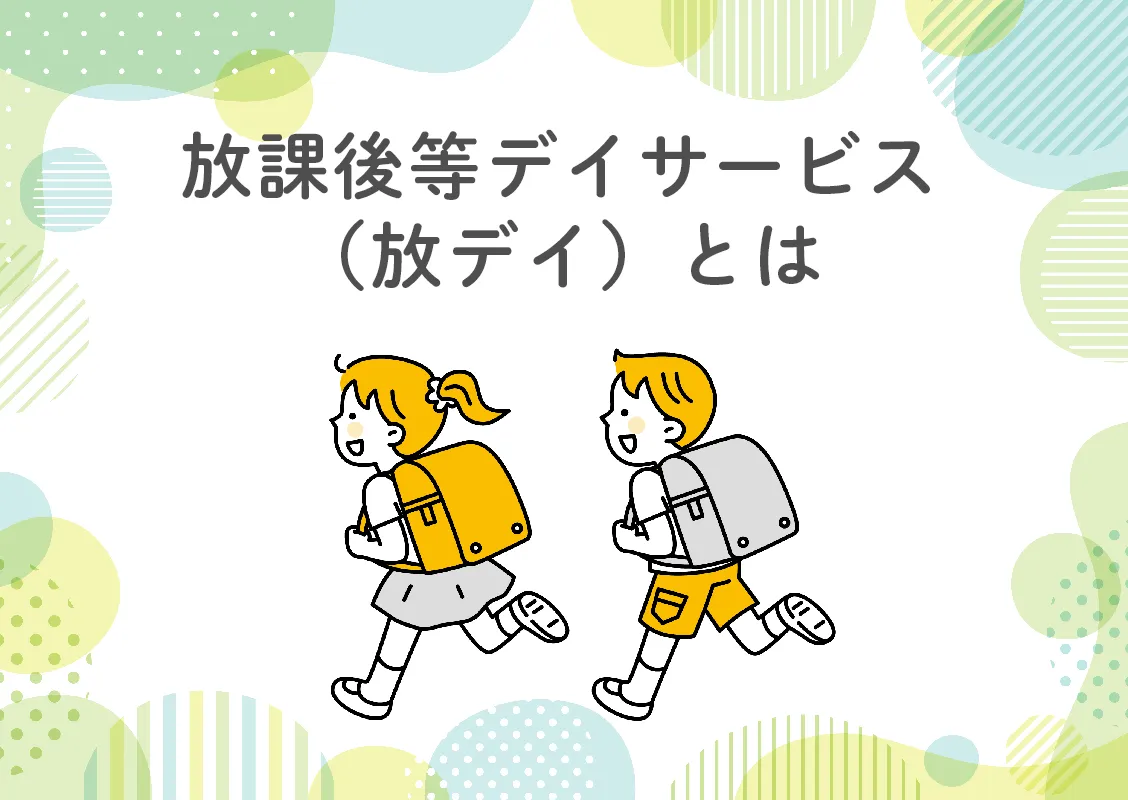

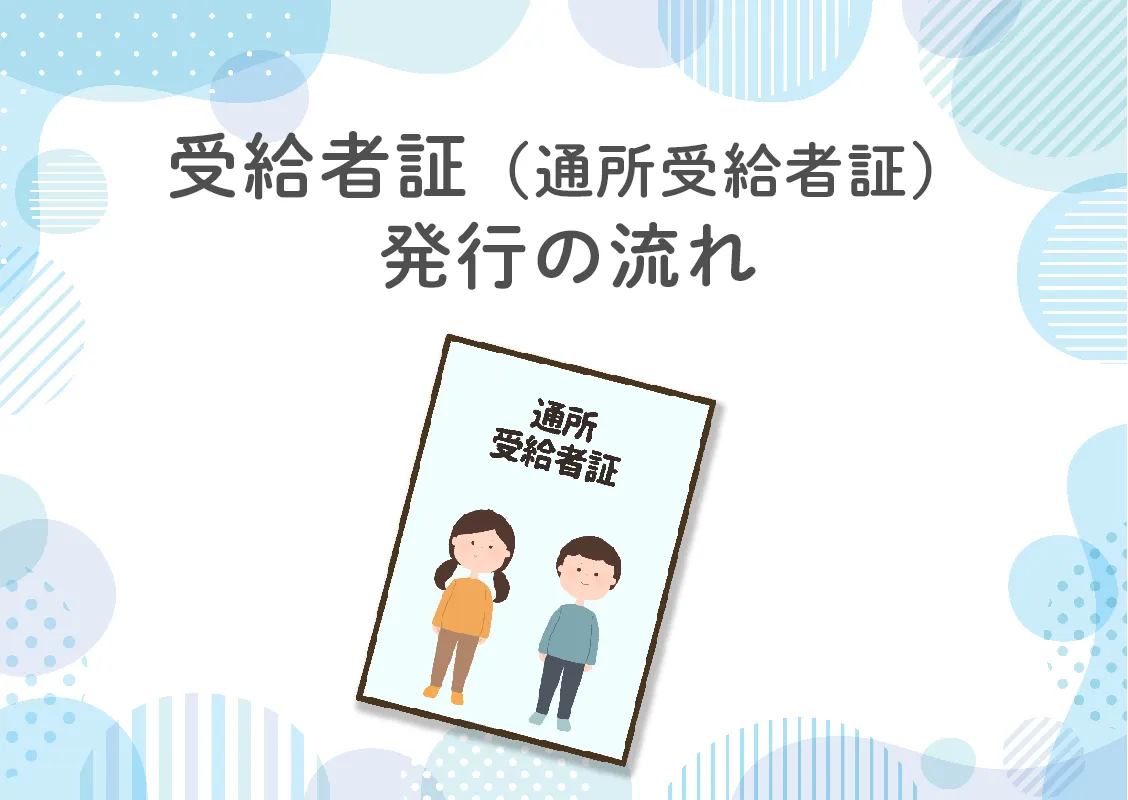
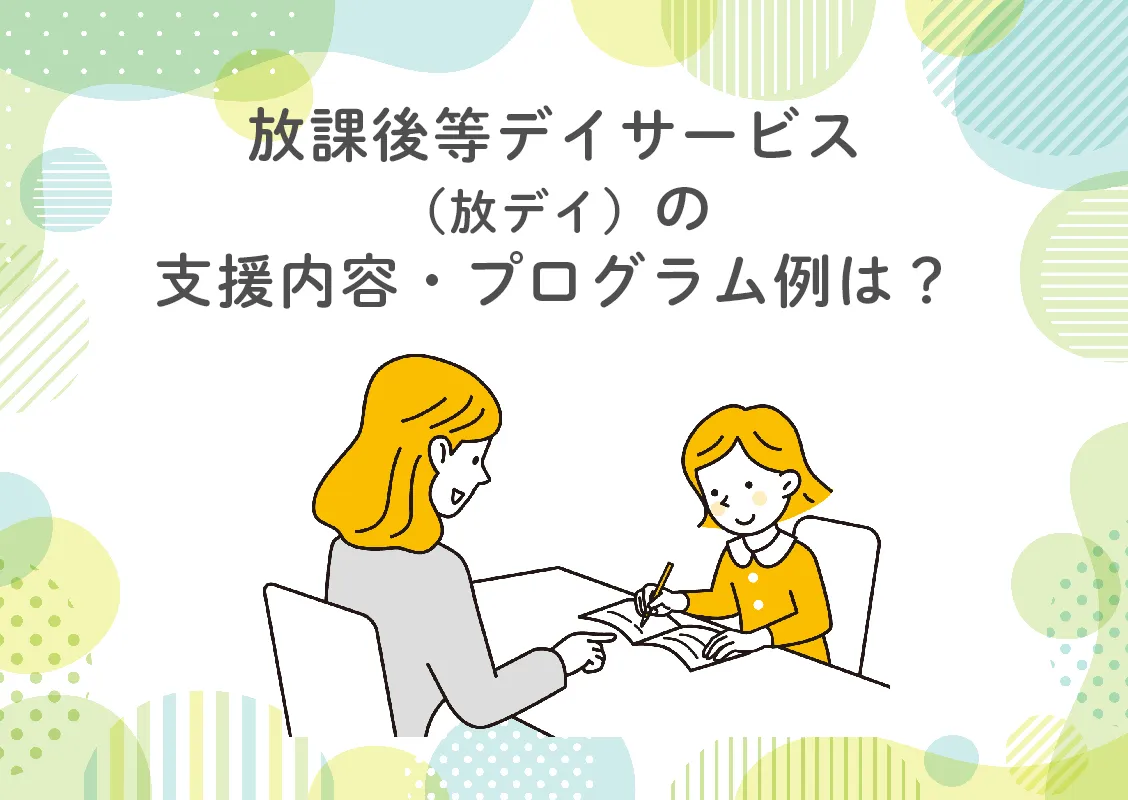



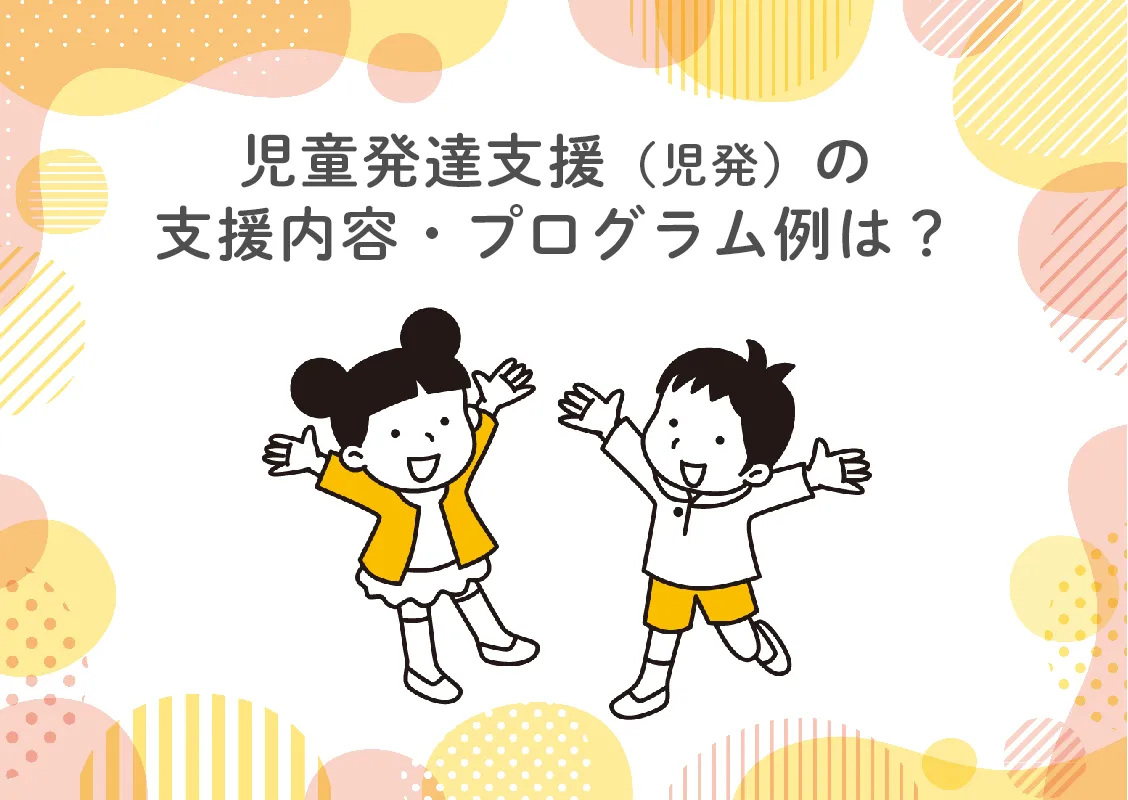


が不登校となり、中学校は頑張って卒業できそうです。卒業後、高卒認定試験を受ける予定で、高校には通いません。色々と調べた限りですと、「高校に行かないという事は、国の定める学校に通っていないので、放課後等デイサービスに通えなくなってしまう」このことを心配しています。この認識で正しいのか明確な情報にたどり付けず、心配しております。現状の制度では、学校に通っていない状態では、高卒認定試験に合格しようが、放課後等デイサービスできないという認識でお間違いないでしょうか?有識者の方いらっしゃいましたら、お知恵をお借りしたく思っております。よろしくお願いいたします。

今長男(中1)小学校の時は支援級現在は普通級に在籍しております。(泣く泣く普通級選択です。)部活はいまいちやる気がなく放課後デイに通所しております。デイサービスの方も普通級での通所は初めてらしく手探りの状態で対応して頂いております。長男はデイサービス自体行くのは問題ないですが今行っているデイサービスは小学生主体の支援がメインです。中学生高校生主体のデイサービスが少なく困っております。役所や相談所等に話をしましたが塾に行くケースがほとんどだそうです。長男はソーシャルスキルにはあまり問題なくどちらかと言えば勉強が苦手(LD診断はない)のタイプです。全国的に中学生対象のデイサービスはあるのでしょうか?


姪っ子なのですが、小学校高学年~中学生になってから放課後デイサービスに行くのをいやがるようになりました。やはり、思春期/女の子特有の悩みもあるようで、なかなかそれが相談できなかったりするようです。思春期(特に女の子)の特化したプログラムなどある療育などあるのでしょうか?また、思春期で、放課後デイサービスがあわなくなったなど、ご経験ある方にアドバイスいただけると嬉しいです。

小学二年生の息子がいます。ASD、ADHDと診断されたばかりです。診断されたばかりなのもあり、普通級にのみ通っています。来年度のことは教育相談で相談予定です。医師には通級を勧められてます。最近、療育に力を入れている放課後等デイサービスに通いはじめ、とても楽しく通っています。(運動療育、個別療育、すごろくやゲームなど集団のSST)コミュニケーションが苦手だと感じますので、そこを伸ばして行けたらなと思っています。今の事業所は、小学生までは通えるのですがその後のイメージがついてません。療育は続けていくものなのでしょうか??みなさまどうされてますか?地域には中学生、高校生向けの事業所や個別療育もあるようです。


のですが、卒業後に大学に通いながら利用できる所はありますか?

中度知的障害と自閉症です。息子は来月卒業し、4月から支援学校の中等部に入学します。現在は放課後、学童や放課後等デイサービスを利用しております。しかし卒業と共に学童は終了となります。中等部入学後も、週に2日は放課後等デイサービスを利用予定です。皆様にお尋ねしたいのは、お子さんの放課後の過ごし方についてです。何をされていますか?特に息子と同じ中学生のお子さんについてお聞きしたいです。

小6の情緒で知的障害ではありません。中学生になっても放課後デイサービスを利用している方がいましたらどんな形で利用していますか?部活との兼ね合いとかもあるとは思いますが。中学生向きのデイサービスがあまりなくどうしても小学生が主体になっているデイサービスが多いので利用方法やこんな風な利用してますとかヒントやアドバイスがあれば宜しくお願い致します🙏🏼


現在は学校に行けてません。中学生ですが、「療育」というのは出来ますか⁉️日常生活を少しでも円滑に送れるようにしてあげたいと思ってます。ご存知の方いらしたら情報下さい。よろしくお願いします。


、不登校児は放課後等デイサービスを利用できなくなったという話は本当でしょうか?今通っている事業者から急にそのような話を聞き、とても心配しています。もし本当だった場合、同じような状況におかれてる方々はどうされているのでしょうか?


こんにちは。現在小学5年生、ADHD(注意欠如)とLD(読み書き)の男の子がいます。学校では通級教室にも行っていますが、生活スキルも身に着けてほしくて放課後デイを検討し見学まで済ませてきました。ですがここにきて放課後デイへ通わせるのは子供にとって良いのだろうか?と少し悩めてきました。理由としては・まずは本人が特別行きたがっているわけではないこと。→行ってみない?と誘って見学は楽しかったようです。・お友達と遊ぶ時間が減る。・行こうと思っているデイは多動のADHDのお子さんが多いように見えた。上記3点です。子ども自身から『行きたい』と言ってほしいところですが、何事にもあまりやる気がないため無理そうです。放課後デイにお子さん通わせておられる方、どういった経緯で行かせましたか?LDに特化した学びをしてほしいところですが、そればっかりともいかないようで・・・親として、レールを敷きすぎているのか?と悩んでいます。些細なことでも構いません。お話聞かせてください。よろしくお願いいたします。
掲載情報について
施設の情報
施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。
利用者の声
利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
施設カテゴリ
施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。


