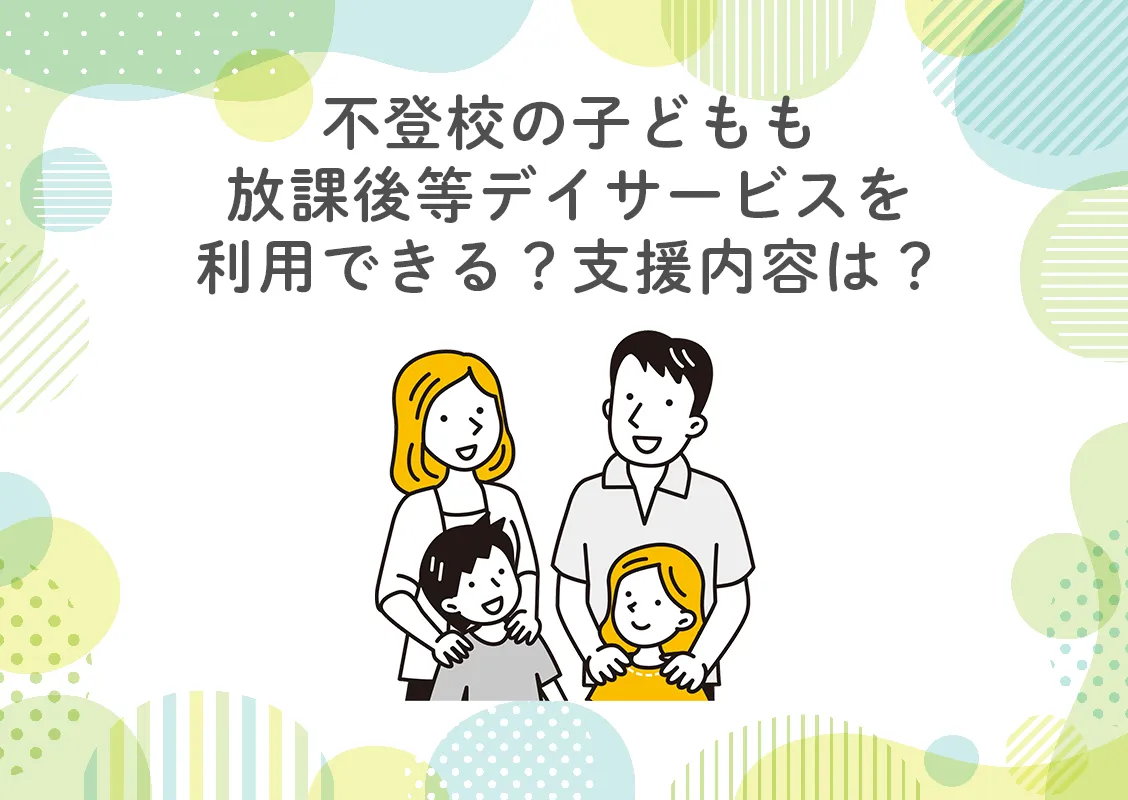
不登校の子どもも放課後等デイサービスを利用できる?支援内容は?【放課後等デイ(放デイ)】
不登校の子どもも放課後等デイサービスを利用できる
放課後等デイサービス(放デイ)は小学校、中学校、高等学校に通う就学児に対して日常や集団生活などの支援を提供する障害児通所支援の一つです。診断や療育手帳などの障害者手帳がなくても、医師の意見書などによって必要が認められれば通うことができます。
放課後等デイサービス(放デイ)には不登校の子どもが休息ができ、安心・安全にその子らしく過ごせる場としての役割もあります。
放課後等デイサービス(放デイ)に通うことができる対象の子どもであれば、不登校の場合も利用できます。不登校状態で学校へ行くことが難しく、医療機関に行ったことがないお子さんの場合でも、医師から必要だと判断されれば、通うことができます。
参考:障害児通所支援に関する検討会報告書 厚生労働省
放課後等デイサービス(放デイ)の不登校の子どもへの支援は、通常の発達支援に加えて学校と連携を図りながら行っていきます。不登校の子どもへの支援はこれまで明文化されていませんでしたが、厚生労働省と子ども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」で明記されました。
参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について
そもそも不登校とは病気や経済的な理由以外の何らかの理由で、年間30日以上欠席した制度のことです。
詳しくは文部科学省により以下のように定義されています。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないまたはしたくてもできない状況にあるために年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理由による者をのぞいたもの
放課後等デイサービス(放デイ)で不登校の子どもへの支援が明文化された背景のひとつとして、不登校の子どもの増加が挙げられます。
不登校の小学生、中学生は2022年度では合わせて29万9,048人で、全体の約3%です。10年前の2012年度は11万2,689人だったため、約3倍近く増加しています。これまでも毎年数千人程度の増加傾向にありましたが、特に新型コロナウイルスが流行しだした2020年度からは2年で10万人以上と大幅に増加しています。

参考:令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省
こういった状況から、不登校の子どもへの支援の必要性が高まったため今回の明文化につながったと考えられています。
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
不登校の子どもに対する放課後等デイサービスの支援内容
不登校の子どもへの支援では放課後等デイサービス(放デイ)だけでなく、家庭や学校などと連携して進めていきます。
不登校の子どもを支援するにあたっては、以下のことが重要とされています。
・子どもの気持ちに寄り添い自己肯定感を育てる
・不登校の要因を分析し、個々のニーズに合った支援を提供する
・子どもの意思を尊重し、学びたいと思ったときに学べる場を提供する
参考:放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)|子ども家庭庁
特に不登校の要因を解消するための個々のニーズに合った支援という点で、放課後等デイサービス(放デイ)では例えば以下のような支援を提供しています。
・ルールの把握や状況に応じたふるまいをするトレーニング
・感情コントロールのトレーニング
・他者との関わり方を学ぶトレーニング
・学習の遅れのサポート
・時間管理方法のトレーニング
・忘れ物やなくしものを減らすトレーニング
・体調管理や生活習慣など自己管理方法のトレーニング
・自分の認知特性や学習しやすい環境を把握するサポート
・ストレス解消やリフレッシュ方法を見つけるための遊びの機会の提供
・ボランティア活動など地域交流の機会の提供
・家族(きょうだい含む)に対してのアドバイス
・学校と連携した合理的配慮の提供 など
ここで挙げたのは一例で、実際の支援は不登校の子どもの性格や特性、発達段階、困りごとなどをもとに、一人ひとり計画を作成して実施されます。
例えば、コミュニケーションにおいても、相手の感情を把握するのが苦手なのか自分の気持ちを伝えるのが苦手なのかによって具体的な支援内容は変わってきます。自己管理方法も、やり方を身につけるほか、アプリなど自分に合ったツールの使い方を見つけるための支援も行います。
放課後等デイサービス(放デイ)に通うことをきっかけとして少しずつ登校を可能にしたり、放課後等デイサービス(放デイ)でできるようになったことが学校でもできるように、学校の担任やスクールソーシャルワーカーなどと連携し、環境づくりや合理的配慮の提供を行います。
加えて、子どもの成長や進級・進学によって状況が変わったときには、計画も変更してその時に合った支援を行っていきます。
最後に不登校の子どもが放課後等デイサービス(放デイ)を利用した際に、在籍校の出席扱いとなるのかについて紹介します。
文部科学省では学校外の施設において、学校への復帰を目的として自立の助けとなるような支援を受けた場合に出席扱いと認めるとしており、実際に放課後等デイサービス(放デイ)の利用が出席扱いとされた例もあります。
ただ、状況によって扱いが異なるため、詳しくは学校や放課後等デイサービス(放デイ)の事業所に問い合わせてみてください。

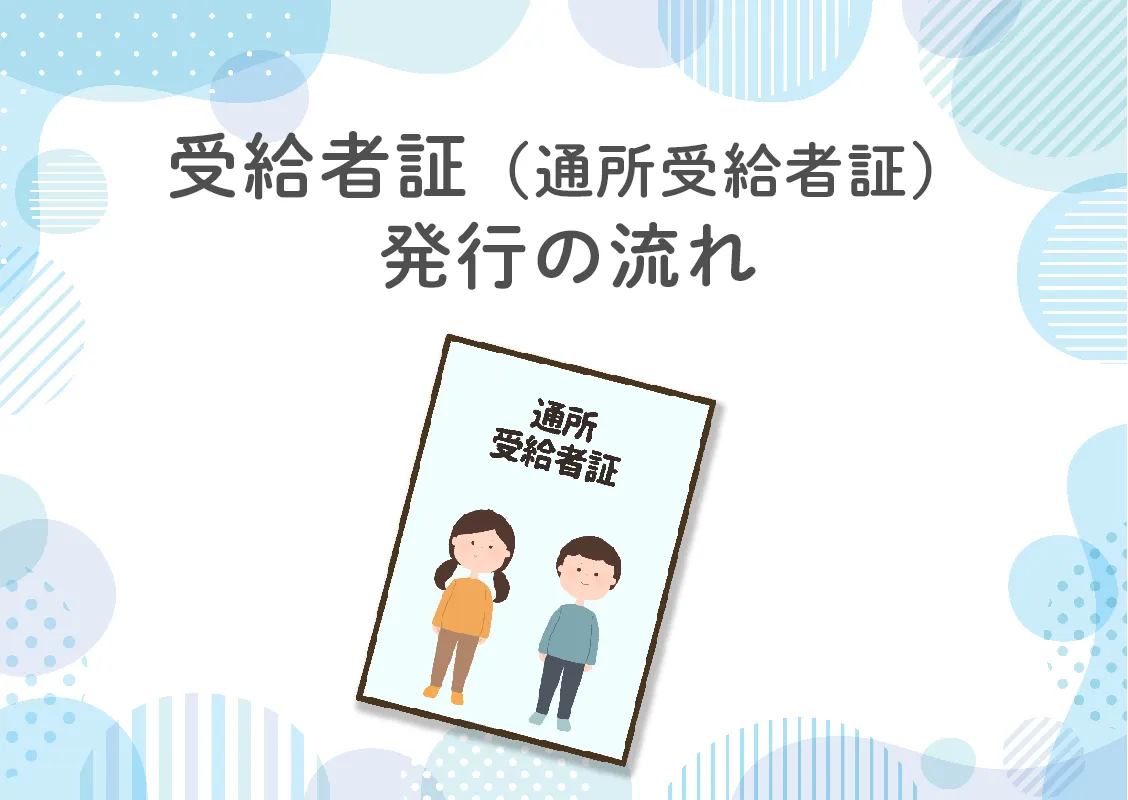
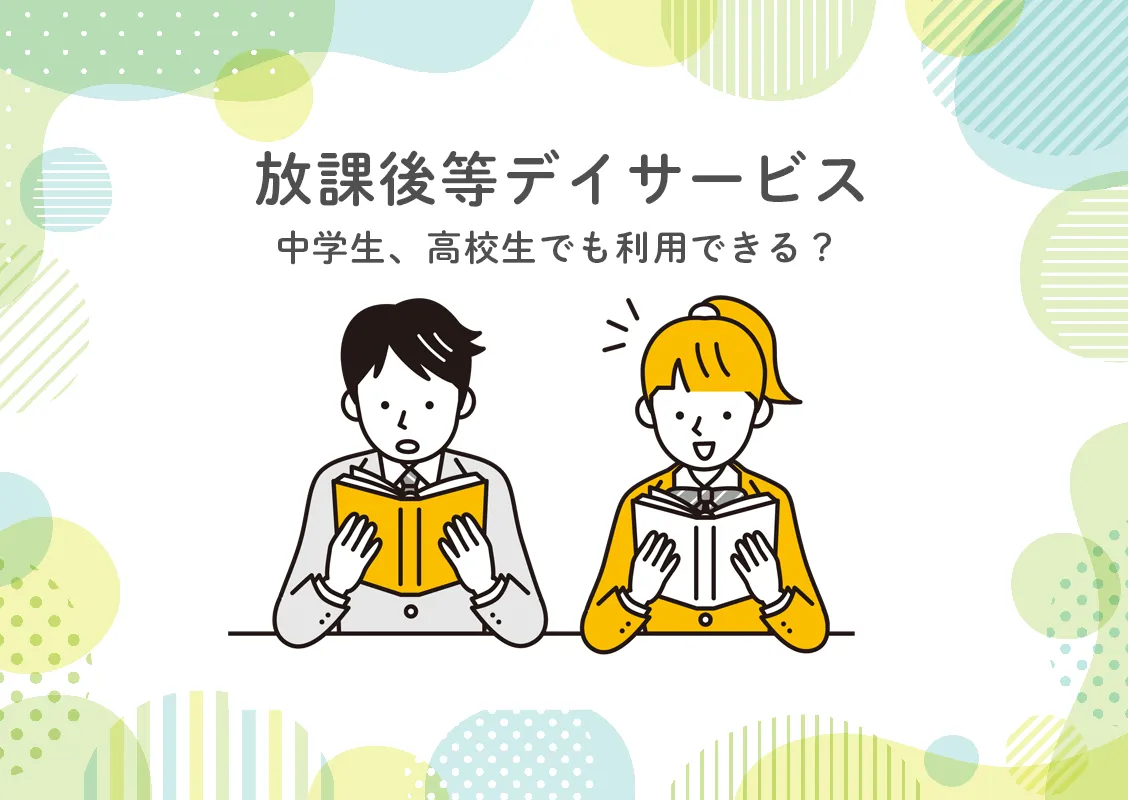
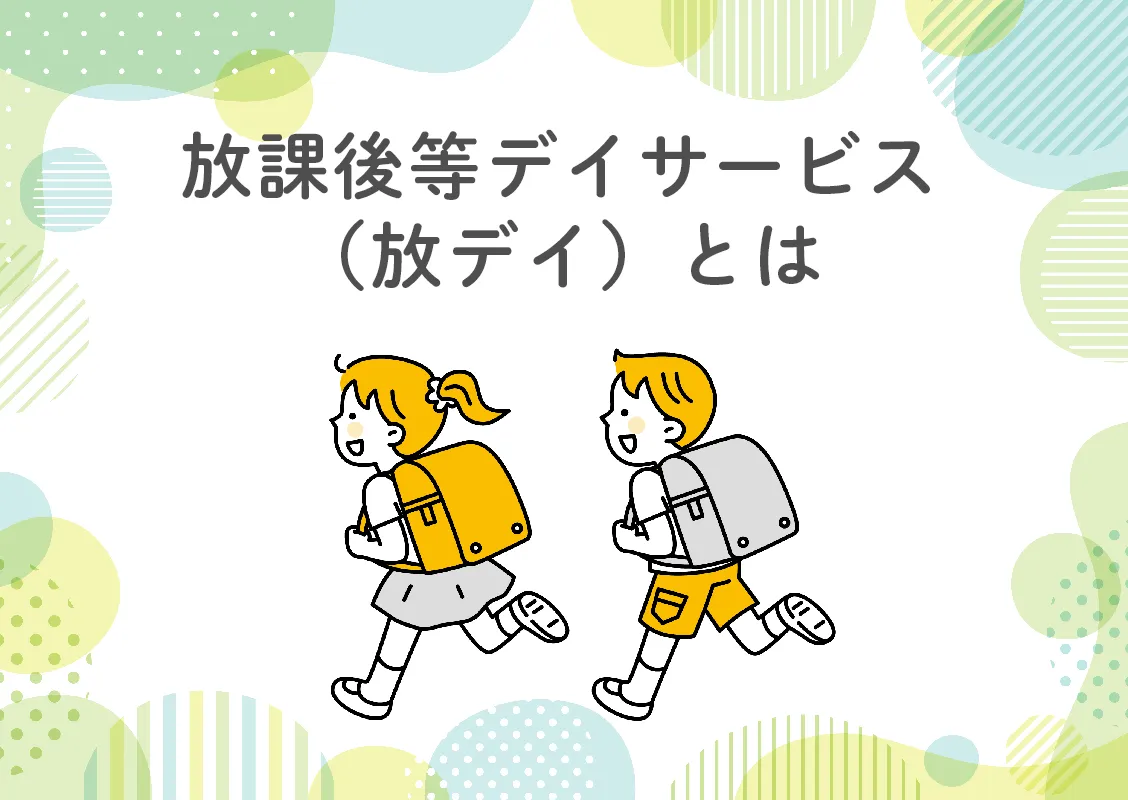


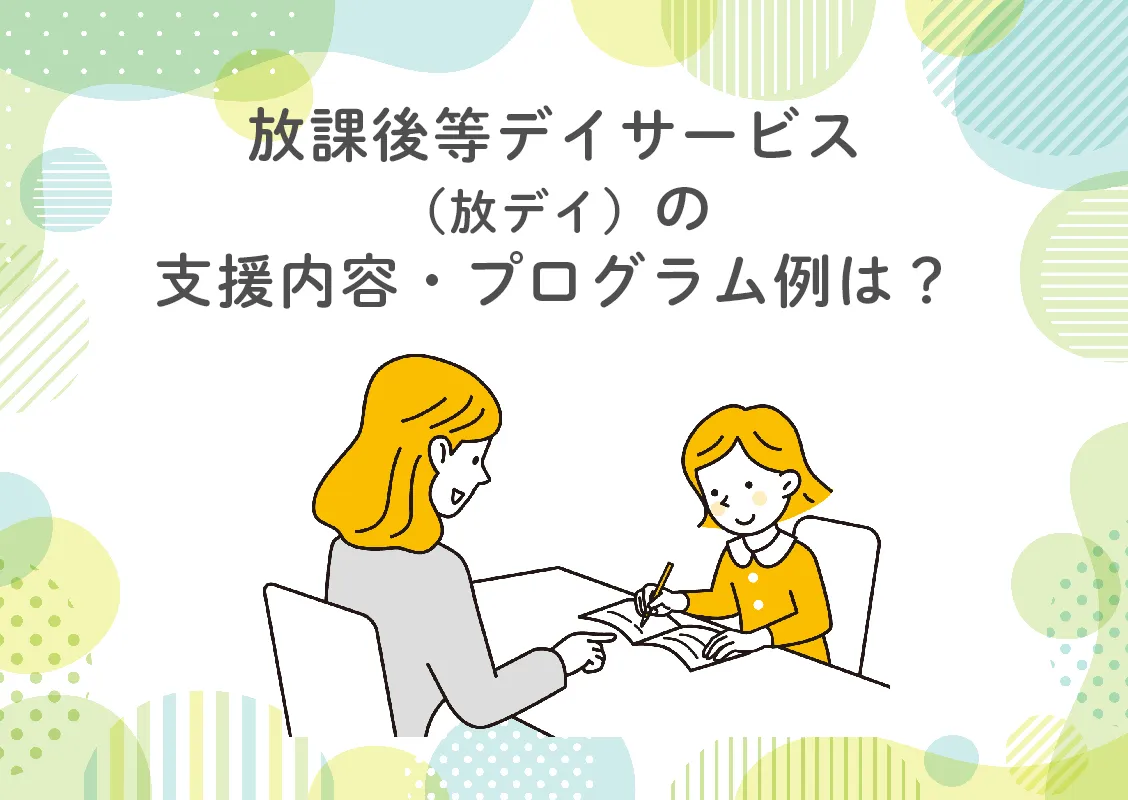





、不登校児は放課後等デイサービスを利用できなくなったという話は本当でしょうか?今通っている事業者から急にそのような話を聞き、とても心配しています。もし本当だった場合、同じような状況におかれてる方々はどうされているのでしょうか?


不登校は小3から始まり、小6で少し行けて、移動教室にも参加しましたが、中学は難しいみたいで、2018.10月から全欠です。私は『放課後デイサービス』について調べたら、うちの市内にあり、受給者証が必要との話でした。娘のドクターは、『その為の診断書書くよ』と言ってくれましたが、そこまでして、行けなかったら、、と考えています。習い事も小3で行けない為全て辞め、2017年からはじめた通級も小6は行きましたが中学ではほぼ行きません、、。同じような状態でもデイサービスに行ってらっしゃる方、いますか?


ービスについて相談です。息子は2歳の時から自閉症スペクトラムの診断を受けていて感情のコントロールが苦手で癇癪持ちで一日に何度も暴れます。怒って着ている服を破ったり保育園でも逃げ出そうとするので、小学校も支援級を検討してます。今週に送迎付きの放課後デイサービスを見学に行くのですが、チェックしておいたほうが良いことや現在放課後デイサービスを利用されているかたがおられましたら見学の際に聞いておいたほうがいい点ありましたら教えていただきたいです、宜しくお願いします。


が不登校となり、中学校は頑張って卒業できそうです。卒業後、高卒認定試験を受ける予定で、高校には通いません。色々と調べた限りですと、「高校に行かないという事は、国の定める学校に通っていないので、放課後等デイサービスに通えなくなってしまう」このことを心配しています。この認識で正しいのか明確な情報にたどり付けず、心配しております。現状の制度では、学校に通っていない状態では、高卒認定試験に合格しようが、放課後等デイサービスできないという認識でお間違いないでしょうか?有識者の方いらっしゃいましたら、お知恵をお借りしたく思っております。よろしくお願いいたします。

保育園の年中ですが、早めに探した方が良いとアドバイスをうけ放課後等デイサービスを探そうと思っています。住んでいる行政で放課後等デイサービスの一覧が載っている資料は頂きました。放課後等デイサービスをどのように決めたか・探し方を聞きたいと思ってます。まだ小学校が決まってませんがどのように問い合わせをした方がいいのかなどを経験したお方にお尋ねしたいです。よろしくお願い致します。

居ます。情緒の通級の先生は優しく対応して下さるので通級には1人で通えるようになりましたが、週2回。普通級にはまだまだ行けそうにありません。引越してきたので友達も居ず、母子で一緒に居る時間が長く、私も辛くなり心療内科へ通い薬を飲んでいます。放課後デイサービスのような、凹凸のある子が怒られず安心して1人で行ける様な場所はないのでしょうか?又、皆さんは不登校の子とどの様にして日中の長い時間を過ごして居るのでしょうか?教えて頂けると助かります。


IQ77、DQ80。ADHD、LD、ASDの傾向が少しずつあるとの診断で、情緒級を希望しています。先月から相談支援専門員に相談し、今から通える療育や来年度の放デイを当たってもらっていますが、多忙なようでなかなかスピーディーに動いてもらえません。そこで自分でも何ヵ所か放デイに電話していますが、どこも空きはなく、来年度も厳しそうです。また、どこも相談員を通して下さいと言われます。このペースでは(このペースでなくても)放デイ利用は無理かもしれません。そうなれば否応なしに学童利用になりますが、同級生と同等に遊べない面があるので、辛い思いをしないか少し心配です。皆様の地域でも放デイは不足傾向だと思いますが、どのようにされているか、またどうされる予定か教えて下さい!


お仕事が週5で17:00まであるので、来年春からは放課後デイサービスを利用したいのですが、事業所から日数を増やせないと言われました。何の支援もない学童保育に預けるのはとても不安で避けたいです。事業所の併用でなんとかカバーしたいと、今必死で資料を集めていますが、週5で見つからなかったらどうしようかと焦ります。お仕事している皆さんはどうしていますか?知恵を貸してください。


こんにちは。現在小学5年生、ADHD(注意欠如)とLD(読み書き)の男の子がいます。学校では通級教室にも行っていますが、生活スキルも身に着けてほしくて放課後デイを検討し見学まで済ませてきました。ですがここにきて放課後デイへ通わせるのは子供にとって良いのだろうか?と少し悩めてきました。理由としては・まずは本人が特別行きたがっているわけではないこと。→行ってみない?と誘って見学は楽しかったようです。・お友達と遊ぶ時間が減る。・行こうと思っているデイは多動のADHDのお子さんが多いように見えた。上記3点です。子ども自身から『行きたい』と言ってほしいところですが、何事にもあまりやる気がないため無理そうです。放課後デイにお子さん通わせておられる方、どういった経緯で行かせましたか?LDに特化した学びをしてほしいところですが、そればっかりともいかないようで・・・親として、レールを敷きすぎているのか?と悩んでいます。些細なことでも構いません。お話聞かせてください。よろしくお願いいたします。

次男が小5で、不登校です。現在は週1回不登校サポート塾(フリースクール体制もとっている)に通い、週1〜2回在籍している小学校に保健室登校などしています。いじめはなく、集団が苦手なタイプです。人に合わせすぎるというか、気を遣いすぎて疲れてしまうようです。本人が塾での勉強にはしっかり取り組むため、少しでも自信になるよう通塾日を学校の出席扱いに出来ないか、と考えています。学校カウンセラーの先生にご相談したところ、前例がないのでスムーズにはいかないかも、とのことでした。フリースクールが学校の出席扱いになっている、またはそういう相談を今現在なさっている方、具体的に学校へはどのような働きかけをされましたか?また、フリースクールから学校への日々の学習報告はどのような形で行なわれているのでしょうか?成功談だけでなく、上手くいかなかった事例や、アドバイスなどもお聞かせ頂ければ有難いです。よろしくお願いします。
掲載情報について
施設の情報
施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。
利用者の声
利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
施設カテゴリ
施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。


