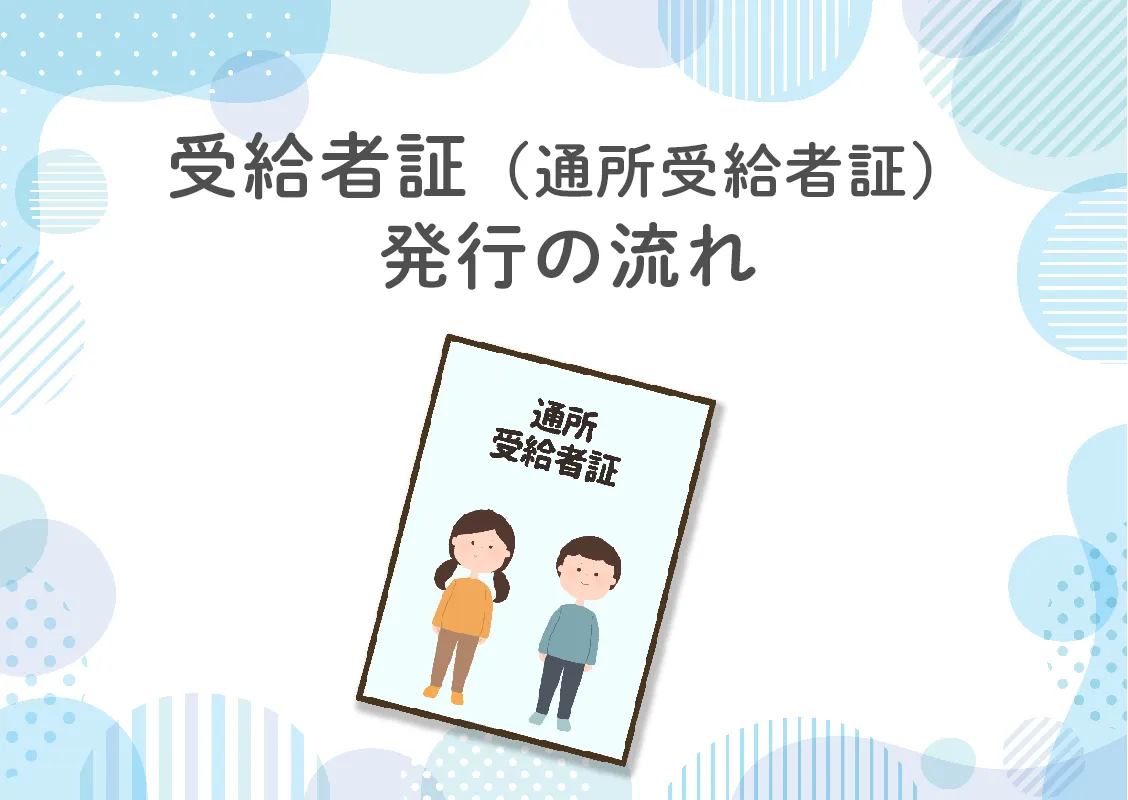
受給者証(通所受給者証)発行の流れ【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】
障害児通所支援の受給者証(通所受給者証)とは?そのほかの受給者証との違い
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を「通所受給者証」といいます。
通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。この通所受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」などさまざまな受給者証がありますが、ここでは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な「障害児通所受給者証」について紹介します。
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
受給者証(通所受給者証)があるとできること
受給者証(通所受給者証)があることで、児童福祉法に基づいて運営されている障害児通所支援事業者等のサービスを利用することができるようになります。
具体的な障害児通所支援とその対象をご紹介します。
・児童発達支援(児発):未就学の児童が対象。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。
・放課後等デイサービス(放デイ):就学児(小学生・中学生・高校生)を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。原則18歳までの年齢制限があります。
ほかにも、居宅を訪問し日常生活の基本的な動作指導などを行う「居宅訪問型児童発達支援」、障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした「保育所等訪問支援」があります。
利用者負担
受給者証(通所受給者証)があると、原則、利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。また、児童発達支援等の場合、満3歳になって初めての4月1日から3年間(3歳から5歳まで)は無償で受けることが可能です。
利用者の負担が大きくなりすぎないよう、ひと月に保護者が負担する額の上限が決められています。ひと月あたりに利用したサービスの量にかかわらず、利用者の世帯ごとの所得に応じて次のように設定されていて、この金額を超えて利用料を支払うことはありません。
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯(収入がおおむね920万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(収入がおおむね920万円を超える世帯): 37,200円
※2024年3月現在
受給者証(通所受給者証)が申請できる対象は
児童福祉法で、対象とされている障害種別は主に次の通りです。
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
また、上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については、専門家の意見書があれば受給者証(通所受給者証)を申請できます。必ずしも医学的な診断や障害者手帳の取得がなくてはいけないわけではありません。
また、対象となる難病は変更となる場合があるため、厚生労働省のホームページをご確認ください。
参考:厚生労働省|障害者総合支援法の対象疾病(難病等)
受給者証(通所受給者証)の申請に必要なもの
申請に必要な主な資料は次の通りです。ただし、利用を希望する障害児通所支援の種類や自治体によっても違う場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。
◻︎支給申請書…役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできるところもあります
◻︎マイナンバーを確認できる書類…申請者(保護者)と子どもの両方が必要です
◻︎発達に支援が必要だとわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師の意見書など
◻︎負担上限金額の申請に必要な書類(世帯状況申告書、課税情報取得同意書、市民税課税(非課税)証明書など)
◻︎障害児支援利用計画案…相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。
受給者証(通所受給者証)の申請に必要なステップ
受給者証(通所受給者証)の申請から交付までは、市区町村によっても異なりますが1~2ヶ月かかる場合があります。
それでは、実際に受給者証(通所受給者証)を申請・取得しサービスを開始するまでの流れをご紹介します。
申請前にやっておくこと
施設の見学
見学や相談は受給者証(通所受給者証)がなくても可能です。あらかじめ、利用したい施設(事業所)を探しておき、空き状況の確認や利用に向けた相談をしておくと、その後の手続きや契約もスムーズに進みます。
実際に、事前に施設への見学や相談を行ってから受給者証(通所受給者証)の申請をするよう呼びかけている自治体もあります。
障害児通所支援施設の探し方【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】
障害児通所支援施設の申し込み方法や時期、見学のポイント【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】
障害児通所支援の利用相談
利用したい施設(事業所)が決まったら、お住まいの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ利用相談を行い、申請手続きに進みます。
支給申請
申請書をはじめ、障害者手帳や医師などの意見書、マイナンバーカードなどの書類をそろえ、市区町村に申請します。
申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成をしてもらえます。または、セルフプランとして保護者や支援者が利用計画案を作成することもできます。
障害児支援利用計画って?作成方法やセルフプランについて【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】
通所支給の要否決定
市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度などを聞き取る面接調査があります。
提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。
決定通知書・受給者証(通所受給者証)の発行
審査の結果サービス利用が妥当だと判断されると支給決定となります。通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証(通所受給者証)が発行されます。
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
通所給付決定はどうやって決まる?
支給申請を受けた市区町村は、面接などの際に、主に次のような事項を参考に支給の要否や支給量を決定しています。
・児童の心身の状態
・児童の置かれている状況
・介護を行う人の状況
・児童や保護者の利用に関する意向の具体的内容
・保健医療サービス、福祉サービスなどの利用状況 など
支給量について
障害児通所支援を利用できる1ヶ月あたりの日数のことを支給量と言います。
支給量は、「児童発達支援(児発)」「放課後等デイサービス(放デイ)」「医療型児童発達支援」「居宅訪問型児童発達支援」「保育所等訪問支援」と、障害児通所支援の種類ごとに月の利用日数が定められます。
例えば、児童発達支援(児発)と保育所等訪問支援を一緒に申請するなど、市区町村が必要と認める場合には、複数のサービスを組み合わせることも可能です。
その場合は、複数のサービスを合わせた上で、適切とされる支給量が設定されることになります。
受給者証(通所受給者証)が手元に届いたら、施設と契約へ
受給者証(通所受給者証)と、受給者証(通所受給者証)の支給量などを踏まえて作成した障害児支援利用計画がそろうと、施設(事業所)と契約することができるようになります。利用を決めた施設(事業所)へ連絡し、契約に向けた手続きを進めましょう。
障害児支援利用計画って?作成方法やセルフプランについて【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】
契約についてはこちら。
障害児通所支援施設の利用契約の流れ【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】
受給者証(通所受給者証)の更新
受給者証(通所受給者証)の有効期間は最長1年間です。サービスの利用を継続したい場合は、期間終了前に更新手続きが必要になります。
受給者証(通所受給者証)の更新手続き
市区町村によって時期に違いはありますが、受給者証(通所受給者証)の有効期間が終了する約2~3ヶ月前に更新の案内が送られてくることが多いようです。
継続して障害児通所支援を利用する際には、改めて申請が必要です。更新の手続きをしないと、期限が切れてサービスが利用できなくなってしまいますので注意しましょう。
支給決定までの流れは、最初の申請時とほとんど同じです。自治体からお知らせが来たら、なるべく早く手続きをしましょう。
申請を行う際には、すでに交付されている受給者証(通所受給者証)と申請書など必要な書類を持って、市区町村の担当窓口で手続きしてください。
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

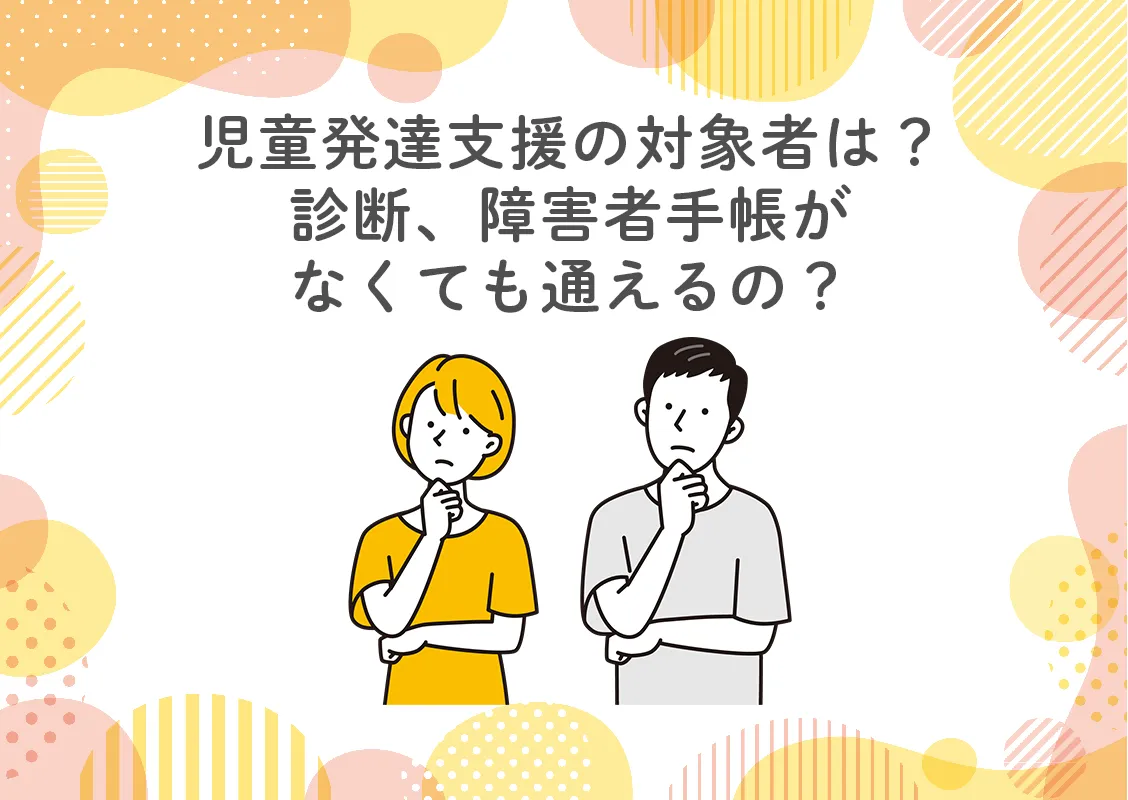



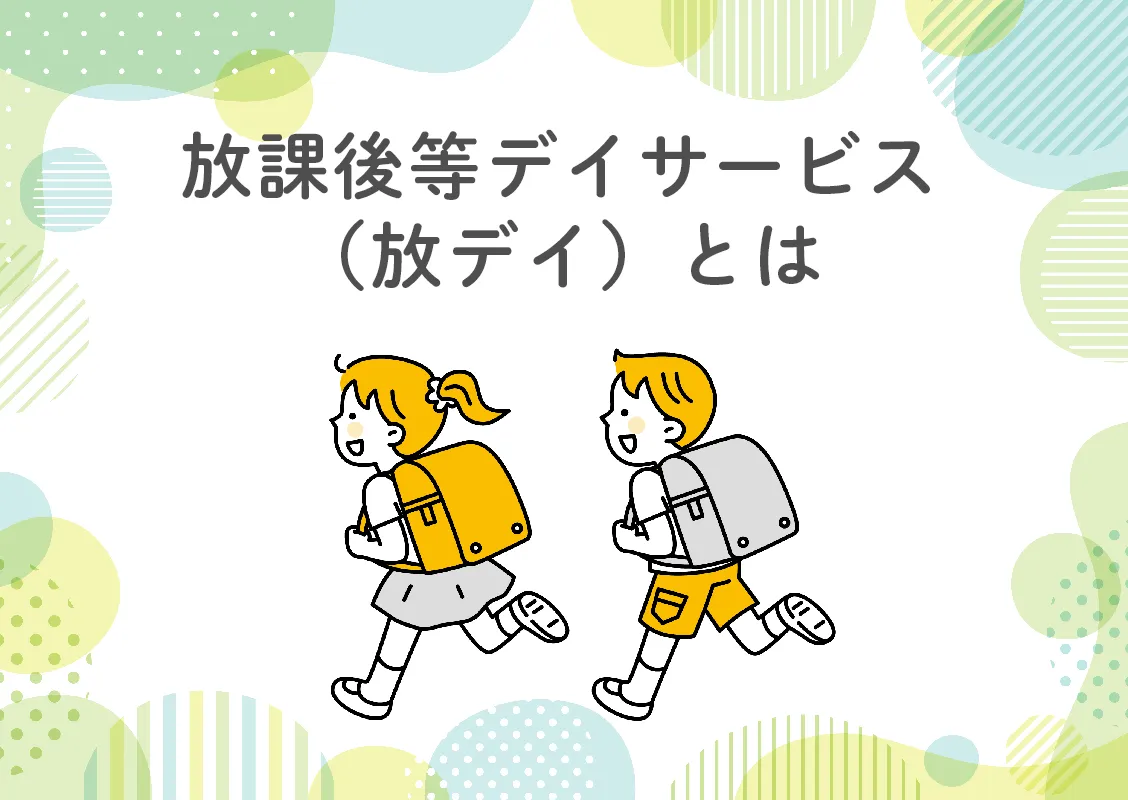

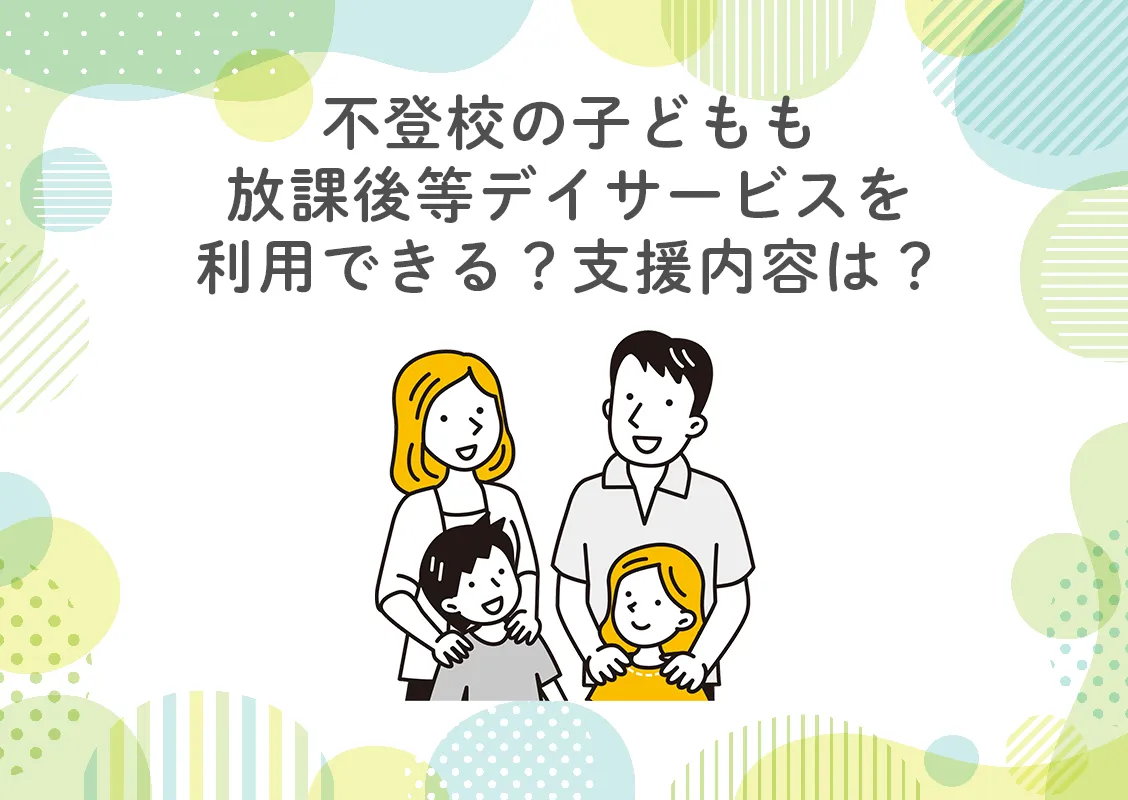




いたいと思っているのですが、通所受給証は発達がみれる病院受診して医師が療養受けた方がいいと判断されたらすぐに発行されるものですか??

後等デイサービスの利用が合うのか悩んでいます。小1、境界知能です。市町村のホームページには通所受給者証が必要と書いてあり、近所にも放デイがいくつかあるようです。まず放デイに連絡するべきか、区役所に相談するべきか、どちらが先が良いのでしょうか。実際に利用されている方の、利用開始までの流れ(相談先、手続き、決め手など)を教えていただけると嬉しいです。

軽度発達障害と診断されている2年生がいます。放課後デイの事が知りたくて、市の関係各所に相談しているうちに、発達検査をすることになり、児相で発達検査を受けました。診断書でも受給証は出せるが、療育手帳が取れそうなので取った方が申請が楽だと言われ、5月末に申請を出してあります。なお、医師の診断書もそれまでに準備し、児相に提出済みです。児相の担当の方も書面はその時点でほぼ準備済みとのことでした。手帳取得までに時間がかかるなら、診断書の状態で受給者証を出してもらうように動いた方が良かったのか、結局同じような時間がかかってしまうのか…いまいち流れが分かりません。手帳を受け取りに来た時に、放課後デイなどの利用方法はお伝えしますと市の方から言われてしまった部分もあるのですが…このまま待っていた方がいいでしょうか?先になんとか動く事が出来ないかを相談した方がいいのでしょうか?初めてなのでイマイチまとまりがありませんが、教えていただければと思います。よろしくお願いします。


小さく生まれて定期的に発達を診てもらってるもうすぐ5歳になる我が子なのですが、現在発達境界域です。(グレーゾーンというのでしょうか…)発達障がいの診断は今のところされていません。ただ1年程の発達の遅れがあります。感覚過敏もあり、集中力のなさ・落ち着きのなさもあります。コミュニケーションは取れてる方ですが、あまり空気を読めないタイプな気がします。通っている保育園では特に指摘はされていません。療育機関で発達検査を受けて発達境界域である事がわかりました。ただ療育機関では今現在、この施設では我が子に出来る療育は無いと言われています。発達障がいの診断をするにはまだ早い、どうしても…というなら民間の療育機関を利用してみてはというお話でした。ただ、親としては少しでも我が子が生きづらくない様に今、出来る事があるなら何とかしたいという気持ちがあります。民間の療育機関を利用するとなると証明書?手帳?の発行がないと実費になるというお話だったのですが…実費では高くてとても通わせられません。こうしたはっきりとしない現状、何とかしたくてもどう動いたら良いのかわからない現状に悩んでいます。どう動いたら良いのでしょうか?失礼な文がありましたら、申し訳ありません。


き、息子も乗り気になった為、受給証の申請に行きました。現在、医療機関にはトゥレット症でかかっており、ウィスクは市の教育センターで受けましたので、トゥレット症の診断書とウィスク結果、放課後ディの利用計画書を持参して行ったのですが、それでは申請が通らないとの事。ウィスクの方での診断書が必要だと‥‥。教育センターは医療機関ではないので、診断書は書いてもらう事ができません。私としてはウィスクの結果が診断書と同じ事なのでは?と思ったのですが。ウィスク結果は全検査こそ平均値ですが、凹凸差がひどく、その差は50です。見る人が見れば、その生きづらさは一目瞭然なのですが、役所窓口では伝わらずその事に関しての書式を提出しろと。かかっている医療機関では「うちで受けたウィスク結果ではないので診断書は書けない」との事ですし、もう一度医療機関でウィスクを受けるにしても2年は期間を開けないと受けられないですよね。どうしたら良いか困っています。受給証をお持ちの方は、どのようにして申請を通られたのか教えて頂ければ‥と思います。長くなりまして申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

るのかがわかりません。日中自閉の不登校の長男を、下の娘のプレ幼稚園の間、自宅でみていて頂きたいのですが。。どなたか利用されたことがある方、サービス自体存在するのか、1割負担で利用できるのか、教えてください。


ネットで見つけた特色ある早期療育施設にどうしたら通えるか電話で聞いてみたら、受給証が必要とのことでした。そしてたぶん発行して貰えるだろうと電話で対応してくれた職員の方は言いました。1歳7ヶ月。今は療育センターの親子教室に月数回行っていて、たぶん高機能自閉症なのかなと思っています。ただグレーゾーンのレベルかなとも思っています。(夫の幼少期にとても似ているようで、夫は幼稚園卒業後ずっと普通級に通いました。)はじめて出てきた受給証という言葉の重さにこれを申請したら、私が息子を障害者にしてしまうのではないか?と戸惑っています。ただ早期療育は魅力的です。親子教室は行きはじめて数ヶ月ですが特に療育を感じません。遊び場の提供という気がしています。低年齢で受給証を申請した方はどのような過程をへて受給証の取得しようとされましたか?よろしくお願いします。

書きで失礼します・外来保育が決まって今週契約、診断書を貰い市役所へ手続きに行く予定・保育園の主任から来年度年少になる際に支援センターの通園部門に入園したい事を強く希望している事を主治医や支援センターの今後関わる人達?担当の看護師に伝えるよう言われてもうそれは伝えてある(そこは私の意思とも一致してる)・でも外来保育を経て通園部門に入るか否かは主治医が決めることになっていると言われた(それは当然だと思う)・そこらへんを主任に伝えるとまだ保育園の枠に余裕があるので待ちますと言われた・そうは言われたものの加配をつけて年少にあげて貰えるかと聞けば言葉を濁されたという状況でして💦もし支援センターでの通園部門に入れることが決まった場合はその手続きは通常の保育園と願書の違いとかありますか?タイミングや時期があるのでしょうか?


幼稚園に通う4歳の未診断の息子がいます。療育に通わせたいのですが、グレーゾーンで軽度の場合、受給者証取得のコツのようなものはありますか?やはり大変さを訴えると取得しやすかったりするのでしょうか。市役所への相談と施設の見学はどちらを先にした方がいいなどありますか?1歳半検診から発達相談を受けていて、2歳の時に親子教室を勧められましたが保育園に通う予定があったので、二つ行くと混乱するかもしれないね、と言われ結局行っていません。診断は小学校入学時でいいのでは?と言われています。2歳で保育園、進級を断られ3歳で幼稚園へ入園しています。年少の時は補助の先生(加配ではありません)が付きっきりになっていましたが、今は担任1人で他に手のかかる子もいるせいか、苦手な製作は他の子と違う物を用意してもいいですか?と言われ承諾しています。もうすぐ夏休みだし、近くに新しい施設ができて空きがあるようなので気になっています。他の場所でも実績のある施設です。いつも長期休暇の時は、週二回幼稚園の預かり保育を利用していましたが、いつもメンバーが変わる為嫌がる事が多いので、この機会に療育に行けたらな、と思いました。宜しくお願い致します。


その児童発達支援についてなんですが、療育の計画書や進捗状況などを事業所は親に提示する必要はないのでしょうか?家族と保育園、事業所との連絡ノートを使用して連携を図ってるのですが、そもそも療育の進捗状況や何を目的に介入を行なっているのかなどを載せた計画書などを作成する義務?必要は制度的にはないのでしょうか?うちのところは見学に行ったり親が参加したりすることができないところなんですが皆さんのところはそういった情報共有などはいかがでしょうか?
掲載情報について
施設の情報
施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。
利用者の声
利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
施設カテゴリ
施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。


